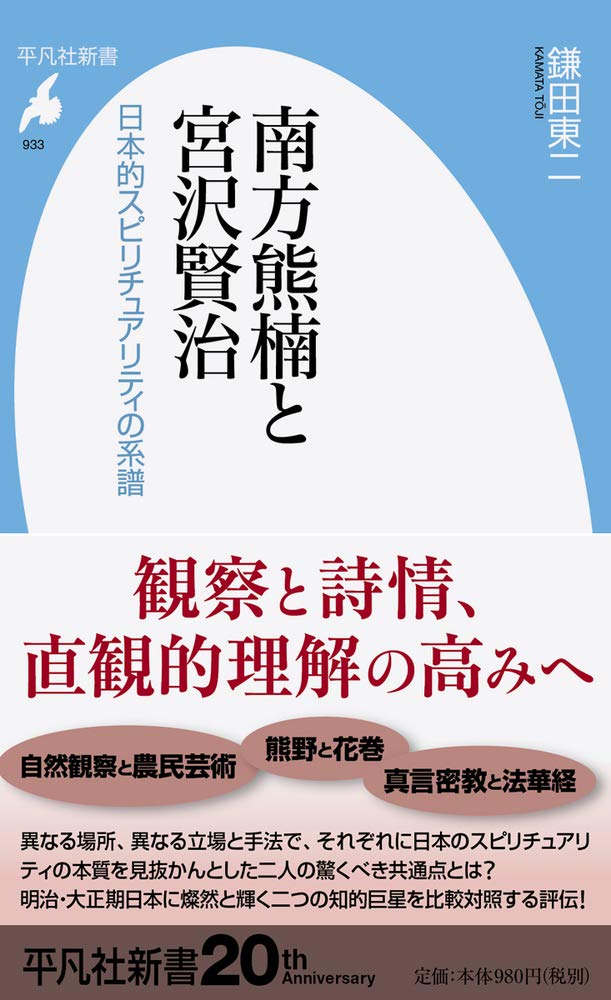04民俗・食– category –
-

身体論のすすめ<京都大学人文科学研究所共同研究班「身体の近代」菊地暁編>
■京大人気講義シリーズ 20211231 江戸時代までの日本人は、同じ側の手と足を同時に前後させる「なんば」という歩き方だった。明治の徴兵制と教育によって今の歩き方になり、「体育座り」も生まれた……。 そういった、所作の変化によって文化が変化する、... -

生命の医と生命の農を求めて<梁瀬義亮>
■地湧社 20211215 梁瀬は、日本で最初に農薬の害を告発した医師だ。彼について書かれた本はいくつか読んだが、本人が書いたこの本がもっともインパクトがあった。 浄土真宗の寺に生まれ、16歳のとき病気になり漢方医にいくと「白砂糖のたべすぎ」と指... -

愛農救国の書<小谷純一>全国愛農会
全国愛農会をつくった小谷純一氏(2004年10月1日死去)による愛農運動の原典の改訂増補版。1978年に出版された。 17歳の時から「人間はどう生きるべきか」「どのようにしたら自分の村を改善し理想の農村を建設することができるか」を探究し、「日本の農... -

青い目の近江商人 メレル・ヴォーリズ<岩原侑>
■文芸社20211031 筆者(1934〜2018)は、近江兄弟社を社長として倒産の危機から救った立役者。 ヴォーリズの建築は有名だけど、彼が近江兄弟社の創始者とは知らなかった。 近江兄弟社の名も、近江さんという兄弟がつくった会社だと思っていたが、「人... -

とうわ よもやまばなし<紺野雅子>
■20211018 1日中かかった結婚式。貧しい家には負担だった。風呂は3,4日に一度しか水をかえないから垢で真っ黒だった。膳も洗うのは3,4日に一度。 うんちは肥料になるから自分の家でするようにする。馬糞を拾って歩いた。 嫁は暗いうちから働き、昼間... -

くじらびと<石川梵>(映画)
■202109 インドネシアの漁村の、マッコウクジラを銛で獲る漁師ラマファたちが主人公。 クジラが年間10頭獲れれば1500人の村人がくらせる。船の舳先からクジラに向かって跳んで銛を突き刺すラマファは危険だが子どもにとってあこがれの職業だ。 そんな... -

ゴールデンカムイ20210912
(アニメと漫画) amazonプライムでアニメの第1部と第2部計25話を一気に見て、第3部はFODの無料お試しで10話を見た。その後の漫画も展開も見たい思ったら、ちょうど漫画を無料公開しているから一気に読んでしまった。 アイヌ関係の博物館や資料館で推奨... -

神と自然の景観論 信仰環境を読む<野本寛一>
■講談社学術文庫20210803 島や岬、洞窟、岩などの自然の地形と信仰のかかわりを論じる。以下に紹介するようにその具体例はいちいち興味深い。でももう少し「意味」の体系を教えてほしかった。 三宅島は「御焼島」であり、伊豆東海岸の白浜は、御焼島... -

身体の零度 何が近代を成立させたか<三浦雅士>
■講談社選書メチエ20210620 衣服の目的は寒さを防ぐためではないという。動きやすさを求めるなら裸が一番だからだ。そもそもの目的は入れ墨と同様「飾る」ことだった。 18世紀のロココの時代までは衣装の目的は装飾にあった。 軍服も当初は装飾目的だっ... -

廃仏毀釈ー寺院・仏像破壊の真実<畑中章宏>
■ちくま新書20210626 廃仏毀釈は、政府の命令でお堂や仏像を破壊しつくす日本の文化大革命だった。なぜこんな政策がとられたのか。日本独特の「神仏習合」の成立から廃仏毀釈にいたる経緯とその結果を丹念にたどる。 神仏習合は神宮寺の建立という形では... -

南方熊楠と宮沢賢治 日本的スピリチュアリティの系譜<鎌田東二>
■平凡社新書20210616 2人ともイニシャルはM.K。賢治は清澄な仏の世界、熊楠は混沌の曼荼羅というイメージだけど、スピリチュアリティという視点から見るとふたりはよく似ていると筆者は説く。 宮沢賢治の「春と修羅」「心象スケッチ」などは、意味不明の... -

「死の国」熊野と巡礼の道古代史謎解き紀行<関裕二>
■(新潮文庫) 202106 いろいろ物議をかもす民間研究者が熊野の歴史をひもといた本。そのまま信じてよいかわからないけど、おもしろい。 熊野への道を石畳で舗装したのは、死者の国に対する憧れだろう(五来重)、新宮市の徐福伝説を裏づけるように昭和3... -

農と言える日本人 福島発・農業の復興へ<野中昌弘>
■コモンズ 20210616 福島はやませが夏に吹き、冷害を受けやすかったから、江戸時代から、稲の品種改良や農具や農耕馬の改良などの工夫をしてきた。明治後期には、会津では稲の品種だけで約60種あり、早稲、中稲、晩稲と植える時期が異なる稲を分散して... -

日本一小さな農業高校の学校づくり 愛農高校、校舎たてかえ顛末記<品田茂>
■岩波ジュニア新書20210604 愛農会と小谷純一を知りたくて入手した。生徒数60人の私立農業高校、愛農学園農業高等学校(三重県伊賀市)の歩みと、老朽化した校舎を減築という手法で再生する様子を紹介している。 デンマークは、1864年にプロシア、オー... -

身体から革命を起こす<甲野善紀、田中聡>
■新潮文庫20210519 同じ側の手足を同時に出すナンバ歩きをはじめ、江戸時代以前は今とはまったく異なる身体の使い方をしていた。甲野は古武術を通して失われた身体技法を再発見し、ふつうでは考えられない動きや技を編み出している。それは武術やスポーツ... -

緑の牢獄 沖縄西表炭坑に眠る台湾の記憶<黄インイク>
■五月書房新社 20210517 西表島の辺境のムラは2度訪ねた。目の前に浮かぶ内離島に炭坑があったと聞いていた。その炭坑の台湾人労働者の歴史をたどったドキュメンタリーの監督が書いた本だ。 西表島の石炭採掘は1960年代までつづいた。 今は無人島にな... -

よみがえれ大和橘 絶滅の危機から再生へ
■あをによし文庫20210512 みかんの原種とされる橘(タチバナ)の歴史や現状を知りたくて入手した。大ざっぱな知識を得るには役立つが、橘と今のみかんとのつながりについても説明してほしかった。 橘は、沖縄のシークヮーサーとともに日本の固有種で、紀... -

鎮守の森<宮脇昭>
■新潮文庫 20210515 その土地の潜在自然植生の森であれば、阪神大震災や酒田の大火でも焼けず、セイタカアワダチソウのような外来種の侵入を許さず、アメリカシロヒトリなどの害虫にもやられない。 山のてっぺんや急斜面、尾根筋、水源地、海に突き出し... -

イザベラ・バードの「日本奥地紀行」を読む<宮本常一>
■平凡社ライブラリー 20210430 「奥地紀行」は、当時の日本人にとって当たり前だったことが、外国人の目を通して記録されており、現代の我々の欠点や習俗がそのころに根をおろし、今も無意識に支配していることを示していると宮本は言う。 バードがさり... -

古寺巡礼<和辻哲郎>
■岩波文庫20210413 学生時代に読んだときは何がおもしろいかわからなかった。和辻が日本の美を発見し、「風土」の哲学の基盤になった本だと何かで読んで30年ぶりに再読した。 読みはじめは退屈だったが、彼の感動と大げさな表現を通じて、だんだん引き... -

新復興論<小松理虔>
■ゲンロン叢書20210320 いわきという地域での震災後の実践活動から哲学を深めた筆者の力量に舌を巻いた。 いわき市の小名浜に住む筆者は、東電や国はもちろん、福島県産品を危険物扱いする反原発派の言論に怒りを覚えてきた。 原発事故によって福島は左... -

平賀源内「非常の人」の生涯<新戸雅章>
■平凡社新書20210317 香川県の志度で平賀源内の旧宅を訪ねた。レオナルド・ダ・ビンチのようなマルチタレントな天才というイメージしかなかったが、最後は獄死していると知り、その生涯を知りたくなった。 源内はもとは本草学者(博物学者)だが、故障し... -

空海<高村薫>
■新潮社 20210201 綿密な取材と想像力で、空海が生きていた時代の風景と空海の人間くささを再現する。 たとえば奥の院のあたりは川の流れる湿地だったが、開創200年後に伽藍焼失に備えて材木を供給するためヒノキが植林された。 空海は「思い込んだら... -

死者を弔うと言うこと 世界の各地に葬送のかたちを訪ねる<サラ・マレー>
■草思社文庫 20210117 イギリスの女性ジャーナリストが、父の死をきっかけに世界の「弔い」の場を巡り歩く。 父は無神論者で「人間なんかしょせん有機物だ」と言っていたが、死ぬ直前、親友が眠る場所に骨をまいてほしい、と伝えた。「単なる有機物」で... -

苦海・浄土・日本 石牟礼道子 もだえ神の精神<田中優子>
■集英社新書 20201118 石牟礼道子の「苦界浄土」は水俣病がテーマなのにある種の豊かさがあふれていた。自然とのつながり。アニミズム的な世界。文学の想像力……学生時代に読んだとき、その理由はわかるようでわからなかった。 この本は、江戸文化の研... -

奇跡の四国遍路<黛まどか>
■中公新書ラクレ 20200925 筆者は過去に、サンティアゴ巡礼や熊野古道などを歩いた。仕事と家事、看病による過労で体調を崩して、現実から逃れるように2017年に遍路に出た。 阪神大震災で妻と娘を亡くした男性は「悲しみは癒えることはない…夜がつらい... -

本とみかんと子育てと<柳原一徳>
■みずのわ出版 20210203 瀬戸内の周防大島でみかん農家を営みながらひとりで出版社を営む友人の久々の著書。 671ページという辞書のような厚みに圧倒されて、なかなか手に取れなかったが、ここ数日で一気に目を通した。 2017年から3年間の日記を中心に... -

山の宗教 修験道案内<五来重>
■山の宗教 修験道案内<五来重>角川ソフィア文庫 20201019 麓の民が山々を自分たちの先祖の霊の行く山「神奈備」として拝んでいた。死者の霊は山へ行き、霊をまつる宗教者として狩人がいた。それが修験道の山の開創者になった。 大峰・熊野の山伏が... -

仏教と民俗 仏教民俗学入門<五来重>
■仏教と民俗 仏教民俗学入門<五来重>角川ソフィア文庫 20201006 お盆やお彼岸、葬式や年忌、位牌といった習俗は仏教だと思われているが、実は本来の仏教ではなく、仏教伝来以前の日本古来の在来宗教の名残だという。 日本の在来宗教は先祖の霊に対す... -

路上の映像論 うた・近代・辺境<西世賢寿>
■路上の映像論 うた・近代・辺境<西世賢寿>現代書館 筆者はNHKの元ディレクター。近現代の時代のなかで滅びつつある、精神文化のなかに地下水脈のように流れてぉた口承文芸や語り物芸能の世界を「語り物としてのドキュメンタリー」という形にしてきた...