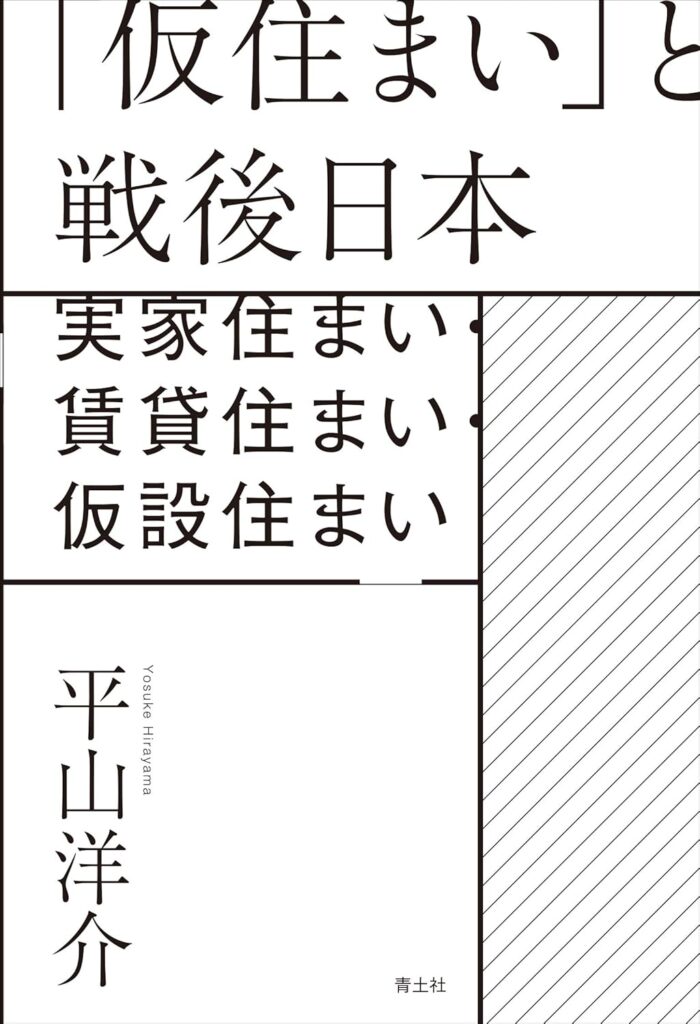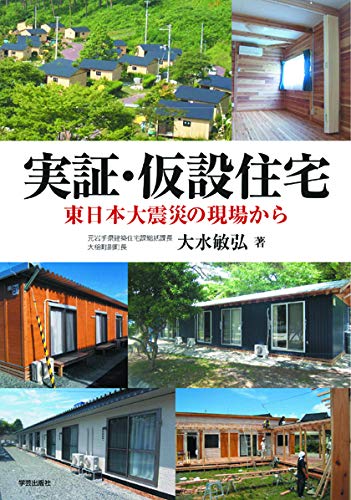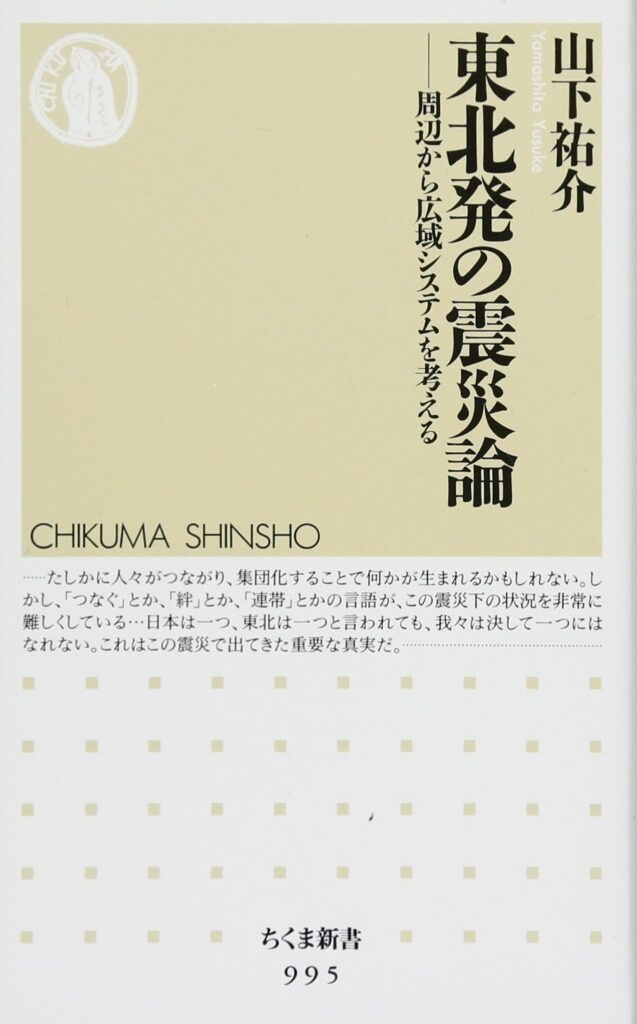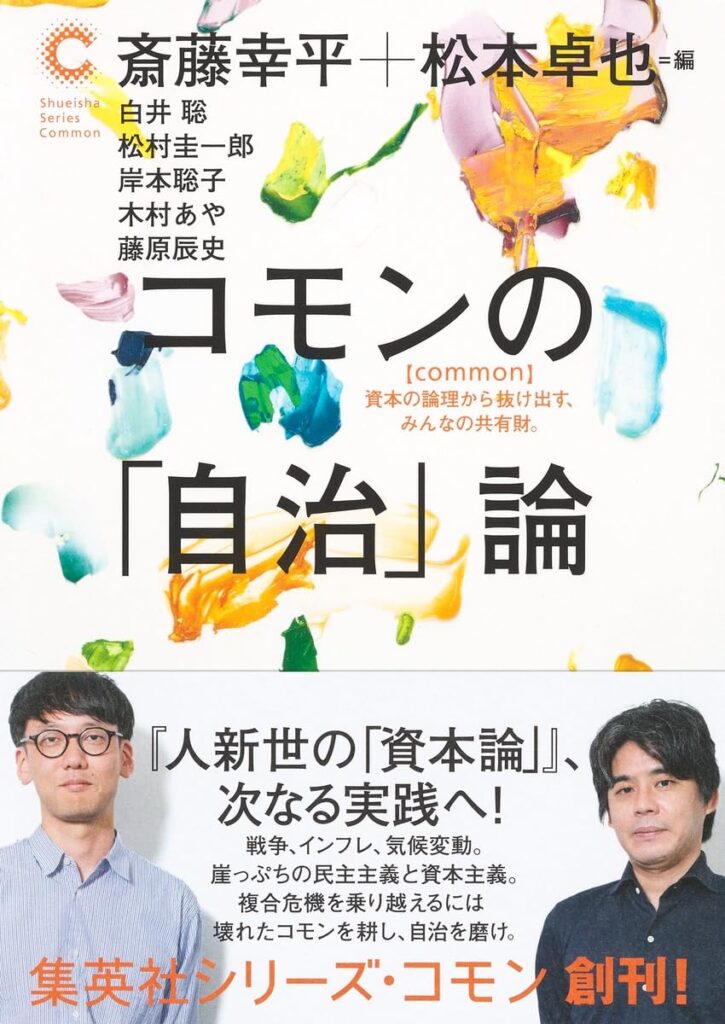07地方自治・行政– category –
-

減災社会シンポジウム「阪神・淡路大震災30年~『大災害の時代』へ継承すべきこと」250208
渦中の斉藤元彦知事の登場におどろくとともに鼻白んだが、議論の中身は濃かった ■室崎益輝さん基調講演▽進歩したこと 阪神淡路大震災では、家族や近所、消防団がかけつけて救助した。それを踏まえてコミュニティ防災が成長した。能登では、壊れた住宅で... -

罹災証明も仮設住宅もいらない 目から鱗の防災対応
「能登の今を知るオンライントーク 変わらない? 日本の災害対応」を聴いた。大阪公立大大学院の菅野拓准教授の講演は、災害対応の「常識」をくつがえすものだった。以下、その要約。 避難所での雑魚寝は1930年から変わらない。災害のたびに戦前... -

「仮住まい」と戦後日本<平山洋介>
■青土社240930 戦後日本の住宅政策は、1950年代に整備され、住宅金融公庫法(50年)、公営住宅法(51年)、日本住宅公団法(55年)を3本柱とした。だが中心を占めたのは、住宅ローン供給をになう公庫だった。 住宅ローン供給の拡大によって、... -

実証・仮設住宅 東日本大震災の現場から<大水敏弘>
■学芸出版240831 筆者は、国交省から岩手県建築住宅課総括課長となり、東日本大震災の仮設住宅建設を担当した。その後に大槌町副町長になっている。全体を網羅する描写力は国の官僚ならではだ。優秀で現場を大切にする官僚が出向していて岩手県は助かった... -

東北発の震災論 周辺から広域システムを考える<山下祐介>
■ちくま新書240625 東日本大震災から2年後の本。筆者は2011年4月まで、弘前大におり、その後東京の大学に移って、被災地を歩いてきた。 <広域システム>と<中心ー周辺>の問題こそが震災であらわになったとする。原発事故にそれが典型的にあらわれ... -

コモンの「自治」論<斉藤幸平・松本卓也編>
■集英社 20240124 「人新世」の危機が深まれば、市場は効率的だという新自由主義の楽観的な考えは終わりを告げる。コロナ禍でのロックダウンのように、慢性的な緊急事態に対処するため、大きな政治権力が要請され「戦時経済」が生まれ、政治がトップダウ... -

古寺巡礼<和辻哲郎>
■岩波文庫20210413 学生時代に読んだときは何がおもしろいかわからなかった。和辻が日本の美を発見し、「風土」の哲学の基盤になった本だと何かで読んで30年ぶりに再読した。 読みはじめは退屈だったが、彼の感動と大げさな表現を通じて、だんだん引き... -

新復興論<小松理虔>
■ゲンロン叢書20210320 いわきという地域での震災後の実践活動から哲学を深めた筆者の力量に舌を巻いた。 いわき市の小名浜に住む筆者は、東電や国はもちろん、福島県産品を危険物扱いする反原発派の言論に怒りを覚えてきた。 原発事故によって福島は左... -

映画「はりぼて」20200803
富山市議会の政務活動費問題をスクープし、市議十数人の辞職につなげた富山市の「チューリップテレビ」の取材の過程を記録したドキュメンタリー。 はじまりは富山市議会議員の月給10万円アップだった。 市議会のドンと呼ばれる自民党議員に「有権者は... -

暮らしの論理 生活創造への道<山本松代>
■暮らしの論理 生活創造への道<山本松代>ドメス出版 20170416 筆者は、戦後直後の生活改善改善運動の、農水省の最初の担当者だった。「生産」一辺倒の主流派に対抗して、農村女性たちの「生活」の改善に取り組んだ。 生活改善運動はアメリカに生ま... -

むらの社会を研究する<日本村落研究学会 鳥越皓之編>
■むらの社会を研究する<日本村落研究学会 鳥越皓之編>農文協 日本におけるむらの研究の流れや、研究の方法、現代の課題などを網羅していてわかりやすい。本格的にむら研究をはじめる人には必読の書だろう。私のような素人が読んでもおもしろかった。 ... -

里山資本主義 日本経済は「安心の原理」で動く<藻谷浩介 NHK広島取材班>
■里山資本主義 日本経済は「安心の原理」で動く<藻谷浩介 NHK広島取材班> 角川 20131103 経済成長ばかりを求めるのではなく、エネルギーや食料をできるだけ自給し、近所におすそわけする。経済指標にはあらわれないが、外部の資本にカネが流れるこ... -

暴走する地方自治<田村秀>
■暴走する地方自治<田村秀>ちくま新書20121215 熊本の細川、三重県の北川、鳥取の片山から橋下・石原にいたるまでの「改革派」の知事が、実は話題先行で混乱しかもたらさなかったのではないか、というスタンスの本。説得力のある部分もあるが、筆者の立... -

町づくろいの思想 <森まゆみ>
■町づくろいの思想<森まゆみ>みすず書房 201209 東京の下町はきらいじゃないけど、東京じたいが素晴らしい町だと思ったことはない。でもこの本を見ると、もしかしたらおもしろい街なのかもしれないし、新しい共同体の可能性を秘めているのではないか、... -

ためされた地方自治-原発の代理戦争にゆれた能登半島・珠洲市市民の13年<山秋真>
■ためされた地方自治-原発の代理戦争にゆれた能登半島・珠洲市市民の13年<山秋真>桂書房 20120110 旅行で偶然珠洲に立ち寄った女子学生が、推進派の現職市長に無名の若者がいどんだ1993年の市長選に参加する。原発計画とたたかう人々のなかで... -

電力と国家<佐高信>
■電力と国家<佐高信>集英社新書 20111124 戦争遂行のため、軍部と革新官僚が手を結んで電力の国家管理を強行した。 それに反対したのが、福沢諭吉の弟子でもある松永安左エ門だった。「官吏は人間のくずである」と言い放ち、戦後も官僚による支配をは... -

バッド・ドリーム 色恋村選挙戦狂騒曲<落合誓子>
■バッド・ドリーム 村長候補はイヌ? 色恋村選挙戦狂騒曲<落合誓子>自然食通信社 20111114 能登半島の珠洲原発計画への反対運動を担ってきたルポライターの筆者が、実際に体験した選挙戦のエピソードをもとにつくった小説。 小さな村に巨大産... -

珠洲原発・阻止へのあゆみ <北野進>
■珠洲原発・阻止へのあゆみ <北野進> 七つ森書館 20110517 奥能登に突如原発計画がふってわき、電力会社と行政が事前調査を強行しようとする。労組などの革新勢力が反対の声をあげ、地元住民が共有地運動をはじめ、漁民が立ち上がり、それをネ... -

地域再生の罠<久繁哲之介>
■地域再生の罠<久繁哲之介>ちくま新書 20100928 専門家が賞賛する地域再生策のほとんどは成功しておらず衰退している。都市計画や建築、都市工学などの「土建工学者」が推奨する、本当は成功していない「成功事例」を視察して模倣するからほぼ確... -

道路をどうするか <五十嵐敬喜 小川明雄>
岩波新書 1091101 ▽15 1952年の新道路法は、田中角栄議員らが提出した。これによって道路建設の補助金制度を設けた。これが新たな中央集権の出発点。補助金ほしさに上京をくり返す年中行事はここからはじまった。 ▽20 1953年提出の道路整備費の財... -

離島発 生き残るための10の戦略 <山内道雄>
NHK出版 生活人新書 1091004 三位一体の改革で交付金が減らされ、基金が取り崩され、いつ破綻してもおかしくない状況に追い込まれた市町村に、「平成の合併」がおそった。合併しても改善は望めない、かといってこのままでは破綻してしまう。じり... -

問答有用 <田中真紀子×佐高信>
朝日新聞社 20090913 おもしろい。田中真紀子はアタマが切れる。 ミニ集会を日常的に開いているから選挙になっても慌てない、という発言は、なるほど、と思った。地元に帰って地元の声をきっちり聴く大切さはいろいろな選挙をみるごとに感じるように... -

ムラは問う<中国新聞取材班>
農文協 20090322 中国新聞の取材班の連載をまとめた。中国山地の山村を手始めに、輸出用作物を大量生産する中国や、自由貿易協定によって疲弊するタイの農村まで出かける。 山村の住民にとっては、「切り捨て」は農協支所の閉鎖にはじまり、市町村... -

SS概論 <成崇 原田勝孝編著>
ハーベスト出版 20080313 1人あたりの公共事業が日本一多く、保守の牙城とされる島根県の姿を、政治家や経済、農業関係者らへのインタビューを通して明らかにしていく。大学院生による本だから、驚くような内容はないが、「1人当たりの公共投資... -

沢内村奮戦記〈太田祖電、増田進、田中トシ、上坪陽、田邊順一〉
あけび書房 20080605 いちはやく老人医療費の無料化を実現したことで知られる岩手県沢内村の歴史を、元村長、医師、保健師といった人たちがオムニバス形式でえがく。田邊氏の写真も心をうつ。 「老人医療の無料化」は、徹底的に草の根レベルでかたりあい... -

島に生きる 魚島村長の離島過疎振興記おもろい村長の夢 <佐伯増夫>
20080522 瀬戸内海の真ん中、どこからも高速船で1時間かかる孤立した村。そんな離島の村で下水道100%、電話普及率日本一、CATV導入、Iターンの呼びこみ……といったユニークな村おこしを実践してきた村長の体験記だ。 「村」という自治体だったか... -

地域を変える市民自治 井手敏彦の実践と思想
緑風出版 20060917 井手氏は沼津市長時代、ゴミ分別を全国に先駆けてやりとげた環境問題の先駆者だ。 「環境問題の人」というイメージだったが、もっと奥深いものがあったことを知らされた。 ゴミ分別の「沼津方式」は、差別されていた清掃労... -

奇跡を起こした村の話 <吉岡忍>
ちくまプリマー新書 20050529 「戦争になだれ込み破滅していった昭和史を少し丁寧に読み解けば、その前段に地方行政の手詰まり、怠慢、無能力があったことがわかるだろう」 冒頭、こんな言葉が出てきて、そうだったんだ、と目の前が開けるような気がして...
1