■電力と国家<佐高信>集英社新書 20111124
戦争遂行のため、軍部と革新官僚が手を結んで電力の国家管理を強行した。
それに反対したのが、福沢諭吉の弟子でもある松永安左エ門だった。「官吏は人間のくずである」と言い放ち、戦後も官僚による支配をはねのけようとつとめた。
その弟子にあたる木川田も同様の思想だった。原発は反対だったが、国家がやるくらいなら民間でやるしかないと判断して自らの故郷の福島に導入した。勲章も拒否した。
だが木川田の弟子にあたる平岩は国家に服従して官僚以上に官僚的な東電の体質をつくってしまった。平岩がトップにたつことで東電は腐っていったと筆者はみる。
だが松永や木川田を評価するだけでいいのだろうか? という疑問が残った。私利私欲を考えず、リベラルな思想を堅持し……人間的に魅力的であることはわかる。だが、平岩が君臨し「役所以上に官僚的」である東電の基盤をつくった責任が、松永や木川田にはなかったと言えるだろうか?
坂本龍馬をはじめとして魅力的な人々がつくりあげた明治政府が、第二次大戦での破滅をもたらしたように、軍部暴走にストップをかけ財界の腐敗を正そうとした「昭和研究会」が大政翼賛会に転身していくように、松永や木川田のすばらしい志と行動力が現在の東電の体質を形成した面はなかったか。
筆者の文章は明快で説得力があるが、この本は、未消化な部分を感じざるを得なかった。
=============
▽29 近衛文麿の親友後藤隆之助が昭和8年にはじめた国策研究機関「昭和研究会」昭和15年に解散するまでのべ3000人が参加。三木清も風早八十二も、清水幾太郎、西田幾多郎、柳田国男……進歩的文化人の集まりだった。
軍部の暴走にストップをかけ、財界の腐敗を正そうとした昭和研究会は、あの大政翼賛会に転身していく。「一国一党の強い政治」を目指した結果、それが裏目となって軍国主義をあおり、日本を戦争に突入させるナチスばりの結社形成に手を貸してしまうことになる。
この時代、政財界の人間は、私利私欲に走る腐敗しきった人種として、右翼からも左翼からも敵対視されていた。
▽33 時代は、自由主義経済から統制経済へ、民間優位から官僚主導へとうつって。いく。「官強民弱」の潮流は否応なく「電力の鬼」の手足を奪う。
「くちばしの青い」役人は、政治を牛耳る軍人の力を背景として松永を糾弾した。軍人も「官吏」であり、民間の生きた経済を知らない彼らが、以後、日本を暴走させ、破滅に導くことになる。
▽48 世界的な恐慌が吹き荒れたなか、資本主義、自由経済の限界、不便さをどの国も痛感しており、1930−40年代は、私益を否定し公益ならぬ国益を優先する「統制経済」こそが、国の未来を切り開く最良の手段として認知されていたことがわかる。
▽63 政治資金の仕掛人との嫌疑で逮捕された松根に松永は「人間は死ぬような病気の経験もなく、命がけの恋愛もせず、くさい飯をくったことがないのでは大した人間にはなれぬ。君は願ってもない経験をしたのだ」と言った。それがどんな過酷なことであれ、命がけの人生体験こそが、人間の血肉になるものだという哲学を、松永は一貫して持っていた。
▽66 「国営の下に役人どもが電気事業をやってもうまくいくはずがないが、さらに肝心なことは民営でなければ大きな人物が育たない。軍部政権ができたら、必ず電力国営を持ち出してくるだろう……」と米国人の友人。松永は首相の近衛に「あなたたちは、大きな戦争をするつもりで電力事業を国営にしようと考えているのだろうが、それは、国をあやまらせることになるのではないか」と言い放ち、軍の怒りを買ったこともある。
▽79 戦後、日本電気産業労働組合(電産)は、官僚統制の撤廃と、発送電事業の全国一元化を経営陣に要求。……GHQは7ブロック案。
▽83 GHQの案では、分割された民間会社が「発送電分離」となっていた。発送電一体は産業の独占を許さない集中排除に引っかかる。あくまでGHQは「分離」 にこだわり松永案を認めようとしなかった
▽86 政府審議会で事務局のお膳立てを松永が拒否。「君らは用事があるときにこちらから呼ぶから、以後わしが申しつけぬ書類を出したり、発言することを禁ずる」
▽97 国会では、社会党や共産党の野党のほうが、国家管理にこだわっているのが興味深い。発送電一体による私企業独占を心配しているわけだ。
▽108 木川田は、終戦直後、労働組合運動のリーダーとして立ちはだかった電産と、激しく渡り合った。「わたくしの会社のある支店長のごときは、非民主的と呼ばれて、組合幹部の前に土下座してあやまらされるといった暴挙が随所に行われた。経営権を守るどころか、経営側の人格は完全に蔑視される有様であった」……しかし、組合の罵声と停電ストの中、「労働大衆の理性に対する信頼を失うことはなかった」という記述には、木川田という人物の大きさを感じざるをえない。
▽120
▽134 1971年、97歳で松永は大往生。遺書に、「死後一切の葬儀、法要はうずくの出るほど嫌いにこれあり、墓碑一切、法要一切が不要。線香類も嫌い。
死んで勲章位階これはヘドが出るほど嫌いに候。
財産は倅および遺族に一切くれてはいかぬ。彼らが堕落するだけです」
▽140 日本の原子力開発は、初っ端から官僚機構と電力会社の陣取り合戦の材料にされた結果、当の「怪物」に対する慎重な論議、警戒が、軽んじられたきらいがある。
木川田のパートナーというべき「日本原子力産業会議」の代表常任理事だった橋本清之助「私たちが、原子力の開発に確信が持てるのは、それは現在、原子力に対する強い反対と批判が存在するためです。あるいは、奇異に受けとられるかもしれませんが、この原子力に向けられている批判、非難、反対こそが、私たちの努力の、いわば道標になっているといえます」(ここまで言える人がいなくなった。反対=敵=監視対象、になり反対派がいなくなった伊方〓)
▽144 資金のやりくりに四苦八苦する日本原子力発電に、再び、国家資金を導入してはどうかと通産省が持ちかけてきた。通産官僚は、このままでは高度成長を目指す日本経済に支障をきたすという大義名分を持ち出し、軽水炉導入の主導権を電力会社から再び国に移そうと画策したのである。これは絶対阻止せねばならない。木川田は、福島への軽水炉導入を急いだ。
▽146 1974年、献金反対にからんだ「電気代1円不払い運動」が広がり、木川田は、政治献金を廃止することを決断し……
▽149 平岩はなぜ、木川田精神を裏切るような経営方針に切り替えたのか。電力会社が原発という悪魔を抱えたせいなのか。あるいは独占企業の傲慢さがそうさせたのか。いずれにせよ、福島第一原発の過酷な事故は、平岩に端を発していると私は見る。
(批判を許さぬ、受け入れぬ体質へ〓)
木川田らにあって、平岩や今の9電力社長たちには決定的にないものがある。それは国家との闘争の歴史と、民間が主導する電力で日本を豊かにするのだという気概、そして企業の社会的責任への自覚というものである。
▽150 平岩が東電・財界の実権を握るようになったとたん、原子力開発の主導権を、簡単に通産省に譲り渡してしまう。平岩が社長になったのが1976年、その翌年に木川田は亡くなっている。
国会の介入を断固拒否して、企業の主体性を守る、という木川田の「攻め」の経営から、リスクをなるべく低くするという「守り」の体制に方向転換した。
▽153 平岩の時代から国と手を結んだ電力会社は、天下りを常態化させ、政治にも役所にも学界にも電力会社の息のかかった人間を送り込み、政官学業の鉄板の体制をつくった。平岩が政治の世界に送り込んだ人間が加納時男〓で、加納は事故を起こした今も「東電をつぶしたら株主の資産が減ってしまう」「低線量の放射線はむしろ体にいい」と非常識なことを言って、原子力を堂々と推進しようとしている。
▽154 平岩の変質は易きに流れ、電力会社から「国家との緊張関係」と「企業の社会的責任」を失わせた。電力会社対国家という対立構造があったからこそ、その緊張関係が「企業の社会的責任」を育てたという側面もあったのだ。(反原発運動があったから安全が担保された〓その力が弱まったとき最悪の事故が)
役所との緊張関係を失った電力会社は、役所以上の役所になってしまった。地域独占、総括原価方式、発送電一体という三つの特権をほしいままにし、一人勝ちをつづけてきた。……原発という「怪物」の安全審査をする原子力安全・保安院の委員が、許可を申請する電力会社側とつながっている、あるいは同一人物などということが平然と行われてきた。
松永は「役人に電力会社を運営できるわけがない」と喝破したが、日発がガタガタになったことで証明された。経営というのはダイナミックなもので、動態的な思考方法ができない役人には所詮無理なのである。そういう奴らを電力事業に取り込んだことが平岩の失敗であった。官僚の思考パターンというのは、組織の維持や拡張しか考えてないといってよい。だから天下り機関をいくらでもつくりたがる。松永や木川田は、そうした官僚の本質をとっくに見抜いていた。
▽156 原発の国有化がいわれているが……こういう事態になっても、官僚というものは反省などしない人種なのである。東電はおそらく彼らが残すだろう。
ただひとつ希望を感じるのは、国家対電力という対立構造が失われた今、原発政策をめぐって「中央」対「地方」という対立構造が見え始めていることだ。山形の吉村知事、滋賀の嘉田知事などが「脱原発」「卒原発」を宣言しはじめている。一度は原発ムラに組みしかれた地方が反撃を開始したということである。
▽160 前福島県知事の佐藤栄佐久は、コミュニティを大事にする政策を打ち出す。「合併する市町村もしない市町村も同じく支援する」姿勢で臨んだ。この姿勢から、国策として原発を押しつけ、安全を無視した事故隠し等をする東電と対決していくことになる。
▽162 ……東京地検に「国策逮捕」された。松沢・神奈川知事が「憲法改正と地方自治」を論じる研究会を設けるよう提案し、道州制を主張したとき、「いま、憲法改正を議論すべきではない。憲法には地方自治の理念はしっかり書いてある。道州制は地方自治にとってマイナスに作用し、権限を渡したくない国に利用される」と反論したそうです。
〓宮城県の市民運動家の沖田〓夫さんが、町村合併が震災の被害の把握と復興を遅らせていると嘆いていました。
▽169 勝俣の答弁で一番腹が立ったのは「計画停電」である。地域独占で供給責任を負う電力会社が軽々に使っていい言葉ではない。独占を放棄するか、社長のクビを差し出さなければ使えない言葉であるはずなのに、メディアも無感覚に使う。


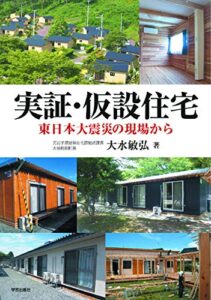
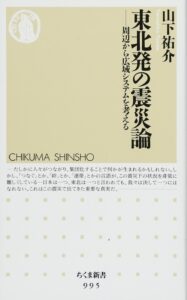

コメント