■ちくま新書240625
東日本大震災から2年後の本。筆者は2011年4月まで、弘前大におり、その後東京の大学に移って、被災地を歩いてきた。
<広域システム>と<中心ー周辺>の問題こそが震災であらわになったとする。原発事故にそれが典型的にあらわれた。
自然災害では、安全確保の主体は地方自治体であり、情報はまず自治体に通報される。 原子力災害の主体は国と事業者だ。事業者→国→自治体→住民という順になる。だが実際は、最初の避難指示は、各役場にさえとどかず、事故を知ったのはテレビを通じてだった。
SPEEDIの情報が流れなかったのは、情報を吟味し知らせる主体を欠いていたからだ。情報を住民に流す決定をだれがくだすのかもあやふやだった。官邸でも当時、SPEEDIが何なのかさえわからずにいた。システムが巨大で複雑すぎて、壊れてしまうと人間の手には負えなかった。その結果、現場から遠く離れた首相が最終判断をくだすことになった。政府の不手際というより、そもそも対処不能だったのだ。
巨大発電所にたよる電力、大規模な水道網……など、広域システムに頼り切った生活のもろさが浮き彫りになったはずなのに、復興の過程ではシステムをさらに強化する方向にむいている。
各地の復興は、それぞれの事情にあうかたちで進められるべきだ。1000年に一度の津波ならば、これを最大値として、逃げたり避けたりする「減災」も選択肢なのに、「国の復興財源には限りがある。気仙沼だけ住民全員の合意を待ち、取り残されることがあってはならない」と知事があおり、「復興を急げ」という一部の「住民の声」に後押しされ、巨大防潮堤と高台移転、広大な土地のかさ上げという巨大ハード事業だけが強行され、海辺の暮らしは認められないというかたちになってきた。
暮らしの視点や周辺の視点が押しやられ、全体をみわたす射程をもたない「中心」の視点で決定されてきた。しかもその決定は、だれかが主体的に決めたのではなく、システムが動いていつの間にかそうなってしまった。経済なら経済、公的機関なら公的機関のそれぞれの中心はあるが、いざという時、そのシステムを動かす最終的は主体(中心)がなかった。
原発事故の避難者から見た解決スキームも、まず第1に、崩壊した人生設計をたてなおす生活再建、第2に地域再生、第3に心身の健康問題であるべきなのに、「賠償」と除染ですまそうとしている。
<中心ー周辺>の呪縛は、自治体間の支援の弊害にもなった。多くの市町村が、上位機関の県の調整や指示をひたすら待っていた。
若者が都市(中心)に集まり、その子や孫の世代は、もはや田舎(周辺)を知らない。周辺を理解しない人々が、周辺にとって重要な決定をくだす時代になってきた。地方への補助金は、かつては「仕送り」だったが、今は「ムダ」とされる。一票の格差問題は、バランスの悪い人口配置を元にもどす議論をすべきなのに、「都市住民が損をしている」としか見なくなってきた。
周辺(地方)から中心はよく見えるが、中心から周辺は見えない。すり鉢の真ん中と縁のような関係だ。首都圏にいる地方出身者は日本という国を実感するが、いまや大半を占める首都圏出身者は大量の情報のなかにいるのに身近な暮らししか知らない。地方を知らない人間が集まる首都ですべてが決められている。
中心にはシステムを動かす主体性はないが、中心は周辺を切り捨てることができる。東北でも、被災自治体の再編統合を叫ぶ人がでてきた。能登半島地震でも「集落再編」「漁港再編」などと都市住民が言いだしている。<中心ー周辺>関係が浮き彫りになってきた。
昭和の大合併までは、より大きなものへの小さなものの下位化(疑似親子化)であり、合併前の単位を基本的に温存し自治を維持したが、平成の合併は、効率の悪い小自治体を解消し、国のシステムを効率化(巨大システム化)することが目的とされた。合併された小地区の自治は淘汰された。
「限界集落」論も同じ流れにある。「高齢化率50%以上」という数字でムラあつかい、どうせなくなるのだから早く消えたらよいという議論が、一定の世論を構成するようになってきた。
地域レベルを見ると、1980年代まで地域の「中心」だった中心商店街が90年代に衰退した。「周辺のなかの中心」が消え、周辺は「中心」の草刈場になってしまった。
東日本大震災は、広域システムの問題をあらわにしたのだから、国家・経済大国・科学という中心的価値に対し、地方主権・暮らし・生活の知恵といった周辺的な復権こそがとえられるべきだった。国民全体で、長期・広域にわたる支援体制を確立し、時間はかかっても着実な復興が実現できるよう、見通しを示すべきだった。だが実際は、広域システムは地道な復興を阻害し、急がせ、場合によってはその基盤をも破壊するものとなってきた。能登の場合は「長期の支援体制」どころか、わずか半年で忘れられようとしている。
東日本大震災の復興への動きは阪神大震災に比べて極端に遅かった。阪神では、仮設住宅ができはじめ、緊急避難期から復旧期へと舵が切られたのが地震発生2カ月半後だった。東日本では、発災から半年2011年8月ごろようやくこの時期になった。災害の規模の差が要因のひとつとされた。だが能登半島地震は東日本よりははるかに小規模なのに、東日本大震災よりもさらに復興のペースは遅い。また東日本について「半年のあいだに被災地以外は平静へと押し戻されてしまった」と筆者はしるすが、能登半島地震はわずか2,3カ月でメディアから消えた。
発災3カ月のボランティア数は阪神は延べ約117万人。東日本の岩手・宮城・福島の災害ボランティアセンターを通じて活動した数は3カ月半で約48万3000人で「ボランティア失速」と報道された。2016年の熊本地震は、ボランティアセンターなどを通じて活動した人は約10万人だった。一方、能登半島地震では3カ月でわずか1万4453人(県集計)だ。
阪神にくらべ東日本のボランティアは「パターナリズム」の問題が出た。効率的に支援活動が進んだ反面、参加する個人や被災地周辺の小さな活動が周辺化してしまった。 田舎の生活を知らない者が多く、被災現場へ行くことをおそれるためか、活動のパターン化も見られた。
能登半島地震の石川県が管理する官製ボランティアはそれに輪をかけて、役所の下請け無賃労働者化してしまっている。
今後、首都直下地震、東海・東南海・南海の地震が予想され、これらが一体となった南海トラフ地震では最悪死者32万人と想定されている。原発事故のさらなる展開、経済メルトダウン、地方地域経済破綻の可能性といった予言は、経済再成長や夢の新エネルギーといった希望の予言よりはるかに真実味を帯びてきた。発展の時代から破局リスクの時代に足をふみこんでいる。
「主体」が見えない広域システム、<中心-周辺>の構造をこのままにしておけば破局は避けられない。広域システムの際限ない合理化に抗するには、日本社会では、「個人」ではなく、小さな共同体の意志としての主体性、社会的主体性をはぐくむ必要がある。そのためには人々がつながり、集団化しなければならない。「ムラ」の再生、ということだろう。
「東北の地は、そうした旧くて新しい社会形成のための実験場として再生しなければならない」
この結論はそのまま能登にもあてはまる。
=================
▽16 阪神大震災と比べても、復興に向けた動きは極端に遅い。
阪神では、仮設住宅ができはじめ、緊急避難期から復旧期へと大きく舵が切られたのが、地震発生から2カ月半後だった。東日本では、発災から半年、2011年8月頃になってようやくこの時期に追いついた。倍の時間がかかっている。
被災地以外の場所では、この間にいつしか平静へと押し戻されてしまったかのようだ。
▽26 <中心ー周辺>システムのもつ矛盾のあわわれこそが、震災で見えてきた大きな課題である。国家・経済大国・科学という中心的価値に対し、地方主権・暮らし・生活の知恵といった周辺的な復権こそが求められるべきもののはずだ。
▽34 原発事故こそ、広域システム構造=<中心ー周辺>
▽38 原発立地の自治体だけが唯一、十分な財政を確保し、少子高齢化問題を克服してきたかに見えていた。3世代、4世代の幸せな家族の暮らしが実現されてきた。(大熊町 ますみさん)
▽41 広域システムを動かしている主体は何なのか。中心は
全体にとっての中心ではなく、経済なら経済、公的機関なら公的機関のそれぞれの中心にすぎない。いざという時には、そのシステムを動かす主体のないシステム。」……さらに、中心にはシステムを動かす主体性はないが、中心は周辺を切り捨てることができる、ということである。
……被災自治体の再編統合が、深い考えもなく、人々の口から漏れ聞こえてくることが、切り捨て問題にかかわる<中心ー周辺>関係をよく表している。(〓能登でも「集落再編」。漁港再編)
▽46 2011年春、津軽から野田へ。渥美公秀(大阪大学教授)は、災害ボランティア研究で、もっとも秀逸な研究と実践をおこなっている社会心理学者である。災害対応カード教材「防災クロスロード」で有名な矢守克也(京大防災研究書)
▽55 弘前は野田村という身の丈にあった対象を設定できたので、4月に入ると毎週のようにボランティアバスが通うように。
そうした作戦をたてられる社会構造と集合意識が弘前にはあった……「新しくねぷたをつくったようだね」……震災を機に、新しいねぷたを市民と行政で無我夢中のうちにつくりあげたような気がしたわいけだ。
……社会的な主体性がある。
▽59 普段は見えないが、それぞれに社会的なまとまりをもっている。それは、小さな村のみならず、都市住民を集団化したり、さらには市町村を超える規模であらわれたりする。
個人の主体を問うよりも、社会のなかのどこに主体がひそんでいるのか、さぐっていく方が建設的なようだ。
▽62 弘前市は、市民が動いたことを優先して、支援の実施先を早いうちに決定した。……ほかでは、<中心ー周辺>の呪縛が、非常事態にもかかわらず、広く観察された。社会性は、主体性を紡ぐばかりではなく、削ぐものでもありうる。(都道府県が支援を調整。多くの市町村では、上位機関の県の調整や指示をひたすら待っていたようだ=能登はさらに)
▽68 大槌町 町長以下、職員33人が死亡。
▽77 津波遡上高の高い岩手県北部よりも、遡上高が比較的低い岩手・宮城県境に被害が集中し、さらに宮城県中南部で波の高さに比して人的被害が非常に大きくなっている……
▽85 自治体が回復しないまま復旧・復興がすすむと、大手コンサルが描く形式だけのものになりかねない。
さらに平成の合併で自治体消滅が災害前に起こっていたところもあり、復興に大きなマイナスの作用を及ぼしている。
▽94 津波常襲地帯では常識といえるような避難さえ実現していなかった。……物理的な衝撃は三陸の被災地に比べれば小さいものの、災害文化の蓄積がとぼしく、避難行動にもそれが反映されてしまい、人的被害が大きくなってしまった。宮城県各町村の犠牲者の多さは、岩手県のそれとは性格のちがうもののようだ。都市性・郊外性に結びつけて考えるのが適切なようだ。
▽106 蝦夷の末裔を名のる安倍頼時が衣川に拠点を構え……安部氏の系譜をついだ奥州藤原氏が、頼朝によって滅亡させられて、最終的に蝦夷社会が和人社会に組みこまれる。
▽131 1970から80年代は、各都市の中心商店街が人口中心地帯であったのにたいし、90年代までには郊外が人口・利益のほとんどを吸収するようになった。……80年代までは、中心と周辺はまだ別々であり、周辺の側にもまだ中心をつかう主体性があった。90年代からの周辺は中心の積極的収奪活動の舞台として位置づけられそうだ。
▽135 若い世代ほど中心に集まるようになり、周辺について十分な認識のない人々が、周辺にとって重要な決定をくだす事態が現れてくる。一票の格差の問題は、本来は、バランスの悪い人口配置状況を元にもどすべく議論すべきだったのが、世代が変わると数のアンバランスしか見えなくなってきた〓。(なるほど、仕送り感覚と「実家」が消えた)
▽143 若い研究者による広域避難者への追跡合同調査をスタート「社会学広域避難研究会」「見えない避難を見えるものにしていこう」。富岡を舞台に。
▽149 原子力災害の最初の主体は、国と事業者。事業者→国→自治体→住民となる。
従来の災害は、災害の情報は、まずは地方自治体に通報されなければならない。自然災害においては、安全確保の責任主体は地方自治体である。
(なのに避難路は国の責任になっておらず、規制委の審査対象にもならない〓)
▽155 SPEEDI 情報を住民に流すとして、その手段は何だったのか、決定はだれが行うべきだったのか。そもそも最初の避難指示が、住民にも、各役場にさえ届いていない。事故を知ったのはみなテレビを通じてである。
官邸でも当時、SPEEDIが何なのかさえわからずにいたのが実態らしい。
……システムが複雑すぎて、壊れてしまうと人間の手には負えなかった。……結果として、現地の人間でもなく、現場から遠く離れた首相が最終判断を下すことになった。
……政府の対応には批判するべきものもあるだろうが、その前に、もともと不可能なことをやっていると理解する必要がありそうだ。
▽159 原発はあくまで危険がなく 住民は安全神話を信じていたのではなく、安全を一方的に押しつけられ、強要されていた。「安全詐欺」というべきものだ。
▽167 周辺から中心はよく見えるのだが、中心からは周辺は見えない。すり鉢の真ん中と縁のようなもので……(能登の実態が見えないからトンチンカンな施策が)
首都圏にいる地方出身者は日本という国を実感しているが、首都圏出身者は大量の情報のなかにいるにもかかわらず、ごく身近な暮らししか知らない。だがその首都圏の真ん中で、すべて国のことは決められている。
▽175 仮設住宅に暮らす高齢者の声が一番目につくものとなり、……若い世代は声を出せずにいる。
……原発事故によって、あらゆる産業が成り立たなくなった今、事故処理以外の仕事は失われている。人々は東電との関係を抜きにもはや暮らすことはできなくなってしまった。まさに原発一色に。
脱原発に親和性があるのは、自主避難者や、ごく一部の強制避難者のみだ。多くは、しばしば隠れるように避難をつづけている。
▽183 避難者の立場から見た本来の解決スキームは、まずは生活再建である。賠償とはイコールではない。崩壊してしまった人生設計を、どんなものへ再現していくのか。第2に地域再生である。第3に心身の健康問題。これら3つは、国が示している対策ではとけない。
……二重住民票の必要性も提唱。
▽187 リスクとつきあうということは「分からない」事態と付きあうということ。だが科学は「分かったこと」の記述にのみ専念し、エビデンスのあることだけが、科学であるかのようにふるまってきた。「分からない」領域まで「分かったこと」ですべて埋め尽くし、過去の経験のみから未来を決定しようとしてきた。そして結局、未来のリスクをもみつぶし、現在の安全のみが強調されて、以前と同じ状況に陥りつつあるようだ。
▽195 阪神では仮設住宅ができるまでに約2カ月かかったのに対し、東日本では6カ月かかっている。もちろんここには災害の規模の差がある。加えて、1995年はまだバブル崩壊後で、経済の余力もあった。
……広域システムの回復には時間がかかる。だから時間がかかっていること自体は、仕方のないことだ。重要なのは、国民全体でこの事態をしっかり受け止め、長期・広域にわたる支援体制を確立し、時間はかかっても着実な復興が実現できるよう、見通しを示してあげることだ。
だが現実には、広域システムは、地道な復興を阻害し、急がせ、場合によってはその基盤をも破壊するものとなっているようだ。
▽205 旧石巻市の市街地……ほぼ全域浸水。平地の都市型津波災害の様相。波そのものの高さは三陸リアス式の沿岸ほどでもなく、建物も多くが残っているが、平地のため広く冠水。死者・行方不明者2500人。
市街地以外でも、……北上川河口に広がる住宅街が広く流された。そのなかに74人の犠牲者を出した大川小学校がある。
▽210 各地の復興は、それぞれの事情にあうかたちで進められるべきなのに、防潮堤プラス高台移転ですべて決定されていく復興計画には識者の間から早くから反発の声が上がっていた。(室崎益輝「「高台移転」は誤りだ」など)
▽217 「国の復興財源には限りがある。気仙沼だけ住民全員の合意を待ち、取り残されることがあってはならない」知事の発言。
「復興を急げ」「行政はなにをやっているんだ」という住民の声。……とりあげられる声は、目立つ声。仮設住宅の人々の声であり、地域権力構造にしっかりとコミットしている人々の声である。後者には公共事業とつながっている人が多い。
▽218 1000年に一度の津波であれば、これを最大値として、逃げたり避けたりする防災(減災)も射程に入れられる。巨大防潮堤や高台移転だけが、人の命を救う唯一の選択肢ではない。
▽222 今回の震災では、暮らしの視点、周辺の視点が脇へ押しやられ、中心の視点がつねに決定をリードしている。しかもその中心の視点は、全体を広く適切に見渡す射程をもっているわけではなく、むしろ様々な次元に多様に分極化して、実はきわめて限られたものでしかないようだ。(都会人は周辺を理解できなくなった人々〓)
▽223 阪神のボランティアは130万人、東日本は2012年11月現在92万人。2011年5月のゴールデンウィークには、その後半に人員が急激に減りはじめ、「ボランティア失速」が報道された。
しかし格段の進歩も。救援物資の量も膨大。阪神の経験がある関西広域連合は、早くから複数県で被災地を分担して支援に入った。体系的に整備された。
▽226 阪神とくれべても……その規模は小さなものではない。
……「足湯」の活動。足のマッサージをすることはもちろんのこと、そこでの会話から本音を引き出すことができるのが特長。この活動は、2004年の中越地震のときに開発されたもので……。
▽232 ボランティアのパターナリズム
第1に中心に対する周辺の従順主義。これによって効率的に支援活動が進んだ反面、参加する個人や被災地周辺の小さな活動が、周辺化してしまった可能性がある。
第2に、活動のパターン化。田舎の生活を知らない者が多く、さらに被害の大きさが、現場の人々とのコミュニケーションを阻害した。今回ほど、被災現場へ行くことへの怖れ、被災者と交流するよりは、まずは確実に役立つことをしようという思考法が働いたことも、活動のパターン化を強く導いた要因と思われる。
(能登の官製ボランティアはさらにひどい〓県がしきる)
▽250 広域システムが解体するような危機が訪れると、システムが大きく複雑すぎるために、個々の人間には手に負えない事態に陥る。
……システムに頼り切った生活の脆さを人々に垣間見せた。しかし、システムの本質を反省し、改善するよりはむしろ、崩壊後の再建においてそのシステムをさらに強化する選択肢をとりつつあるようだ。
▽253 巨大防潮堤と高台移転、広大な土地のかさ上げという、巨大ハード事業のみを結実して、もはや防災システムの前に海辺の暮らしは一切認められないというかたちへと進んでいる。しかもこれだけの大きな決定にもかかわらず、誰かが中心になって主体的に決めているのではなく、システムが動いていつの間にかそうなっているにすぎない。
▽257 平成の合併は、効率の悪い小規模自治体を解消し、国のシステムをより効率化するための操作として遂行された。昭和の合併までは、自治を維持し、合併前の単位を基本的に温存するものだったのに対し、平成の合併では、しばしば小さな単位の完全解消がイメージされて、合併された自治体の自治の淘汰が目された。
同じような解消・淘汰型の再編は、限界集落問題のなかにもイメージされていた。……2000年代の社会変動は……小さな国のより大きな国への吸収である。以前の再編が、より大きなものへの小さなものの下位化(疑似親子化)であったとすると、平成の合併は、小さな国としての自治体機構の解体と、そのかわりにあらわれる巨大なシステム化を意味していた。
▽264 明治期前までの支配は土地の統制だった。土地管理や収穫物の管理ほどには人間そのものの管理に強い関心はなかった。
明治以降、西欧にならって人口を管理してきた。それでも戸籍は家単位であり、個人を直接統制するのではなく、家を統制することで、個人の統制は事足りていた。
戦後、戸籍は夫婦単位になった。こうした家から個人への移行を、我々は集団主義からの個人の解放として理解してきた。しかしそれは……国家と個人の間に中間項がなくなる。……個人に直接、統治が及ぶようになると、個人と国家が直接向き合う関係になる。
▽266 限界集落論も、高齢化率50%以上という数字でムラを扱う論理だ。ムラを数で勘定して、どうせなくなるのだから早く消えたえもらったらという議論が、実際のムラの暮らしを知らないままに、世論の一部を構成してきた。
▽269 三陸の津波常襲地帯では、津波伝承が避難誘導において機能し、多くの人が逃げている。本来は復興にむけて様々な論点を比較考量する必要があるのだが、「あなたのためだから」と強引に復興の未来図が技術的問題に回収されてしまう。
▽271 巨大システムには本当の中心がない。内部は様々に分化し、どの中心も、それぞれの領域内での中心であって、どこからも全体が見えてない。各システムの中には中心と周辺はあるが、全体の中心=中核はない。
▽272 絶対的な神の存在があるから個人として主体になりうる。日本人にはこの絶対的で合理的な世界がない。日本人に個としての主体性がないのは、文化の差。
日本社会のなかの主体性とはなにか。それは小さな共同体の意志。
個の主体性に対する社会的主体性。共同体的主体性。
▽275 我々は個になったとたん、無力化する文化のなかにいる。重要なことは、人々がつながり、集団化することにある。
▽279 本番はこれからだ。首都直下地震、東海・東南海・南海の地震。これらが一体となった南海トラフ地震では最悪で死者32万人と想定されている。
原発事故のさらなる展開、経済メルトダウン、地方地域社会や地域経済破綻の可能性……が我々のシステムには予言されている。経済の再成長や夢のようなエネルギー供給システムといった希望ある予言よりは、社会の破局を展望する予言のほうが、真実味を帯びてきた。 発展の時代から、破局リスクの時代へ。
▽280 未来に対する負の予言に抗する知、広域システムの際限ない合理化に抗する知は、時間と空間、心と社会を、西洋近代とは根本からちがうところでとらえ直すことで生まれてくるだろう。
……東北の地は、そうした旧くて新しい社会形成のための実験場として再生しなければならない。





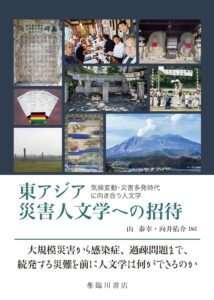

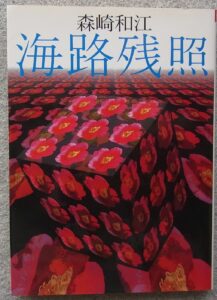
コメント