「まちで生きる、まちが変わる つくば自立生活センターほにゃらの挑戦」(柴田大輔、夕書房)の著者と登場人物が「自立生活はだれにでもできる」をテーマに語りあうシンポジウムが東京で開かれた。
1990年代に、筑波の学生だった障がい者の活動からはじまった「ほにゃら」の話は「自立」とはなにかを鋭く突きつける。
自立生活とは「自分が決める」こと。自分がやりたいことを介助者に伝えて実現することだ。
「自立生活」におけるヘルパーとふつうのヘルパーとちがうのは、「指示をうけて行動する」こと。気を効かして先回りしてはならない。
ヘルパーを利用する際、「自分で決めてそれを伝える」というのは実は大変だ。
髪型とか着たい洋服とか、ズボンをどっちの足から履くとか、どのおかずを最初に食べるとか……すべて言葉で伝えなければならない。
介助者がやってしまったほうがはやい場合でも、先回りせず、信じて、待つ。ときにはイライラして相手の悪いところばかり見えてしまうこともある。
高齢者介護のヘルパーでは、「まちがい」を極力避ける。自立生活でのヘルパーは、お互い失敗は織り込み済みで「失敗して、試行錯誤すればよい」と考える。
「ほにゃら」の代表の女性は、福井県育ちで、家から出たくて、筑波の大学院に進学した。自立生活センターの助けをかりて半年かけて準備して一人暮らしを実現した。最近結婚もした。
「好きなときに寝て,好きなときに起きて、夜中にコンビニにいけるのが楽しい!」と言う。そっか、夜中のコンビニかぁ。
趣味はKinKi Kidsの追っかけ。
24時間のヘルパーがついていて、入浴時は2人が介助する。
「デート中もヘルパーさんがついてきます」と言って会場を笑わせた。
「障がい者運動」というと、まじめな人しかとりくめない印象があるけど、柴田さんは「楽しいから」つづけているという。「ほにゃら」の女性のかわいい発言を聴いていると、どんな障害があっても自立生活は可能であり、そうすることで、本人の幸せだけでなく、周囲に明るさと生きる力をもたらすのかもしれないなぁと思った。
目次





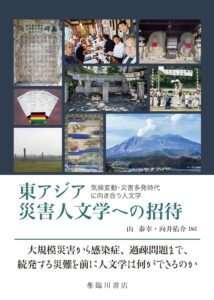


コメント