「日本、美のるつぼ」を見に京都国立博物館へ。行列ができているから迷ったが、待ち時間は20分程度というからならんだ。2000円。
最初は目玉は、葛飾北斎の富嶽三十六景や国宝の「風神雷神図」
明治政府は、日本を美術や歴史をもつ「文明国」だとしめすため万博に参加し、美術工芸品や文化の発信に力をいれた。フランス語で「日本美術史」も出版した。
1873年のウィーン万博には、漆器や陶磁器などの美術工芸品や、山梨県御嶽神社の御神宝水晶玉、鎌倉鶴岡八幡宮の北条政子の遺品の手箱や源頼朝の太刀、正倉院宝物などが出品された。ところがこれらをのせて帰国の途についた船ニール号が1873年、南伊豆沖で座礁・沈没してしまう。
翌年、宝物の一部がひきあげられた際、漆器の蒔絵の保存状態がよかったことから、豪華客船で蒔絵がつかわれるようになった。
葛飾北斎は江戸時代はそれほど知られていなかったが、モネ、ドガ、ゴッホ、ゴーギャンらが激賞することで、ジャポニズムとして一気に世界で評価された。19世紀末のパリでは月刊誌「Le Japon Artique」(芸術の日本)が刊行された。
国宝の「風神雷神図」もまた、明治以降に評価されるようになった。
「琳派」という言葉は、近代国民国家として「伝統の創出」のためにつくられた概念だという。
(当初は「光琳派」という呼称は当時の現代作家をしめした。明治中期に欧化主義がおとろえ、アーネスト・フェノロサや岡倉天心によって日本美術が再評価されるようになって刊行された本が「琳派」像形成に影響をあたえた)
海外の目によって作品が評価され、海外の目を気にして「伝統」がつくられていたというのが興味深い。
次に、古代から順に、海外とのかかわりをたどっていく。
三種の神器である剣・鏡・勾玉は、弥生時代から国産される。高松塚古墳の壁画(模写)は中国の影響が色濃い。中国では中東からもたらされたラクダの像なども出土している。
遣唐使の時代になると仏教美術がはいってくる。絵入りの経典は漫画的でかわいい。9世紀の円仁の旅行記「入唐求法巡礼行記」(国宝)の本物が展示されているのにはおどろいた。
鎌倉時代は禅宗がもたらされる。雪舟も遣明船にのり、中国の影響をうけて山水画をえがいた。
中国の銅鏡を換骨奪胎して和製銅鏡をつくりあげたり、割れた椀を金つぎでつなぎあわせたものに「美」をみる文化は、今につながる。漆器がわれてそれを修理したあとはなんともいえないあたたかみがかんじられる。「もったいない」はアートになりうるのだ。

大航海時代になると「唐物」は「舶来品」の意味になり、東南アジアやベネチアのものも「唐物」とされた。十字架のはいった家の瓦や「尾張まりあ」墓碑、「南蛮式具足」、フェンシングでつかうような西洋式の剣などもある。
液体をいれる角徳利の蓋のネジを切る技術は、ポルトガル人がもたらした小銃の尾栓から学んだ最新技術だったという。
17から18世紀にかけてはグローバル化で生産地が多元化する。世界地図の屏風は、新たな世界認識を日本人にもたらした。逆にヨーロッパの宮殿に伊万里焼や蒔絵のコーヒーカップなどが輸出された。
明末・清初の動乱時代には、多くの中国人が日本に逃げてきた。江戸初期に来日した黄檗宗の開祖・隠元隆琦はインゲン豆や明朝体、原稿用紙などをもってきた。
海外とのかかわりのなかで「日本の美」をうきあがらせる、という切り口が斬新でおもしろかった。






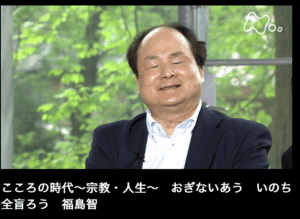

コメント