■臨川書店2505
京大人文研の共同研究班「東アジア災害人文学の構築」の中間報告。
「津波てんでんこ」「地震がきたら竹藪に逃げろ」といった言い伝えや、慰霊碑や追悼碑などの「災害遺産」を研究する「人文学」も、災害時に役立つのではないかという問題意識ではじまったという。
まず、人間がどう「自然」と対峙してきたかの歴史がおもしろい。
ルネサンス期のローマの庭園は「自然の美を殺す人工の支配」が特徴で、近代のイギリス庭園は「自然のままの風景を一定の形に入れたもの」だった。日本の庭園は、「自然のまま」ではなく、無秩序な自然からまとまりをつくりだそうとする。自然をケア(看護)することで「自然」を維持するという考えは、環境破壊にともなう災害への対応に生かせるという。
1755年のリスボン大地震は「神はなぜこんな思いをさせるのか」と、キリスト教信仰にたいする懐疑をもたらした。「地震は天罰」という説も流布した。
カントは、ペルーやチリの住宅の、2階は軽い木材でつくるという工夫を例示してリスボンの防災対策の誤りを指摘。「人間は自然に順応することを学ばなければならないのに、自然が人間に順応してくれるように望んでいる」と書いた。また、地震が温泉や鉱石層の形成、植物への栄養供給をもたらすことをあげて、「地震は天罰」とする主張は「人間は神の配在の唯一の目的だとうぬぼれている」と、人間中心主義を批判した。
こうしたカントの考え方を「相地の学」として具体化したのが寺田寅彦の風土論だった。
昔は人間は自然に従順で過去の経験に学んでいたが、科学の発展とともに自然を克服しようとした。しかし関東大震災では「過去の地震や風害にたえたような場所にのみ集落を保存し、時の試練にたえたような建築様式のみを墨守」した。「20世紀の文明という空虚な名をたのんで、安政の昔の経験を馬鹿にした東京は大正12年の地震で焼き払われたのである」
西洋という一地域に生まれた「分析科学」を無批判的に日本の風土に応用したことが関東大震災の悲劇の理由だと寺田は指摘し、「分析科学」によって分断された人間と自然との関係を「相地の学」の観点から修復するべきだと考えた。「自然に順応することを学ばねばならない」というカントと同じだ。
「風景」とは客観的に「ある」ものではなく、特定の時間と場所において特定のものとしてあらわれる。近世から近代のヨーロッパでは、森が風景の代表だった。中世以前は森は恐れと畏怖の対象だった。
日本の縄文時代以前のカミは個々の動植物や出来事そのものだった。弥生時代になるとカミが抽象化され、そのカミを具体化するため、依り代やカミが宿る場所が必要とされた。古代や中世では、人は風景を自然物としては見ず、カミを見ていた。
「風景が壊れるとわたしが壊れる」感覚は、イエやムラという共同体の存続に価値をおく文化から生まれた。
近代の思想は主観と客観をわけるデュアリズム(二元論)だが、日本の西田幾多郎や和辻哲郎もモニズム(一元論)を唱えた。和辻は、風土とは、外部にあって人間に影響を与えるものではなく、わたしのありかたそのものが風土だとした。
住みなれた町からひきはなされて「わたしが壊れてしまう」のは、認知症の悪化や孤独死などにあらわれる。風景とその人をつながった連続体としてとらえる視点があれば、従来とはちがった復興の道筋が見えるかもしれない、という。
図書館や学校、公園など人びとが自由につどう場が充実している地域は、熱波などの災害でも生存率が高く、住民の平均寿命が長い、という研究があるとははじめて知った。
災害時はさらに他者との対話が重要になる。仮設住宅で集会所が不可欠である所以だ。
平時に「哲学カフェ」をひらくと、地域に潜在している「地元地知識人」があつまってくる。まちづくりが活発な地域には、地域の内部と外部を媒介し、有益な情報や知識、資金などを外部から調達する担い手が存在する。「媒介的知識人」をとおして外部の専門家や支援者と協働することで道が切り開かれることが多い。
平時も災害時も必要な要素はそれほどかわらないのだ。
====
▽序章 山泰幸
京大人文研の共同研究班「東アジア災害人文学の構築」の成果の一部をまとめた書籍。
災害に対応するために生みだされ、蓄積されてきた知恵や工夫、技術などを総称して「災害文化」と呼ぶことができる。
「津波てんでんこ」などの言い伝え。「地震がきたら竹藪に逃げろ」などの言い伝えや災害伝承。
慰霊碑や追悼碑などの「災害遺産」「災害遺構」
桜島の黒神地区の鳥居の上部だけが地上にでている「黒神埋没鳥居」 1914の大正の大噴火で埋まった。当時の村長の判断で、後世に噴火の記憶をつたえるために残されることになった。
香港出身の哲学者の張政遠は、哲学者の実践として「古寺巡礼」にヒントを得て、東日本大震災の被災地を巡る「被災地巡礼」をしている。仙台の波分神社をは、津波の記憶をもつ神社であり、そこを訪れることはその記憶を蘇らせることであると述べている。
小川伸彦「は、文化財トリアージをとりあげ、・・・
加藤泰史は、リスボン大地震と関東大震災がもたらした思想的地殻変動に関して、カントの地震論と寺田寅彦の風土論をとりあげる。リスボン地震は、キリスト教信仰への懐疑をもたらす。感とは自然固有の秩序を配慮して、「自然に順応すること」を通じて防災をおこなうことが合理的であると主張する。カントの発想を「相地の学」として具体化して新たな災害学の地平を切り開こうとしたのが寺田寅彦の風土論だったと指摘。
……地域ごとの自然災害に対応するには、日本人論としての風土論を越えて、地域ごとの風土に応じた複数の風土論、多重的な自然災害に応じた重層的風土論が求められること、防災と風土の哲学の実践的な取り組みが必要だと述べている。
岡田憲夫 土木計画学から出発し、鳥取県智頭町の現場とかかわってきた。その経験をもとに能登半島地震の地域復興プロセスのヒントを探る。
現代社会は「続発する災難Persistent Disruptive Stressors」にさらされており、各地域はこれおw乗り越えるための「希望」と「誇り」を「自分たちのことばで表現しあえる場」をつくることが先決であり、それは「共に生きよい地域」として小さく着実に復興しつづける創造的で戦略的なまちづくりの条件となる。
梶谷真司は、哲学対話が急速に広まったのは、東日本大震災以降であると指摘し、……災害と対話の関係について論じている。
▽第1章 滋賀県下の明治29年水害記念碑 市川秀之
▽第2章 中国における禹王の治水功績遺跡と伝承 植村善博・竹内晶子
中国の禹王とくらべて、日本の伝統的な水神や河神は自然神であり、その怒りを鎮めるため祈祷する受動的な信仰が中心である。
日中は対照的な自然観・河川観と信仰を有していたといえよう。
▽第3章 中国災害考古学事始 向井祐介
中国では、地震や火山による災害リスクは主として周縁地帯に集中し、黄河や長江などの大河川流域では大規模な水害が定期的に発生している。歴史文献の上では蝗害や干魃が主たる災害として数多く記録されてきた。
1976年の河北省のM7.8の唐山地震では死者24万2769人
2008年の四川省のM8.0の四川大地震は死者6万9277人、行方不明者Ⅰ万7923人。
ただ、地震は辺縁で発生。大都市に暮らす人々にとっての身近な脅威は水害や疫病だった。
1887年の黄河洪水は死者90万人以上。1931年の長江・淮河流域の大洪水は2520万人以上が被災し、その4割が周辺地域へ流出した。さらに同年には各地で水害が多発し、被災者は5000万人を超えた。
……1937年日本軍は南京を陥落させた。その進軍を阻止するため国民党軍は、黄河南岸の堤防を決壊させた。数万人が犠牲に。広大な地域が水没し、大量の避難民が西安駅北側の大明宮地区に到達。
21世紀初頭でも10万人以上がバラック生活を継続していた。
2007年、遺跡を保護整備するため、バラックをすべて撤去し、住民たちを移転させた。2010年に大明宮遺址博物館が完成
▽第4章 防災と選別の社会学 仏像トリアージから考える 小川伸彦
京都市消防局 「仏像トリアージ(文化財トリアージ)」
2008年に消防局の文化財防災担当者が発案。国宝を赤、重文を黄、府指定文化財を青、市指定文化財を緑で色分け。火災発生時に重要度の高い順に搬出するという計画。
ところが、その作業で寺社を訪ねたところ、文化財に指定されていない秘仏や本尊も多数あることが判明。トリアージの「順位づけ」のニュアンスに反発が強いことがわかった。そこで消防局はトリアージの不使用を決め、トリアージタグを「文化財タグ」に改称。搬出した仏像の首にかけるなどし、照合にもちいることに。
……
▽第5章 和辻哲郎の「風土」論再考 上原麻有子
和辻の「風土」に関する研究は「世界の諸民族の国民性(民族性)を比較研究考察するための基礎理論として構想」されることからはじまった。
「人間の歴史的存在がある国土におけるある時代の人間の存在となる」
いつ生きるかのみならず、どこに生きるかが、人間存在を把握するための決定的な要因となる、と考えた。
……日本の庭園とヨーロッパの庭園のちがい
ルネサンス期のローマの庭園は「人工の支配」「自然の美を殺すこと」が特徴。
近代のイギリス庭園あるいは自然庭園は「ただ自然のままの風景を一定の形に入れたもの」
日本の庭園は、「自然のまま」ではない。無秩序な荒れた自然のうちから秩序やまとまりをつくりだすという努力。……自然に人工的なものをかぶせるのではなく、人工を自然に従わしめねばならぬ。人工は自然を看護することによってかえって自然の内からしたわしめる。
……主役は自然であり、影ながら人は自然をケアする。だがこの「看護」なしには自然美はあり得ない。
……自然と人工は協働調和的に統一するのだ。自然だと見せかけておきながら、非ー自然化する。
……能面からは人間らしさが徹底的に抜き去られているが、面をかけた役者が「動く肢体」を得ると「表情を抜き去ってあるはずの能面が実に豊富きわまりのない表情を示し始めるのである」
「自然的な生の動きを外に押しだしたもの」の表現ではなく、逆にそのような「表情を殺す」こと、あるいは「自然性の否定」である。……
人間の内面という自然を表現するために、役者の身体的演技も能面の作りも、非ー自然化されているのだと言えよう。
……看護によって非ー自然をつくり、自然を維持する。この考えは、くり返される自然災害による生活圏の破壊や地球環境の修復不可能な変化の危機に直面している我々にとって、重要な導きとなるだろう。風土としての看護的自然は、より広く応用される必要がある。
【福岡さんの言っていた「自然型」 自然をつくる】
▽第6章 大地が揺れると思想が変わる 加藤泰史
1755年のリスボン大地震 キリスト教信仰そのものにたいする懐疑をもたらす。
寺田寅彦と前批判期のカントの地震をめぐる議論はとおに西洋近代科学にたいする根本的批判を含む。カントは、自然固有の秩序を配慮することを通して、予防措置を講じることが災害に対して合理的な防災だと主張した。
「人間は自然に順応することを学ばなければならないのに、自然が人間に順応してくれるように望んでいる」とテーゼ化。
……これを「相地の学」として具体化して新たな災害学の地平を切り開こうとしたのが寺田寅彦の風土論であった。
……カント ペルーやチリでは、石組にするのは1階だけで、2階は下敷きになっても死なないように軽い木材でつくるという用心がみられるという事例をあげ、地震にたいするリスボンの防災政策がまったく不十分であったことを指摘した。
……地震は被害をもたらすと同時に、温泉や鉱石層の形成、植物への栄養供給などの「有用性」をあげ、地震の原因の両義性を指摘。
地震は天罰だ、という論についてカントは「人間は神の配在の唯一の目的だとうぬぼれている」と、人間中心主義そのものであるとみなした。天罰論批判は、同時に人間中心主義批判でもあることになり……
……寺田寅彦の風土論
科学が発達していなかった時代は、過去の経験を尊重してそれに学ぶというしかたで人間は自然に従順だった。文明化の過程で過去の経験にかわって科学的知見を重視することで、人間は自然に反逆してそれを克服しようとした。
しかし関東大震災が示したのは「過去の地震や風害にたえyたような場所にのみ集落を保存し、時の試練にたえたような建築様式のみを墨守してきた。そうだからそうした経験に従ってつくられたものは関東大震災でも多くは助かっているのである」(天災と国防)
「……20世紀の文明という空虚な名をたのんで、安政の昔の経験を馬鹿にした東京は大正12年の地震で焼き払われたのである」(津浪と人間)
……問題は、文化的に特殊的であるにすぎない「分析科学」を無批判的に日本の風土に工学的に応用した点に求められる
「……天然を相手にする工事では西洋の工学のみにたよることはできないのではないかというのが自分の年来の疑いであるからである」
「分析科学」じたいがその理論を工学的に応用する場合に風土的知識が必要なのである。「分析科学」盲信に対する根本的批判をふくむ寺田的風土論であり「相地の学」の再評価につながる
寺田は「分析科学」によって分断された人間の自然との関係を「相地の学」の観点から修復することで「地震による災害」にそくしてあらわれる「分析科学」の「短所」を克服できると考えた。これはカント的論点の具体的展開。
……「土着化」に重要なのは、カントのいう「人間は自然に順応することを学ばねばならない」という観点であり、「分析科学」は日本固有の「風土的合理性」を組みこんで変容しなければならないと同時に、現在の「相地の学」はそうした「風土的合理性」を発見し照明する役目も担うことになろう
……リスボン大地震では、キリスト教信仰そのものの危機をまねき、関東大震災では、風土論という日本独自の学問が立ちあがった。
寺田寅彦は、カントの災害学的な論点も具体的に継承……風土論というと和辻となっているが、寺田の風土論はもっと注目されてもよいだろう。
▽第7章 防災と風土の哲学 山泰幸
「風土」は和辻が1928年から29年にかけておこなった大学の講義にもとづいて書かれた。
ハイデガーが人間存在を時間性においてとらえたのにたいして、人間存在の空間性に着目して考察したものとされる。
日本人の国民性を「台風的性格」と考察。
……台風的風土の特徴は、「……受容的、忍従的な態度」
……寺田が「地震的契機」を重視することで「天然の無常」という宗教的な根源感情に関心を寄せたのに対して、和辻は「台風的契機」に着目することで「慈悲の道徳」という協働的な市民感覚の重要性を説く。
……和辻「主体的な人間存在の自己了解としての風土」
……和辻「あらゆる時代を通じて日本人は家族的な『間』において利己心を犠牲にすることをめざしていた」
……和辻は地震的性格については一切ふれることなく、家族のために利己心を犠牲にする側面にのみ着目し、これを「台風的性格」と関係づけて論じた。
……「津波てんでんこ」という災害伝承。
……「日本人論としての風土論」をこえて、地域ごとの風土に応じた複数の風土論、多重的な自然災害に応じた重層的な風土論が必要となるだろう。……住民と研究者がともに語り合い、行動をともにしながら、それぞれの地域の防災にふさわしい風土論を創造する必要がある。
▽第8章 風景とともに立ち直る 寺田〓宏
イタリアの地震で壊滅し、集落ごと街に移転したジベリーナという地区の街区を保存した、ランドスケープ・アート作品であり記憶の場である「グランデ・クレット(巨大な亀裂)」……
風景が壊れることが、わたしが壊れることであり、風景が立ち直ることはわたしが立ち直ることであるということは……
風景とは文化的事象であるから……ある特定の時間と場所においてある特定のものが風景となる。
近世から近代のヨーロッパにおいては、森が風景の代表的なものであった。
中世以前においては、風景ではなく、恐れと畏怖の対象だった。
日本の古代においては……佐藤弘夫によると、縄文時代以前のカミは個々の動物や出来事そのものだった。弥生時代になると、カミが抽象化されるが、、今度はそのカミを具体化する必要ができて、依り代とよばれる物質やカミが宿る場所が必要になったという。風景はカミと重ね合わせて見られた。
美術史家の山本陽子は、見えてはならないとされていたカミが、仏教が伝来することで、表象されるようになり……つまり、日本の古代や中世では、人は風景を見ても、そこに自然物は見えておらず、そこにはカミが見られていた。風景は風景ではなく、カミであった。
……風景が壊れると、わたしが壊れるというのは……定住を前提とし、イエやムラという共同体の存続に強い価値観を見出す文化が生じさせたものであるということになる、
……モニズム(一元論)とデュアリズム(二元論) 近代の思想は主観と客観をわけるデュアリズムだが、日本の哲学者は、西田も和辻も……モニズムを唱える。
和辻は、環境と人間はダイレクトにつながっており、いわば「二にして一」の関係にあると考える。
……風土とは、外部にあって、人間に影響を与えるものではない。風土において、人間が見出すのは外部の自然環境ではなく、むしろ、自己という内部のあり方である。わたしのありかたそのものが風土なのである。和辻もまたモニズム。
……住み慣れた町から別の場所にはなれたことで、わたしが壊れてしまうというとき、風景とその人を分けるのではなく、ひとつのつながった連続体として、つつみこんでとらえる視点があれば、そこには従来とはちがった復興や立ち直りの道筋や方法が見えてくるのではないだろうか。
(〓ふるさとから引き離されて、ぼけてしまった老人。風景を失うと自分もこわれる、というのは、むずかしい話をしなくても、実態としてすでにあるのでは)
▽第9章 続発する災難ダイナミクスの時代と持続可能な地域復興 岡田憲夫
智頭町 「日本ゼロ分のイチ村おこし運動」
……災害を乗り越えて生きぬいていくための「希望」と「誇り」を「自分たちのことばで表現しあえる場」をつくることが先決である。それは「共に生きよい地域」として小さく着実に復興しつづける創造的で戦略的なまちづくりなのだ。……
▽第10章 現場で活きる人文学の可能性 大西正光
桜島防災 1万6000人の地区
SMARTガバナンス
S=small、sorid 小さくても活動主体の身の丈に合った一步を継続すること
M= moderate multiple 適度な規模感で、さまざまなに異なる視点、立場を有する主体で構成する
A=anticipatory adaptive 適応的に動く
R=risk-concerned responxive リスクと懸念される事柄に対して対応する
T=transform
ワークショップでは、住民の立場から自由になにが懸念されるか、どのようなアクションが必要か語ってもらった。言葉で語ること自体が、各住民が何かの問いを構成するために必要な行為だと考えた。言葉で語れば、新たな疑問も浮上する。
桜島火山観測所を訪問 軽石などにふれる。身体で経験する機会を通じて、自宅にとどまった後の困難がどれだけ大変か想像できるようになる。
広域避難先を視察して、収容能力が決定的に不足している事実を知った。
▽コラム 災害と対話 梶谷真司
哲学対話が広まるきっかけは東日本大震災だった(〓それだけ必要とされた?)
だいじなのは、それぞれが自ら考え、言葉を見つけること。それは、一人で考えることによってではなく、他者との対話を通して、他者の言葉や考えと突き合わせ、そこから触発されることで可能になるのである。
語られたテーマは……「負い目」「罪悪感」「後ろめたさ」……医療従事者はとりわけ、専門的知識が生かせない、なんのためにここにいるのかわからないという思いに苦しむ人が多かったようである。対話をするうちに、物資を送るとか瓦礫の撤去をするような結果の見えやすい支援以外は「支援」ではないといった硬直した見方があることがわかった。
しかしやがて「あらためて何かを支援するというよりも、どちらかというとその人のもとの生活に近いような形で何かを手伝う、一緒にいることなのかなって、いまでは思っています」という意見も出てくる。
……なんらかの、安心して共に語り、考える場が必要である。……災害の後、突然対話の場を設けようとしても難しい。だからできれば、普段から様々な人たちが集まり、話しあう場、同意したり共感したりするのではなく、むしろそれぞれの立場、それぞれの思いを語り、ちがいを受け止めながら共に考える場をつくっておくのが、災害に備えることになるのではないだろうか。
▽コラム まちづくりにおける語りあう場のデザイン 山泰幸
パリでは、日曜の朝に、カフェに人びとが集まって、さまざまなテーマについて語りあう「哲学カフェ」と呼ばれる場がある
図書館や学校、公園など人びとが自由に集まる場が充実している地域は、熱波などの災害でも生存率が高い。平時においても住民の平均寿命が圧倒的にながいことを明らかにしている(クリネンバーグ)。
人々が自由に集まれる場「社会的インフラ」の重要性。【仮設住宅における集会所の大切さ〓】
2013年からのフランス留学で、哲学カフェに出会い、これがまちづくりに役立つと直観して、帰国後、各地のまちづくりの現場に哲学カフェを導入してきた。
徳島県東みよし町のカフェ・パパラギで2015年から3カ月に1度、哲学カフェを運営。
大切なルールは、「相手の意見を批判してもいいが、否定してはいけない」「(表情など)否定的な表現もしてはいけない」攻撃的な否定は禁止。
互いの発言に対して、敬意を示すことで安心が得られるし、何よりその場の雰囲気がとてもよくなる。
哲学カフェは、地域のなかに潜在している「地元地知識人」とも呼ぶべき人びとが集まってくる。
カフェを通して、語り合いの作法を習得した人たちが、それぞれの活動において、語り合いの場づくりを試みるようになった。
まちづくりが活発な地域には、地域の内部と外部を媒介し、かつ有益な情報や知識、資金などを外部から調達できる、ある種の知識や技術をもった担い手が存在している。筆者はこのような人物を「媒介的知識人」と名づけている。
……地域内部の人だけではなく、外部の多様な分野の専門家や支援者たちと協働し、その知恵や技術を結集することによって、道が切り開かれる。
▽コラム 災害と幸福 趙寛子
近代の成長期には、科学技術の発展で自然を制御できるという考えが強まった。……ところが自然災害を神の怒りとして恐れていた時代が過ぎ去ると、今度は、国際社会の対立から生じる人災が襲うようになった。
……第二次大戦後、25億の世界人口が50億になるのにわずか37年しかかからなかった。
グローバル経済の競争と紛争は未来に対する不確実性を高め、人びとの欲望と諦めが入り交じった状態が、現代人の心身を不健康にしている。
このような状況で、災害人文学は重要。単なる物理的な対策だけでなく、人間と自然に対する深い理解と洞察にもとづいた知恵を育むことが求められている。
……14世紀のペストで、多くの人びとは既存の宗教の教義に疑問を投げかけ、世俗的な生活の価値を重視し、人間の身体と疾病の研究にとりくんだ。
21世紀の私たちは、大規模な自然災害が予想されるなか、どのような矛盾を解消し、新しい生き方を追求できるのだろうか。
……一つの考え方として「人は死により消滅しない」という仮定を立てて、新しい生き方を実験してみたらどうだろうか。……
「人は自然の摂理のなかで永遠に生きている」と考えるようになったら、自然災害を怖がることなく、生きることの意味をじっくり考えられるであろう。
……幸せは、健康や仕事、お金があって自ら得られる「自足感」ではない。幸福とは、他人や社会のためになる活動によって与えられる福、すなわち「行福」でもある。行いの結果として、他人から「尊重、信頼、尊敬」の念をうけ、互いに感謝の念を交感するとき、互いの存在の意義が充満になってくる。
……災害への備えは単なる物理的・技術的な対策だけでなく人びとの心のあり方や社会のつながりを強化することにもなる。国内外的に相互の必要性を補完しあい、互いに感謝しあえる社会を作ることが、究極の災害対策となると考えられる。







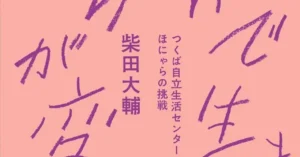
コメント