■第三文明社250303
能登の民俗文化が消えてしまうのではないか、どうしたら防げるのかヒントを得られるかと思い、「復興と文化」という名にひかれて購入した。勉強になる内容もあったけど、私の知りたいこととははずれていた。
以下、興味深いところを抜粋。
▽山中茂樹さん
阪神淡路大震災で提唱された「創造的復興」で、被災者生活再建支援法の原型となる制度の提唱や、幹部職員を有識者らとチームを組ませて被災者の声を聞いてまわる被災者復興支援会議の設置などの成果をあげたと評価する。
一方、東日本大震災や熊本地震では、「創造的復興」を唱えながら、国に財政出動を求める中央依存型の災害復興に矮小化され、空港民営化や農地集約化といった新自由主義的経済復興に変質したという。能登半島地震でも知事は「創造的復興」をかかげるが、どうやら後者に近いようだ。
村山富市首相は「一般的に自然災害等によって生じた被害に対して個人補償をしない、自助努力によって回復してもらうということが原則になっている」(1995年5月)と答弁したが、小田実らの市民・議員立法運動によって98年、被災者生活再建支援法が成立し、「私財形成に公的資金を投じることは許せない」とする新自由主義派の壁に「蟻の一穴」をあけた。2007年には支給最高300万円という改正支援法が成立した。
▽津久井進弁護士
制度を前提に生活を切っていく残酷さ。そうではなく、憲法の生存権と生活の実態から制度の運用を組み直す必要性を説く。
被災者の苦しみを生みだす原因は「法制度」の側にある。個々に異なる困難は、法制度という画一的・類型的な救済措置ではカバーしきれない。一人ひとりの被災者に「人」が寄り添って個別の支援をする災害ケースマネジメントが必要だと説く。以下の指摘はいずれも重い。
「能登半島地震直後の1月4日び石川県庁は、危機管理関連の部署以外は平時モードだった。生命維持の限界水準となる72時間が過ぎる瞬間にも庁内で緊張を感じられなかった」
「災害弔慰金の申請をして認められなければ災害関連死と認定されないことが災害関連死の実態が見えない一因になっている」
「能登半島地震の復興が遅れている最大の原因は、ボランティアの不足にある。あるいは、ボランティアの本質である「自由」「自立」「利他」が忘れられ、行政のお手伝いをする下請的存在に成り下がっているところにある」
▽藤井克徳(日本障害者協議会)
障がい者や精神障害や認知症、それに準じる人たちが人口の2割超を占めており「マイノリティー」ではない。
災害時、それらの人が犠牲となるリスクが際立っている。阪神大震災を契機に「福祉避難所」がつくられたが、能登半島地震2週間の時点で、被害の大きい7市町で福祉避難所が開設されたのは想定の2割だった。
▽島薗進
かつてお盆のとときに人はよく泣いたが、文明社会に進むことによって泣くのが下手になったーーと戦時中に柳田国男は述べた。
他者が自分の悲嘆に共鳴すると期待できない状況では心を開いて泣くこともできない。
▽辻内琢也 医療人類学
2021年から、ゼミの学生による、同世代の原発事故被災当事者へのインタビューをはじめた。当時小学生だった被災当事者たちが、この10年間、どのように暮らしてきたか。避難先学校でのいじめ、福島育ちを秘匿しながら生きてきた孤独感、親の顔色をうかがいつづけてきた日々……。当事者の悲痛な語りは、学生たちに大きな衝撃を与え、しだいに尊敬の念が芽ばえていった。当事者にとっても、誰にも話せなかった思いを同世代の学生たちに傾聴してもらうことで、安心と癒やしが得られる場となった。
困難を抱えた個人同士が連帯することで、変革への風を起こすことができる。
□井口時男 大震災と俳句
東日本大震災でも文学は変わらなかったが、俳句だけは大きくかわった。
関東大震災には震災詠はほとんどなかった。「ホトトギス」によって俳壇を支配していた高浜虚子の俳句観によるものだった。虚子は、俳句というものは春夏秋冬を滞りなく循環する穏やかな自然を詠むものだと考えた。
「写生」を唱えたのは彼らの師の子規だったが、子規にとっての写生は、類想によってマンネリ化していた「月並俳句」を打破する手段だった。
子規においては「手段」だった写生を弟子たちは目的化してしまった。写生は自然の模倣再現をめざすから、想像力による虚構は排除された。
1931年、水原秋桜子がホトトギスを離脱し、社会的な主題を詠みはじめる。子規の改革の初志を継承したのは、彼ら昭和の「新興俳句」だった。だが戦時体制でつぶされた。虚子の「花鳥諷詠」にしたがった俳人たちは俳句会をあげて戦争に翼賛した。
1950年代に金子兜太らが「社会性俳句」運動を展開したが1960年の安保闘争敗北を機に俳句界も保守化する。
そんななか、現代俳句協会の呼びかけに俳人協会や日本伝統俳句協会が応じて編まれた「東日本大震災を詠む」は画期的だった。
□柳田邦男
日本の政治・行政において、危機管理の基本的な思想が形成されてないことが問題。
2002年に文科省の地震調査研究推進本部地震調査委員会が、三陸沖から房総沖にかけてマグニチュード8級の津波地震が30年以内に20%の確率で発生するおそれがあるとの報告書をまとめた。ところが、発表直前に内閣府の官僚から「上と相談したところ、非常に問題が大きく、今回の発表は見送り、取扱について政策委員会で検討したあとに、それに沿って行われるべき」と、発表を控えるようにという横やりが入った。さらにやむを得ず発表する場合においては、発表文書の冒頭に、「この予測は信頼性が低いものなので、防災対策の見直しが迫られているものではない」と言うに等しい文章を加えるよう要請してきた。
「歴史的な地震は震源や規模などを科学的に確定する資料が不十分であり、そうした科学的根拠に乏しいデータはこれから起こる地震を予知する対象から除外すべきだ」という悪質なロジックだった。
たとえば平安時代には、大規模な津波をともなった貞観地震が起きたが、、これも官僚のロジックでは、参照されないデータにされてしまった。
事故前、福島第一原発を襲う想定津波最高水位は5.7メートルとされ、原子炉建屋の敷地は、海面から10メートルの高さだから津波対策は十分だとされた。ところが実際は高さ15メートル前後の津波が襲った。
国や東電の責任者は異口同音に「想定外」と言ったが、専門家の警鐘に耳を貸さなかっただけ。非常用ディーゼル発電機は、地下階にならべていたために水没した。原発事故は想定外などではなく、国や東電の安全性確保への思考停止が招いたものだった。
パンデミック対応も同様だ。
ドイツでは2013年にコッホ研究所が提出した「リスク分析報告書」をもとに、ドイツ全土でいざという時に速やかにPCR検査ができる態勢が整えらた。コロナの感染拡大に早い段階で対応できた。平時において最悪の事態をリアルに想定して、具体的対策を準備していた。日本はコロナ初期、多くの国民がPCR検査さえ受けられない状態だった。初動があまりに遅かった。
福島原発事故では、政府事故調査・検証委員会の委員長代理をつとめた。
政府の調査は、が周辺地域の汚染状態や、震災関連死の数、農業生産の被害額といった、マクロな数字で捉えられる被害ばかり。広域避難による家族の離散・崩壊、ふるさとの喪失、PTSDなど、ミクロな視点でも被害者に多大なダメージを与えた。これらすべてを調査することを強調してきた。
全容調査の大切さは水俣病の歴史から学んだ。公式発見は1956年で、59年には厚生省の食品衛生調査会が、主因をは、魚介類に蓄積されたある種の有機水銀化合物であると答申した。熊大の調査によって、原因物資が工場排水にあるのではないかと指摘されていた。
これにたいしてのちに首相になる池田勇人・通商大臣は、有機水銀が工場から流失したとの結論は早計であると反論し、国による排水規制や、漁獲規制がなされなかった。政府が、チッソ水俣工場による公害と断定するのは1968年だった。9年間でさらに多くの患者を生んでしまった。
水俣病が公害の原点と呼ばれるのは、公害発生時に国が原因究明に乗り出さず、対応を遅らせ被害を拡大させたという、日本の危機管理や災害対策の思想の欠如を象徴しているからであり、本質的に同じことが東日本大震災・福島原発事故でも繰り返された。能登半島でも今世紀に入り、地震が何度も起きていたのに事前に対策が立てられていなかった。
日本に安全・安心の柱となる危機管理の思想を築くことが急務だ。
ボランティア活動は、社会は隙間だらけだということを浮き彫りにした。とくに行政や司法がつくる隙間によって、支援の手が届かず切り捨てられる被災者は多い。そうした観点からも、日本の安全文化を考えた時に、ボランティアは大きな柱となるだろう。
=====
□石牟礼道子
□山中茂樹
▽31 生存機会の復興は、生活、営業及び労働機会の復興を意味する。道路や建物は、この営生の機会を維持する道具立てにすぎない。
▽40 (都市計画の中央集権的な)建て付けにささやかな抵抗を試みたのが阪神・淡路の被災地の貝原県知事だった。2段階都市決定方式。第一次の都市計画としては、まちづくりの大枠の決定にとどめ、それ以後、関係住民と徹底した論議を積み重ねて、第2次の都市計画を決定する。
…市が「まちの骨格」を最初の決定し、その枠内で「小さな改良」を被災者に委ねるという上意下達の仕組み…という批判。
とはいえ、2段階方式のおかげで、「広い道路はいらない」として住民独自のまちづくり案を携え渡り合った地区がある。
▽42 景気低迷期に発生した阪神の震災の復興には、右肩下がりのベクトルを一気に押し上げる革命的ななにかが必要だった。貝原知事によって提唱されたのが「創造的復興」。
…被災者生活再建支援法の原型となった総合的国民安心システムの提唱やフェニックス住宅再建共済制度の単県実施、幹部職員を有識者らとチームを組ませて被災者の声を聞いてまわる被災者復興支援会議の設置など、「人間復興」よりそう支援制度がセットで実施されたことも忘れてはならない。
東日本の宮城県や熊本地震の熊本県では、「創造的復興」を唱えながらも、国に財政出動を求める中央依存型の災害復興に矮小化され、震災をきかとして空港の民営化や農地の集約化などを推進する新自由主義的経済復興に変質した。
▽44 2007年、年齢・所得要件を取り払い、支給最高300万円という改正支援法が成立。
だが、この支援法は、東日本の広域避難者には役にたたなかった。福島県外に避難した人たちは対象外となった。…おおむね被災者支援は、被災した都道府県か市区町村に居住している人たちに限られる属地主義で貫かれている。
□津久井進弁護士
▽54戦災の焼け野原と見誤るような能登半島地震の被災地で必要なのは、希望の光である。人権が危機にさらされた災害時だからこそ、憲法の理念を追求し、実践する意義がある。
▽58 災害関連死は「救うことができる命」だった。…災害関連死として認定されるには、災害弔慰金の申請をして認められた場合に限られる。「災害関連死の実態が見えてこない要因のひとつは申請主義です」
▽60 「借り上げ復興住宅」で「やっと安心して暮らせる」と…月日がすぎ、身体も弱ってきたときに突然退去を求められるというケースが西宮や神戸で起きた。一方、宝塚や伊丹市は終生、借り上げ復興公営住宅に住みつづけることを認めていた。
▽63 総務省が立ちあげた「全国避難者情報システム」に登録しない人は世の中に存在しないのと同じあつかい。
▽64 国や福島県は、事故から6年たった2017年3月で区域外避難者に対する住宅無償供与の支援を打ち切った。19年3月には家賃補助の支援までも打ち切った。
▽65 苦しみを生みだす原因は「法制度」の側にあるのではないか。一人ひとり異なる個々の困難を、法制度という画一的・類型的な救済措置ではカバーしきれないからではないか。…一人ひとりの被災者に「人」が寄り添って個別の支援を行えばよい。災害ケースマネジメントを提唱する理由はそこにある。
□藤井克徳(日本障害者協議会)
▽74 東日本の災害関連死のうち発災時荷障害者手帳をもっていた人の割合は21%。16年の熊本地震では28%。国の推計では障害者は人口の9%であり、障害者が犠牲となるリスクが際立っている。
▽82 阪神を契機に、「福祉避難所」が開設されることに。能登半島地震の発災後2週間の時点で、被害の大きい石川県内の7市町で福祉避難所の開設にいたったのは想定の2割にとどまった。
▽86 多くの自治体は個人情報保護法を引きあいに、障害者手帳の情報を共有することに慎重な姿勢を見せた。そうしたなか、陸前高田市と南相馬市の市長は、情報を開示するという英断を下した。法18条には「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」は、第三者に個人情報の開示ができるとの例外が定められている。
▽89 インクルーシブな避難所 「熊本学園モデル」
「障害者」とは
①障害者手帳をもっている人。身体が436万人、知的が109万人、精神が135万人。たえだし精神障害者については手帳を求めない人が相当数にのぼる。そこで、医療費軽減制度を使っている人でカウントすると、615万人というデータがでてくる。多く見積もれば1160万人が「障害者」のカテゴリーに含まれる。
②難病や薬物依存症、弱視や難聴など、「谷間の障害」にある人たち。1000万人を超えると思われる。
③認知症患者730万人。
単純に合計すると2890万人となり、人口の2割以上となる。けっしてマイノリティーではない。
□島薗進
▽117 かつてお盆のとときに人はよく泣いたが、文明社会に進むことによって泣くのが下手になったーー戦時中にこう述べたのは柳田国男。
…他者が自分の悲嘆に共鳴してくれることを期待できない状況では心を開いて泣くこともできない。…東日本大震災後、しばらくは、多くの日本人が悲嘆を分かち合おうとする姿勢を大事にしていた。だが、悲嘆の共同性は次第に後退していく。
▽120「人間の復興」という観点からは、悲嘆と怒りと問いかけの側面を除外した「復興」はとても頼りなく不十分である。
▽122 水俣 埋め立てられ1990年に「エコパーク水俣」が完成した。2006年に「水俣病慰霊の碑」。このまわりに本願の会による石像が点在。52体を数える。
□辻内琢也 医療人類学
▽130 2014年から避難者の帰還政策を打ち出し、避難指示解除準備区域に指定されたエリアから避難指示を順次解除していった。帰還者には住宅の修繕や再建の補助金を用意した一方で、避難を継続する人に対しては住宅提供の打ち切り措置を進めていった。…帰還者と避難者のあいだで分断が生じた。
▽138 東京電力が負うべき賠償責任を国が税金をもちいて肩代わりすることで、国民の避難者に対する差別や偏見を助長させてしまった。「税金で暮らしてるからたくさん買いものをしている」などと。
…加害責任をあいまいにし、不十分な賠償・補償を実施することで、社会に分断と対立の種をまいた。帰還政策を拙速に進め、各種支援策を打ち切ったことは「原発事故は終わった」という印象にもつながっている。
▽143 避難の継続と帰還のいずれを選択しても同等の補償を受けられる仕組みを設けることが有用だ。それによって、避難者が生活の実情に合わせた決定を下すことができる。…被災者の見守りやケアを行う復興支援員の活動を支援することも重要だ。子供のスモールコミュニティを守る為、学校と避難先をつないだオンライン授業の実施も視界に入れてもよいだろう。
▽148 能登半島地震が発生した際には、原発事故の被災当事者から、「能登の子どもたちが避難することになっても、私たちと同じ思いはさせたくない」というメールを受け取った。1日1日生きぬくなかで、彼ら自身が紡いできた物語が他の誰かを救おうとしている。時間的な展開のなかで、被災当事者たちの苦悩が希望へと転じようとしているのだ。
…困難を抱えた個人同士が連帯することで、変革への風を起こすことができる。
□大澤真幸
▽155 日本が未曾有の事故に直面しながらも重要な決断を下せない理由の一つに、世界宗教の洗礼を受けていないことがあるのではないか。それにかわって日本を支配してきたもの、それは「空気信仰」ではないだろうか。
▽157 原子力政策を巡る大きな決断を下せないもう一つの理由 「未来の他者」への想像力が欠如。…エネルギー政策や気候変動対策など、次世代の人々にも影響を与える大きな選択をする際には、自らの人生の時間を超えた時代感覚が必要。
▽163 国民という共同体に対する帰属意識は、「我々の死者」を持つことで可能になる。…戦後を生きる日本人が未来の他者への視点を欠く最大の理由は、こうした「我々の死者」を失ってしまったから。「我々の死者」を失ったのは、戦争に敗れた時ではないか。敗戦を通じ、自らが信じてきたことの過ちに気づいた。そして、戦前の死者たちの願望や希望を、私たちは打ち捨てなければならないと知った。
□川島秀一 民俗学者 浜通りの震災後の漁業
□磯前順一 日文研
▽202「生者のざわめく世界で 震災転移論」2024年3月に刊行。震災で津波にのみこまれる事態とは、物理的にのみこまれるだけでなくて、感情的にのみこまれてしまい、生き残っても心が損なわれてしまいかねないことである。死者に対しては、生き残った家族は罪悪感をかかえる。死んでしまいたいという感情が人から人へと感染していくさまを「転移」とよんだ。
…被災地の外側では、被災地に行かなければ震災という出来事をなかったことにすることさえできる。結局、死者の思いを自分が訳せると過信していた研究者たちは消え去っていった。むしろ、訳することができないと感じている者たちが今も被災地に踏みとどまりつづけている。なんとか聴こうとし、その原風景をかいま見ようと被災地にとどまって活動しているのだ。
▽209 フロイトによればに「喪の行為」とは、死者や悲しんでいる人、あるいは自分のこうむった悲しみに対して、自分にはなすすべがないこと、その無力さを認めることである。自分が悲しみで「壊れている」とわかる人間は、完全に悲しみでつぶされてはいない。悲しみを否定することなく、その感情を噛みしめる事。それが「喪の行為]なのである。
▽218 タクシーの運転手や、祈念館の職員、宿泊施設の関係者など、被災地を往来する多様な人たちの交流のただ中に身を置く立場の者、さまざまな情報が耳に入ってくる人たちから、主に聞き取りをすることにした。被災地とその外部の中間。
▽222 原発周辺で故郷を失い、その魂もいまだ十分にと弔われていない人たちに対しては、その無念の気持ちを招き寄せて、言葉にしていかなければならない.生者に伝わる言葉に、死者の言葉を翻訳していかなければならない。
福島さんの絶叫短歌。
□井口時男 大震災と俳句
東日本大震災でも文学は変わらなかった。だが、唯一俳句は大きくかわった。
▽230 関東大震災には震災詠はほとんどなかった。ホトトギスによって俳壇を支配していた高浜虚子の俳句観に基づく指導の結果だった。虚子は弟子たちに大震災のことを詠むのを禁じ、自分でも詠まなかった。俳句というものは春夏秋冬を滞りなく循環する穏やかな自然を詠むものだという虚子の俳句観があった。「客観写生」を主唱していた…。
▽それでも虚子の「避社会性」に対して「接社会性」を打ち出していた碧梧桐は「震災雑詠」18句を発表しているが、散文の切れ端みたい。トリビアルな細部だけを詠み、事態や感動の中心をわざと外した……不自然。…
虚子も碧梧桐も、俳句の機能を写生に限定し、しかもその写生の中心を「描写」としてとらえている点で同じ。
▽233「写生」を唱えたのは彼らの師の子規だった。しかし子規にとっての写生は、類想によってマンネリ化していた「月並俳句」を打破するための手段だった。…だが、弟子たちは子規において手段だった写生を目的化してしまった。写生は自然の模倣再現をめざすから、想像力による虚構は虚偽として排除される。その結果、俳句は現実に従属してしまった表現として自立できなくなる。
▽234写実(現実)と空想(虚構)の両方を合同させて「大文学」を創出するべきなのだ。これが俳句を近代の「詩」たらしめんとした子規の初志である。虚子も碧梧桐も、写生にのみ「偏僻」し「拘泥」した。小説だってリアリズムに「拘泥」したあげく、私生活を切り売りする私小説への「偏僻」した。「非空非実の大文学」という理念の復活は戦後文学まで待たなければならなかった。
▽235 1931年、水原秋桜子がホトトギスを離脱。この運動を総称して「新興俳句」と呼ぶ。関東大震災後に出現した「新興文学」にならった命名である。……子規の改革の「初志」を継承したのは、虚子でも碧梧桐でもなく、昭和の「新興俳句」だったのである。
文化都市に独裁者の黒き脱糞
戦争が廊下の奥に立つてゐた
言論弾圧の対象になり(京大俳句事件)、つぶされた。「避社会的」な虚子の「花鳥諷詠」にしたがった俳人たちは無事だった。以後、俳句会はあげて戦争に翼賛する。
▽240 「社会性俳句」運動の先頭にたったのが金子兜太だった。1950年代の現象だった。60年の安保闘争敗北を転機として、俳句界も保守化に転じる。
▽242 現代俳句協会の呼びかけに俳人協会や日本伝統俳句協会が応じて3派閥が加わり編まれた「東日本大震災を詠む」は画期的。
□柳田邦男
▽251 根本的な問題は、日本の政治・行政において、危機管理の基本的な思想が今もって形成されてないことです。
▽259 「組織事故」という観点から対応を練っていく。徹底的に「なぜ」と問いつづけることで、その根本の原因を究明する
▽264 能登半島では今世紀に入り、地震が何度も起きていました。その能登半島の地震でさえ事前に対策が立てられていなかったのです。日本に安全・安心の柱となる危機管理の思想を築くことが急務です。
▽265 21世紀に入ってから、自然災害の被災者や、さまざまな事故の被害者たちがつながりあうという、新しい文化が生まれつつあります。20世紀には見られなかった現象で、私は希望をもって注目しています。
▽268 阪神で、専門職のボランティアで代表的だったのが、黒田裕子さんでした。東日本でも気仙沼に拠点をおいて…医療従事者としての被災者支援におけるボランティアのモデルケースを築き、後継者の育成にも努力。





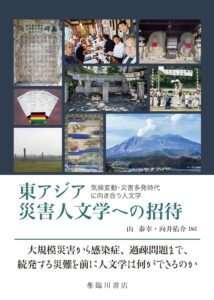

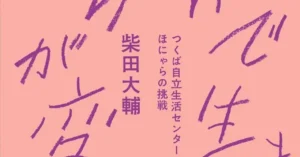
コメント