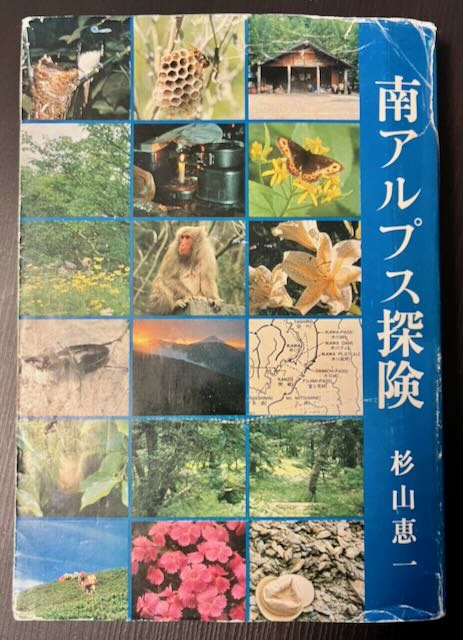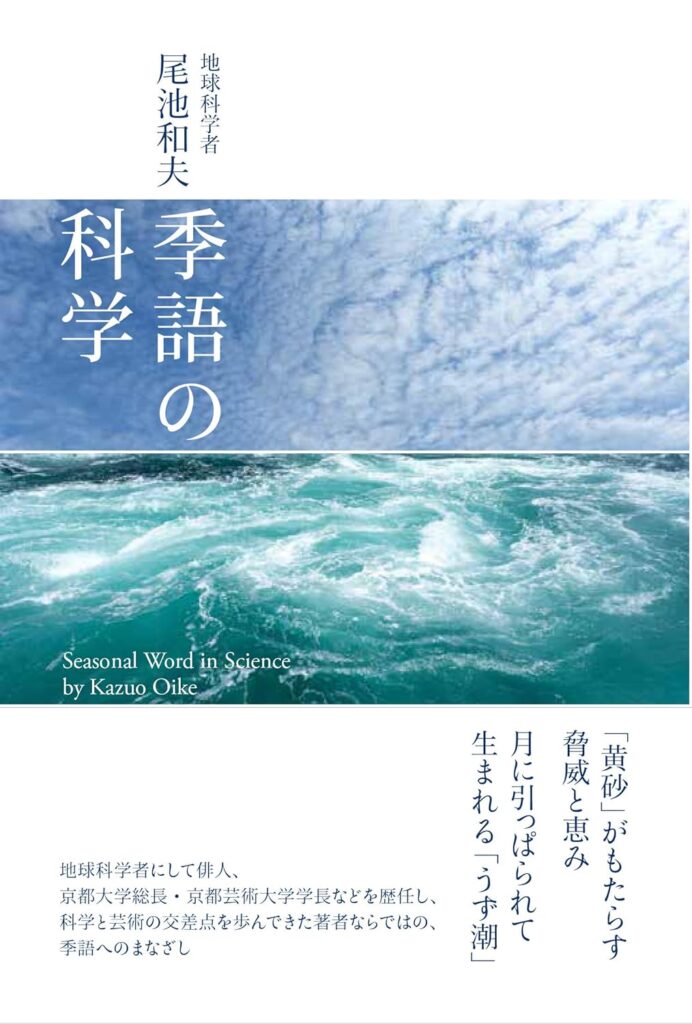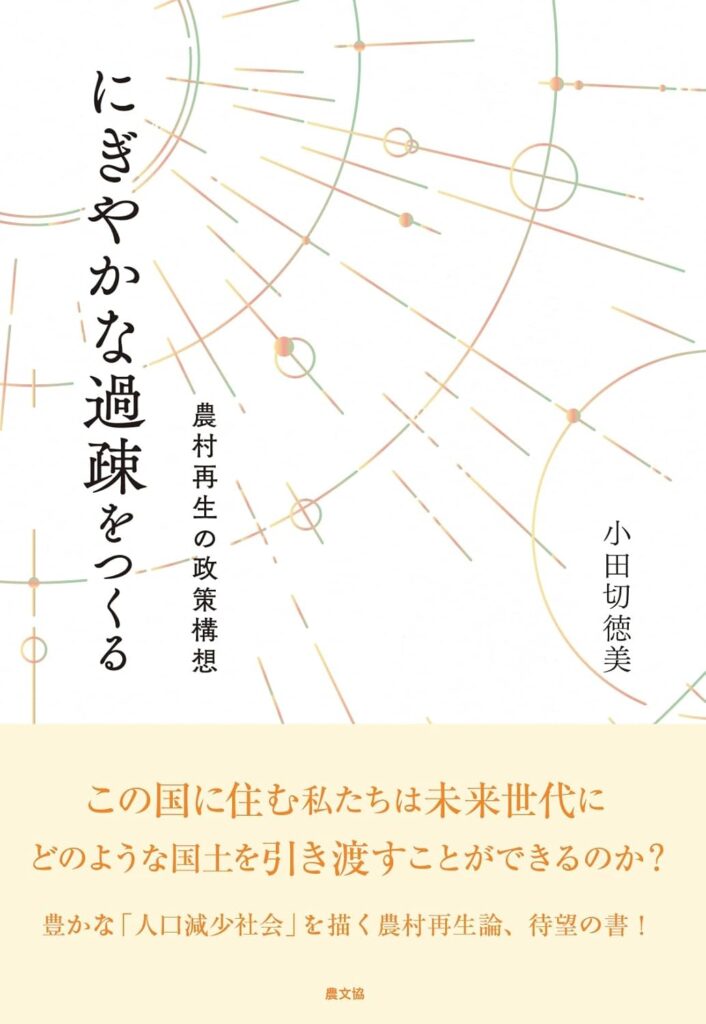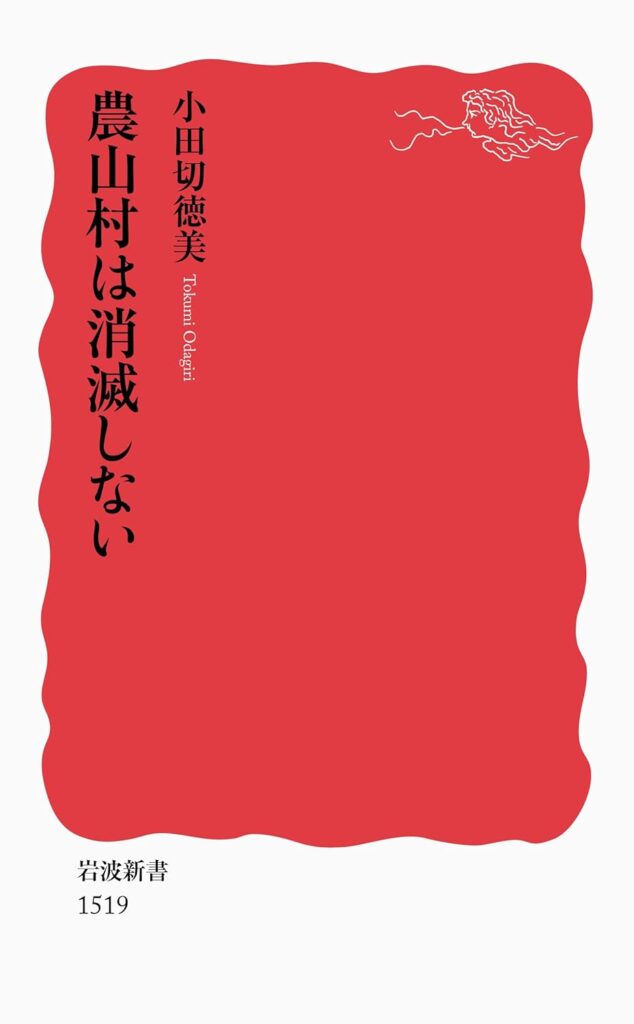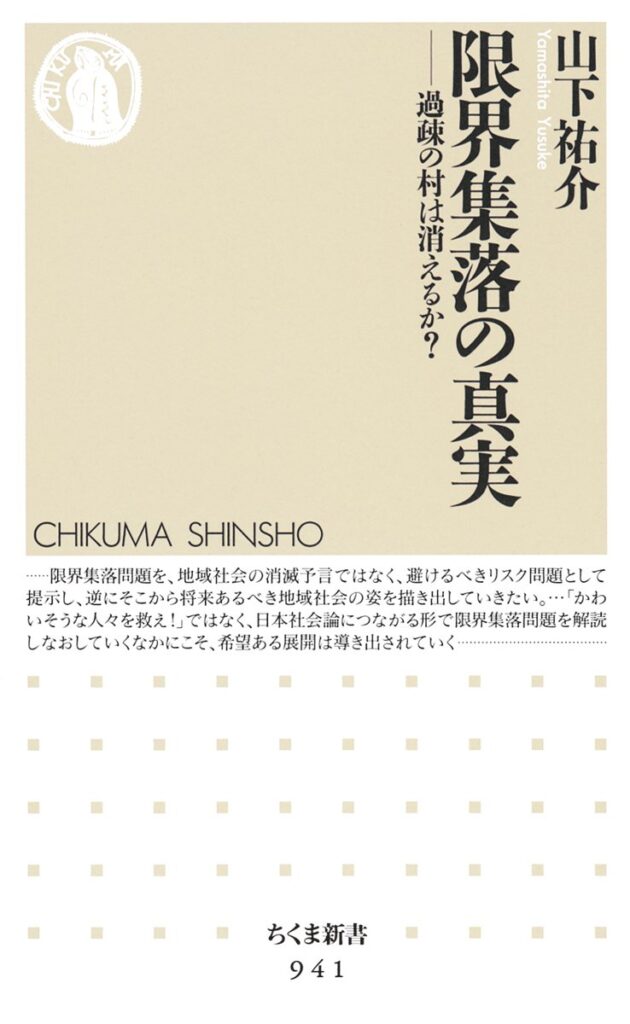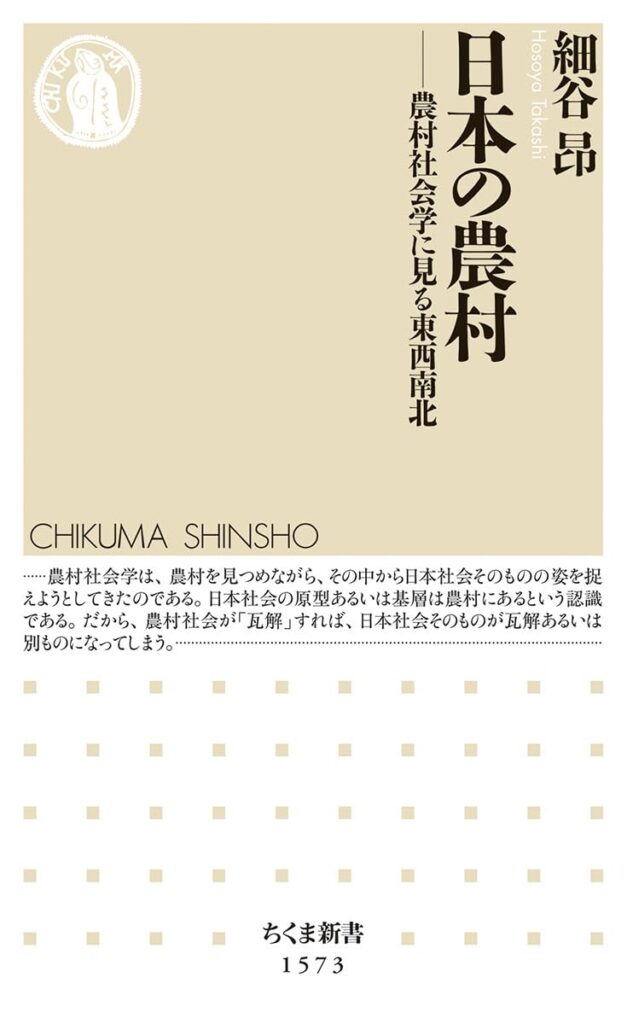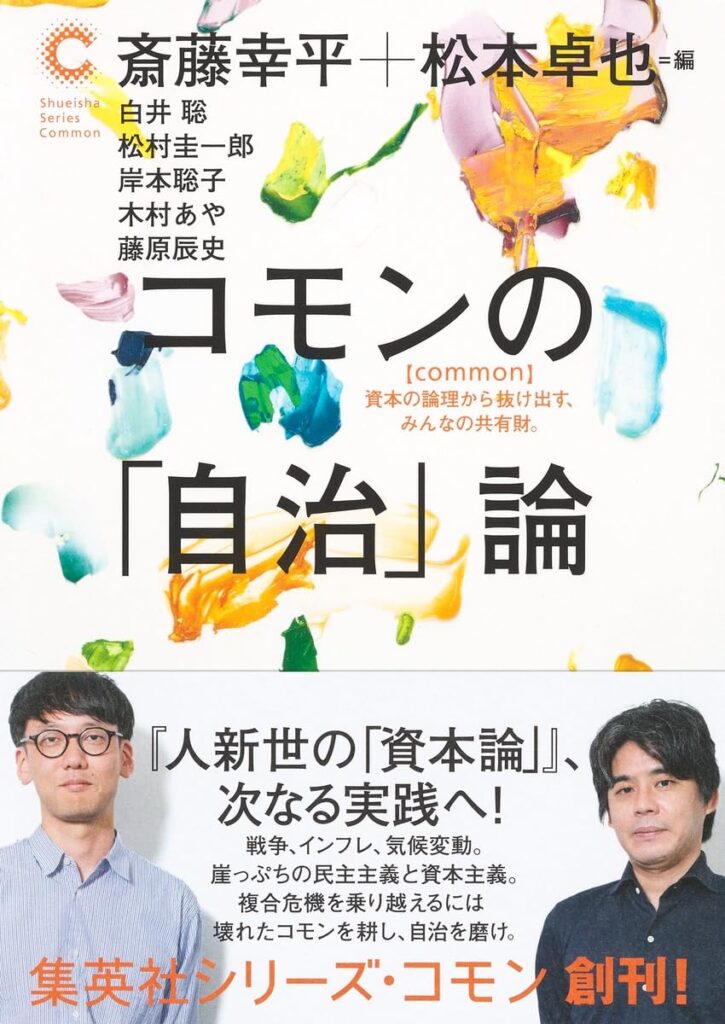05環境・農業– category –
-

南アルプス探検<杉山恵一>
■260118 私は1990年に新聞記者になり静岡支局に赴任した。 黒澤脩さんという静岡市の図書館長が黒俣という山の集落の古民家にすんでいて、不思議な人たちが毎月のように囲炉裏をかこんで酒を飲んでいた。 筆者の杉山さんは静岡大の教授で、黒俣の飲... -

季語の科学<尾池和夫>
■淡交社250520 元京大総長の地球科学者は俳人でもある。俳句の季語とその科学的裏づけや解説をくわえていて、文理を超えた博覧強記ぶりに舌を巻く。「へーそーだったんだぁ」というおどろきに満ちた本。以下その羅列。 日永 かつて1日のはじまりは日没... -

にぎやかな過疎をつくる 農村再生の政策構想<小田切徳美>
■農文協240816 「にぎやかな過疎」は、石川県羽咋市の限界集落の移住者を撮ったテレビ金沢のドキュメンタリーのタイトルからとった。 人口減少は進むが、移住者や地域の人々がワイワイガヤガヤする様子をそう名づけた。今後の地域づくりの目標は「持続的... -

農山村は消滅しない<小田切徳美>
■岩波新書240731 「限界集落」という言葉や、「増田レポート」が「消滅自治体」をリストアップしたことに違和感を感じてきた。一方、そう簡単にムラはつぶれないと、山下氏や徳野貞夫氏は論じる。筆者は基本的に後者の立場である。 農山村の空洞化は「... -

限界集落の真実 過疎の村は消えるのか? <山下祐介>
■筑摩新書 20130806 「限界集落」は高齢化によって消滅することになると1990年代初頭に予想したが、高齢化で消えた集落はほぼない。「高齢化→限界→消滅」の事例はほぼゼロ。これまでにも集落消滅はあったが、そのほとんどは、集落が元気で人口も若い... -

日本の農村 農村社会学に見る東西南北<細谷昂>
■ちくま新書202403 南北朝時代以来つづいてきたとされる「村」が今、消えようとしている。能登半島地震は「村の終わりのはじまり」ではないかと思える。 「村」はそもそもどうやって生まれ、存続してきたのか? そんな疑問をもって本書を手にした。学者... -

コモンの「自治」論<斉藤幸平・松本卓也編>
■集英社 20240124 「人新世」の危機が深まれば、市場は効率的だという新自由主義の楽観的な考えは終わりを告げる。コロナ禍でのロックダウンのように、慢性的な緊急事態に対処するため、大きな政治権力が要請され「戦時経済」が生まれ、政治がトップダウ... -

映画「風の島」<大重潤一郎監督>
■20240115 1983年に沖縄の陶芸家・大嶺實清氏が西表島の沖にある無人島・新城島(パナリ)でつくられていた土器「パナリ焼」を復活させた際の記録映画。 パナリ島はシーカヤックのツアーで訪ねたことがあったが、無人島に古い土器文化があったことなどは... -

田中正造 21世紀への思想人<小松裕(ひろし)>
■筑摩書房20230816 水俣病の原田正純さん、震災被災地の農業をささえた新潟大の野中教授ら、現場からの発想と行動を徹底した人とおなじにおいがする筆者だ。そして、田中正造こそがその原点であると位置づけているようだ。 正造は伊藤博文とおなじ1841... -

通史・足尾鉱毒事件1877〜1984<東海林吉郎・菅井益郎>
■世織書房20230801 田中正造記念館のスタッフに「足尾銅山鉱毒の全体像を知るのにおすすめ」といわれて購入した。1984年出版だが東日本大震災後の2014年に復刊した。 足尾銅山の開発は1610年ごろはじまり、銅の5分の4は幕府御用、残りはオランダに輸出さ... -

山に生きる 福島・阿武隈 シイタケと原木と芽吹きと<鈴木久美子・本橋成一>
■彩流社202307 東京新聞の女性記者が、阿武隈山地の里山の人々と、稀有な写真家の導きで成長する物語だ。 舞台は福島県の阿武隈山地にある旧都路村(2005年から田村市)。 都路は、全国でも有数のシイタケ原木の産地だった。「シイタケを栽培するため... -

評伝・石牟礼道子 渚に立つひと<米本浩二>
■新潮文庫20230317 はじめは新聞記者の文章だなぁと思って読みはじめた。ところがしだいに石牟礼道子や渡辺京二が乗り移ったように現実と幻の境をふみこえたり、もどったりする。 正気と狂気、この世とあの世、前近代と近代、陸と海のあいだの渚。 合... -

「美食地質学」入門 和食と日本列島の素敵な関係<巽好幸>
■光文社新書221212 日本食が豊かになったのは明治以降、早く見積もっても江戸期以降だから、「日本食が豊かなのはこの地質のおかげ」とは言い切れないと思うけど、発想のしかたはおもしろい。 ごく簡単に結論をかくならば、4枚のプレートがひしめきあい... -

福島がそこにある<ロシナンテ社>
■解放出版社 20221029 有機農家、自主避難者、支援した人……福島の被害と苦しみをオムニバス形式で紹介する。「被曝すると障害者が生まれるかもしれないからというもっともな理由で語られていました。……ある人はお姑さんから「あなたがこの地で避難せずに... -

センス・オブ・ワンダー<レイチェル・カーソン、上遠恵子訳>
■新潮文庫 2209 海洋学者のレイチェルは、人間を超越する自然の不思議を実感している。「地球の美しさと神秘を感じとれる人は、科学者であろうとなかろうと、人生に飽きて疲れたり、孤独にさいなまれることはけっしてないでしょう。たとえ生活のなかで苦... -

魂を撮ろう ユージン・スミスとアイリーンの水俣<石井妙子>
■文藝春秋20220918 アイリーンはアメリカ人の父とお嬢さん育ちの母のあいだで生まれたが両親とも離婚し再婚した。居場所を失って米国の祖父母の家で育った。 ユージンは幼いころに母にカメラをあたえられ、絵画をたしなんで写真を「絵」としてつくりこ... -

みな、やっとの思いで坂をのぼる<永野三智>
■ころから 20220529 幼いころ、踊るように歩く水俣病患者のまねをして近所の患者を傷つけた。思春期になると水俣出身を隠すようになり、「患者がいるから私がこんな目にあうんだ」と考えた。子どもができると「この子を水俣出身にしたくない」と長期の... -

原発プロパガンダ<本間龍>
■岩波新書20220513 博報堂の営業担当だった筆者が、原発プロパガンダの変遷とそのねらい、効果をあきらかにしている。広告主に弱いメディアと、その弱点を広告代理店がたくみに利用してきたことがよくわかった。 3.11以前、「原発は日本のエネルギーの... -

食べものから学ぶ世界史 人も自然も壊さない経済とは?<平賀緑>
■岩波ジュニア新書 20220508 自然の動植物をとって食べていた時代から、食べものは次第に商品化して、ついには投機の対象になった。小麦やトウモロコシ、砂糖といった食べものの歴史をたどることで資本主義の変遷を浮き彫りにする。資本主義化が食を変... -

生命の医と生命の農を求めて<梁瀬義亮>
■地湧社 20211215 梁瀬は、日本で最初に農薬の害を告発した医師だ。彼について書かれた本はいくつか読んだが、本人が書いたこの本がもっともインパクトがあった。 浄土真宗の寺に生まれ、16歳のとき病気になり漢方医にいくと「白砂糖のたべすぎ」と指... -

生命の農 梁瀬義亮と複合汚染の時代<林真司>
■みずのわ出版 20211127 梁瀬は、いちはやく農薬の健康被害を告発し、自ら有機農業も実践した。有吉佐和子の「複合汚染」(1974〜75)では「昭和の華岡青洲」と評され、患者からは「現代の赤髭」「仏様のような先生」と慕われた。 戦争中、軍医として... -

MINAMATA 20210929
ユージン・スミスと水俣を描いた映画。楽しみにしていた。「ライフ」で活躍する巨匠だが、沖縄戦の取材の際のけがで、食事もろくにできず、アルコールに頼っていた。 そんなユージンが水俣と出会い、患者らとふれあうなかで生きがいを回復させていく。... -

生命系の未来社会論 気候変動とパンデミックの時代 抗市場免疫の「菜園家族」が近代を根底から覆す<小貫雅男、伊藤恵子>
■御茶の水書房20210720 新型コロナウイルスによって、貧困に陥る母子家庭が増える一方、Go To トラベルで高級ホテルに予約が集中する。格差と分断が常態化した。 気候変動も、2030年までに温室効果ガス排出量を45%、50年までに実質排出ゼロにしなけれ... -

人新世の「資本論」<齋藤幸平>
■集英社新書20210717 人新世とは、人間たちの活動の痕跡が、地球の表面を覆いつくした年代という意味らしい。 気候変動は待ったなしのところに来ている。エコ産業によって環境と経済成長を両立できると考えるグリーンニューディールなどの気候ケインズ主... -

農と言える日本人 福島発・農業の復興へ<野中昌弘>
■コモンズ 20210616 福島はやませが夏に吹き、冷害を受けやすかったから、江戸時代から、稲の品種改良や農具や農耕馬の改良などの工夫をしてきた。明治後期には、会津では稲の品種だけで約60種あり、早稲、中稲、晩稲と植える時期が異なる稲を分散して... -

日本一小さな農業高校の学校づくり 愛農高校、校舎たてかえ顛末記<品田茂>
■岩波ジュニア新書20210604 愛農会と小谷純一を知りたくて入手した。生徒数60人の私立農業高校、愛農学園農業高等学校(三重県伊賀市)の歩みと、老朽化した校舎を減築という手法で再生する様子を紹介している。 デンマークは、1864年にプロシア、オー... -

共生の時代 使い捨て時代を超えて<槌田劭>
■樹心社 20210506 福島第一原発事故以後、「安全」をめぐって生産者と消費者の間に亀裂が生まれた。「安全安心」だけでは何かが足りなかった。有機農業やエコロジー運動の先駆者が「有機農業」になにを求めていたのか知りたくて1980年代の本を手に取った... -

鎮守の森<宮脇昭>
■新潮文庫 20210515 その土地の潜在自然植生の森であれば、阪神大震災や酒田の大火でも焼けず、セイタカアワダチソウのような外来種の侵入を許さず、アメリカシロヒトリなどの害虫にもやられない。 山のてっぺんや急斜面、尾根筋、水源地、海に突き出し... -

苦海・浄土・日本 石牟礼道子 もだえ神の精神<田中優子>
■集英社新書 20201118 石牟礼道子の「苦界浄土」は水俣病がテーマなのにある種の豊かさがあふれていた。自然とのつながり。アニミズム的な世界。文学の想像力……学生時代に読んだとき、その理由はわかるようでわからなかった。 この本は、江戸文化の研... -

放射線はなぜわかりにくいのか<名取春彦>
■あっぷる出版社 202007 政府は「ただちに健康に影響はない」、反原発系の学者は「少しでも危ない」と言う。国際機関の基準も、内部被曝をカウントしておらず科学的とは言えないらしい。どの程度の放射線を浴びると人体に影響が出るのか? どこも明確...