■岩波ジュニア新書 20220508
自然の動植物をとって食べていた時代から、食べものは次第に商品化して、ついには投機の対象になった。小麦やトウモロコシ、砂糖といった食べものの歴史をたどることで資本主義の変遷を浮き彫りにする。資本主義化が食を変質させてきたこともよくわかる。
米麦は1反(10アール)からの収量は数百キロだが、ジャガイモやサツマイモは約2トンとれる。
なのに穀類が重視されたのは、長期間保存でき富の蓄積に都合がよいのに加え、地下のイモとちがって実が見えるから収穫を査定し課税するのに便利だったからだ。
それらの穀物が「商品化」の主体となった。
大航海時代、ポルトガルやスペインは、新世界の金銀を欧州に持ち帰った。それがオランダや英国に流れこみ、経済の中心は北上する。
バルト海を沿岸で、小麦・大麦・ライ麦や、北海のニシンやタラの塩漬けの交易が盛んになった。沿岸の麦類をイベリア半島に輸出するなど、北海・バルト海貿易と南欧の地中海貿易を組み合わせることで商業国家として台頭したのがオランダだった。
砂糖はプランテーションで奴隷を使って栽培するることで「世界商品」になった。17世紀半ばは貴重品だったが、18世紀半ばに砂糖を入れた紅茶が普及しはじめ、19世紀半ばには価格が急落して英国労働者の日常的な食事になった。
手っ取り早く高カロリーを得られる食事として、小麦パンと砂糖入り紅茶が英国労働者の食事になった。
産業革命後、大地主と、工場経営の資本家との力関係が逆転し、国内農業を守る関税を定めた「穀物法」が1846年に廃止されると、米国やカナダからの小麦輸入も急増する。
産業革命後の自由放任主義による過剰生産で世界的な恐慌が起きた。それを克服するため公共投資が活用され(ケインズ革命)、資本主義の黄金時代を迎えた。日本も1955年から高度経済成長に入った。
米国の農業政策によって大量生産されるトウモロコシを原料に「ブドウ糖」などの新しい甘味料が大量生産されるようになる。最近まで日本はトウモロコシを世界一輸入していた。日本人の身体の炭素の4割はトウモロコシ由来だった。
1960年代の「緑の革命」は、生産性が高いハイブリッド種子と 化学肥料、農薬によって進められた。裕福な農家は収穫を増やし、穀物価格を押し下げ、貧しい農家を破産や借金漬けに追い込んだ。
日本は幕末の開国によって、海外の小麦や砂糖が流入する。
幕府は、居留地に外国人をとどめ、日本の商人が出向いて取引をするようにした。それによって欧米資本の国内への進入を食い止めたから、国内の資本蓄積が可能になり、アジアで唯一産業革命を実現することにつながった。
開国直後、輸入された真っ白な小麦粉は「メリケン粉」(アメリカの粉)と呼ばれた(在来の小麦粉は「うどん粉」)。
メリケン粉は均質で大量調達できたから麺類や菓子・パン、軍用ビスケットなどの工業原料として使われた。
輸入された砂糖は「洋糖」として、従来の砂糖と区別された。神戸で洋糖引取商から巨大財閥になったのが鈴木商店だった。
大豆は肥料である大豆粕の形で輸入した。それを使って桑を育て、生糸や絹製品を増産して外貨を稼ぎ、産業革命の原資にしようとした。
メリケン粉や洋糖、大豆をもとに、今につながる大手食品企業や製粉、精糖、製油産業が形成された。
戦後は、1985年の「プラザ合意」で、一気に円高が進んだ。86年の「前川レポート」は、国際競争力にとぼしい農業をスクラップし、その市場を外国産農産物にあけわたすという内容だった。これらによって日本の食市場は一気にグローバル化した。
また、ドルショック(金とドルの交換中止) によってゴールドで裏づけする必要がなくなって、所有するゴールド量や労働者がつくりだす価値の量とは別次元で金融資産を増やせるようになった。それが食料を含めてあらゆるものを投機の対象とする経済につながったという。
=================
▽24 穀物より芋の方が早く楽に大きなデンプンのかたまりを育てられる。でも、硬いからに包まれた軽い種子である穀物の方が長期間保存でき、遠くから輸送して集めることができた。富の蓄積に都合がよかった。
イモは地中に育つからどれだけ収穫できるか見えにくいが、穀物は一目瞭然。役人にとって収穫を査定しやすかった。支配する側にとって富の蓄積と課税に便利だった。
▽29 大航海時代、ポルトガルやスペインは、新世界の金銀を欧州に持ち帰った。金銀の流入で物価が上昇して経済が混乱。貿易や借金の支払いなどを通じて、新世界から奪って増えたお金はオランダや英国に流れこみ、経済と金融の中心は欧州を北上。
バルト海を囲む沿岸で交易が盛んになり、ドイツ東部やポーランドで生産された小麦、大麦、ライ麦や、北海のニシンやタラの塩漬けして樽詰めしたものなどが、交易された。バルト海沿岸の麦類をイベリア半島に輸出するなど、北海・バルト海貿易と南欧の地中海貿易を組み合わせることで商業国家として台頭したのが、ライン川河口で海に面したオランダ。
欧州諸国は「重商主義」で発展。……国王や特権商人が金銀をより多く貯めた国が強い国
▽39 砂糖 17世紀半ばまでは貴重品だったが、18世紀半ばには、砂糖を入れた紅茶や糖蜜が普及しはじめ、19世紀半ばには価格が急落して英国労働者たちの日常的な食事になるまで普及。
プランテーションで奴隷を使って砂糖を「世界商品」に。
▽43 手っ取り早く高カロリーを得られる食事として、買った小麦パンと砂糖入り紅茶とが英国労働者の食事になった。「朝から十分なカロリーを補給し、ぱっちりと目のさめた状態で働ける労働者」を用意するのに役立った。
小麦も、産業革命後、米国やカナダなどから安く輸入する動きが強まる。国内農業を守る関税を定めた「穀物法」が1846年に廃止。地主たちと、都市部の工業を率いる資本家たちとの力関係が逆転。
▽46 白い小麦パンと白い砂糖という「近代食」を主食とすることで、虫歯や結核に……身体がボロボロに。「食生活と身体の退化 先住民の伝統食と近代食 その身体への驚くべき影響」
▽47 第一次フードレジーム
▽ 自由放任主義による過剰生産で恐慌へ →ニューディール政策・ケインズ革命→資本主義の黄金時代。日本も1955年から高度経済成長
▽70 米国の農業政策によって大量生産されるトウモロコシを原料に新しい甘味料が大量生産。日本の食品化学者が1971年に開発。「異性化糖」「ブドウ糖」と呼ばれる。砂糖より安く、冷凍焼けを防げて、液状だからドリンクにも好都合。「果糖ブドウ糖液糖」はトウモロコシからつくられたHFCSの可能性が大。
……最近までトウモロコシを世界一大量に輸入していたのが日本だった。身体の炭素の4割はトウモロコシ由来だったという実験も。
▽75 米国中心の第2次フーとレジーム 大量生産の大豆やトウモロコシをえさに肉や卵、乳製品を大量生産する構造。大量生産した小麦や砂糖、油脂、動物性食品を原料とする加工食品・外食産業の発展。
▽90 1960年代、緑の革命 背が低く収穫良が多いハイブリッド種子 化学肥料を大量に投入しても倒れず収穫を増やせる。そのぶん病害虫に弱いため農業を必要とし、F1のため、種子を毎年購入しなければならない。
裕福な農家は収穫良を増加させ、穀物価格を押し下げ、貧しい農家を破産に追い込んだ。
農業資材の市場が飽和してくると、貧しい農民たちにも融資して、緑の革命の種子や農業資材を購入できるようにした。
「北」が「南」にカネを貸して、「北」の商品を「南」の農民に買わせ,その利益が「北」の企業に流れる一方で、その借金は「南」の農民に残るという構図。
▽104 幕府は、居留地に外国人をとどめ、日本の商人たちが出向いて取引をするようにした。江戸時代に商品経済が発展し有力商人たちがいた。これらの商人たちが居留地で外国商人たちに対応し、外国勢力を水際でとどめることができた。欧米資本の国内への進入を食い止め、日本での資本蓄積を可能にした実力と環境が、19世紀アジアにおいて日本だけが産業革命を遂行できた要因のひとつと考えられている。
産業革命の資金源として、国際貿易を担い外貨を稼ぐ日本の商人を育てようと、政府は三井や三菱などを支援して、政府の商人「政商」として発展させた。
▽106 開国直後、真っ白な小麦粉が輸入され「メリケン粉」(アメリカの粉)と呼ばれた。在来の小麦粉は「うどん粉」と呼ばれ、製麺につかわれたりしていた。
メリケン粉は均質で大量に調達できたため、麺類・菓子・パンの加工用として、軍用ビスケットやお菓子を製造する工業原料として使われた。
海外から輸入された砂糖も「洋糖」として、従来の砂糖とは区別された。神戸で羊糖引取商から操業したのが巨大財閥になった鈴木商店。
▽108 同じころ大豆も輸入増。肥料として農業を近代化しようとした。大豆粕を肥料にして、桑を育て、当時の主力輸出品だった生糸や絹製品の生産を増加して外貨を稼ぎ、産業革命を進めるもくろみ。
▽110 メリケン粉や洋糖をもとに大手食品企業が誕生。製粉、精糖、製油産業も形成。
▽112 石油化学産業が発展する前は、動物や植物を原料とする油脂は戦争のためにも重要な物資。日本は石油資源に
とぼしい一方で、満州の大豆、朝鮮半島周辺の魚油、東南アジアのココナツやパームなど、当時の世界における油脂始原の4割近くを勢力下に押さえていた。
▽117 「食と農の戦後史」
▽132 1985年の「プラザ合意」米国の貿易赤字を縮小するため、日本円やドイツマルクを含む通貨の対ドルレートを変えさせた。円高に動かして輸出をおさえようとした。
1986年「前川レポート」国際競争力にとぼしい農業部門などをスクラップし、その市場を外国産農産物にあけわたす政策。日本の食市場は一気にグローバル化。
▽141 オイルショック ドルショック(金とドルの交換を中止) 金で裏づけしないので、金の在庫量の制限なく金融資産を楽に増やせるようになった。
持っているゴールドの量や労働者がつくりだした価値の量とは別次元でお金が増やせるようになった。
▽143 3つめのショックは穀物価格の急騰。1972〜74。米国からの大豆が減り、日本は、ブラジルのアマゾン大開拓を支援
▽158 全体のまとめ
▽

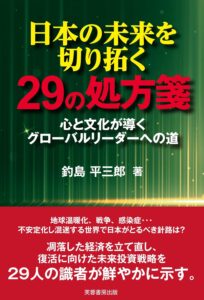



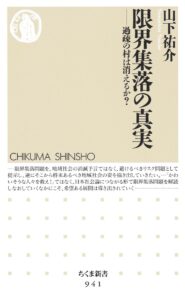
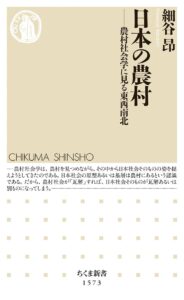

コメント