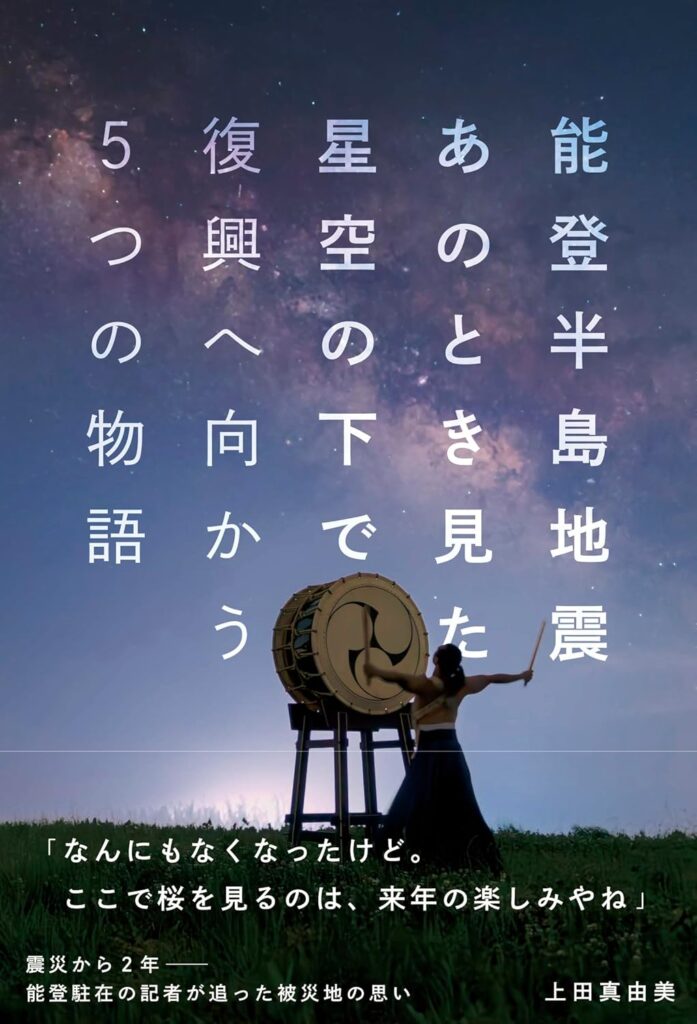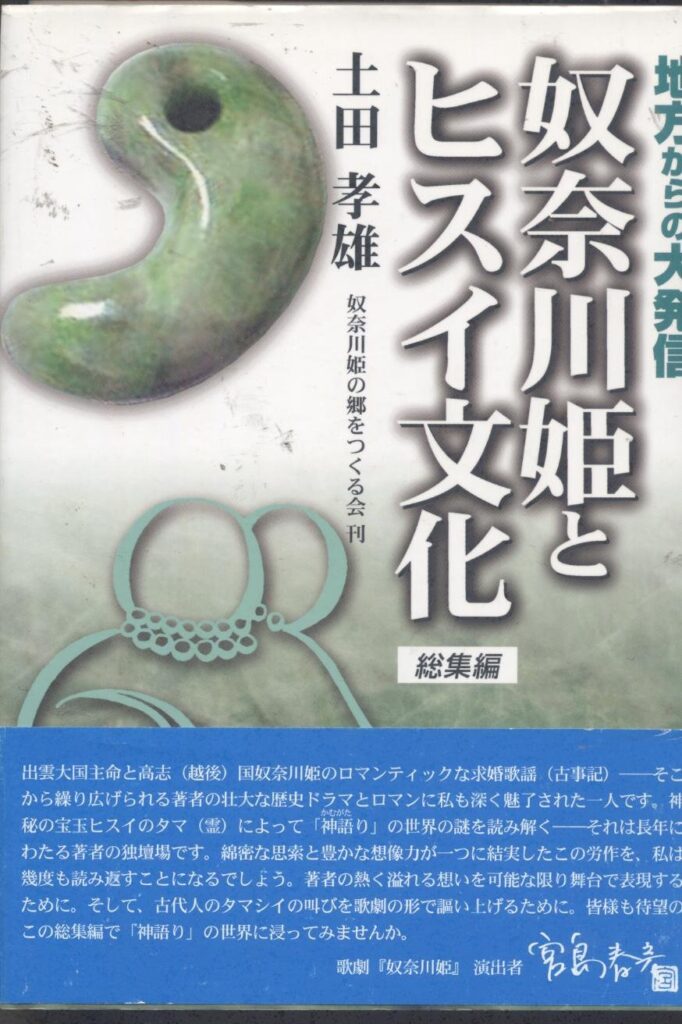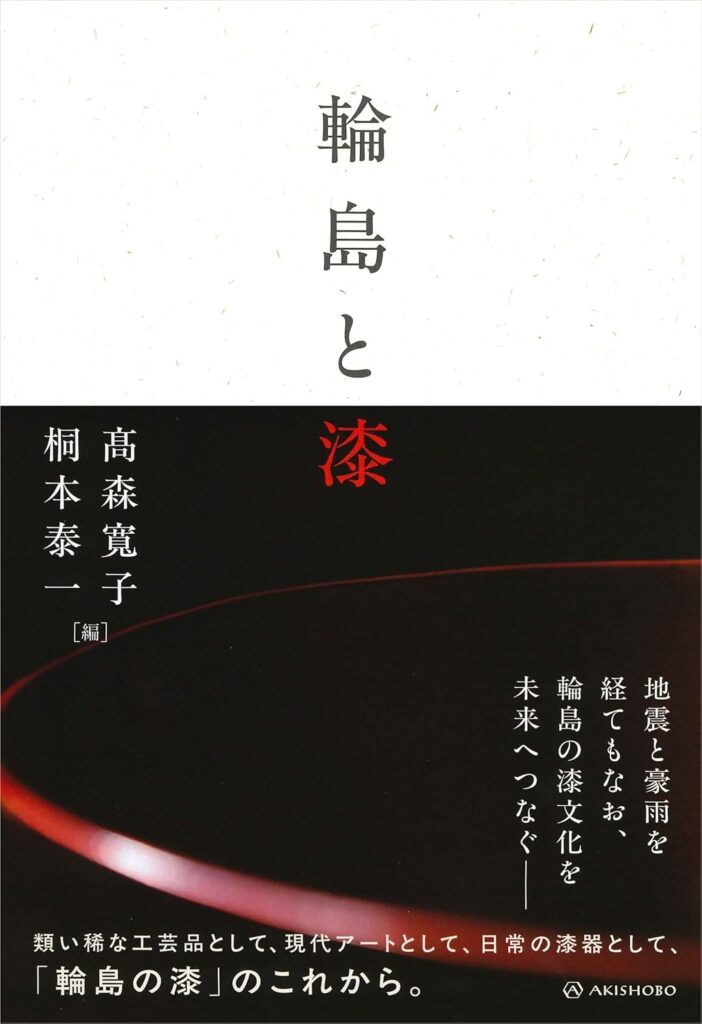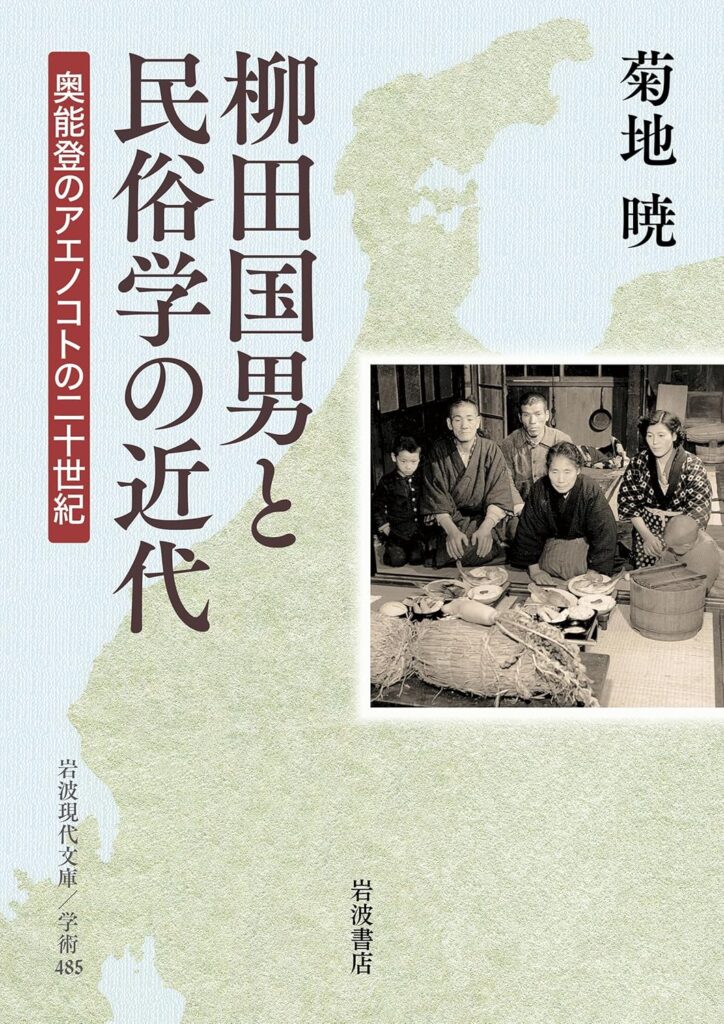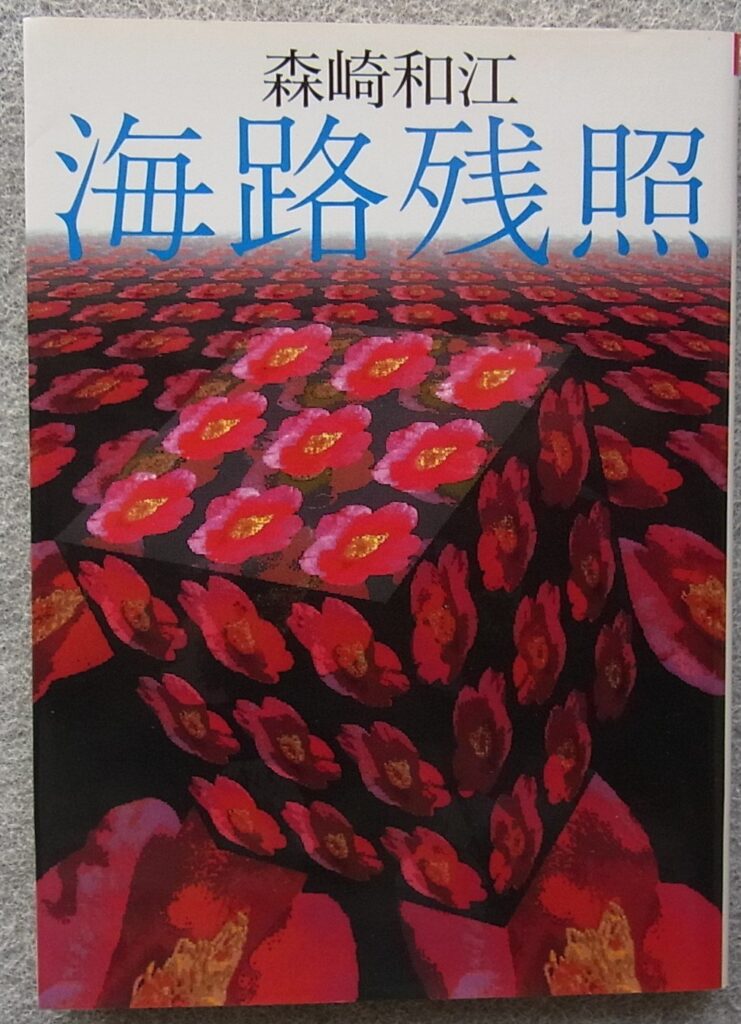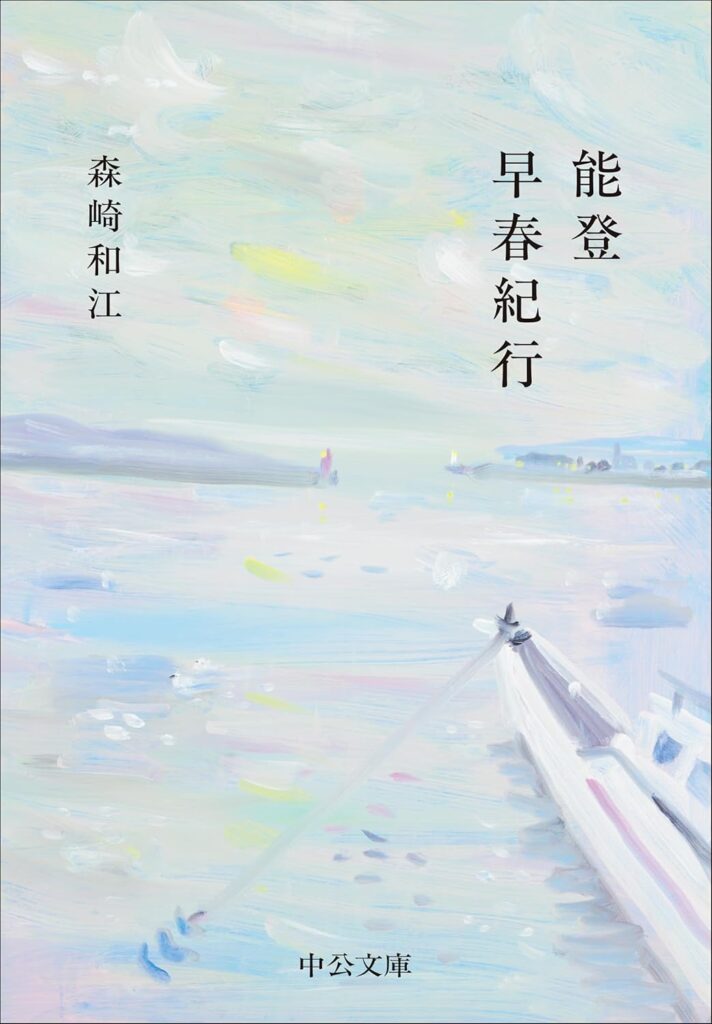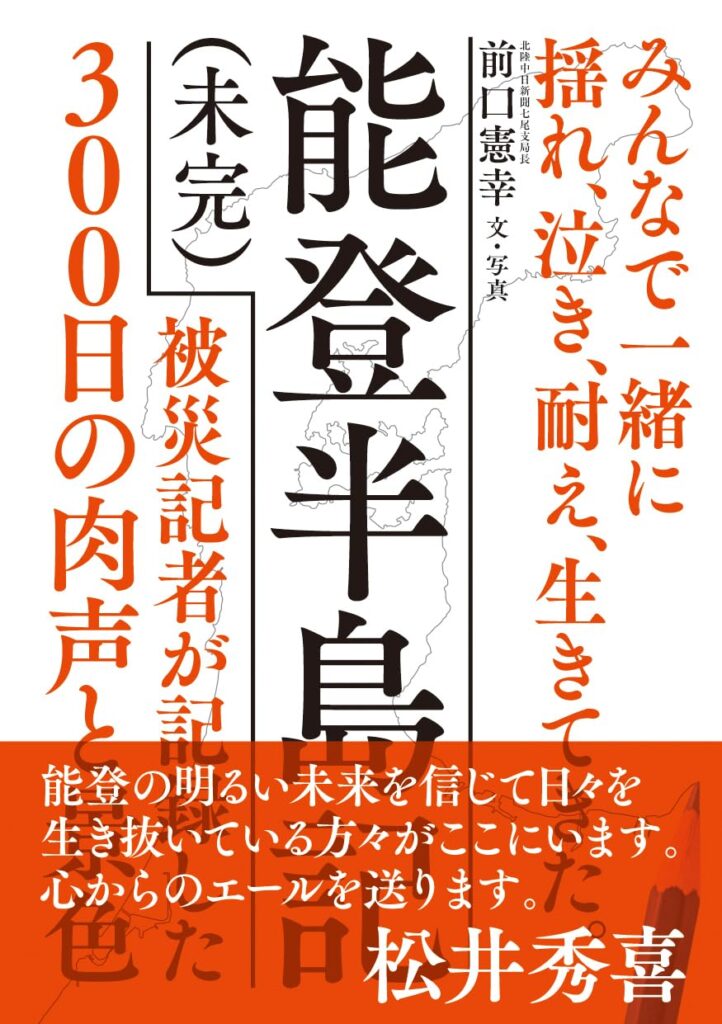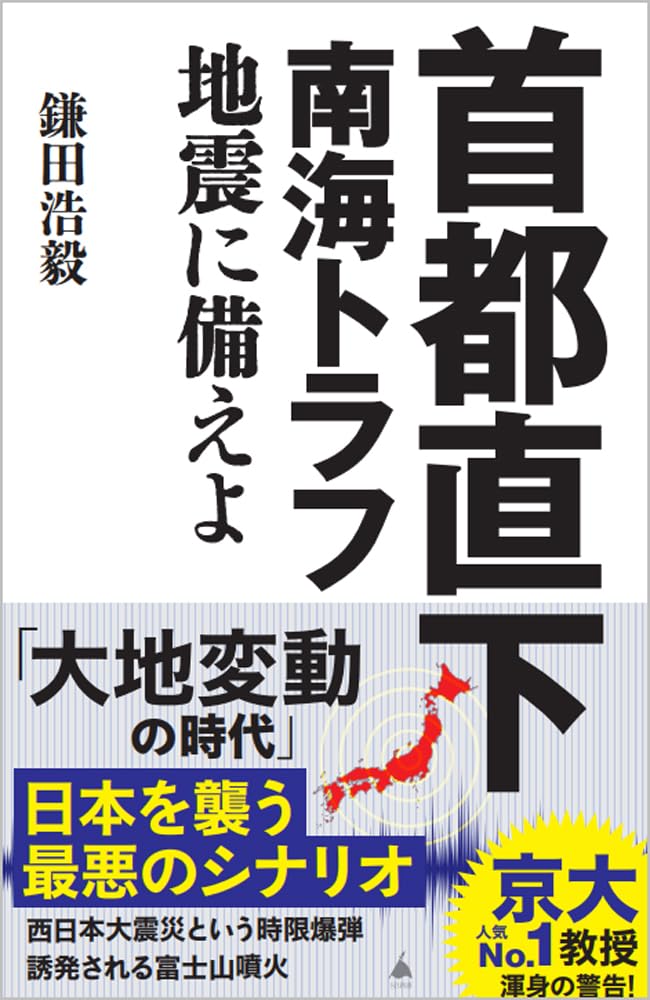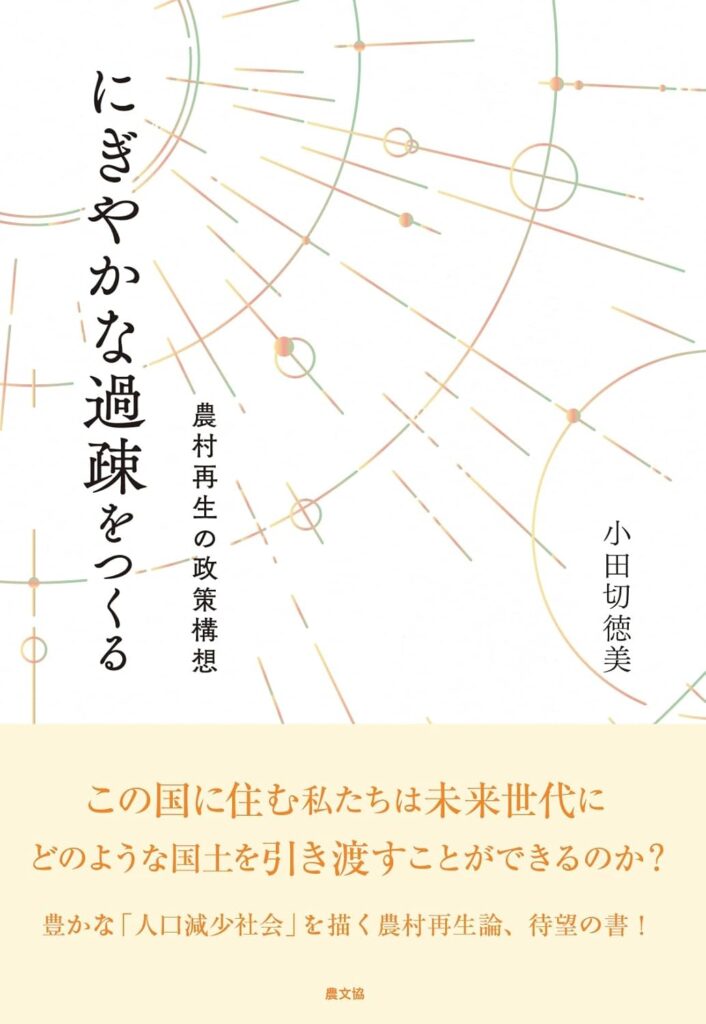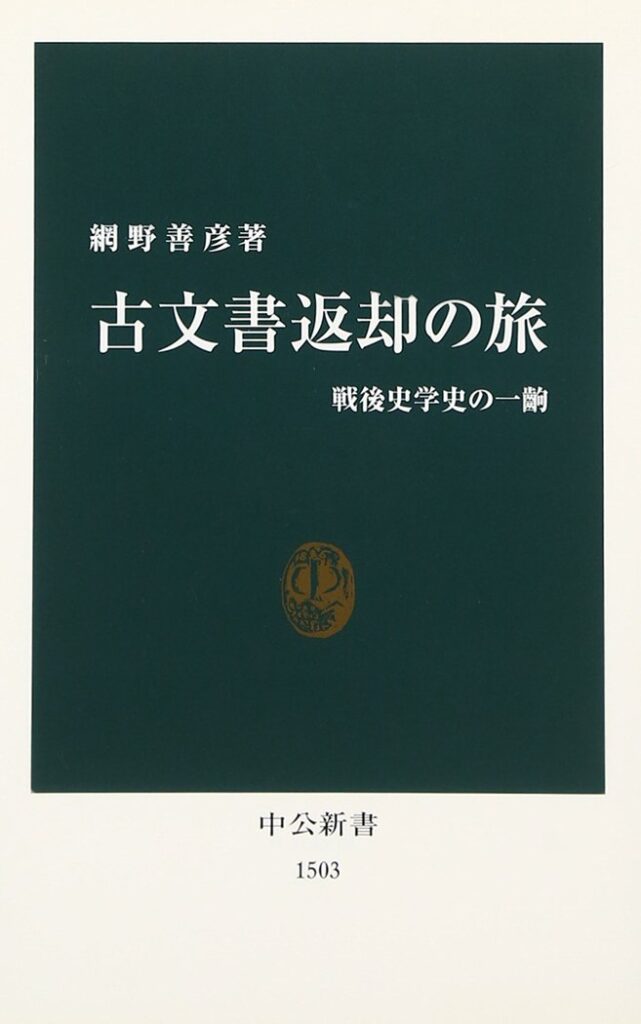能登・北陸– category –
-

能登半島地震 あのとき見た星空の下で 復興へ向かう5つの物語<上田真由美>
■朝日新聞出版 251217 筆者は、能登に駐在する記者の募集にこたえて能登半島地震3カ月後に東京から赴任した。 新聞記事は、事実を早く端的に伝えようとするからもれてしまうものがある。「新聞記事からこぼれ落ちてしまうけれど伝えたいこと」を「wi... -

奴奈川姫とヒスイ文化 総集編<土田孝雄>
■奴奈川姫の郷をつくる会251120 出雲とのつながりやフォッサマグナが生みだしたヒスイと信仰の関係を知りたくて奴奈川姫伝説のある糸魚川を訪ねた。地元の民俗資料館でこの本を入手した。 昭和14年までは日本ではヒスイが産出するとは思われていなか... -

輪島と漆<桐本泰一・高森寛子編>
■亜紀書房20250719 輪島は、日本一人間国宝にあえる町だ。ワイプラザというスーパーに行くと、ちょこちょこ人間国宝さんが買い物をしていた。 この本は、スーパーでよくお見かけした人間国宝の小森邦衛さんと、輪島の漆器業界のトップランナーである桐... -

柳田国男と民俗学の近代 奥能登のアエノコトの20世紀<菊地暁>
■岩波現代文庫250713 柳田国男がつくりあげた民俗学の実践は、農山漁村の民俗そのものの再発見以上に、ローカルな民俗をいかにしてナショナルなるものに接続させかが課題だった。柳田は、全国各地の民俗学徒を総動員して「日本」を語る共同体をつくりあ... -

能登デモクラシー<五百旗頭幸男監督>
私は新聞記者として奥能登の4市町を担当していたが、穴水町は話題の少ない、おだやかな町だった。 能登は全体に保守的で、役所がいばっていて、議会はなぁなぁなのだが、珠洲市には原発問題、輪島市では震災がれき問題があったから「野党」が存在した... -

海路残照<森崎和江>
■朝日新聞出版 20250328 玄界灘につたわる、ほら貝を食べて不老長寿になった海女が津軽に流れていくという伝説からはじまり、若狭や隠岐、越後の寺泊、佐渡の小木…の八百比丘尼の跡をたどる。 人魚の肉を食べて幾百年も生きつづけた八百比丘尼の伝説は... -

滞在型支援の金田真須美さん
■全国防災関係人口ミートアップ250224 支援者には興味がない。被災者からなにをどうしたらよいか、引き出すくらいしかできない。 丹波市の水害では役所からボラセンを立ちあげてくれ、と言われた。 センターの箱物とネットと電話回線、軽トラック2台... -

能登早春紀行<森崎和江>
■中公文庫250209 海女漁のある村では、女を不浄視して船に乗せないということがほとんどない。女性を不浄視する社会は、死をも穢れとする。森崎は、性も死も切り捨てるのではなく、生命の一部としていつくしもうとした。だから鐘崎の「海女」に興味をおぼ... -

能登半島記(未完): 被災記者が記録した300日の肉声と景色 <前口憲幸>
■時事通信出版250211 北陸中日新聞七尾支局の記者が、被災後の能登で暮らし取材する日々を毎日つづってきた絵日記のようなコラム。 生活者にしか見えない風景や言葉や知恵が立ちあがってくる。 たとえば非常時の備えは、「最優先は飲食ではなく、まして... -

減災社会シンポジウム「阪神・淡路大震災30年~『大災害の時代』へ継承すべきこと」250208
渦中の斉藤元彦知事の登場におどろくとともに鼻白んだが、議論の中身は濃かった ■室崎益輝さん基調講演▽進歩したこと 阪神淡路大震災では、家族や近所、消防団がかけつけて救助した。それを踏まえてコミュニティ防災が成長した。能登では、壊れた住宅で... -

罹災証明も仮設住宅もいらない 目から鱗の防災対応
「能登の今を知るオンライントーク 変わらない? 日本の災害対応」を聴いた。大阪公立大大学院の菅野拓准教授の講演は、災害対応の「常識」をくつがえすものだった。以下、その要約。 避難所での雑魚寝は1930年から変わらない。災害のたびに戦前... -

「不屈の器」
■NHK250119 輪島を代表する漆器工房「輪島キリモト」の、能登半島地震からの10カ月間を描いたドキュメンタリー。さすがNHKという作品だった。 元日に地震が襲い、桐本さんも5人の職人の家も全壊・全焼……となった。 18日後にようやく電気がくると工... -

首都直下南海トラフ地震に備えよ<鎌田浩毅>
■SB新書241221 まもなく起きる首都直下型と南海トラフの大地震。富士山の噴火の可能性も高まっている。大災害にどうそなえ、どううけとめればよいのだろうか。 能登半島地震はM7.6で、この地域では記録がある1885年以降で最大規模だった。数年前... -

にぎやかな過疎をつくる 農村再生の政策構想<小田切徳美>
■農文協240816 「にぎやかな過疎」は、石川県羽咋市の限界集落の移住者を撮ったテレビ金沢のドキュメンタリーのタイトルからとった。 人口減少は進むが、移住者や地域の人々がワイワイガヤガヤする様子をそう名づけた。今後の地域づくりの目標は「持続的... -

古文書返却の旅 戦後史学史の一齣<網野善彦>
■中公新書20240507 東海区水産研究所の一室で1949年、全国の漁村の古文書を蒐集・整理・刊行し、文書館・資料館をつくるという事業がはじまる。研究所の月島分室が担当し、日本常民文化研究所に委託した。 だが1954年度で水産庁は研究所への委託予算を... -

映画「風の島」<大重潤一郎監督>
■20240115 1983年に沖縄の陶芸家・大嶺實清氏が西表島の沖にある無人島・新城島(パナリ)でつくられていた土器「パナリ焼」を復活させた際の記録映画。 パナリ島はシーカヤックのツアーで訪ねたことがあったが、無人島に古い土器文化があったことなどは... -

北の無名碑 加賀移民の足跡をたどる<池端大二>
■北国新聞社 20230528 北陸から相馬・中村藩(福島)への真宗移民について知りたくて入手した。 天明の飢饉で、奥羽では、農民が故郷を捨てる流亡が相次いだ。50年後の天保の飢饉でも多くの農民が餓死し、町への逃亡者が続出し、人口が3分の1に激減... -

映画「はりぼて」20200803
富山市議会の政務活動費問題をスクープし、市議十数人の辞職につなげた富山市の「チューリップテレビ」の取材の過程を記録したドキュメンタリー。 はじまりは富山市議会議員の月給10万円アップだった。 市議会のドンと呼ばれる自民党議員に「有権者は... -

富山県の歴史
■山川出版社 20190527 読みにくくおもしろくない。でもまあ、辞書的には使える。以下抜粋。 ▽2 「環日本海諸国図」は1994年に富山県土木部が作成。 ▽4 城下町富山は「外山」と記載されることが多かった。 …越中の国は、古代のはじめは越の国に属した... -

作業中)世界遺産を守る民の知識 <関口広隆>
■世界遺産を守る民の知識 <関口広隆>明石書店 20150123 ▽4 田んぼの上に帽子のように森がこんもりかぶさっている。森の少し下は、薪や用材を手に入れる林になっているところも。田んぼの下には、耕す人たちの家がぽつぽつ散らばり、…さらに下には人び... -

作業中)若狭 日本の風景を歩く<水上勉>
■若狭 日本の風景を歩く<水上勉> 20141216 若狭は原発のイメージが強すぎて、小浜以外は魅力を感じていなかった。小浜に魅力を感じるのは、若狭では珍しく原発がないことと無関係ではない。自然の景観の美しさは同じでも、原発ができると精神文化は大... -

縄文人の世界 日本人の原像を求めて<梅原猛編 三方町縄文博物館長>
■縄文人の世界 日本人の原像を求めて<梅原猛編 三方町縄文博物館長> 20141111 □梅原 ▽12 今まで狩猟採集をし、流浪していて、文化の低いと考えられていた縄文人が実は定着していて、しかもかなり高い精神文化をもっていたらしいということは明らかに... -

魚津フォーラム米騒動を知る
■魚津フォーラム米騒動を知る <NPO法人米蔵の会> ▽米蔵の会理事長 慶野達三「米騒動は今日の国民一人一人の生活、基本的人権を求めた先駆けであり、歴史的に大きく評価されます」 ▽大成勝代 編集長 魚津の米騒動は社会に混乱をもたらしたという目に... -

藤野厳九郎<土田誠> 魯迅と藤野厳九郎<芦原町教委>
■医師藤野厳九郎<土田誠> 20141004 著者87歳で書いた本。元新聞記者。小説風に記してあり、とても読みやすい。幼いころ藤野の診察を受けた。新たに20人に取材したという。 ・見渡すかぎり水田がつらなる越前平野に20数年ぶりに帰ってきた。 ・父も祖父... -

鶴のいた庭<堀田善衛>
■鶴のいた庭<堀田善衛> 20140718 富山県高岡市の伏木の取材に関連して読んだ短いエッセー。堀田善衛の本はずいぶん昔に読んだことがあったが、北陸の豪商の出身とは伏木を訪ねてはじめて知った。 堀田は伏木で最大の回船問屋「鶴屋」に生まれた。庭には... -

北前船の近代史 <中西聡>
■北前船の近代史 <中西聡> 成山堂書店 20140522 北前船が生まれた時代や経済の背景、北前船がもたらした経済の影響などを綿密に記してありとてもおもしろい本だった。 北前船というと江戸時代というイメージがあるが、江戸時代に藩と結びついて活躍し... -

北前船おっかけ旅日記<鐙啓記>
■北前船おっかけ旅日記<鐙啓記>無明舎 20140513 三度にわたる長期取材はまず、100冊ほどの資料を集めて200カ所の寄港地を割り出した。そのうち164の港をめぐった。その取材日記をまとめた。 第2次取材では、取材予定先100カ所以上に資料の... -

北陸線の全駅乗歩記<澤井泰>
■北陸線の全駅乗歩記<澤井泰>文芸社 201403 北陸企画のネタ探しのために買った。文章じたいがよいわけではないが、北陸線とその視線の駅をすべて降りているから、北陸のそれぞれの町の概略や名所、食べ物などを知るのにぴったりだった。鉄道が好きだか... -

能登・間垣の里 文化的景観保存調査報告書
■能登・間垣の里 文化的景観保存調査報告書 <輪島市教委201203>20121218 ▽8 西保地区は、上山、西二又、上大沢、大沢、赤崎、下山、小池の7字からなり、1889から1954まで西保村だった。役場は大沢。 1954年に輪島町・大屋村・河原田村... -

ためされた地方自治-原発の代理戦争にゆれた能登半島・珠洲市市民の13年<山秋真>
■ためされた地方自治-原発の代理戦争にゆれた能登半島・珠洲市市民の13年<山秋真>桂書房 20120110 旅行で偶然珠洲に立ち寄った女子学生が、推進派の現職市長に無名の若者がいどんだ1993年の市長選に参加する。原発計画とたたかう人々のなかで...
12