■鶴のいた庭<堀田善衛> 20140718
富山県高岡市の伏木の取材に関連して読んだ短いエッセー。堀田善衛の本はずいぶん昔に読んだことがあったが、北陸の豪商の出身とは伏木を訪ねてはじめて知った。
堀田は伏木で最大の回船問屋「鶴屋」に生まれた。庭にはつがいの鶴を飼っていた。
屋根の上には海を一望できる望楼があった。北前船の船主屋敷には望楼が残っているところが多いが、「見張っていた」と説明されるだけで本当の意味は理解できなかった。この本を読んではじめてわかった。和船は、汽笛を鳴らすことができない。港に近づいても自分の存在を知らせる術がない。そこで望楼で水平線を見張り、船が見えるとみんなに知らせ、水夫が泊まる部屋の掃除や料理、宴会の準備などをはじめた。船が着くと、祭りのように町がわきたった。
また、遠眼鏡で空を観察して天気を予測し、出航日などを決めていた。陸の指揮所の役割を果たしていた。汽船の導入によって、望楼もまたお役ご免になった。そういう歴史を知ると北前船の船主屋敷を異なる視点で見られておもしろい。
千石船から合子船、蒸気船と変わり、隆盛をきわめた北前船の問屋は没落する。その急激な変化を、栄枯盛衰を見てきた曽祖父の姿と重ねあわせて描いている。
=====================
▽316 白壁の倉にとりかこまれた、屋根の上に小さな望楼のついた家がある。
▽ 庭で鶴を飼っている。千と萬という名前のつがい。回船問屋ヤマイチ鶴屋の象徴。渡り鳥がこの庭の池に何十何百か来て、去った。羽を切られていた鶴は、かわるがわるにやって来ては去ってゆく渡り鳥にとりかこまれ、いつも池にとり残されていた。
▽320 曽祖父は、・・・千石船から帆船(スクーナー)、合子船、すなわち鉄と木と、帆と蒸気とを併用した船、更に石炭を焚き濛々と煙を吐いて走る鉄船までの変遷を見てきた曽祖父は、・・・二羽の鶴と鶴屋そのものの運命をも見透かしていたのかもしれなかった。
私が生まれて1年後の大正8年、滑川に発して全国に波及した米騒動もまた、・・・それが全国的な規模をもちえたということ、これも曽祖父にとっては異常な衝撃であった。・・・合子船や蒸気船が、湾の入口でkたたましい汽笛を吹鳴することが出来るようになってからは、屋上の望楼も廃物になってしまった〓。
▽322 百畳はたっぷりあったはずの二階の間。・・・階段は店の次の間の押し入れの中にあった。しかも、この階段は、箱をつみかさねたような風になっていて、いつなんどきでもとりはずすことが出来る。
・・・要するに、家はなにものかに対して完全に擬装していたのである。・・・官憲にとって、廻船問屋とは、密輸入、密航業者であったのである。・・・銭屋の家の構造もまた似たりよったりのものであった。
・・・合子船や蒸気船は、けたたましく帰港の合図の汽笛を鳴らす。けれども、帆をかけただけの和船は、陸から見つけられるまでは、たとえどんなに苦難の航海をつづけて来たとても、帰港を知らせるためのどんな手だてももっていない。それを見張っているのが、この望楼のおもな役目であった。
・・・望楼で遠眼鏡をもって水平線を睨み、空の雲と海の色とをこまかに観察し、明日、明後日、一週間後、一カ月後、二カ月後の、他国の空と海の模様を、経験と勘だけに頼って考え詰める役目の人は・・・いわば陸の指揮所に立った船長である。しかも彼は測候所長をも兼ねなければならぬ(〓だから藤井能三が測候所をつくった?)
・・・「御船のお帰り--」と大声を発したとする。船頭や水夫たちの、留守居の家々は、にわかに息づき、・・・雨戸をあけ、戸障子をはたき・・・買い物に走り・・・問屋は二階三階に下働きの人々が上がり込んで雨戸をくり、窓を開あけ・・・倉をあけて朱塗りの膳や・・・をとりだし・・・花街へ知らせが行き、歌妓たちは風呂へ走り髪を結い・・・。
▽324 曽祖父も祖父も、学校の名のつくどんなものへも上がったことがなかった。学校とは、ようやく私の父と母の代から上がることになったものであった。女の人が歯に鉄奨(かね)をつけて、真っ黒な歯を色あせた唇のあいだからのぞかせていたのも、つい昨日のことなのだ。
・・・黒漆に金蒔絵のついた駕籠。曽祖母が輿入れしてきた。後年、この家が粉みじん粉砕されたとき、この駕籠が、子供たちの一年間の学資になろうとは、まだ誰にも想像がつかなかった。
b・・・曽祖父は対象1年の元旦の早朝、北の海に海鳴りの底深くとどろくなかで、静かに息をひきとった。数え年96歳、名を善右衛門といった。(堀田善衛の名前もそこから〓)




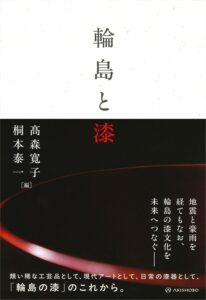


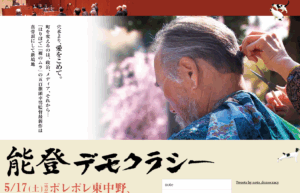
コメント