渦中の斉藤元彦知事の登場におどろくとともに鼻白んだが、議論の中身は濃かった
■室崎益輝さん基調講演
▽進歩したこと
阪神淡路大震災では、家族や近所、消防団がかけつけて救助した。それを踏まえてコミュニティ防災が成長した。能登では、壊れた住宅で亡くなった人は阪神の1/2?だった。コミュニティ防災が浸透したから、津波から避難も早かった。
▽光と影
学ぶ側だけでなく伝える側にも神戸での被災経験を伝えてこれなかった責任がある。
たとえば避難所の環境。仮設トイレは導入されたが、雑魚寝環境は30年たっても同じ。
「制度・しくみ」=形式にしばられてうまくいっていないこともある。
東北の高台移転につかった制度は、本来は、水害の際に僻地の住宅を中心市街地に移転させるためのものだった。だから対象は住宅だけだった。東日本の被災地ではインフラがなにもない高台に移転するのに、住宅だけが対象となってちぐはぐだった。
▽阪神の教訓
「防災」だけではなく、一定のリスクは許容しながらよりよい社会をつくり「減災」を考える。
消防防災だけではなく、災害がおきる前に「危機管理」をする。一方、想定外のことがおきたときのために「クライシスマネジメント」も必要。
平時と災害時のとりくみをつなげ、福祉と防災を一体化する必要がある。 従来の復興はまず計画をつくって事業をはじめた。LA火災でのアメリカの対応は、計画と事業を同時にすすめている。被災者への財政支援は先行させている。
▽復興
被災者の考えをベースにしなければならない。創造的復興というのは「人間を軸にした新しい社会へと、質的に世の中を変える」という意味。阪神淡路をきっかけにハードよりも市民活動中心の社会ができはじめた。(最近は少し萎えてきたが)避難所の運営も市民がになう。
町づくり協議会と、行政と住民の間をつなぐ中間支援組織が必要。この組織は住民7,行政3の割合で重みをおく。
▽記録の重要性
①調査をしてニーズを科学的にとらえる。
教訓資料集など多くの記録をのこした。活動した人や遺族のオーラルヒステリー、生の声を残してきた。
②5,10,15年と、5年おきに検証事業をして、復興の方針を修正してきた。
日本は現物支給中心だが、それよりも現金支給を積極的にしたほうがよいケースも。サンフランシスコや台湾ではカネをくばることが、自由で多様性をみとめる意味で重要だった。現物支給は硬直的な対応になりがちだ。「国際総合検証会議」はそう指摘していた。国際的に検証するというのも大切だが、最近はないがしろにされている。
▽計画の策定
バラックをたてられないようにと「2カ月は仮設住宅は禁止」とし、復興計画をつくるまで動かなかった。それが大きな混乱をもたらした。
料理は「はじめちょろちょろなかパッパ」だが、復興は逆。復興は最初のがれき処理や家屋の解体は2カ月でやりきるスピード感が必要。まずがれきを撤去してきれいになったら、今度はあわてず、未来の絵をじっくり考える。そこでは時間をかけないといけない
阪神淡路大震災後、住宅再建の公費助成の制度ができた。一方で、地域経済の建て直しが弱かった。地域経済の再生と住宅再建は車の両輪のはずなのに。生業再建に少し手を抜いていた面があった。(〓能登はますます)
▽復興基金
地域が自由に使える「復興基金」が必要。これも阪神淡路大震災をきっかけにはじまった。
1999年の台湾の地震で「基金」が効果をあげ、2004年の中越地震ではコミュニティが自由に使えるようにした。なによりも大きかったのが、コミュニティが基金をつかって復興支援員の若者3人を雇用したこと。これこそ能登に伝えないといけない〓〓。
▽被災者復興支援会議
副知事もはいって週1回会議して、メンバーが仮設住宅に入って声をきいた。アウトリーチ。そこからLSA生活支援員を仮設や公営住宅におくなど新しいシステムや、NGO、コミュニティ、企業、行政がタイアップする制度をつくってきた。
▽災害動向
巨大化とともに多様化している。たとえばアレルギーの子や要介護者、外国人に冷たいおにぎりだけでよいのか。住宅再建に300万円配るだけでよいのか。どんな制度にするのか、役所側ではなく、ボランティアやコミュニティの側が献立を提案する必要がある。災害が巨大化しているのだから、防災も進化する必要がある。
▽インフラ復興から人間復興へ
能登の避難所は「生きる権利」が軽んじられている。元々借家に住んでいた人は「仮設から1年で出ていけ」と言われている。「1人1人の命と暮らしを守る」を目標にしないといけない。
▽仮設より応急修理
公費解体にいっせいに流れているが、「修理して住みたい」という人が多い。仮設住宅より「応急修理」のほうが安いことが多い。250万もかければ住みつづけられる。
仮設住宅をつくるより、最初から恒久仮設をつくる。
高齢者と若者が集団的に住むコレクティブハウジングも阪神淡路大震災後に提案されたが軌道に乗らなかった。公営住宅の大量供給というのは改めたほうがよい。
▽システム改善
災害救助法は戦後直後からほとんど変わっていない。「復興」は法体系がほとんどない。コミュニティ維持や地域経済をどうするか掘り下げないといけない。
私は30年前は火災の専門家だった。大火を防ぐには木造はだめ。強風を考えれば50メートル幅の道路も整備しなければならない。だが、そうしようとすると進まない。だからまずは元の生活にもどすこと。30年後からは燃えない町づくりに手をつけなければ、と考えた。その30年後がきている。
「自律分散社会」のコンパクトシティー これは1カ所に集めるという意味ではなく、コンパクトでも自律できる町という意味。
高齢福祉社会には「地域福祉住宅」の普及を。
■上田真由美 能登現地報告
死亡者は526人、この1週間で関連死が10人増えた。
昨秋から解体業者が宿泊できるようになり、解体がすすんで更地が増えてきた。朝市は5ヘクタール249棟。今は更地に。
いまだに電気や水道がだめな集落も。玄関口まで水道が通れば「通水」とされるが、家のなかの配管がなおらず使えないケースも。
9月の豪雨災害で16人死亡。集落はあちこちで孤立した。仮設6カ所218戸で床上浸水。
奥能登の人口は50804人。輪島・珠洲は1割減。住民票ベースだからもっと減っている。草刈りができず、道普請もできず荒れる集落が増えてきている。
輪島は9小学校を3つに減らす計画。珠洲は9校(うち2校は小中学) 地域コミュニティの核だからと統合しない方針。ただ「大きな学校で学ばせたい」という声も。大谷小中学校は23人だったが今は全校生徒5人。
「町づくり協議会」をつくる動き。正院では先週発足。
狼煙は50世帯100人で高齢者が67%だった。月1回第2土曜の夜、復興会議。その結果をすべて周知している。今は70人くらいはもどってきた。
珠洲の「復興支援ガイドツアー」やのと鉄道の「語り部列車」も。
■パネルディスカッション
▽御厨
阪神淡路の際、下川辺復興委員長に「資料を残さないといけない。同時進行で話をききたい」とオーラルヒストリーとして貯め込んだ。「30年は出せないよ」といっていたが説得して3年で公開した。
▽阪本
阪神のときは神戸大学院生。火災も消せない、自衛隊は要請がないからと出動できない、避難所はトイレもなく、食料や物資を奪い合う。なぜこんなことに? そう思って防災を研究してきた。
①大地震はおきないという思いこみ。震度5程度の地震を県や市は想定していた。被害想定してそれを裏切られた。「被害想定」からの発想でよいのか?
②地方分権。自治体が対応するが、被災自治体を支援する仕組みがなかった。今になって考えはじめている。
③自治体は「支援」を活用するマネジメントができていなかった。
一方、地域の力が命を救った。避難所では地域やボラが対応した。
その後、医療やボランティアの全国組織がつくられて、すぐに現地に入る体制ができた。能登半島地震では私も1月2日に石川県にかけつけた。阪神とは大きくちがった。3日には穴水の避難所へ。独自に福祉避難所を開設していた。珠洲ではボランティアが避難所の悉皆調査を開始していた。災害がおきてすぐに民間も入るようになった。
▽頼政
被災地NGO協働センター 阪神のときは6歳で広島にいた。
七尾に拠点をおき、物資をあつめて配布した。2月から5000人が利用。在宅被災者はほとんど支援がなかった。ごはんをつくれれず洗濯もできない。
「好きなものを好きなだけもっていってください」
お茶を飲めるスペースをつくった。
足湯をしていろいろ話を聞いてニーズをひろう。
阪神のときより支援は多様化しているが、「自粛」によって一般のボランティアが少ない。ボランティアの力は「役立つ]だけではない。毎日きてくれるおばあちゃんはがんの末期で余命1カ月と言われていた。「私は元気だよというためにきとる。リハビリになるし」。7月に亡くなった。ボランティアがいたからがんばって生きてきたのかなと思う。
▽長沼 神戸新聞論説委員・防災士
27歳だった。西宮の自宅が全壊しとじこめられたあと救出され、仕事にでた。
阪神の教訓は、耐震化したかどうかでまったく被害がちがったこと。耐震化率は上がってきているのは、新しい家が増えているから。田舎では古い家がそのまま残っている。能登でも同じことが繰り返された。関連死をゼロにしたい、と思ってきたが、能登の避難所は30年前と同じ。阪神淡路のとき最初の関連死は「避難所で老人24人死亡」と報じた。能登や熊本は直接の死亡を関連死がうわまわる。
▽阪本
災害対策本部の設置や、現地に国がはいるスピードはスピードアップしている。でも自治体にも省庁にも災害のプロがいない。寄せ集めで同じ失敗をくりかえす。
▽門脇
阪神のころは「心のケア」はなかった。その後浸透してきたから支援に入れるようになった。
▽阪本
記録を残すことと人材育成が大切。東日本では宮城に行った。阪神のときの生活調査の結果はわかるが、どうやって進めたのか、様式はどうだったのか知りたかった。それが「人と防災……」に残っていてありがたかった。「記録」を使って、災害対応にあたる人を育成する。
▽御厨
東日本では神社境内の石碑が倒れた。それを処分するという。よくみたら、江戸時代の地震について漢文でくわしく書かれていた。漢文だから忘れられていた。記憶を伝えるのは難しい。
▽御厨
南海トラフのことで高知市を取材した。すごい緻密な対応表をつくって訓練をくりかえしている。だが、来るか来ないかわからない地震のためにくりかえしてつかれていた。避難塔のドアに鍵がかかっていたから指摘したら「ドアをあけるとごみの山になります」と言われた。
▽阪本
ふだんの生活を豊かにして災害時に機能するようにする。たとえば北海道の〓では役場を作る際に住民の希望を入れて、カフェとランドリーと運動施設を併設した。これはまさに災害時に活用できる。
▽頼政
防災だけをやってるとつかれる。運動会に防災の要素を加えるとか。外国人は訓練なんか出てこない。ならば国際交流センターで防災食の試食をする。ふだんの活動に災害要素をプラスする。







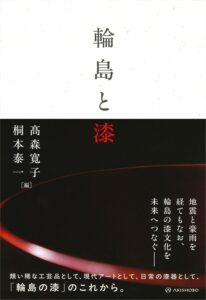
コメント