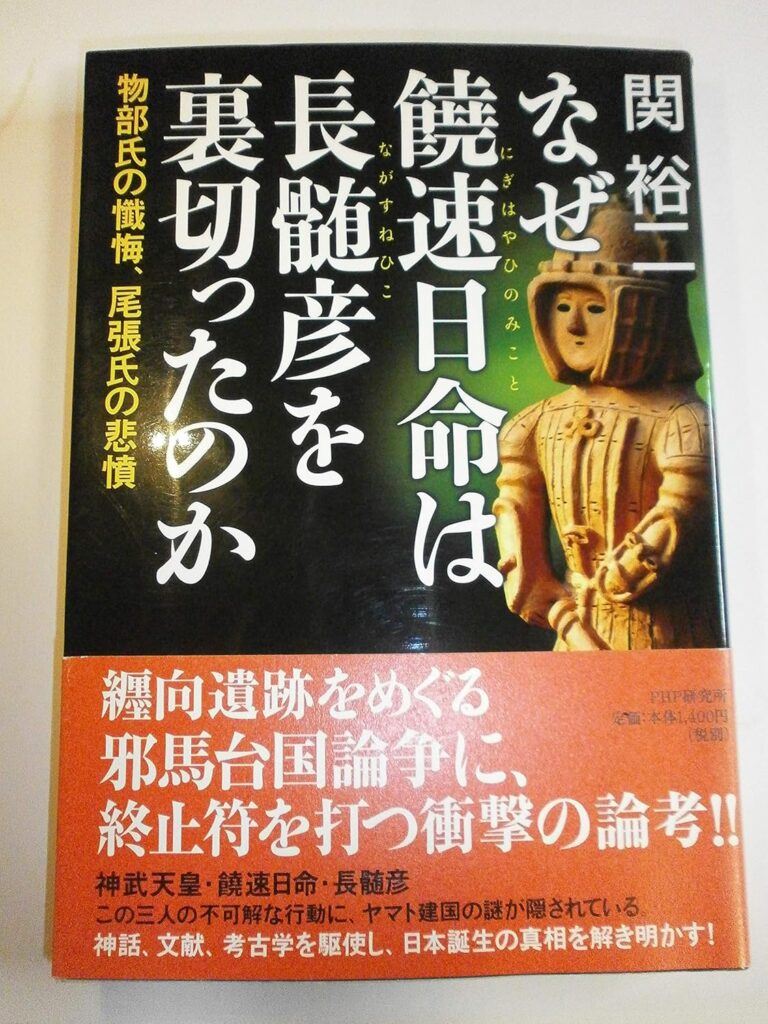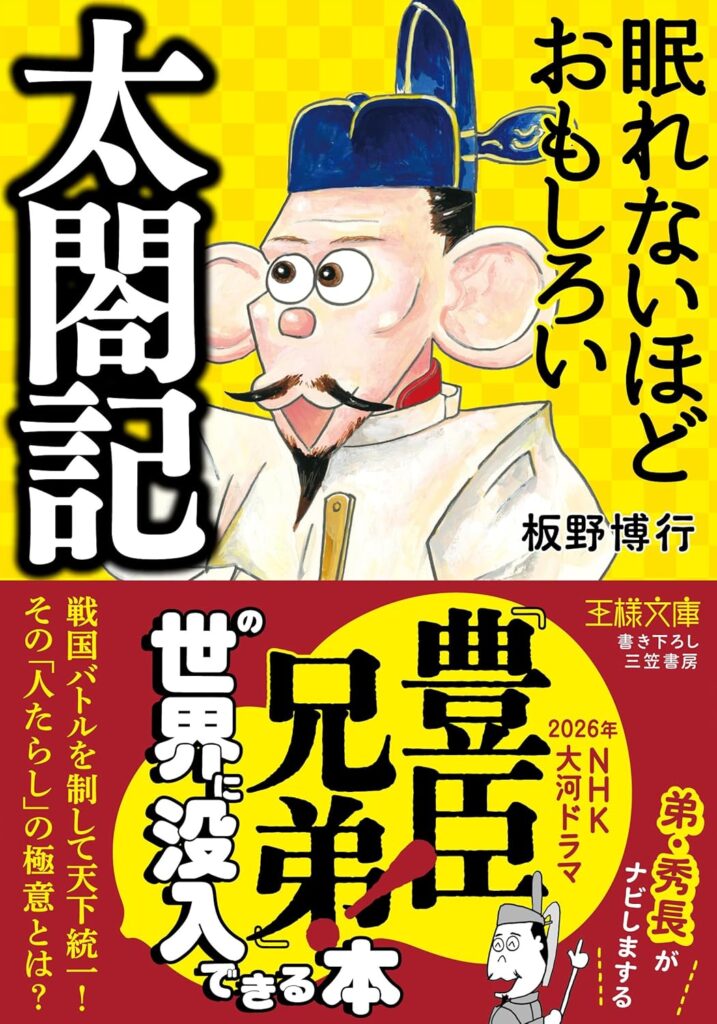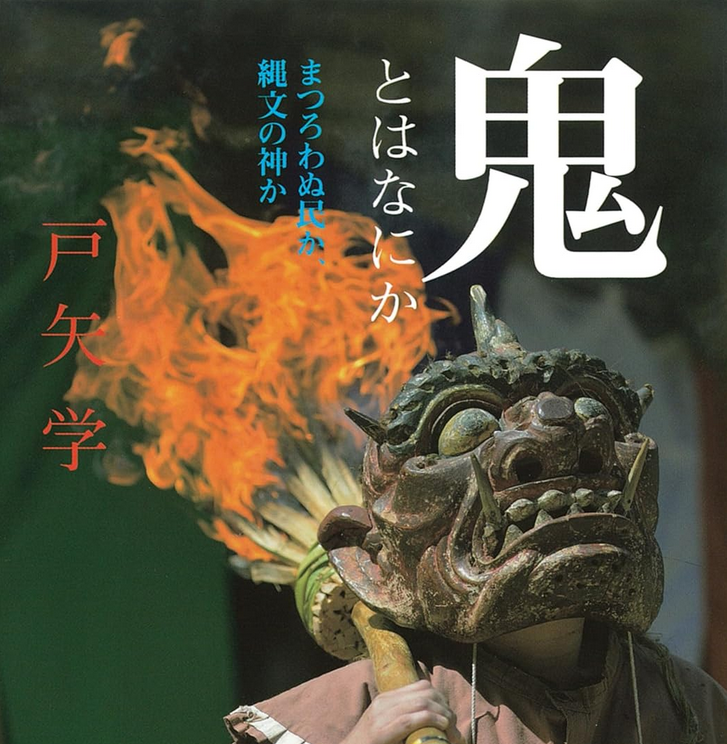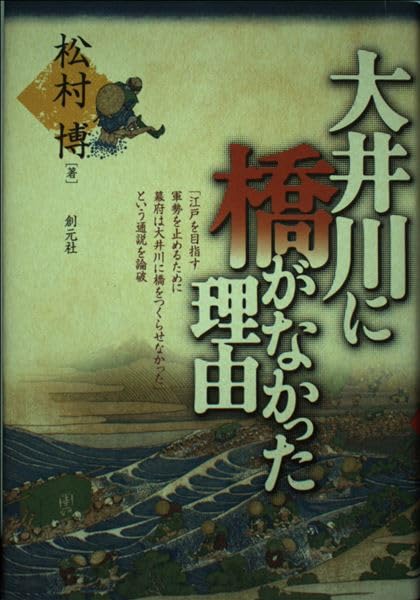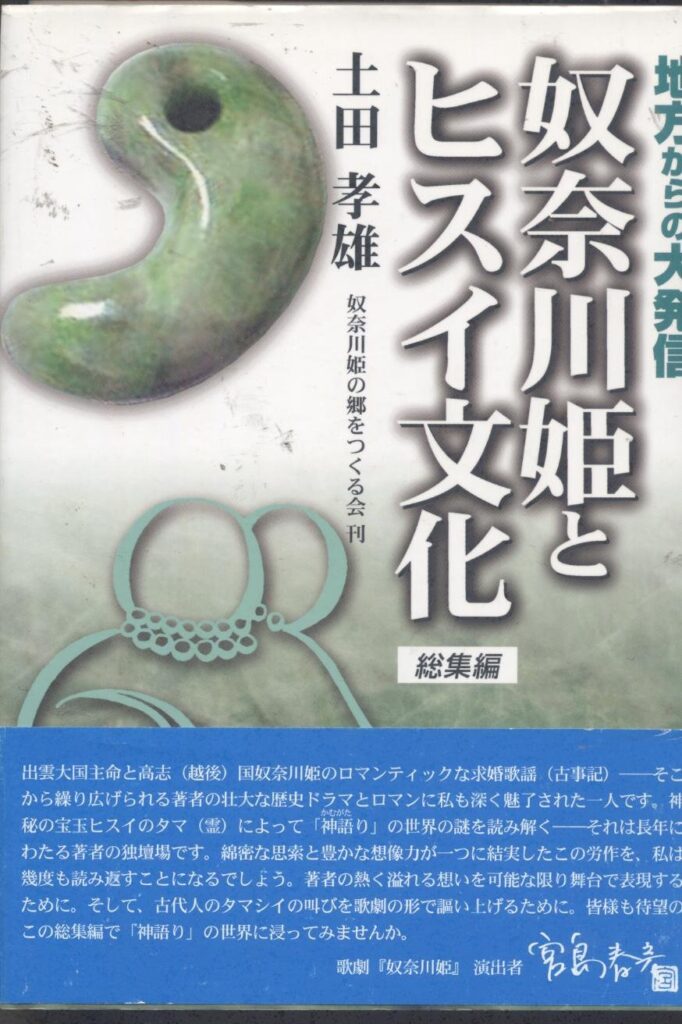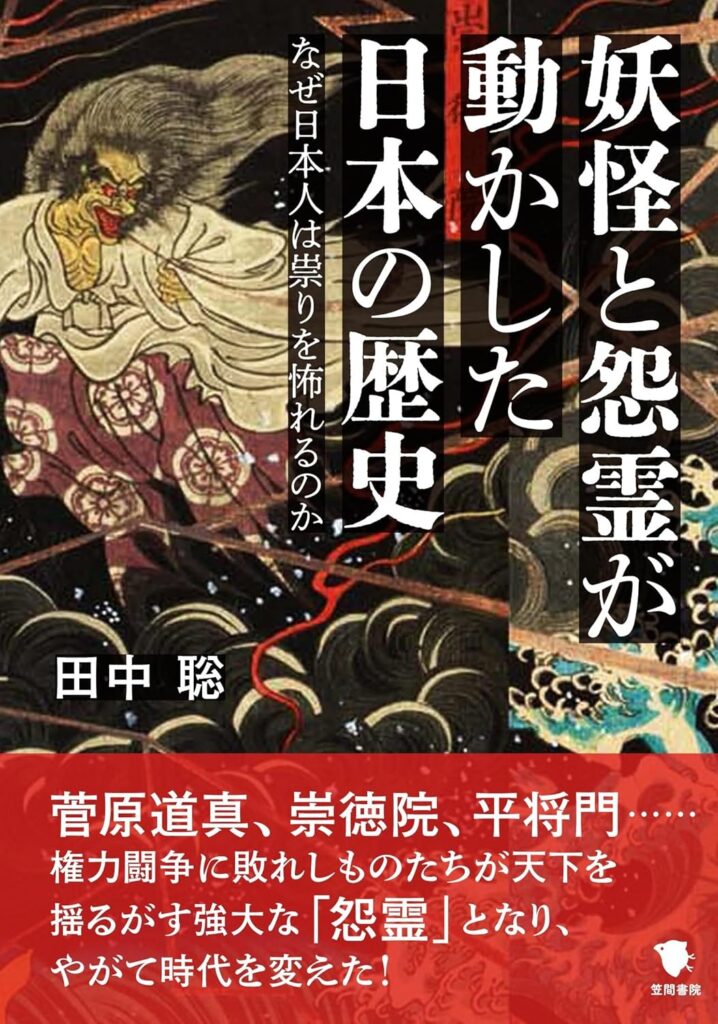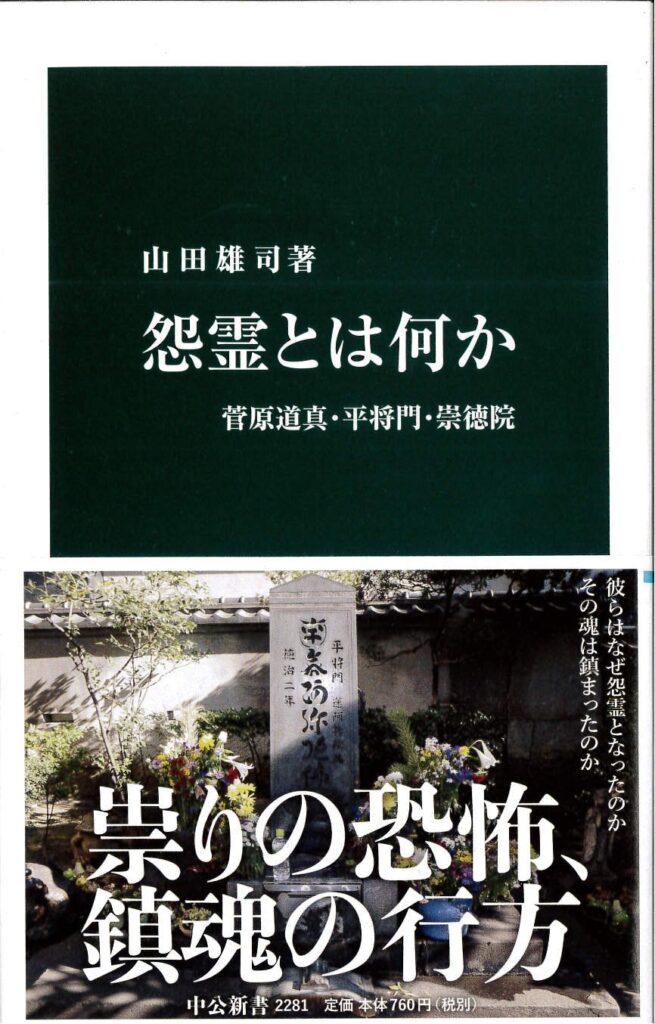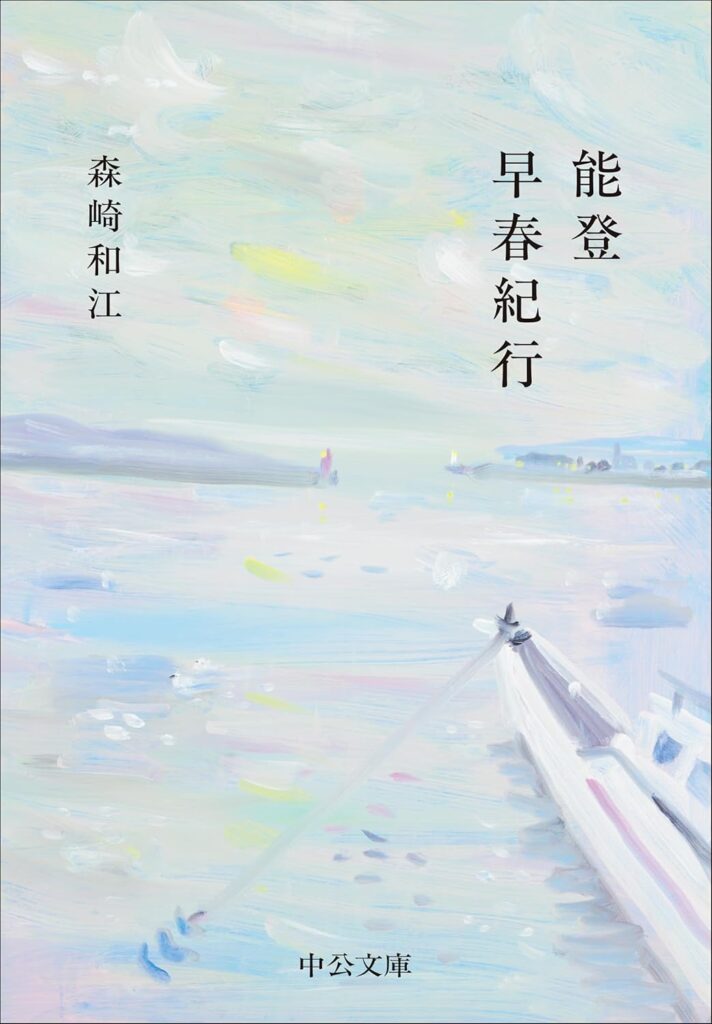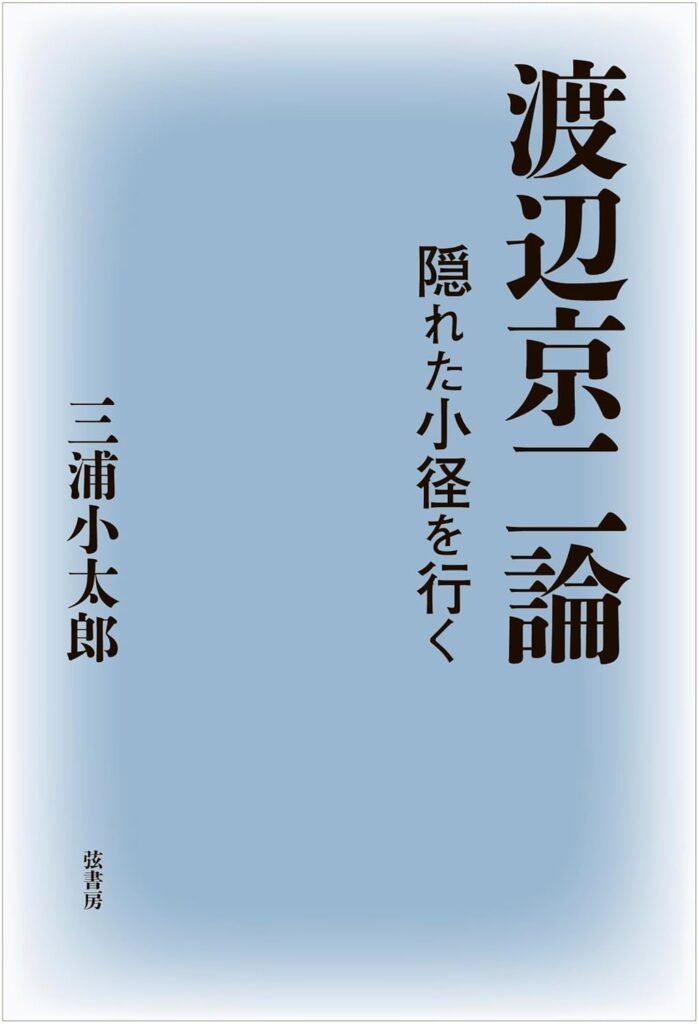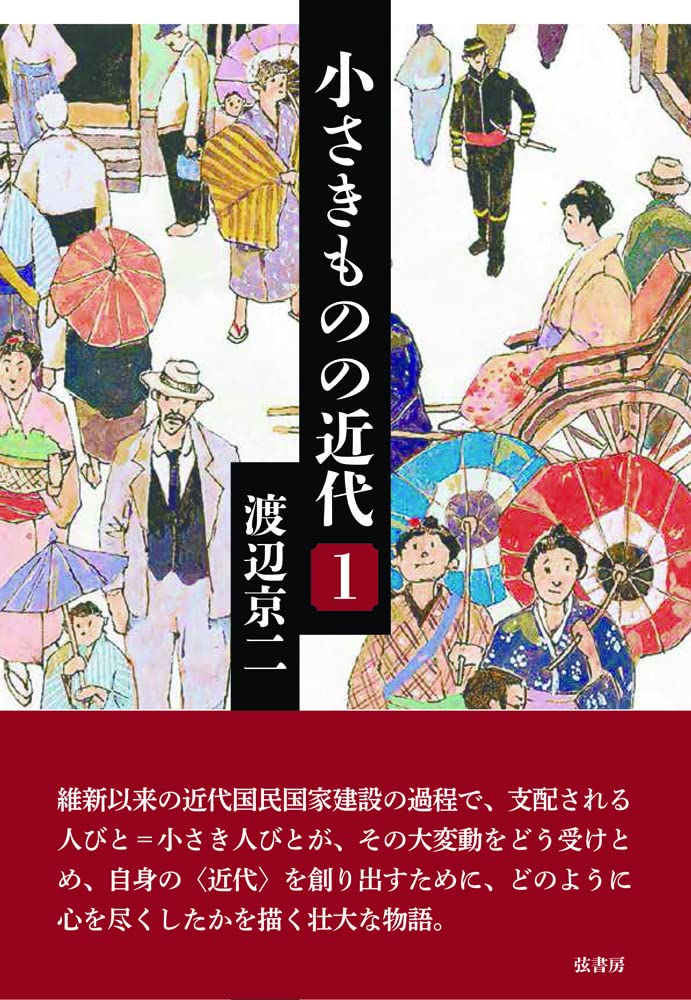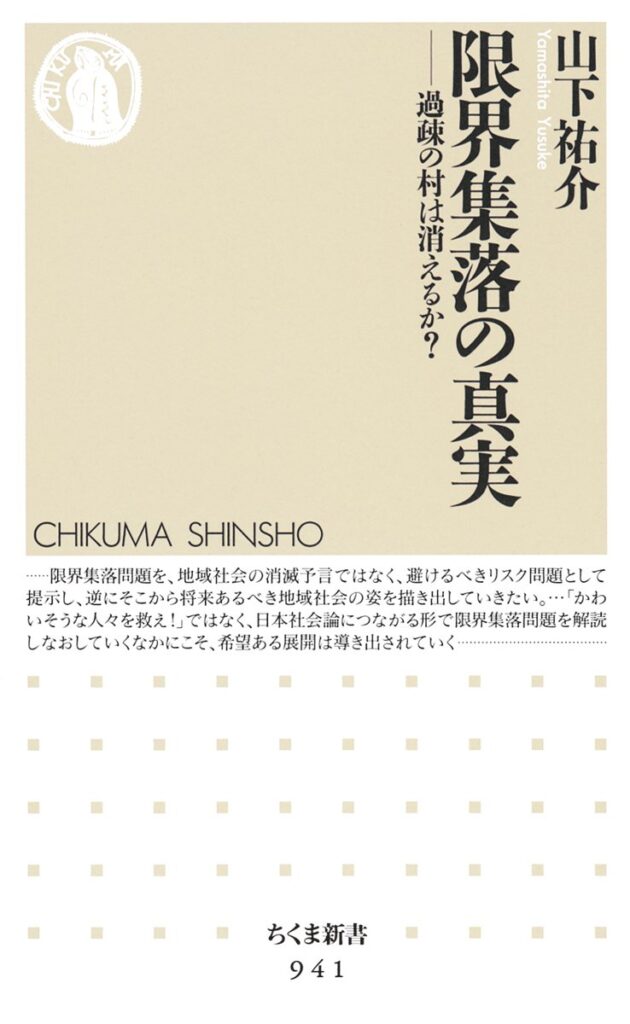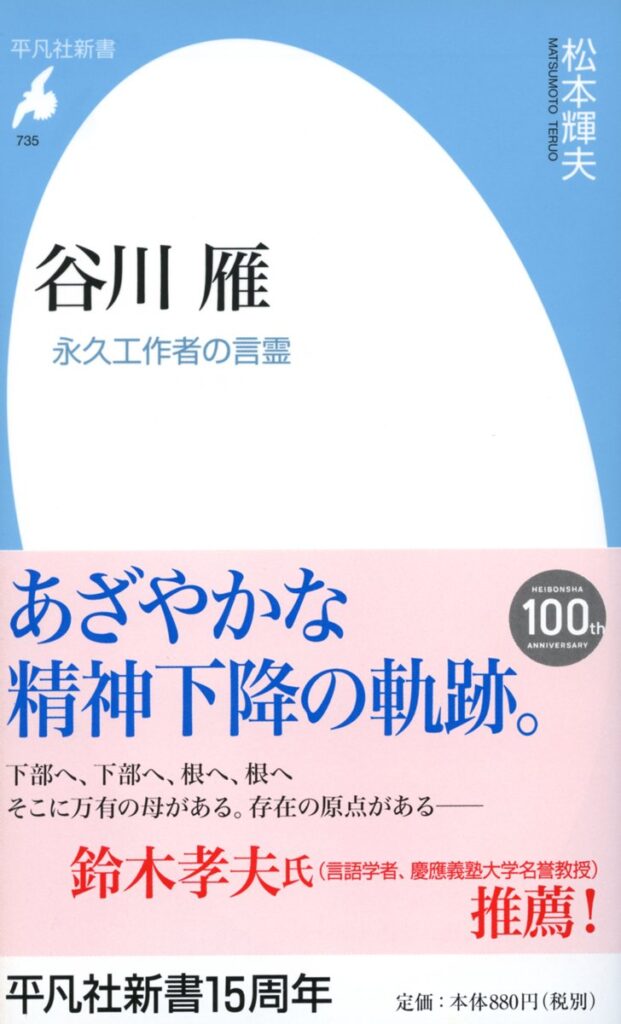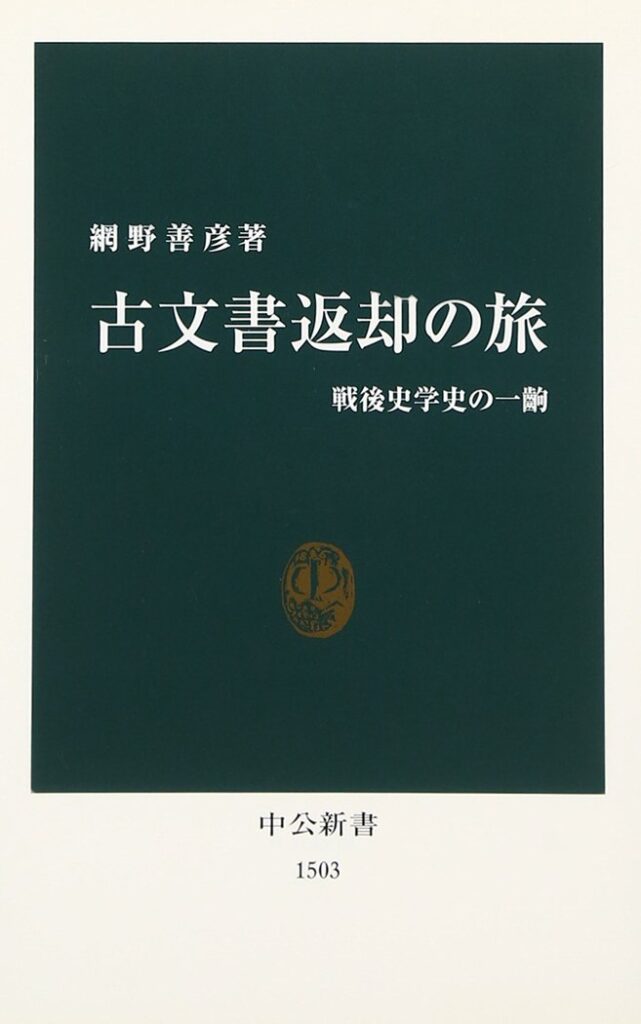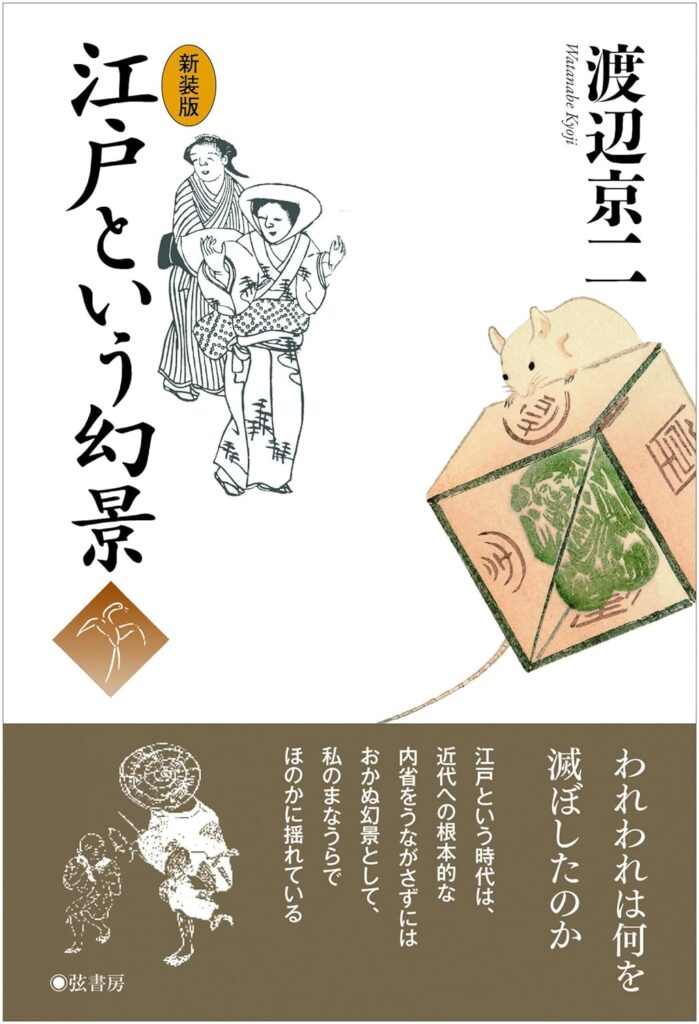11歴史〜現代史– category –
-

なぜ饒速日命は長髄彦を裏切ったのか 物部氏の懺悔、尾張氏の悲憤<関裕二>
■PHP 260121 筆者の論は考古学の主流ではない。とてもおもしろいけど、推論が多くて眉唾的な部分も多そうだ。どこまで信じてよいかわからないが、一気に読んでしまった。 神武に先だち、物部氏が北部九州から東遷したという考えは、邪馬台国北部九州... -

眠れないほどおもしろい太閤記: 戦国バトルを制して天下統一! その「人たらし」の極意とは?<板野博行>
■王様文庫 251230 弟の豊臣秀長が、兄の秀吉の人生を紹介するという仕立て。 墨俣の「一夜城」など、秀吉は天才的な軍略家というイメージがある。だが彼のすごさはいくさのうまさではなく、複数のグループに仕事のはやさを競わせて効率をあげるなど、人... -

鬼とはなにか まつろわぬ民か縄文の神か<戸矢学>
■河出文庫251208 都では追儺や御霊会のように鬼を魔物として退治する祭りが盛んだが、地方ではなまはげのように鬼(来訪者)を歓迎する祭りが多い。 ヤマトでは、古来の神を悪鬼として追いやり(追儺)、新しい神に従うものはヤマト人とされた。従わぬ... -

大井川に橋がなかった理由<松村博>
■創元社251210 大井川に橋も渡船もなかったのは、軍事的配慮といわれている。その根拠として、1626年、新旧将軍の家光と秀忠が上洛した際、家光の弟の駿河大納言・忠長が大井川に浮橋を架けた。これにたいして秀忠は「大井川は街道の難所であり、関所... -

特別展「世界遺産 縄文」
■@京都文化博物館 251126 2021年に世界遺産になった北海道と北東北の縄文遺跡群をまとめて紹介している。以下、へぇーっと思った部分だけ抜粋。旧石器時代は気温が低いから動物を中心に食べ、遊動生活だった。1万6000年前に縄文時代になると土... -

奴奈川姫とヒスイ文化 総集編<土田孝雄>
■奴奈川姫の郷をつくる会251120 出雲とのつながりやフォッサマグナが生みだしたヒスイと信仰の関係を知りたくて奴奈川姫伝説のある糸魚川を訪ねた。地元の民俗資料館でこの本を入手した。 昭和14年までは日本ではヒスイが産出するとは思われていなか... -

妖怪と怨霊が動かした日本の歴史 なぜ日本人は祟りを怖れるのか<田中聡>
■笠間書院 251108 源氏物語の怨霊の様子からときおこす。光源氏の最愛の妻の紫の上は、嫉妬にともなう怨霊にとり殺される。生霊という言葉は、紫式部が創作したとされる。 清少納言は「枕草子」で、「病は、胸。もののけ。あしのけ」と書いた。「胸」... -

怨霊とは何か 菅原道真・平将門・崇徳院<山田雄司>
■中公新書 「怨霊」の歴史を調べたくて検索していたら、ほぼ同年代で、同じ時期に同じ学部にいた筆者を見つけて入手した。 一般論からはいるから退屈な部分も多いが、怨霊がいかに世の中をうごかし、時代ととにどう変化するのかよくわかった。実は今も怨... -

能登早春紀行<森崎和江>
■中公文庫250209 海女漁のある村では、女を不浄視して船に乗せないということがほとんどない。女性を不浄視する社会は、死をも穢れとする。森崎は、性も死も切り捨てるのではなく、生命の一部としていつくしもうとした。だから鐘崎の「海女」に興味をおぼ... -

渡辺京二論 隠れた小径を行く<三浦小太郎>
■弦書房250201 渡辺京二の人物論や文学論は、渡辺自身がその人と同調して、なりかわって自分の内側から自分の思想として論じてきた。著者の三浦もまた、渡辺に直接会ったのは数えるほどしかないのに、作品を通じて渡辺になりきって内在的に渡辺の思想を... -

小さきものの近代1<渡辺京一>
■弦書房 241226 これまで読んだ著者の作品とくらべると、微に入り細をうがちすぎてわかりにくい部分があるが、江戸時代に生まれた日本人と、明治以降の教育でそだった日本人とは異民族といえるほど文化や習俗が異なることや、尊皇攘夷や維新の評価などが... -

限界集落の真実 過疎の村は消えるのか? <山下祐介>
■筑摩新書 20130806 「限界集落」は高齢化によって消滅することになると1990年代初頭に予想したが、高齢化で消えた集落はほぼない。「高齢化→限界→消滅」の事例はほぼゼロ。これまでにも集落消滅はあったが、そのほとんどは、集落が元気で人口も若い... -

谷川雁 永久工作者の言霊<松本輝夫>
■平凡社新書 240613 谷川雁は1960年前後、吉本龍明とならびたつカリスマ的思想家で、「連帯を求めて孤立を恐れず」というフレーズの生みの親であり、「原点」という言葉を普及させた。 筆者は東大の学生時代に筑豊で雁とであった。柳田国男と折口信... -

古文書返却の旅 戦後史学史の一齣<網野善彦>
■中公新書20240507 東海区水産研究所の一室で1949年、全国の漁村の古文書を蒐集・整理・刊行し、文書館・資料館をつくるという事業がはじまる。研究所の月島分室が担当し、日本常民文化研究所に委託した。 だが1954年度で水産庁は研究所への委託予算を... -

江戸という幻景<渡辺京二>
■弦書房 20240415 かつて江戸時代は封建的な遅れた体制だと評価されていたのにたいし、最近の江戸ブームでは、江戸時代の近代に通じる部分をとりだして「実は意外に近代的だった」と評する。どちらも近代を基準に過去を評価している。 渡辺は、江戸は、... -

通史・足尾鉱毒事件1877〜1984<東海林吉郎・菅井益郎>
■世織書房20230801 田中正造記念館のスタッフに「足尾銅山鉱毒の全体像を知るのにおすすめ」といわれて購入した。1984年出版だが東日本大震災後の2014年に復刊した。 足尾銅山の開発は1610年ごろはじまり、銅の5分の4は幕府御用、残りはオランダに輸出さ... -

変異する資本主義<中野剛志>
■ダイヤモンド社20230222 市場にまかせず国内産業の充実をはかるべきというのは納得できるが、強大な権威主義国家である中国に対抗するため軍事力を増強するべきだという論には首をひねった。 いまの日本の政治はこの本の流れにのろうとしているのでは... -

近江商人学入門<末永國起>
■淡海文庫 20210924 近江商人の出身地は、琵琶湖の湖西の高島、蒲生郡の八幡と日野、神埼郡の五個荘、愛知郡の愛知川沿いから犬上郡、機業地の長浜周辺にいたる地域にひろがっている。渡来人によって開かれた古代以来の近江の先進性を基盤に、中世には... -

日本探検<梅棹忠夫>
■講談社学術文庫20220906 知識は、あるきながらえられる。あるきながら本をよみ、よみながらかんがえ、かんがえながら歩く。これは、いちばんよい勉強の方法だとわたしはかんがえている-- あるきながら思想をふかめ、「日本」の文化や歴史の構造を発... -

21Lessons 21世紀の人類のための21の思考<ユヴァル・ノア・ハラリ>
■河出書房新社 20220402 産業革命後、工業国の経済や軍隊は、膨大な数の庶民を必要とした。その結果、20世紀はおおむね、階級や人種などの不平等は縮小してきた。 20世紀の後期は、民主国家が独裁国家を圧倒してきた。民主主義は、情報を処理して決定... -

古都の占領 生活史からみる京都1945-1952<西川祐子>
■平凡社20220415 ある時代を生きて空気感は感じていても、その時代について理解できることなどほんの一部に過ぎない。 筆者は少女時代を、米軍の支配下の京都で過ごした。自分自身の記憶にある当時の空気感の意味を、80人とのインタビューや府庁や市役... -

沖縄が日本を倒す日<渡瀬夏彦>
■かもがわ出版20220331 沖縄県の翁長元知事は沖縄の自民党の中核にいたが、辺野古基地への反対を掲げて「オール沖縄」の旗頭になって知事に就任した。彼が亡くなると、国会議員だった玉城デニー氏が跡を継いだ。 筆者は、取材者というよりも、デニー氏の... -

青い目の近江商人 メレル・ヴォーリズ<岩原侑>
■文芸社20211031 筆者(1934〜2018)は、近江兄弟社を社長として倒産の危機から救った立役者。 ヴォーリズの建築は有名だけど、彼が近江兄弟社の創始者とは知らなかった。 近江兄弟社の名も、近江さんという兄弟がつくった会社だと思っていたが、「人... -

ゴールデンカムイ20210912
(アニメと漫画) amazonプライムでアニメの第1部と第2部計25話を一気に見て、第3部はFODの無料お試しで10話を見た。その後の漫画も展開も見たい思ったら、ちょうど漫画を無料公開しているから一気に読んでしまった。 アイヌ関係の博物館や資料館で推奨... -

人新世の「資本論」<齋藤幸平>
■集英社新書20210717 人新世とは、人間たちの活動の痕跡が、地球の表面を覆いつくした年代という意味らしい。 気候変動は待ったなしのところに来ている。エコ産業によって環境と経済成長を両立できると考えるグリーンニューディールなどの気候ケインズ主... -

身体の零度 何が近代を成立させたか<三浦雅士>
■講談社選書メチエ20210620 衣服の目的は寒さを防ぐためではないという。動きやすさを求めるなら裸が一番だからだ。そもそもの目的は入れ墨と同様「飾る」ことだった。 18世紀のロココの時代までは衣装の目的は装飾にあった。 軍服も当初は装飾目的だっ... -

生きろ 島田叡 戦中最後の沖縄県知事20210406
戦中最後の沖縄県知事・島田叡の生きざまを、周囲にいた人の証言によってたどるドキュメンタリー。 東大を出て内務省に入ったが、一度も中央に戻らず地方を巡った。口癖は「アホになれ」。上に対してものを言い、部下に好かれる役人だったらしい。 沖... -

路上の映像論 うた・近代・辺境<西世賢寿>
■路上の映像論 うた・近代・辺境<西世賢寿>現代書館 筆者はNHKの元ディレクター。近現代の時代のなかで滅びつつある、精神文化のなかに地下水脈のように流れてぉた口承文芸や語り物芸能の世界を「語り物としてのドキュメンタリー」という形にしてきた... -

さらば、政治よ 旅の仲間へ<渡辺京二>
■晶文社 20191216 安倍政権の進める有事法制などの動きを進歩的な人は「いつか来た道」と評することが多い。それに対して「日本が戦前のナショナリズムに回帰しているわけがない」「左翼は思考停止している」と批判する。安保闘争などで運動に参加した... -

幻影の明治<渡辺京二>
■平凡社 20190422 筆者は、封建的で遅れていた江戸時代を、維新政府は近代的につくりかえた、という歴史観を「逝きし世の面影」で覆し、平和で穏やかで外国人を魅了した時代像を提示した。そんな渡辺氏は明治時代をどう見るのか知りたくて読んだ。 自由民...