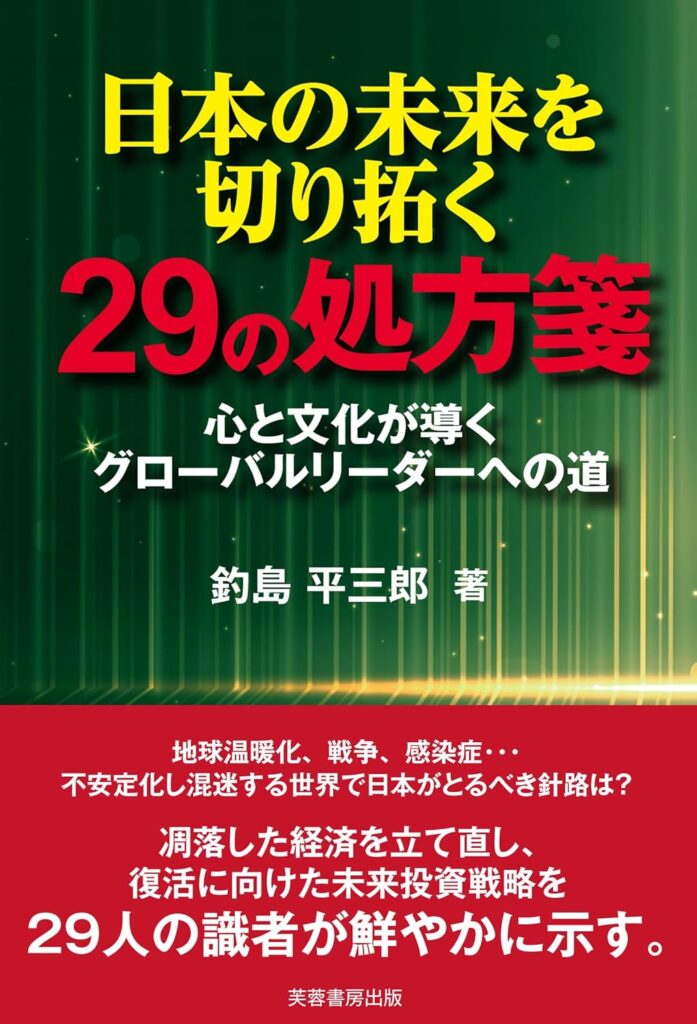10経済– category –
-

日本の未来を切り拓く29の処方箋<釣島平三郎>
経済人である筆者が29人の人にインタビューして、日本の「未来」を考える本。日本の1人あたりの名目GDPは2000年の世界2位から2023年には34位になった。「失われた30年」の理由として、登場人物たちがあげるのは--・1990年代後半か... -

変異する資本主義<中野剛志>
■ダイヤモンド社20230222 市場にまかせず国内産業の充実をはかるべきというのは納得できるが、強大な権威主義国家である中国に対抗するため軍事力を増強するべきだという論には首をひねった。 いまの日本の政治はこの本の流れにのろうとしているのでは... -

食べものから学ぶ世界史 人も自然も壊さない経済とは?<平賀緑>
■岩波ジュニア新書 20220508 自然の動植物をとって食べていた時代から、食べものは次第に商品化して、ついには投機の対象になった。小麦やトウモロコシ、砂糖といった食べものの歴史をたどることで資本主義の変遷を浮き彫りにする。資本主義化が食を変... -

人新世の「資本論」<齋藤幸平>
■集英社新書20210717 人新世とは、人間たちの活動の痕跡が、地球の表面を覆いつくした年代という意味らしい。 気候変動は待ったなしのところに来ている。エコ産業によって環境と経済成長を両立できると考えるグリーンニューディールなどの気候ケインズ主... -

国際経済学入門<高橋信裕>
■国際経済学入門<高橋信裕>ナカニシヤ出版 20160527 分厚い本で敬遠していたが、読んでみると思った以上にわかりやすい。 経済学の理論って、専門家が正反対のことを言うことも珍しくないから、科学というよりイデオロギーに近い印象がある。さまざ... -

作業中)「分かち合い」の経済学 <神野直彦>
■「分かち合い」の経済学 <神野直彦>岩波新書 20141218 スウェーデン語の「オムソーリ」。悲しみの分かち合い、という意味。競争一辺倒ではない「分かち合い」の経済をめざす。「ラーゴム」はほどほどという意味。極端に貧しいことも、極端に豊かなこ... -

今よりマシな日本社会をどう作れるか 経済学者の視野から<塩沢由典>
■今よりマシな日本社会をどう作れるか 経済学者の視野から<塩沢由典>SURE 20131007 1970年代にインフレと不況が併存したことが、ケインズから、反ケインズの新自由主義(neoliberalism)への転換の契機になった。 世界大恐慌のとき、米国... -

脱グローバル論<内田樹、中島岳志、平松邦夫、小田嶋隆、平川克美>
■脱グローバル論<内田樹、中島岳志、平松邦夫、小田嶋隆、平川克美> 講談社 20130907 平松・前大阪市長が中心になって呼びかけた4回のシンポジウムのまとめ。 グローバリズム経済とは要するにこういうこと、という姿をわかりやすく示してくれる。 た... -

始まっている未来 新しい経済学は可能か<宇沢弘文・内橋克人>
■始まっている未来 新しい経済学は可能か<宇沢弘文・内橋克人>岩波書店 20130324 宇沢氏が提唱する「社会的共通資本」は「大切なものはカネにしてはいけない」という考え方で、「大切なものはカネにしろ」という市場原理主義の対極にある。 CO₂... -

成熟ニッポン、もう経済成長はいらない<橘木俊詔、浜矩子>
■成熟ニッポン、もう経済成長はいらない<橘木俊詔、浜矩子>朝日新聞出版20111210 「国」が問題解決ができない現状では、きめ細かく問題を解決するため日本全体を顔の見える規模に分割するべきだとして、2人とも地方分権を主張する。それには共感でき... -

地域再生の罠<久繁哲之介>
■地域再生の罠<久繁哲之介>ちくま新書 20100928 専門家が賞賛する地域再生策のほとんどは成功しておらず衰退している。都市計画や建築、都市工学などの「土建工学者」が推奨する、本当は成功していない「成功事例」を視察して模倣するからほぼ確... -

消費税のカラクリ <斎藤貴男>
■消費税のカラクリ <斎藤貴男> 講談社現代新書 20100830 消費税は逆進性があるけど、消費に対する一律課税だから手間がかからない安定財源である。益税などの業者が得するしくみは直さなければならないが、こうした財政状況では引き上げは仕方... -

なぜ日本は行き詰まったか <森嶋通夫>
日本では儒教が、忠君愛国を正当化し国内統一を果たす役割を果たした。武士階級を大学卒業生という知識階級に発展的に解消させたことが、封建主義を資本主義に転換させることにつながった。政治家も官僚も国営企業の首脳も国会議員も学者も……武士出身で... -

国際経済学入門 グローバル化と日本経済 <高橋信弘>
ナカニシヤ出版 20090613 「中学生にもわかる」というほど簡単ではない。とくに前半の数式の説明はじっくり読まないと理解できない。でも、貿易がもたらす効用とか、比較優位といった概念がどういう計算から生みだされるかがわかっておもしろい。 後段の... -

現代福祉と公共政策<小野秀生>
文理閣 20090118 自由主義が不況によって破綻することで、経済における政府の役割を重視するケインズ主義が生まれる。税金を投じることで景気対策をするというシステムが機能するには、大量生産・大量消費のシステムが不可欠だった。それが第二次大戦... -

日本にできることは何か <森嶋通夫>
岩波書店 20081220 中国の大学での講演と講義の内容をまとめている。 ウェーバーによると、資本主義の源はプロテスタントであり、中国や日本の儒教はプロテスタントに近い合理的な宗教ではあるものの、上位者を尊敬する考え方が非合理的だったが故... -

貧困の克服–アジア発展の鍵は何か <アルマティア・セン>
集英社新書 20081201 経済が発展すると、教育が発展し識字率もあがるという従来唱えられてきた順番ではなく、高い識字率こそが経済発展の基盤になるという。江戸時代から識字率がきわめて高かった日本などの例をあげ、アジアの経済発展の基盤だとみる... -

福祉社会 社会政策とその考え方 <武川正吾>
有斐閣アルマ 20080626 「福祉社会」とはなにかを知るための概説書。けっしてわくわくする本ではないが、効率的であるはずの官僚組織が硬直化し、福祉を進展させるうえで障害となってしまう過程をウェーバーの理論をもとに論ずる部分などは、興味深かった... -

ボランタリー経済の誕生 <金子郁容 松岡正剛 下河辺淳>
実業之日本社 20080105 社会主義やケインズ的福祉国家などの「大きな政府」ではなく、かといって市場一辺倒の「小さな政府」でもない第3の道を「ボランタリー」にもとめる。 イギリス産業革命とアメリカ独立とフランス革命によって準備された近代国家... -

思想としての近代経済学 <森嶋通夫>
岩波新書 20071111 セイ法則がキーワード。供給が増えればそれによって需要は増えるという考え方であり、これがなりたつということはいくらでも投資機会がある状態だから、完全雇用がなりたっていた。 ところが、消費社会となり、投資の機会がなくなる... -

反戦略的ビジネスのすすめ <平川克美>
洋泉社 20061127 戦略でとらえるだけでいいのか。グローバリズム的な考えだけでビジネスを進めていいのか。モノを媒介に客とのコミュニケーションをはかる、そうしたヒトヒネリした思考のなかに、ビジネスの楽しさややりがいがあるのではないのか---... -

持続可能な福祉社会 <広井良典>
筑摩新書 20060906 「福祉」「経済」「環境」「税制」「民俗」…… 普通、それぞれの分野でバラバラに論じられ、全体を統合するような議論はなかなか生まれない。 筆者はそのすべてを大風呂敷でおおうような議論を展開するから、新鮮で刺激的だった。 戦... -

日本がアルゼンチン・タンゴを踊る日
ベンジャミン・フルフォード 光文社 20060831 政官業とやくざが癒着し、不良債権の半分近くをやくざが占めていることが、日本の経済をだめにした。 経済問題というより腐敗の問題であり、日本はメキシコ並の腐敗国家だという。 日本経済を復活さ... -

著作権の考え方 <岡本薫>
岩波新書 20060610 ①会社の仕事の一環で書いた記事を大幅にリライトして本にする場合、著作権はどうなるか。 ②講演会できいた話をネットにだした場合、著作権にふれてしまうのか。 ③ネット上に自分がだした文章をそのままほかにコピーされ公開されつづ...
1