有斐閣アルマ 20080626
「福祉社会」とはなにかを知るための概説書。けっしてわくわくする本ではないが、効率的であるはずの官僚組織が硬直化し、福祉を進展させるうえで障害となってしまう過程をウェーバーの理論をもとに論ずる部分などは、興味深かった。社会政策の基本的な知識をえるにも最適だろう。
でも、社会政策のありかたを中心に論じているため、背景にある哲学や思想の流れについての説明は弱い。さらに、現場レベル・草の根レベルの庶民の知・民俗知を評価する視点をもっていないのも物足りない。近代主義の視点をのりこえる視点はほとんど提示していない。-----覚え書き------
▽福祉という言葉の意味。狭義の福祉は対象者が社会的弱者に限定。広義の福祉は、語源的な意味「幸福」に対応する。「福祉国家」「公共の福祉」など。
▽10 自立=依存しないこと
個人主義的な幸福追求は、「経済的に自立した健康な青壮年」をもとにしている。そういう人には第3者は不介入を貫かなければならない。それにたいして、何らかの意味で依存している人には、自助が可能となるような地点までの援助が必要だ。そこに狭義の福祉の考え方の根拠がある。
▽36 需要と必要
ニードという言葉をつかうことは専門家支配に加担する。「必要」と言えばよい。
自立した幸福追求をおこなえない場合、政府が社会政策をつうじて、個人の幸福追求を支援する。(〓あくまで基本は個人主義)「需要」は個人の主観的欲求に基づき、「必要」は、社会的な価値判断に基づく。
▽56 社会政策のなかには「必要」ではなく「需要」に基づくものも。
行政需要と行政必要のちがい。
貢献原則と必要原則 市場による分配が主として貢献原則に基づくのに対して、社会政策による分配は必要原則に基づく。しかし賃金決定に必要原則が影響することもあり、社会政策にも貢献原則が反映される。
▽必要の判定基準 専門性→社会通念→主観的判断 左側ほど客観的必要
専門性=専門家 社会通念=官僚制のなかで具体的な形をとってあらわれる。
77 必要は価値判断を前提とする。判断が困難という理由で判断を回避すると、ニヒリズムとなる。個人の価値判断の背後にある社会の価値判断を探る努力をすることで、、価値判断の問題を合理的な討論の議題にできる。必要の判定には、専門家・官僚・当事者といった主体が関与する。
79 バルネラビリティ=弱い立場 脆弱性。克服策がセキュリティ
自分をバルネラブルな位置に置くことによって、かえって、安定のなかでは知りえない新たな関係が開かれるという考え方も。
▽90 「家族」から生産の要素が消えていく。生活に必要なものの多くを市場から調達するようになる。
「国家」は市場や家族から必要な資源を入手できない人に救援の手をさしのべる。イギリスの救貧法。市民社会のなかでは「慈善」。
▽94 明治以降は家族と国家が重要とされ、両者が一体的にとらえられた。家族と国家以外の領域は危険なものとして無視されるか、不在のユートピアとして理想化されてきた。だから「市民社会」という言葉がよそよそしい響きをもちがち。
▽100 まとめ
▽124 資源の再分配 小さな政府か大きな政府か。小さな政府を標榜する人は「国民負担率」の抑制が唱えられる。
普遍主義と選別主義 資力調査の有無で両者を区別することが多い。選別主義は必要原則に忠実にみえるが、スティグマ付与の問題がある。
▽官僚制と専門主義 134〓〓 官僚制は、規則が定めたときの状況が変化すると柔軟な対応がとれなくなる。効率のためつくられた規則が不効率をうみだす。ところがこれに官僚は気づくことがめったにない。手段と目的の転倒は官僚制組織の構造に由来するとマートンは主張。
145 社会サービスの供給には、官僚・専門家・利用者が関係してくる。官僚制は大規模組織を運営するうえで能率的だが、規則に同調過剰になるために、杓子定規などの逆機能が生じることもある。ストリードレベルの官僚制による逆機能が利用者には問題になる。
専門家は官僚組織のなかでは、クライアントの利益を擁護することも可能だが、専門家支配を生みだす危険もある。
▽社会政策 171 社会政策の目的は、各分野におけるマイナスの価値(無為・窮乏・疾病・能力障害・陋隘・無知)を回避することに重点があった。しかしプラスの価値「自己実現・豊かさ・健康・能力発揮・快適さ・発達)にも注目する必要がある。社会政策の手段は給付と規制。
▽所得保障 185 厚生年金の分類
192 最低生活水準を基準とした貧困の定義 憲法25条やILOやWHOのいう「基本的に必要」という基準は、生物学的生存に必要な生活必需品に加えて基本的な社会サービスを含む。 相対的剥奪としての貧困=コドモの誕生日にプレゼントを買ってあげられないなど。
▽保健と医療
213 医療保険は1883年にドイツで生まれる。日本ではブルーカラー対象に1922年に健康保険法、震災でおくれて開始は1927年。1940年にホワイトカラー対象の職員健康保険。一般住民対象の国民健康保険法は1938年成立したが、市町村単位の保険組合設立も加入も任意。1958年、改正し、1961年に国民皆保険に。
▽住宅 266 ホームレスの広い意味での概念。イギリスの法的定義=そこに安全に立ち入ることができない。そこに住む者から暴力の脅威ないし実際の暴力にさらされている。そこに住みつづけるのが適当ではない。移動式の住居をもっているが、それを置いて住む場所がない、など。立ち退き要求によって居住の継続を脅かされている人々もホームレス。日本の最低居住水準以下の住居で暮らす人々は、ホームレスないしその脅威にさらされている人びとという。
日本のホームレス自立支援の特別措置法のいうホームレスとは「都市公園・河川・道路・駅舎その他施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者」という狭い概念。
▽福祉国家と福祉社会 対立物とみるのは好ましくない。「福祉国家から福祉社会へ」ととらえられがちだが、両者の連携を模索するべき。福祉国家の社会政策というものが、福祉社会の諸部門や諸制度との分業関係のなかで成立し発展してきた。人間の必要は福祉国家と福祉社会の連携で充足されるべき。
混合福祉 福祉多元主義の議論
公共部門、インフォーマル部分、ボランタリー部門、市場部門などが社会サービスを供給。部門間の関連の仕方を示した概念に「福祉レジーム」がある。これは「福祉国家レジーム」(自由主義・保守主義・社会民主主義)を発展させた考え方。





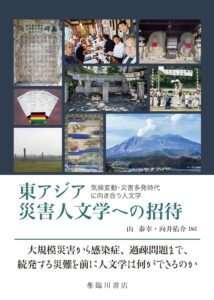
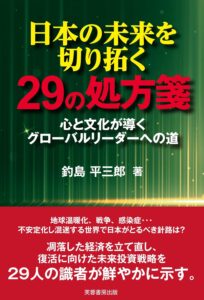

コメント