あけび書房 20080605
いちはやく老人医療費の無料化を実現したことで知られる岩手県沢内村の歴史を、元村長、医師、保健師といった人たちがオムニバス形式でえがく。田邊氏の写真も心をうつ。
「老人医療の無料化」は、徹底的に草の根レベルでかたりあい、「さだめ」を「課題」に転じる地道な運動の成果のひとつにすぎない。本当に大切なのは、医療費ゼロという表面的な結果ではなく、草の根レベルの地道な民主主義の活動にある。
「部落ごとに対話の場をつくるなかで、個人や家庭がそれぞれにかかえこんでいた悩みを、相互にたしかめあうとき、自分だけの悩みではなく、部落全体、村全体の悩みとなっていく。悩みを解決するための方向と目標と決意をしっかり定めて、村民全体が確信をもって連帯し、運動する……」という記述が、まさに沢内村の村おこしの核心であろう。
信州の佐久総合病院や愛媛県の「地区診断」と同様のとりくみだった。
戦後直後、後に村長になる深沢ら3人は、週に3晩、宗教的な人生学、法律などなどをテーマに語る農民学校をつくった。さらに村づくりにむけて、どこに問題があり、どうすれば解決がつくかを徹底的に話しあうため、婦人会を組織する。役場内では組合をつくった。一つの職場・地域で生き抜くには、組織をつくり、自分達で自分達の問題点を見出して解決をしていく必要があるとの認識からだった。だから村政でも、広聴と広報による住民との信頼関係を基本とし、常に社会教育を優先させた。
深沢は1957年に村長になると、昼も夜も集落へでかけて1年間徹底的に話しあった。研究者の手をかりて問題点を集約した結果、①あまりに雪が多い②あまりに貧困③あまりに病人が多い、という3つの問題が浮上した。
村の現状を徹底的に調査することを重視する。たとえば婦人会は、2年間毎日学童の弁当の調べる。青年は90カ所に2メートルの穴をあけて土質調査をする。これが後の土地改良の基礎になった。
医療はとりわけ悲惨だった。病の時には貧しさのために医者に診てもらえないのに、死亡診断書を書いてもらうために、子供の亡骸を医者のもとへはこばねばならないこともあった。乳児死亡率日本一の村でもあった。
そこで、最も発言力の弱い65歳以上の老人と乳児の医療費を60年から無料化し、翌年からは60歳以上に対象を拡大する。人口1200人に1人にあたる4人の保健婦を配置し、徹底的に家庭訪問をすることで乳児死亡率ゼロを記録するにいたる。
老人医療費無料化直後は、今まで金がかかるということでじっと我慢していた老人たちで病院がいっぱいになった。無料化によって重病の早期発見につながり、沢内村の老人医療費は県平均の半分以下に減った。
なにより、家計を気にせずに病院にいけるようになって、おばあちゃんが、家族の健康に気を配る健康管理者のような役割をはたすようになったという。
合併後の旧沢内村がどうなったのか、見てみたいと思う。
-----覚え書き-----
▽35農民学校 戦後引き揚げてきた深沢と太田と東京帝大をでて共産党に属する斉藤竜雄という医師が3人で農民学校をつくる。村づくりには、住民とともに悩み苦しむことが大事だと、週に3晩、宗教的な人生学、法律などなどをテーマに語る。
村づくりのためには組織づくり。皆の意見がお聞いて、どこに問題があり、どうすれば解決がつくかということを徹底的に話しあう必要。まず婦人の組織づくりをするため、毎晩のように自転車で各集落に泊まりがけででかけて婦人会ができる。さらに連絡協議会をつくる。これが自分たちの命を守る組織的な活動母体ができあがった。
役場の職員の給料が低すぎるということで、管理職の教育長だった深沢が先頭にたって職員組合をつくった。
住民が一つの職場に、地域に、あるいは生活の中に本当に生き抜くためには、まず組織をつくり、自分達で自分達の問題点を見出して解決をしていくことが必要である。すなわち広聴と広報による住民との信頼関係が村づくりの基本。
▽38 s32に深沢が村長に。太田はブラジルから帰国して新潟にいたが、「教育長になれ」とよばれて村にもどった。
集落へ出ていって、昼も夜も徹底的に話しあうということを1年間つづけ、岩手大学の先生らの手をかりて、分類し、問題点を集約した。その結果、あまりに雪が多い、あまりに貧困、あまりに病人が多い、という3つの問題点がある、とわかった。住民一体となってこの問題と取り組むことが行政の基本ということで、各集会に出向いて話しあった。
▽41 まずは雪から。住民自らが意欲を持ってやる姿勢にするためには、村がブルドーザーを買って除雪してあげるという形ではなくて、自ら苦しみながら問題を解決していく姿勢が必要。「冬季交通確保期成同盟会」という民間組織。
雪おろしが大変。10年間研究し、住宅を改造。9割の住宅が、どんなに雪が降っても雪おろしを必要としないという家屋構造に。
▽44 とんでもない医師。麻薬中毒だったり……
▽45 新生活運動 調査を完全に。すぐ結論をだすのではなく、途中でおりて反省してまた進むという途中下車型に。指導者は引率型ではなく演出型に。婦人会は、2年間毎日学童の弁当の調査をする……青年は90カ所に2メートルの穴をあけて土質調査。これが後の土地改良の基礎になる。時間を守る運動、冠婚葬祭の簡素盛大化運動、新暦にかえる運動……
▽48 健康 最も発言力の弱い65歳以上の老人と乳児を昭和35年から国保10割給付に。36年からは60歳以上に。「健康管理課」をつくり、縦割り解消。人口1200人に1人にあたる4人の保健婦を配置。徹底的に家庭訪問をする。乳児死亡率37年にゼロに。
沢内村には、常に社会教育を優先させて、社会教育のためにすべてを費やすという考え方が基本にある〓。
▽56 沢内村の老人医療費は昭和56年に1人18万6729円。岩手県平均は40万1149円。普通の病院では7割から8割が老人で占められているが、沢内村立病院では4割以下。それだけ健康度が高くなった。
□
▽57 昭和52年から35歳以上59歳までの全村民の人間ドック。55年以降、胃癌で亡くなった人はほとんどいない。
▽70 増田医師が赴任したとき深沢村長「医者は給料が高いね」「給料は高いと思うが、村にとって必要なのですから払いますよ。しかしサラリーマン根性を出したら承知しません」「医療は人助けです。サラリーマン根性でできるわけがないでしょう」と抗弁した……本当に沢内村は医療で困っていた。だから、村長は村の人達の生命を守るために自分の命をかけていたし、初対面の私にも医師としての自覚を求めたのだった。
▽72 悲惨な無医村。 死亡診断書を書いてもらうために、亡骸を医者のもとへ運ばねばならなかったこともあった。病の時には貧しさのために医者に診てもらえず、死んではじめて医者のもとに運ばれる。
沢内村は乳児死亡率日本一の村でもあった。
▽73 深沢村長は、国や県への陳情のために村を出たことがなかった。もっぱら集落をまわり住民と話し合った。そして豪雪と貧困と多病が村の当面の行政課題であると宣言した。
無料診療。国民健康保険法違反の疑い、と行政監察から指摘されると、深沢村長は「それはあるいは国民健康保険法に違反するのかも知れませんが、末端の法律はともかかく、少なくとも憲法違反にはなりませんよ。これをやらなければ、経済的に困っている村の人達は、憲法が保障している健康で文化的な最低の生活すら得られないのですからね。もし訴えるのであればそれでもいい。最高裁まで争いますよ」〓
▽81 日本最初の老人医療費無料の村 無料になると、老人でいっぱいになった。今まで金がかかるということでじっと我慢していたのだろう。文字通り一銭も持たずに来院する老人も多かった。
▽87 無料は無駄、という批判。役場側から「せめて1割負担を」の提案。これに対して、老人クラブを中心に無料継続の署名運動がおきた。アンケートを実施すると、「無料診療を続けて欲しい、そのためにはある程度の保険税の値上げはやむを得ないだろう」というものだった。
「ものいわぬ農民」といわれ、めったに積極的に発言しない。が、このときは、積極的な態度表明があった。
……「無料の薬は効かない」という患者の意識。……いろいろあったが、今では「今日は注射はいらないよ。薬も飲まなくて大丈夫」といえば納得してくれるようになっている。無料バスに乗ってきて〓、話を交わし、弁当を食べて帰ってゆく老人もみられる。
▽94 「今の老人達は金を持っているから治療のため出させた方がよい」という声をきく。が、自分の病気の治療のため金を出すとなると、その金をむしろ孫のためや家計の足しにした方がよいと考える老人も多い。自分以外の家族のことを心配する心をいとおしいと思う。姥捨て山とは、若い者が老人を捨てる山ではなく、老人が自分からすすんで入りこもうとする山なのである。
▽100 健康管理課 医師が健康管理課長に。保健婦と村立病院とのつながりがなく、バラバラだった。少なくとも保健関係スタッフだけでも一緒になろうと、病院の一室に課をかまえた。医師・保健婦・事務員・栄養士。 (〓中山町)
▽107 健康管理は少し間違うと人間管理になりやすい(〓ここまで配慮・民主主義の意識)。私はよく職員に「ヒットラーになるなよ」と冗談をいう。住民と十分な対話を交わしながら活動してゆくことが、健康管理が人間管理に陥らない最良の方法。
▽115 人間ドックの料金の議論。病院収入6000円では実費にも不足するということで300円値上げしてもらったが、保健調査会は1日議論した。……自己負担が増えれば受診が抑制され、一般会計負担をふやせば他の事業にも支障をきたすかもしれない。病院負担を増やせば経営に影響し、それが村民負担になる。それらをふまえて村民自身が決めていく。議論するほどお互いの理解が深まる。とても重要な過程だと思う。
保健調査会での議論は、深沢村長による行政主導型の保健活動が、加藤医師による医師主導型をへて、住民主導型へと移っていくステップであると考えている。
▽147 住宅改善 かやぶき民家。囲炉裏はあるが、寒い。患者を裸にして診察するのは病気を悪化させるようなもの。住宅改善は常居の冬期間の暖房からはじまる。天井をはり、すきま風をふせぐために、肥料袋やビニール幕が使われた。囲炉裏の跡に薪ストーブが置かれた。
雪で周囲を覆われ、家の中は暗い。赤ちゃんにくる病を多発させた。加藤先生は昭和38年に北海道にみられる大屋根方式を採用し、病院の看護婦宿舎を設計した。改善家屋の普及のために大工達を説得する。かやぶきの家は25年で屋根を葺き替え50年で建て替えるといわれるが、ちょうどその時期になってきた。しかも原野が開拓され茅場がなくなっていた。
▽167 病院の赤字。1人当たりの医療費は年々減少している。1人あたり2万円も県平均を下回る。全村でみると1億円節約。病院は3000万円の赤字だが、総じて村の健康維持費は黒字だと御理解願いたい。
□
▽184 老人医療無料化で、我慢していたのが受診も高まり、家庭内も明るくなった。
各部落で発育がよいと思われる乳児を優良児として村で表彰し、母親よりも育児に影響あるお婆ちゃんに「オバアチャン努力賞」として座布団をあげることにした。効果はてきめん。……(〓家族の実態を知るからこそでてきた知恵)
▽193 結核になっても、経済的な面から入院できない人が多かった。生活保護の医療扶助は該当にならなかった。食べるだけの農地でも、堆肥を作るための草刈り場がある。それを処分してからでないと扶助は認められなかった。〓
▽197 集団就職列車につきそう保健婦。
▽198 昭和32年、一般を対象とする保健活動もはじまる。歩いて部落を移動。……検診に続いて行われる衛生教育や、保健連絡員さんの家で夜に開かれる座談会に力を注ぐ。テーマは、寄生虫、トラコーマ、高血圧対策。……婦人科医も、手拭い一人一本運動(トラコーマ予防)を始めるなど、全村的に保健活動が高まった。
□
▽219 部落ごとに対話の場をつくるなかで、個人や家庭がそれぞれにかかえこんでいた悩みを、相互にたしかめあうとき、自分だけの悩みではなく、部落全体、村全体の悩みとなっていく〓。悩みを解決するための方向と目標と決意をしっかり定めて、村民全体が確信をもって連帯し、運動する。
□参議院での増田進証言録 1982年
▽276 高額医療のほとんどは脳外科医に行って手術を必要とするような脳内出血とか末期ガンの患者が医療費の大半以上を食ってしまう。そういう患者が減ったことで、非常に医療費が下がった。
▽282 お年寄りは財布を息子にゆずる、……気にせずに病院にいくという心の余裕。家族の中の健康を気を配る。家庭のなかのおばあさんがちょうど健康管理者のような非常に行き届いた気配りがあるということをたくさん見聞きする





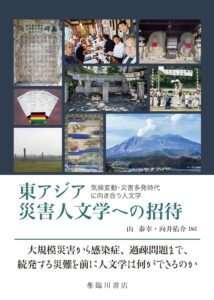


コメント