岩波書店 20080612
熊本の新聞社のルポをまとめた。新聞記事はえてして型にはまってしまうことが多いが、この本は、新聞社自らの責任をも追求し、自己切開し、マスコミも「個」が大切であると言い切っている。ハンセンの問題は、個人・組織・社会の本物と嘘をみわける鏡なのだろう。
宿泊拒否事件で、自治会側がホテルの謝罪を拒否したのを契機に、「おまえたちと一緒に温泉に入りたくない」「税金で食わせてもらっているくせに思い上がるな」という世論の「逆切れ」が入所者を襲う。
悲惨な人生をあゆんできた元患者にとって、勝訴判決は大きな希望となった。判決をうけいれる小泉の決断は、おそらく彼がなしとげた唯一の善政だろう。だが国が謝罪しても、差別の構造はなにもかわっていない。ある意味、ハンセン病を社会全体でうけとめて解決することが、弱い者いじめの社会をかえることにつながるのではないかとも考えさせられる。
隔離政策はあまりに重い。患者たちの人生のすべてをめちゃくちゃにした。その責任は政府だけにあるのではない。隔離へとみちびき断種させ、世界的には隔離をやめる流れがあったのに従来の政策を固守した医師。隔離政策をやめなかった政府と国会。「ライ病患者野放し」などという記事を書いたマスコミ。そしてなにより露骨な差別をあびせて隔離を当然とし、最前線で患者をあぶりだした世間……。世の中の絶対的多数派が権力といっしょになって患者たちを迫害した。その構図は戦争と同じである。
植民地・朝鮮の療養所の状況は日本国内よりさらにひどかった。松ヤニとりやレンガづくりなどの重労働が強制され、神社参拝を拒めば拷問され、懲罰として断種された。患者は奴隷や囚人とおなじあつかいだったという。
------覚え書き------
▽ ジャーナリズム精神というものがあるとすれば、それは組織ではなくおそらく個人に属するのではないか。
▽ 11 自治会側がホテルの謝罪を拒否したのを契機に、露骨な差別感情が入所者を襲った。「おまえたちと一緒に温泉に入りたくない」「税金で食わせてもらっているくせに思い上がるな」
▽ 13 「謝罪として、ホテルを廃業したい」本来加害者であるホテルを、被害者であるかのように印象づける廃業宣言。ふたたび非難や嫌がらせが相次ぐ。
▽ 28 偏見におびえていたが、同窓会に出席。国の責任を認めた熊本地裁判決、全面解決への決意を示した首相談話……時代が固くなった心の壁を溶かしてくれた。
▽ 34 地域にもどる 団地の3階から見えるのは生きた街並み。……子どもたちの笑い声、カレーや焼魚のにおい。「外の世界には、生活の音やにおいがあるんです」
▽ 43
▽ 48 「人生被害」「生き直しがしたい」
▽ 51 患者の子、とばれないか、いつも不安におびえていた。両親の存在を疎ましく思った日々。療養所内では、断種、堕胎が行われた。授かった命を守るため、終戦の前年、両親は療養所を飛び出し、宮里さんを生んだ。1948年に再収容されるまで、親子水入らずの時をすごした。「大人になってから、親と一緒の写真はないんです……」
……親との絆さえ破壊した。人が人として生きられぬ。
▽ 62 自治会機関誌 「予防法の下、それまで言論の自由など考えられなかった。戦後、新憲法……入所者の権利意識も高まっていった」 機関誌「菊池野」は唯一、自由にものが言える場。(綴り方)
▽ 85
▽ 100 社会学者の蘭さん 10年間で40の人生をききとり「病の経験を聞き取る――ハンセン病者のライフヒストリー」を出版。(〓どう書いているのか)
「やっぱり今はいただけません」「でもね。病気のことは誰にも話さず生きてきたけど、ハンセン病あっての自分。この本の中に、本当の人生はあると思うんです」
▽ 107 中国のハンセン病回復者村 日本の若者が訪れる。ワークキャンプでトイレを建設。黙々と働く姿に、村人も次第に心を開くようになり「朋友」と言ってくれるまでになった。
▽ 109 ボランティアに関心がないと言われる中国の学生をどう動かすか。……しだいに現地の大学生も参加するようになる。
▽ 115
▽ 122 韓国の小鹿島と台湾の療養所の入所者が、日本政府に補償を求めた訴訟。台湾の原告は勝ち、韓国の原告は負ける。
入所者には、軍事物資の松ヤニ取りや、レンガ作りなどの重労働が強制された。ノルマが達成できないと職員から死にそうになるまで殴られ、神社参拝を拒めば監禁室で拷問を受けた。日本の療養所とちがい、断種は懲罰の一つだった」
法廷には、日本の入所者が集まって支援した。「自分の補償問題は解決しているのに、この裁判に必死になって取り組んでくれた」……判決から4か月後、厚労省は補償法を改正し、小鹿島、楽生院の入所経験者を対象に含めた。
▽ 130 かつて日本でも、有名な寺社のそばには、施しを求める患者たちが集まり、集落を築いた。(インドは今も喜捨にたよって生きる)
▽ 156 ハンセン病市民学会が2005年に誕生。ハンセン病問題を形骸化させず、次世代に継承していく受け皿。
▽ 162 熊本地裁判決の翌日、新聞各紙は「断罪された政府と国会の怠慢」……といった社説が載った。が、裁かれるべきは国と国会だけだろうか。
戦前と戦後、地域から患者を一掃する「無らい県運動」が官民一体の運動として展開された〓。患者をあぶりだした最前線の実行者は「世間」だった。(戦争責任問題と同じ構図〓)
……日本のハンセン病の権威者たちは、国際的潮流にも逆らい続けた。「隔離不要論」が常識となるなか、これに逆行する形で新法をつくり、隔離収容を進めた。
法曹界も強制隔離による人権侵害を放置してきた。殺人罪に問われた元患者の男性が無実を訴えながら死刑に処せられた「藤本事件」。」裁判は、裁判官が医療刑務支所などに出向いて開かれた。審理は「非公開」。憲法に保障された裁判さえまともに受けることができず、死刑も抜き打ち的に強行された。
▽ 年表 1931年 らい予防法制定。在宅患者の強制隔離始まる。(〓稲葉先生が子どものころはこのへん?)
1940年、厚生省が「無らい県運動」徹底を通知。
1948年、患者を断種、中絶手術の対象とした「優生保護法」制定。
1949年、第二次無らい運動始まる
1951年、国立療養所の3園長が国会で隔離強化を求める。





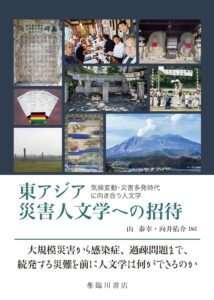


コメント