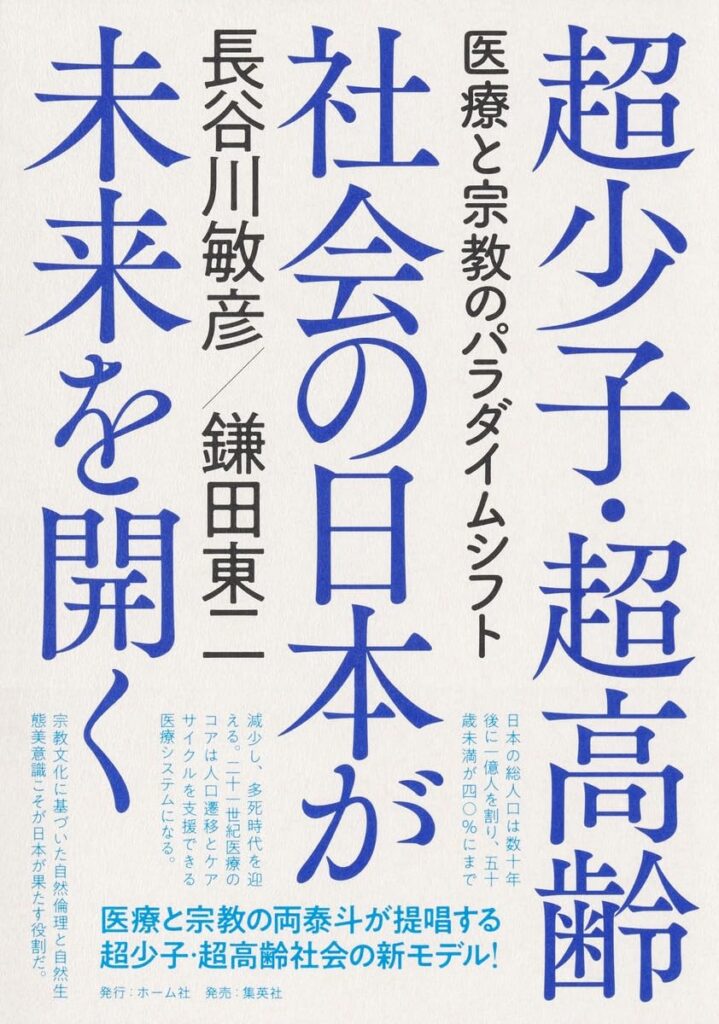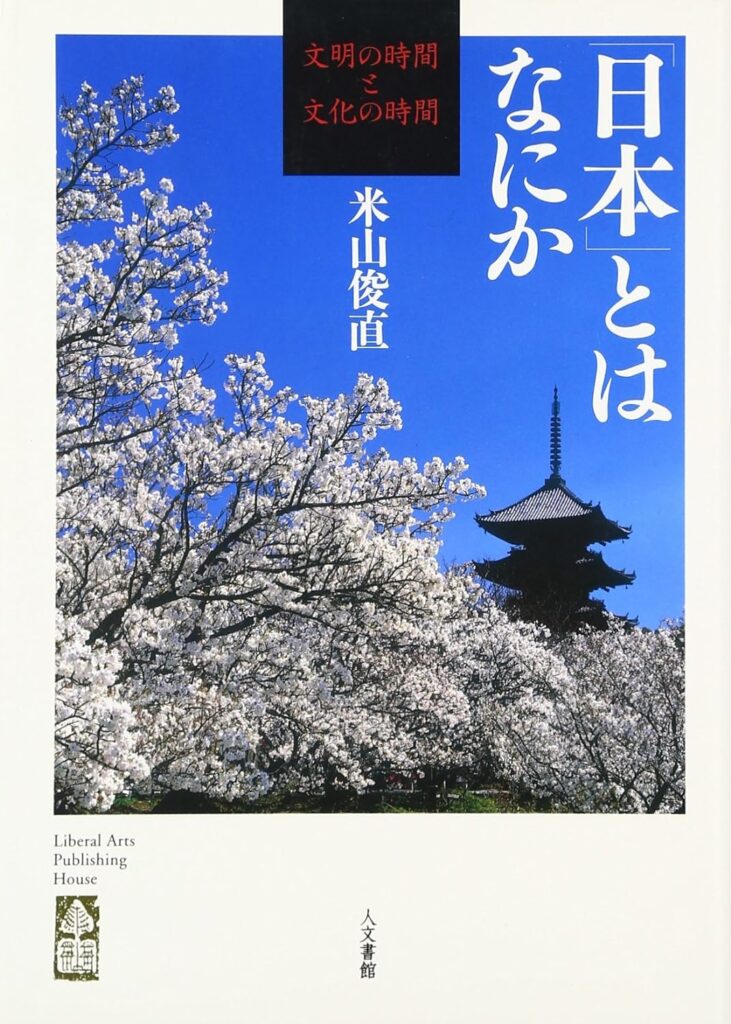Uncategorized– category –
-

「月よ私をうたわせて」出版3周年記念LIVE「サバイバーたちの明日へ」
「月よ私をうたわせて」出版3周年を記念するライブに参加した。「自死」という重い現実のなかから「生きぬく」大切さと美しさを伝えるコンサートだった。【「月よ私をうたわせて」の紹介はコチラ】 のえさんは37年の人生のさいご、大阪・長居公園ち... -

古代DNA 日本人のきた道
■250611 国立科学博物館 人類は300万年前にアメリカで誕生。6万年前にアフリカを出て世界に広がり、日本列島には4万年前にたどりついた。 石垣島の新空港建設にともなって2007年に見つかった白保竿根田原洞穴遺跡は、25体の人骨が見つかり... -

超少子・超高齢社会の日本が未来を開く<長谷川敏彦/鎌田東二>
■集英社241231 超少子高齢社会の日本のどこに希望があるのかを、宗教哲学者と医療福祉制度を設計してきた医師が論じる。 長谷川は阪大医学部4回生のとき、心斎橋で「ロックンロール神話考」というミュージカルを見た。演じていた長髪ヒッピー男が鎌田だ... -

タイムカプセルのように広重をみる
あべのハルカスへ「広重―摺の極―」をみにいく。 安藤広重だと思っていたら、今は歌川広重だという。本名は安藤重右衛門。安藤は姓で広重は号であり、両者を組み合わせるのは適当ではないということで、教科書では1980年代に安藤から歌川に修正され... -

「日本」とはなにか<米山俊直>
■人文書館 240619 著者はアフリカから祇園祭などの日本の祭りまで調べてきた文化人類学者。学生時代、私は彼の祇園祭フィールドワークのゼミに参加させてもらった。えらぶらない人で、フィールドワークで鉾町に2カ月みっちりかかわるのは得がた... -

水底の歌 柿本人麿論 上下<梅原猛>
■新潮文庫 20230727 松尾芭蕉とならぶ日本最大の詩人である柿本人麿は長らく、島根県益田市の高津川河口の鴨島で死んだとされてきた。だが、そんな辺鄙な島で国府の役人が死ぬわけがない、と、斎藤茂吉は、海辺ではなく江の川上流の湯抱で人麿は死んだと... -

出雲と大和 古代国家の原像をたずねて<村井康彦>
■岩波新書20230711 古典や神社の文書などの引用が多くて、読みやすいとはいえないけれど、中身は刺激的だった。 奈良盆地の、三輪山の大神神社や葛城の高鴨神社といった神社の祭神が出雲系で、丹波や富山、吉備、「国譲り」以前の伊勢にまで出雲系の信仰... -

神々の体系<上山春平>中公新書
■中公新書20230625 1972年の古い本。二上山や三輪山が信仰の拠点として生きていた飛鳥から奈良時代、当時の人々はなにを信じて生きていたのか知りたくなった。「神々の体系」というタイトルがぴったりに思えて入手した。 信仰の中身を描いたものではなく... -

動的平衡3 チャンスは準備された心にのみ降り立つ<福岡伸一>
■小学館新書2023021 生命は、たえずみずからをこわし、常につくりかえることでエントロピー増大の法則に抗う動的システムであるとする「動的平衡」を提唱した著者が、生物学や医学、芸術についてまで論じている。その幅の広さにおどろく。でも芸術論より... -

眠れないほどおもしろい日本書紀<板野博行>
■三笠書房20220810 高校時代、古事記は神話がおもしろかったけど、4倍の長さの日本書紀は読みとおせなかった。 古事記は、自国民にむけてかかれたのに対して、日本書紀は国家によって編纂された「正史」であり、皇室の支配の正当性を国の内外(特に中国... -

生物と無生物のあいだ<福岡伸一>
■生物と無生物のあいだ<福岡伸一>講談社現代新書 20171006 福岡氏の説く「動的平衡」とは何を意味するのか知りたくて、読んでみた。 推理小説を思わせる達意の文章で、分子生物学の最先端の歩みをしろうとにもわかりやすく紹介している。 細菌に... -

だれのための仕事 労働vs.余暇を超えて <鷲田清一>
■だれのための仕事 労働vs.余暇を超えて <鷲田清一> 講談社学術文庫 20170210 生きがいって何だろう。労働と余暇とわけられたとき、労働は苦役で、余暇は遊びとされる。その分割が、仕事から遊びの要素を奪い、遊びからやりがいの要素を奪った部... -

作業中)やっぱりおもろい関西農業 高橋信正編著
■やっぱりおもろい関西農業 高橋信正編著 昭和堂 20120707 都市型農業、狭い、近江商人の三方よし、など、関西の農業の特徴をふまえた取り組みを紹介。農業、流通、商売。それぞれの事例がおもしろい。 ============== ▽25 近江商人に商人道を教えたの... -

寺社勢力の中世--無縁・有縁・移民<伊藤正敏>
■寺社勢力の中世--無縁・有縁・移民<伊藤正敏>ちくま新書 20111003 中世は王権の力が弱まり、全体社会のなかで国家が占める割合が最も小さな時代だった。寺社勢力が力をもち、義経らの「犯罪者」をかくまう無縁所(アジール)となった。先端文明と... -

民俗の知恵--愛媛八幡浜民族誌 <大本敬久>
創風社出版 20050307 博物館学芸員が、自らの出身地の愛媛県八幡浜市周辺の民俗文化について地元紙に掲載した記事をまとめた。 自分が育った土地に伝わるなにげない習慣・文化が、民俗学の世界では、全国的な事例として取り上げられていた。「外の目」...
1