■人文書館 240619
著者はアフリカから祇園祭などの日本の祭りまで調べてきた文化人類学者。学生時代、私は彼の祇園祭フィールドワークのゼミに参加させてもらった。えらぶらない人で、フィールドワークで鉾町に2カ月みっちりかかわるのは得がたい体験だった。
その後、何度か講演を聴き、何冊か著書は読んだが、ぼくの取材領域とはかさならないまま、2006年に亡くなった。
能登半島地震をめぐって、先生が提唱した「小盆地宇宙」について復習したくて最晩年の文章をまとめたこの本を手にした。
「ムラ」について「安易な『近代化』のかけ声では容易に消滅するようなチャチな存在ではない」という評価は谷川雁に似ている。三内丸山遺跡をとおして縄文を重視していた。農村社会の都市社会化を指摘していた……などなど、興味深いテーマがつまっていた。
このおもしろさになぜ20代のぼくは気づかなかったのか?
考えてみたら、米山の著作を読んだのは1985年から93年で、網野善彦や佐原信らの歴史学は当時から読んでいたものの、ぼくが農山村集落をめぐるようになったのは2002年からだった。みずから現場を歩く以前は、米山のすごさに気づけなかったのだろう。03年ごろに米山の著作を再読していたらまっさきにインタビューに行ったのに……後悔してもはじまらないのだが。
「小盆地宇宙」。日本の文明と文化の多様性を分析する際の基礎的な単位を米山は「小盆地」とよんだ。盆地の内部には、それぞれ「世界観」が存在するからだ。
閉鎖的な空間の中心に、物資や情報があつまる城下町があり、盆地底の水田地帯と丘陵部の棚田、畑地、果樹園、茶畑、桑畑などの地帯、それを里山と奥山がとりかこむ。そこには弥生時代以来の稲作もあり、幕藩体制下の行政単位である領主と武家屋敷があり、物資を流通させる商家や鍛冶屋などの手工業者の居住する城下町がある。その一方で、「山に隠れる人たち」が、縄文時代以来の伝統を伝えている。
盆地にとって重要なのは、周囲の山々から流れでて、次の盆地や平野とむすぶ河川だ。こうした多様で小さな盆地世界と流域世界にこそ、日本文化の基層が存在していると米山は考えた。
全国各地の「小京都」は、京都をモデルとした小盆地世界である。とくに江戸時代以降、小盆地の中心に京都をモデルとする小さな文化都市が形成された。秋田の角館は、佐竹氏の一族が入城してから町並みを京都ににせ、川の名を鴨川とよび、山にも小倉山・東山と名づけた。(小和田哲男「城と城下町」)
「小京都とは、文明にあこがれたそれぞれの地方の人々が、都ぶりを移植して……雅を導入しようとした心意現象の表現の結果であるといえよう。それは上代の日本人が外来の仏をありがたいものと感じ、仁義礼智信の徳目に納得した態度をとり、律令制を採用した心意と共通している。あるいは文明開化の時代になって、自分を野蛮・半開・文明の三段階のうち半開と位置づけ(福沢諭吉)、西欧に追いつき追い越すことを目指した心意とも共通である。この向上心は、日本人のひとつの民族性といえるかもしれない」と日本人の民族性まで論じる米山の展開力は梅棹忠夫に似たものをかんじる。
戦後も長いあいだ、日本の社会構造は、都市性の論理ではなく、農村の論理によって組織され、だから社会の近代化が遅れたと考えられていた。米山は、農村の論理は封建的なだけでなく、妥当な論理性と合理性をふくむと考えたが、一方で、日本の社会の基盤を形成していた農村社会と農民のメンタリティーは、20世紀末に大きく変質し、日本列島は都市列島になり、農民を市民に変えたと米山は論じた。農民は、言葉の本来の意味での「百姓」へと回帰したとも論じている。谷川雁は、市民化・都市化をマイナスに評価したが、米山は、市民化した農民を「百姓化」としてプラス面も見ていた。
縄文へのこだわりもおもしろい。
日本の歴史は弥生から現代までとされてきたが、三内丸山遺跡によって、それ以前に、弥生から現代までとほぼ同じ1500年継続した縄文集落があったことがわかった。(真脇遺跡はさらに長い)
文明の基点を、弥生時代ではなく、三内丸山遺跡を生み出した縄文時代に置きかえることによって、日本文明の歴史を2300年前から5000年前にまでさかのぼらせることができると米山は考えた。
三内丸山は、周辺に栗林があり、ヒョウタン、エゴマ、ゴボウなどを栽培していた。洗練された漆器や、糸魚川のヒスイ、北海道の黒曜石もつかわれていた。幅12メートルの道路が420メートルにわたって海の港にむかってのびていた。これらは農耕や広い地域の交流を示している。
エスキモーやピグミー、アボリジニなどの調査から、物質はかぎられ、家族集団を超えた社会組織をもたず、世界観も単純な自然崇拝にとどまり、食物を求めてさまよって暮らす……というのが、狩猟採集社会だと考えられていた。しかし上記の諸民族は極限的な自然条件のもとにあり、亜寒帯から亜熱帯地域までの、自然環境がゆたかな地域の狩猟採集民については言及されていなかった。三内丸山遺跡は、その問いに答えるヒントになったという。
米作りは、現在は平野が中心だが、織豊政権までの日本では、天水利用による、渓谷や中山間地の棚田が主流だった。それが、分権から集権への統治機構の変化、土木技術の発達、治水・灌漑・干拓、品種の選抜がかさなり、米の石高によって経済の規模をはかる制度が導入された。米本位の土地利用と経済秩序が、極度の土地節約的、労働集約的な農耕文化を生み出した。
一方、餅をつかない正月が全国にのこっていることから、サトイモが主食だった地域があり、白米が国民食になったのは、戦時中の配給の影響が大きいとも指摘した。
「京都」については、秦氏ら渡来人によって基礎がつくられたという歴史からひもとく。
源平合戦という最初の危機は、古代的な政治都市から宗教都市へと変質してのりこえた。第2の危機の応仁の乱後は、町衆が登場して西陣の機織りが発展し商業都市に脱皮した。第3の危機の東京遷都では、「古都」となるよりも、近代都市の道をえらんだ。祇園祭の中心は祇園感神院だったが、明治の神仏分離令で八坂神社と改称された。祭神を牛頭天王から素戔嗚命に変更し、天台宗の末寺の地位を捨て、国家神道のなかの地位を高めた。
京は17世紀は重要な商工業の中心で、その地位が18世紀になってから大坂に移った。1634年には、京・大坂にはそれぞれ41万人前後、長崎・堺は5万人、江戸は数十万人だった。18世紀になると江戸は130万人に達して、世界有数の大都市になった。
=========
▽18「日本のむらの百年」1967をまとめて以来、むらー農村共同体のそなえてきた生命力を評価し、安易な「近代化」のかけ声では容易に消滅するようなチャチな存在ではないと主張してきた。富国強兵の国家目標にあわせて伝統的なむらの長所を抹殺するような施策をとりつづけてきたことに対する批判があり、各地のむらに伝承されてきた人々の知恵に対する尊敬の気持ちが、この発言をうながしてきたのだと思う。
▽32 バリ島 火口湖が島全体の水源になっていて……水利慣行はきびしい慣習法としておこなわれている。……火口湖を水源とする推理組織のつくる、灌漑文明にささえられた、独特のバリ文化を基礎としている。バリの人々の生業は、農業というよりも百姓……バロン劇やケチャダンスを演じる芸能人であり、木彫、石、更紗の工人であり……
▽38 昔の米作りは、小規模な天水利用による、渓谷−中山間地の水田、すなわち棚田が主流であった。
……織豊政権までの日本は、定住の中心は盆地や中山間部の河谷段丘をもちいる棚田が中心であった。その後、分県から集権への統治機構の変化、土木技術の発達と、大規模な治水、灌漑、開拓干拓の可能性、米品種の選抜と栽培技術の発達、そして石高評価という、経済価値尺度の結果をうながすことになる。こうして、米本位の土地利用と経済秩序が、極度の土地節約的、労働集約的な農耕文化を導いてきたというのである。
▽49 島根県の雲南。佐藤忠吉さん。61年には集中豪雨の水害で次男が亡くなった。……62年買っていた乳牛の乳房炎が多発……農薬・化学肥料をつかった水田の畔草をたべていたことがわかった。
……木次有機農業研究会を発足。カーソンの沈黙の春(1987)、有吉の複合汚染(1975)が浮上する70年代よりも10年もはやく,地域で活動をはじめていた。
加藤歓一郞 無教会派のクリスチャンで、考え方は宮沢賢治に、行動は田中正造に学べと説いた。その影響下に、佐藤さんたちは近代化農業への懐疑をもちつづけた。
▽59 七福神のうち、なぜエビスだけが日本の神なのだろう。(大黒は、大国主と重なる部分もあるが、本来は大黒天)
……宮田登は、寄り神、漂着神というルーツは述べるものの、なぜ唯一の土着神がエビスとよばれるのかについては答えていない。
……宮本常一先生は……「エビスたちの列島」では、エビス神を「日本人以外の祭った神」という説を捨てて、列島の原住民の神とみている。
▽64 縄文時代には、東北日本の方が人口は多かった。強い蝦夷のイメージは記紀に登場するが、それがエビスだったといえる。……国譲りで、タケミカヅチ・フツヌシにたいして大国主は「子の事代主命に聞いてほしい」という。コトシロヌシは美保の岬でツリをしていたが、「父も私も従います」と、海中にカキをつくってかくれてしまった。「この、コトシロヌシを後世の人はエビス神として祀っている……」
コトシロヌシは奈良県の山中にもまつられている。葛城郡で、鴨という一族がいた。山城にうつって賀茂と書くようになる。鳥類をとらえる狩猟民だった。その祀る神にコトシロヌシがあり、土地の人は今日エビス神として祀っている。
日本列島の先住民そのものがエビス出会った。そのエビスたちが祀った神がエビス神だという視点は、エビス神の疑問を解決する糸口になる。
▽70 日本の陸上主義は、8世紀の奈良時代の100年と、明治以後、敗戦までの80年ぐらいで、陸上交通が中心だったのは1300年のうち10分の1にすぎないという。9世紀からは海と川の交通にもどり、11,2世紀には大陸から大量の青磁や銭貨が持ちこまれる。13世紀後半以降には銭が社会に浸透する。そのころから15.6世紀にかけて重商主義になり、「港湾の都市ネットワーク、あるいは廻船人のネットワークは、日本列島全域におよんで形成されており、それは列島外にもまちがいなくつながっています」(網野)
「14世紀以降の日本の社会は経済社会であり、資本主義はそこから考えなくてはならないと……建前は農本主義でありますが、きわめて都市的な社会だったのです」
▽90 縄文時代 縄文時代晩期まで、東日本の人口密度烏は西日本にくらべてはるかい高い。
▽94 東北アジア一帯の採集文化を「ナラ林文化」とよぶ。クリ・クルミ・トチなどの堅果類、球根類、イノシシ・シカ、サケ・マス。
温暖化で6500〜6000年前から照葉樹林が拡大し、ウルシなどの照葉樹林文化が伝播。ヒョウタン・エゴマ・ユリ、ヤマイモ・ヒガンバナなども水さらしで食用に。
縄文後期(4000〜3000年前)晩期(〜2300年前)になって焼畑農耕が伝来。そして水田農耕が普及する。稲作以前には西日本には焼畑農耕があり、北からはそば・ヒエ・オオムギ・カブなどナラ林文化の作物も入ってきた。
……坪井洋文氏は、……日本各地の「モチなし正月」を調べ、イモと餅の象徴性の対比から、畑作文化の存在を提示した。
▽96 白米飯が一般化するのは、大戦中の配給制度が、米食を全国に普及させた結果ではないか。
……「イモと日本人」で坪井さんは、「モチなし正月」の事例を全国からあつめていて、サトイモがモチと同等、あるいはそれ以上の意味をもっていたことを示した。
▽102 三内丸山 集落周辺に栗林 ヒョウタン、エゴマ、ゴボウなどの栽培していた種子。農耕は存在。ウルシの椀に朱塗りを縫ったものも。球形のヒスイに穴をあけた玉。鏃の材料として北海道の黒曜石も。
▽124 京都盆地の開発は、聖徳太子の時代から渡来人の手に委ねられていた。松尾神社を秦都理が701年に勧請したといわれ、稲荷神社も秦氏の祭祀とされているし、秦河勝が蘇我氏や聖徳太子とちかく、広隆寺の弥勒菩薩像は太子から与えられたとされ、近くに蚕の社もある。
秦氏は大堰川の治水にも貢献。秦氏が新羅系なのに対して、高句麗系の高麗氏は八坂神社をまつり……百済系は桓武天皇の生母の高野新笠が百済系の系譜をひいている。
▽135 京都の危機 第1は、源平合戦。それを古代的な政治都市から宗教都市へと変質して危機を脱した。京都五山もその時に建設された。第2は応仁の乱。商業都市へ。町衆が登場して、救う。その基礎に西陣の機織があった。第3は東京遷都。このとき、みずから古都となるよりも、近代都市の道をえらんだ。
政治都市からはじまって、宗教・商業・近代化と三転しつつ現在をきずきあげてきた(林屋辰三郎)
▽140 高野澄「京都魔界案内」 一条戻橋、神泉苑、珍皇寺、鳥辺山、羅生門、将軍塚、愛宕山、御霊社、蓮台野、鞍馬山、太秦、大内裏、比叡山、化野、吉田山、志明院、岩倉、逢坂山、貴船、土蜘蛛塚。
▽161 祇園祭最大の変革 明治の神仏分離令で、祇園感神院という名称が八坂神社と変更されたときではないか。
……天台宗の末寺の地位から、神道の神を選択して、祭神を牛頭天王から素戔嗚命に変更し、国家神道のなかの地位を高めた。
▽176 江戸時代、大量の銀や寛永通宝が流出し、イネドネシアでは通貨として使われていたという。…
1638年の島原の乱を最後に、230年にわたって、戦いのない時代となっている。元禄時代の人口は約3000万と推定されるが、これだけの巨大民族が、これだけ長いあいだ、平和を楽しんだ例は、世界史上ほかに例を見ないことだろう。
……17世紀前半の2400万から1世紀の間に約2倍に増加。東日本では減少し、西日本で増加している。明治以降は、逆に西日本が減少し東日本が増加している。
京は17世紀にはなお重要な商工業の中心で、その地位が18世紀になってから大坂に移ったとされている。1634年には、京・大坂にはそれぞれ41万人前後、長崎・境は5万人、江戸は数十万人を数えたようだ。18世紀になると江戸は130万人に達して、世界でも有数の人口を擁する大都市になった。
▽184 両国の広小路は興業の拠点。仮設の小屋などの仕掛けとエネルギッシュな人々の動きとが一体となった、独特のにぎわいに満ちた界隈としての広場。……この土地が網野さんのいう「無縁」の原理が働く一種の解放区であったのではないか。
……「明治6年ごろ、こうした見世物は大圧迫をうけ、よしず張りの小屋掛や川沿いの水茶屋が取り払われた。近代国家の発展とともに、都市空間が管理の下にくみこまれ、江戸時代の猥雑な生命力をもったアジール的な場が奪われてしまった」
▽191 都市としての江戸は、京をまねて東叡山をつくり、不忍池を琵琶湖にみたてて弁天を祀った。山王、住吉など、神仏は西から勧請している。
▽194 私は「日本文化」は単一でなく、およそ百の盆地を単位に成立していて、それぞれが小宇宙=地域文化を形成していると述べた。その単位を「小盆地宇宙」と呼んだ。
……日本文明は、二つの焦点=中心をもつ楕円であり、弥生時代に北九州と近畿という2焦点をもっていたが、13世紀に鎌倉武家政権が成立し、17世紀初頭から江戸幕府が生まれ、19世紀中頃の明治維新によって東京に継承されることによって、近畿と関東、上方と江戸・東京という2中心に移り、相対的に北九州の地位が低下した、というふうに考えている。
しかし、縄文時代を行旅にいれるならば……東日本には「ナラ林文化」が、はるかに豊かな基盤を準備していた。
弥生稲作文化はあきらかに東にむかって伝播し、国家統一の基盤になっていったのであるが……
▽197 小盆地宇宙 閉鎖的な空間の中心に城があり、城下町があり、そこで物資や情報の集散がおこなわれている。盆地底の水田地帯とその周囲の丘陵部の棚田、畑地、果樹園、茶畑、桑畑などの地帯、それを取り囲む山地=里山にはじまり、より深い奥山にいたる山地帯をふくめて、その全体を小盆地宇宙と呼んだのである。そこには、弥生時代以来の稲作もあり、幕藩体制下の行政単位である領主と家臣団の武家屋敷があり、物資を流通させる市場をもつような商家や鍛冶屋などの手工業者の居住する町場(城下町)があり、……他方では、「山に隠れる人生」ー縄文時代以来の伝統もいきいきと伝えている空間、というイメージである。
▽203 小盆地とそれをとりまく相対的にクローズドな空間を、日本文化の基礎単位と考えようというのが、私の小盆地宇宙論である。
▽211 小和田哲男さん「城と城下町」に京都を模範とした町割としての「小京都」を紹介。……大内氏の山口が中世に成立し、小京都だったのに対し、角館は近世になってつくられた。佐竹氏の一族が入城し、町並みを京都ににせ、川の名を鴨川とよんだり、山にも小倉山・東山と名づけるなど……
▽215 小京都とは、文明にあこがれたそれぞれの地方の人々が、都ぶりを移植してその文化の拠点にも、雅を導入しようとした心意現象の表現の結果であるといえよう。それは上代の日本人が外来の仏をありがたいものと感じ、仁義礼智信の徳目に納得した態度をとり、律令制を採用した心意と共通している。あるいは文明開化の時代になって、自分を野蛮・半開・文明の三段階のうち半開と位置づけ(福沢諭吉)、西欧に追いつき追い越すことを目指した心意とも共通である。この向上心は、日本人のひとつの民族性といえるかもしれない。
▽220 日本列島の歴史は、弥生から現代までのまとまりのほかに、別の時間があることがしだいに明らかになってきた。三内丸山遺跡が別の1500年におよぶ縄文期の持続した時間が提示されたのである。
糸魚川のヒスイがこの地で加工されていたことは、なんらかの流通機能をになう人々が存在していたことを示す。幅12メートルの道路が420メートルにわたって、海に向かってのびていることは、この土地が港につながっていたことを示している。
この1500年という文明の時間は、優に弥生〜現代の文明の時間に匹敵する。(真脇はさらに)
……照葉樹林文化の重要な文化要素とされるウルシを用いた漆器が、縄文時代におどろくべき洗練さをしめしているのは、縄文農耕論を補強するばかりでなく、より広い地域の長い交流を示唆する。
▽223 エスキモー、ピグミー、アボリジニ……調査し、物質文化において極端に少なく、社会組織において家族集団を超えた組織をもたず、世界観においても単純な自然崇拝にとどまり、食物を求めて遊動的生活を営んでいるという、狩猟採集社会の原型を描いてきた。……しかし例示された諸民族はすべて極限的な自然条件のもとにあった。中緯度帯の亜寒帯から温帯、亜熱帯地域の狩猟採集民は、農耕民に変化するか、あるいはおきかえられてゆくのであるが、この地帯の狩猟採集民がどこに行ったのかは、ついに論じられないままだった。三内丸山は、その問いに答えるヒントを豊かな情報として伝えているのだ。
▽226 ヨーロッパではもともと文化と文明はほとんど同義につかわれていた。それが、後進的なドイツが英仏に対抗して、文化を文明よりも優位に位置づけた。ゲーテやシラー、モーツァルトやベートーベンの「精神的文化」は、英仏の誇る「物質文明」よりも価値が高い、という訳である。日本は明治以後このドイツ流の「文化」の考え方を輸入して、文化が文明よりも上等なものと位置づけた。それが戦後になってさらに教化された。文化国家、文化人、文化住宅、文化なべ……文化といえば上等というラベルを貼ることになった。
■末原達郎
▽236 農村社会の変動の原因となるものが、都市社会もしくは都市性の発展であることに米山は気づいていた。
……日本では戦後も長いあいだ、日本は農村社会の集合体として考えられていた。あるいは日本の社会構造じたいが、都市性の論理ではなく、農村の論理によって組織されていると考えられていた。また、農村の論理こそが日本の社会の近代化を遅らせている考えられていた。しかし米山は、農村の論理がけっして封建的で、古くてまちがっているだけのものではなく、妥当な論理性と合理性を含んでいるものとしてとらえていた。
その一方で、21世紀の日本の社会を、もはや農村の集まった社会ではなく、全体として都市化し、市民化した社会へと移行したものとしてとらえている。長いあいだ日本の社会の基盤を形成していたと考えられている農村社会と農民のメンタリティーは、20世紀末にいたって大きく変質し、日本列島を都市列島に変え、農民を市民に変えたと論じている。しかも農民は、時には言葉の本来の意味での百姓へと回帰していると路地ている。都市研究が農村研究と結合することになる。
▽240 京都の根底には渡来人の文化が色濃く存在している。……京都はまさに複雑系の世界。祇園祭のなかにもさまざまな要素が混在。御霊信仰、八坂神社独自の信仰集団、町衆……
▽242 農耕が開始された時期こそ、文明が育まれる最初の時期だとみなす考え方がある。……穀物生産による食糧の余剰と蓄積が、文明を生み出す基礎となったとする考え方である。逆に、農業生産が中心になる以前であった縄文時代は、厳しい生活に追われる貧しい狩猟採集の世界であったのではないかと想像されがちである。
……日本文明の基点を、水田農耕が普及した弥生時代におくことから、三内丸山遺跡を生み出した縄文時代に置きかえることによって、日本文明の歴史を2300年前から5000年前にまで遡らせて考えることができるとする。
▽244 日本文明と日本文化を見る場合の多様性を分析する場合の基礎的な単位として、米山は「小盆地」を発見する。日本列島を、平野世界としてでも、山岳世界としてでも、沿岸世界としてでも見るのではなく、盆地群にこそ日本社会の原型が見出しうると論じる。この盆地にとって重要なのは、周囲の山々とそこから流れでて、次の盆地や平野と結びつけていく河川の存在である。この河川の流域もベースン(盆地・流域)とよばれる。こうした多様で小さな盆地世界さらには流域世界にこそ、日本文化の基層が存在していると米山は考える。
……小規模の盆地の内部には、それぞれ小規模ながらも文化的には世界観と呼んでいいものが存在している。そうしたコスモロジーを含んだものが、小盆地宇宙論の基礎となっている。
……小京都論は、実は京都をモデルとした日本の数多くの小盆地世界とみごとに対応している。小盆地の多くは、その中心に京都をモデルとするような小さな文化都市があり、とくに江戸時代以降になると、城下町がこうした小さな文化都市であることをみたす要件となっていたのではないか。
■2006年2月5日 奈良女子大での最終講義
2月2日に「余命3カ月」と宣告



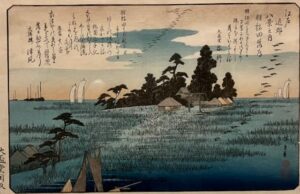

コメント