■岩波新書20230711
古典や神社の文書などの引用が多くて、読みやすいとはいえないけれど、中身は刺激的だった。
奈良盆地の、三輪山の大神神社や葛城の高鴨神社といった神社の祭神が出雲系で、丹波や富山、吉備、「国譲り」以前の伊勢にまで出雲系の信仰が広がっていた。上賀茂神社の祭神もそのひとつだ。 そうした事実から、かつて出雲系の氏族が連合国を形成して畿内を支配しており、その最有力のクニが邪馬台国だったとする。
魏志倭人伝には邪馬台国までの道のりの記述がある。「東水行20日」というと瀬戸内海ルートとかんがえる研究者が多いが、瀬戸内は潮の流れが難しい。「水行」には対馬海流がある日本海をつかい、「投馬国」というのは出雲あたりで、さらに東へ「水行10日」の丹後で上陸し、陸路で1カ月で到着したのが邪馬台国。つまり邪馬台国は奈良にあったとする。
邪馬台国が大和朝廷につながるという説については否定する。記紀の編纂時に「倭の女王」は登場するが、邪馬台国も卑弥呼の名もでてこないからだ。
出雲系連合王国である邪馬台国は、九州から遠征してきた神武によって攻められ、降伏する。それが「国譲り」だという。
大和を支配した王権は、出雲勢力が強い周辺地域の服属をめざす。
たとえば海部氏と始祖を同じくする尾張氏は、神武の大和占領後、新天地をもとめて尾張(愛知)にうつった。その後、尾張氏は大和朝廷に服属し、草薙剣をまつるために創建された熱田神宮の祝部とされた。
天照大神をまつる場所をさがすため、豊鍬姫と倭姫が55年間巡行する話は、それぞれの土地の有力者を帰順させる経緯だったという。
磐座信仰が出雲系に多いのは、鉄の鉱脈を掘る工人たちが山中の巨大な岩塊に特別の思いを抱いたからだ。三輪山の麓には製鉄がおこなわれた形跡があり、御所市の「葛城御歳神社」の背後の山にも磐座と鉱脈があった。製鉄が「国作り」の中核を占めていたが故に、出雲系の神と磐座祭祀がむすびついた。
修験道の創始者の役小角の父は高鴨神社の神人で、母は物部の娘だった。出雲系の鴨氏と物部氏の血を引き、鉄をもとめて山を歩いた出雲のDNAをもつ人だった。
「桃太郎」は、岡山では「吉備津彦と温羅(うら)」の伝承がベースだとされている。
崇神天皇の時代に百済から温羅という王子が飛来し、鬼ノ城をかまえて鬼ノ岩屋という洞窟にすみ、人々を襲った。大和朝廷から派遣された吉備津彦命がこれを退治した……。
温羅が築いた鬼ノ城は、白村江の戦いのあと、西日本各地につくられた、朝鮮式山城という。
吉備津彦が戦のために石の盾を築いたとする場所は弥生墳墓の楯築遺跡(倉敷市矢部)を指す。古代人には、山上の城は鬼の住居に見えたのだ。温羅伝説の背景には、中国山地のたたら製鉄があり、工人たちが鬼にしたてられた。大和王権が吉備津彦命をとおして鉄資源の掌握をはかったとすると、桃太郎は、実は弱者をいじめる権力側の人間だったのかもしれない、と推測する。
=======
▽王朝時代、国守(受領)は任国に下ると、主要な神社を「巡拝」したが、平安末期になると、その煩を省くため、国衙のそばに神々をまとめて祭るようになった。それが惣社。
▽3 三輪山の麓の大神神社は、大物主神(大国主神とおなじ)を祭神とするが…
ここに神奈備信仰や磐座信仰といった自然信仰があり、それに人格神への信仰が重層して存在した。
大物主神が三輪山に祀られた経緯…記紀がともに、「国作り物語」の最後を、海から来た神、実は大国主神自身を三輪山に祭ることで終わっている。それは出雲勢力が大和に進出して葦原中国の支配を完了したことの証しだった。
▽17 大己貴神と大国主神とは一体の神。大己貴神による国土形成が大和国におよんで完了したとき、大己貴神の霊魂は三輪山に奉祭されて大物主神とよばれた…
これらの神々により、出雲の勢力が大和や北陸に及んだこと、…大己貴神の霊が三輪山にまつられることで国作りが終わり、出雲神話も完了するのである。
▽19 「磐座信仰」は、出雲系統の祭祀=信仰を表徴するものといってよいだろう。…▽丹波・亀岡の出雲大神宮(〓行った!)峯のふところに巨石があり、その前方に社殿が営まれている。
▽21 大和から河内に抜ける磐船街道の磐船神社(交野市私市)の磐座。ニギハヤヒノミコトが高天原から乗ってきたという「天磐船」に擬してまつるようになった。
▽23 宮津・籠神社の奥宮・真名井神社境内に磐座。
▽26 上賀茂神社の祭神も出雲系。
▽27 磐座信仰は、出雲系にかぎるものではない。にもかかわらず磐座を出雲系のしるしとしたのは、…磐座の発見は、鉱山の開発、ことに鉄生産の仕事と深いかかわりがある。工人たちが鉱脈の単作で山中を巡る間にであった巨大な岩塊に特別特別の思いを抱いたのにはじまった。三輪山の麓には製鉄がおこなわれていた形跡があり、御所市にある「葛城御歳神社」は背後の山に磐座をまつるが、ここにも鉱脈があり…
製鉄が「国作り」の中核を占めていたことからすれば、出雲系の神と磐座祭祀との関係は本質的なものだったと言えるのである。
▽28 「国譲り」以前、伊勢の朝熊山麓、現在の宇治山田一帯に出雲系の神を祭る神社があり、そのご神体が磐座であった。
伊勢の地で、鏡をご神体とする神宮系の神々に対して、出雲系の神々が磐座であったのは見事なまでに対蹠的であった。
しかもその朝熊神社の神々は、いまも伊勢神宮の境外別社として祭られている。
▽32 出雲大社のもとは、斐川町の仏経山頂の磐座。=出雲の三輪山
麓にうつされた曽梏能夜神社の境内には「さざれ石」が山上の磐座にかわる石神として祭られ、出雲大社への遥拝所とされている。
▽35 熊野大社の元宮 天狗山の山頂近くの磐座
須我神社(大東町須賀)の奥宮の磐座
▽邑南町の岩屋神社の巨石群
▽40 大己貴神と磐座信仰のつながりは万葉の時代から人々の認識するところであった。
▽44 出雲国中央の山あいの来次こそが大国主神の国作りの原点であり(意宇郡がもとではない)
▽53 出雲国の中枢は斐伊川の中流域、現木次町当たり。機能ごとにいくつかの地域にわけ、それらが有機的にむすびあわされ、全体がなりたっていた。
四隅突出墓が出雲文化圏の特徴。出雲から北陸の富山あたりまで分布。丹波(京都)には存在しなかったとされてきたが…発見。
▽62
▽80 瀬戸内海はこの時代、進むにすすめぬ「穏やかな地獄」だった。東への舟行につかわれたのは日本海。東流する対馬海流がある。
「東水行20日」の投馬国というのは出雲あたりであり、さらに東の「水行10日」は丹後当たり。ここで上陸し、陸路で1カ月で到着したのが邪馬台国だった。つまり奈良だった。
▽89 邪馬台国は、領域を4つにわけ、北に物部氏、西南に鴨氏、東に大神氏。
これら3氏族は出雲系。邪馬台国は出雲系氏族連合によって擁立された王朝であった。
後に出雲国造が出雲から大和朝廷に出てきて神賀詞を奏上するが、注目されるのは、4つの神社を皇室の「近き守神」とすることを述べている事実。三輪の大神神社、葛城の高鴨神社、飛鳥の伽夜奈流美(かやなるみ)神社、宇奈提の川俣神社。これらは大和朝廷以前から出雲系の神社として存在していたことを前提にしている。
▽92 記紀には卑弥呼は出て来ない。日本書紀には「倭の女王」などとして3度登場する。
…神功皇后 研究者の多くが、日本書紀は、卑弥呼を彼女になぞらえている、とか、同一人物とみている、と理解したのは不思議ではない。
▽109 神武軍の侵攻を阻んだ軍勢は出雲勢力だった。邪馬台国連合は、王国を守るために総力を結集していた
▽111 長髄彦 神武に頑強に抵抗。最後は主人である饒速日命に殺される。饒速日命は神武に屈服する。
添御県坐神社(奈良市三碓)、登弥神社(奈良市石木町)。なかでも前者の祭神の一座、武乳速命のことを現地の人は長髄彦だと信じ、「自分たちの先祖は長髄彦にしたがい、生駒山頂から大きな石を神武の軍兵に向けて投げたものだ、と戦いのさまを昨日のことのように語ってくれる古老がいたとのことだった。先祖が長髄彦にしたがって戦ったという伝承を信じ、誇りにしている人たちが現代もいるというのである。
古老の言によれば、当社の祭神から長髄彦の名が消えたのは明治になってからだという。…長髄彦は生駒地域の首長だっただけでなく、饒速日命の率いる邪馬台国連合の総大将であったとみられる。
▽116 神武の大和侵攻は史実を反映していると確信した。
▽118 総帥・饒速日命が、もっとも信頼のおける部下の長髄彦を殺してまで、最後に帰順した。主戦論をおさえて無血開城。
▽124 饒速日命は出雲系とみられる。大神神社の祭神・大物主命が本来は蛇であり、出雲大社も神在月で八百万の神を先導するのは竜蛇神で、ともに蛇神信仰がもとになっている。(大宮の氷川神社も「水」がもとだった〓)
▽128 大和を支配した王権が次にめざしたのは、周辺地域、とくに出雲勢力が強い地域の服属であった。
▽129 草薙剣は熱田神宮に祭られている。尾張氏は大和朝廷に服属し、草薙剣を奉祭するために創建された熱田神宮の祝部とされた。
▽134 奈良県田原本町の鏡作神社。内侍所に祭る神鏡を鋳造する際、ためしに鋳造した鏡をご神体とする。…邪馬台国時代、鏡作り工房があり、大和朝廷になってからもつくられたのだろう。
▽140 伊勢神宮をさがすため、豊鍬姫と倭姫が巡行する。…それぞれの土地の有力者を帰順させ…伊勢神宮の経済的基盤の整備にあたった。巡行は、それぞれの土地に4年を基本として、長くて8年間滞在しては次の目的地に移る。…豊鍬入姫が21年、倭姫が34年、合計55年の歳月を要している。
▽143 伊勢の祭祀は、大和王権が確立する段階で、天照大神=鏡を社殿に祭ったのにはじまるのだから、出雲の神よりも新しい。
▽148 尾張氏は海部氏と始祖を同じくする。神武が大和にはいったあとに、新天地をもとめて尾張(愛知)の地にうつったものとみられる。
▽153 出雲と筑紫の関係は古来非常に親密。
▽157 役小角の父は高鴨神社の神人で、母は物部の娘。鴨氏と物部氏の血を引き、鉄を求めて歩いた出雲のDNAを伝える人物であった。古くから葛城に住んだのは、出雲から移ってきた人たちで、鴨族とよばれる集団だった。
▽158 上賀茂神社が背後の神山の磐座信仰にはじまるのにたいして、下鴨神社はふたつの川の合流点に祭られる川合社としてはじまっており…
▽167 畿内周辺をおさえた大和王権が次に制圧すべきところは、瀬戸内海沿岸、とくに吉備(岡山)であり、九州であったろう。
▽168 仁徳天皇は、大和盆地をはなれ、難波の高津宮で即位。瀬戸内海重視の最大の意思表示であった。…難波津は、他国への出口であり、倭国への入口であった。
▽169 吉備国は、邪馬台国連合の有力なメンバーであったと考える。
▽173 桃太郎の話は、地元岡山では「吉備津彦と温羅(うら)」の伝承がベースであるとする。吉備津神社に伝わる縁起の「温羅伝説」
崇神天皇代に百済から温羅という王子が飛来し、新山(鬼ノ城)に城をかまえ、近くの岩屋(鬼ノ岩屋と呼ばれる巨大洞窟)にすみ、人々を襲ったので、大和朝廷から派遣された吉備津彦命に退治された。その髑髏を吉備津宮の釜の下に埋めた。命の夢に温羅があらわれ、…人々の事の吉凶を釜の音で知らせると告げた。これが鳴釜神事の起源とする。
温羅が築いたという鬼ノ城は、白村江の戦いのあと、西日本各地につくられた、朝鮮式山城のひとつであるが、築城を指導した亡命百済人が温羅の原像になったのだろうか。〓
吉備津彦が戦のために石の盾を築いたとする片岡山は、弥生墳墓の楯築遺跡(倉敷市矢部)を指す。昔の人には、高い山上にある城は鬼の住居に見え、遺跡に残るストーンサークルはあたかも矢を防ぐ盾に見えたのだろう。これに記紀の吉備津彦伝承が加わり、温羅伝説が生まれたと思われる。
温羅伝説の背景には、中国山地の鉄生産があり、そのかかわりのなかで、工人たちが鬼にしたてられたものと考えるが、ここでも、吉備津彦命を通じて吉備の鉄資源の掌握をはかった大和王権を忘れてはならない。桃太郎は、実は弱者をくじく権力の座にある人物だったのかもしれない。〓
▽179 出雲国造について、本拠は東部の意宇郡にあり、同郡内の熊野大神を奉祭していたが、のちに西に移り、杵築大赦を奉祭するようになった、というのがほぼ定説になっている。しかし…前者の祭神は櫛御気野神であり、後者は大国主。私は定説はとらない。
…もとの本拠は出雲国の中央部で、斐伊川の中下流、神名火山(仏経山)の山麓一帯であった。
▽180 出雲国造が706年、意宇郡の大領に補任される。国造は元来地域の豪族だが、律令制の国郡制のなかで群司とされた。中央からの国司の下に置かれた。「大領」になったのは、1郡にかぎるとはいえ失った権限を取り戻したともいえる。
▽183 出雲国風土記 国造広嶋が全体の統括者。本来なら国司がすべき仕事を国造がしていた。
大国主神はこう宣言した。「葦原中国は天孫にゆずるが、出雲国は私が断固守る」
▽193 熊野大神をミケの神としてとりこむことで、出雲大社全体を整えたのではないか。出雲大社を内宮とすれば熊野大社は外宮であった。
▽214 706年以来、国造として兼ねていた意宇郡の大領職を、公務怠慢や私利追求を理由に798年に解かれる。こうして出雲国造家は、神官としての国造にもどることになった。
…出雲国造による「神賀詞奏上」も、長岡京、平安へと遷都してまもなく終わってしまう。大和を守る「四神」も意味を失う。
…京都の賀茂社は「天神」とされ、伊勢神宮とならび朝廷の崇敬を受けるにいたった。
▽219 出雲系の神々にとって、山城・平安京遷都を画期としてきびしい時代がはじまった。中でも大国主神を奉祭する出雲国造だった。
▽222 意宇郡大庭屋敷を拠点とする活動は798年、大領職を解かれたことで終わる。本拠の杵築にもどり、二重生活も解消した。しかし、熊野大社の鑚火殿でおこなっていた、国造の代替わりの火継ぎ式だけは今もつづけられている。鑚火殿でつくられた火で調理した齋食を新国造が食べることにより、祖霊の霊魂を継承する儀式。そして国造のみ、終生この最初の神火で調理したものを食べつづけなければならない。熊野大神が御饌の神であることの意味も理解できよう。
▽228 岡山や広島の国司神社 みな大国主神をまつっており、明治以前は「国主神社」と称していた。明治の一村一社制により村内の社祠をあつめるとき「国司」に名を改めた。「国主」−「国の主」では国家に対して具合が悪かろう、という自制が働いた。唯一改めなかったのが新見市内では上市の国主神社。
新見に国司神社が多いのは各集落に1社ずつ大国主神を祭る社があったから。昔から製鉄が盛んで、これにあたった出雲族が祭っていた。
…国司神社のあるところには近辺に鉄生産の跡や伝承がある。…大国主神信仰は、原始古代から近世におよぶ鉄生産とのかかわりのなかでひろがった。
▽242 大国主はたくさんの異名をもつ神として有名。古代以来の製鉄集団による信仰を特徴としたことはあきらかで…。つねに国作りと不可分な形で呼ばれるのは、国土開発の神というのがこの神に付与された最高の概念であったからである。
▽244 伏した狛犬=出雲系 「社日」さまとよばれる五角形の石柱も出雲系のしるし。



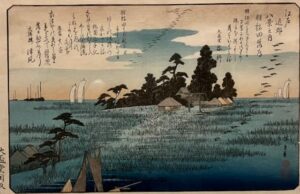
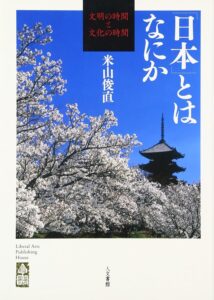

コメント