■新潮文庫 20230727
松尾芭蕉とならぶ日本最大の詩人である柿本人麿は長らく、島根県益田市の高津川河口の鴨島で死んだとされてきた。だが、そんな辺鄙な島で国府の役人が死ぬわけがない、と、斎藤茂吉は、海辺ではなく江の川上流の湯抱で人麿は死んだと結論づける。たたら製鉄の仕事の監督にきて、伝染病に罹患してしまった、と。辞世の歌をのこしているから、じりじり悪くなる病ではない。事故でもない。だとしたら流行病だ、と茂吉は考えた。
学界と歌壇は、斎藤茂吉の人麿終焉地の説をほぼ信じた。
梅原は茂吉の説にまず反旗を翻す。 人麿が「自らの死を傷む歌」をつくったのは、自らの死が確実であることを意識しながら、その死がのぞましくないからだ。
人麿は死後、「神」としてまつられた。神になる人は、藤原広嗣、菅原道真、平将門、崇徳上皇など、恨みをのんで死んでいった人間ばかりだ。
5つの歌を丹念によみこむと、島にながされ、そこで水死という形で処刑されたと読める。その場所は、従来の伝承どおり、高津川河口の鴨島だった……。
斎藤茂吉の説への反証をするうちに、茂吉に影響をあたえた江戸時代の国学者・賀茂真淵らが最大の敵として浮かび上がる。彼以降のほとんどの学者は、茂吉もふくめて彼らの影響下にあった。
賀茂真淵や契沖は、五位以上の貴族の死は「薨」「卒」と表記されるのに人麿は「死」と表記されていることや、五位以上なら正史にしるされるが、人麿は正史にでてこないことから、人麿は六位以下だったと判断する。石見の僻地につかわされた下級役人が、偶然の病で死んだ、という筋書きだ。
だが、 紀貫之が編纂した「古今集」の真名序・仮名序には人麿は三位、すくなくとも五位以上であるとしるされている。真淵は「それは後世の人がまちがって書き加えた」と断じた。
梅原は、真淵の判断に疑問を抱く。紀貫之が、人麿の運命や地位を誤記するわけがない、真淵の認識のどこかに誤りがあるはずだ、と。
実は、柿本人麿とほぼ同時期に、天武10年に従五位下に位置づけられている柿本猴(佐留=さる)が死んだ。
猨は人麿の父、という説もあるが、2人は同一人物ではないか、と梅原は思いつく。人麿の生年が猨とほぼ同じである可能性があることを証明していく。
「猨(サル)」という名は蔑称である可能性が高い。時の権力者の不興を買って蔑称を押しつけられる例は少なくないからだ。
人麿は、皇族の挽歌をいくつもつくってきたが、もっとも人麿を重用した持統天皇への挽歌はつくらなかった。それは「ヒトマロ」が「サル」と女帝に改名されて近江か四国の岑島に追放中だったからではないか。
さらに「猿丸大夫」の伝説に梅原は目をむける。猿丸は「有名な歌人」とされながら、古今集にも万葉集にもその名がでてこない。実は「サルマル」は「ヒトマル」ではないか……。
人麿=猨なら、身分上の説明はつく。罪人として流されていれば「死」と表記されるのもおかしくない。
人麿の死んだ(和銅元年)わずか1カ月前、藤原不比等が権力の掌握をはたしている。
藤原氏をトップとした律令制の秩序と、古くからの勢力とつながっていた詩人とは相容れなかった。当代一の詩人の死は「律令体制(藤原)に逆らうとこうなるぞ」という脅しとして機能したのではないか。
地方へ赴任して伝染病で死んだかわいそうな下級官僚ではなく、中央の権力争いにやぶれ、世にも悲しげな辞世の歌を残して入水自殺した流刑の貴族だったのだ。
人麿の立場を明確にするために、梅原は、古事記・日本書紀・万葉集の「意味」を考察する。
人麿の歌と古事記、日本書紀では天孫降臨の描き方が少しずつ異なる。
八百万の神の合議によって「皇子」が降臨していたのが、「皇孫」が降臨することになり、次に、天照大神と高木神の命令で皇孫が降臨することになる。最後の日本書紀では、高皇産霊尊(高木神)の命令で皇孫が降臨する。
神の衆議は、天武帝死後の不安な政治情勢を示し、天照大神とは持統であり、その後、外祖父である高木の神=不比等=が権力をにぎる……という経緯が神話のなかに表現されていると梅原は見る。
柿本神社は全国に70あり、大和新庄の柿本神社などの人麿像の首は、すぽっとはずれる。後世の像も、首がすっぽり抜けるものが多い。しかも天平年間には人麿は水難の神になっている。
そもそも、万葉集の相聞歌の多くは引き裂かれる男女の歌であり、挽歌の多くは強いられた死の歌だ。万葉集の巻一と巻二、すなわち「原万葉集」の中心テーマは人麿の死であり、「原万葉集」のねらいは、人麿を死に追いやった藤原権力の告発だったと梅原は説く。
そう考えれば、橘諸兄が、藤原との対決を覚悟しはじめた天平勝宝5年に原万葉集がつくられたという伝承に符号する。諸兄や家持の時代に、人麿が復権されたのだ。
その後、藤原がふたたび権力を独占する。大伴家持は左遷させられ、死の直後、大伴継人の反乱に関与した容疑で官位を剥奪される。
ところが、桓武天皇の死の間際に復位される。桓武の弟で、桓武が息子に天皇をつがせるために無念の死を遂げた早良皇太子(崇道天皇)の怨霊鎮魂のためだった。家持は崇道天皇の近臣としてつかえていた。
橘諸兄と家持による万葉集A(原万葉集)は、藤原仲麻呂らによって勅撰集の地位を奪われ、仲麻呂体制の成立とともに大伴家持も左遷された。左遷中に家持は20巻におよぶ歌集をつくった。
しばらく眠っていたその万葉集が、桓武天皇が没し、早良皇太子(崇道天皇)の怨霊がおそれられた大同元年に、家持と彼の主君の早良皇太子の怨霊鎮魂のためにふたたび勅撰化された……と、万葉集の制作過程を梅原はえがく。
徳川時代の国学者たちは浪人や町人で、身分秩序のきびしい封建時代を暗い社会とし、それを否定する明るい社会として日本古代を理想化し、古事記や万葉集を「聖典」と考えた。素朴で明るい神話=古事記、健康でますらおぶりな歌集=万葉集、という見方が国学者たちによってつくられ、明治以後もうけつがれた。
古い日本の魂は、そんなに、浄く、明るく、直きものではない。浄く、明るく、直き魂は、律令支配者がつくった「上からの道徳」にすぎない。不気味で、暗いものが、日本人の魂の底にある。この本で梅原はそう主張している。
======
▽146 文武4年から大宝元年にかけては歴史において画期的な時期だった。律令国家ができあがったときであり、藤原氏の独裁体制の基礎ができた年である。そういう年とともに、人麿の宮廷詩人としての活動が終わっている。
持統天皇の時代とともに人麿の活躍ははじまり、持統時代とともに人麿の活動は終わる。持統は大宝2年没だが、このとき人麿は挽歌をのこしていない。
持統3年から文武4年までのはなやかな宮廷詩人としての活躍の後に、讃岐国と石見国へ行った。
▽160 仁多郡横田、三成、八束郡鹿島古浦の地からフイゴ口や鉄滓が認められ、少なくとも古墳時代中期、後期ごろから製鉄がおこなわれていた。
仁多郡、飯石郡の一部にかぎられている。
▽204 万葉集は2回にわたって選ばれたのではないか。はじめは、橘諸兄と大伴家持、二度目は平城天皇とだれかによって。3人とも藤原氏にたいして敵対意識をもっていた。
藤原の独裁体制がゆるんだ時期が、2度あった。橘諸兄の時代と平城天皇の時代である。
▽215 不比等と一体となって政治をとった元明女帝をたたえる歌が人麿には一首もない。専制体制にあっての一種の抵抗では。
▽237 国府の近くにある韓島から、高津の沖合の鴨島に移動することが命じられる。妻から離され、…死ぬために。
▽238 古代人は、伝承を偽造することをめったにしない。伝承の偽造は、徳川中期以降である。名所めぐりがおこなわれるようになると、伝承は偽造されるが、それ以前はそんなことをしても、利益にならない。
▽266 人麿は「ひじり」とよばれ、赤人は「人」とよばれる。人麿はすでに神だった。日本において、死後まもなく神になるのは、非業の死をとげた人であった。
聖徳太子も、「詩聖」とよばれた菅原道真も。
▽277 律令によって法律家が支配する時代へ。死後の世界の実在性を信じなくなりはじめていた。…もしも人が死んで灰や煙になるとすれば、巨大な墳墓や石室は必要がなくなる。見事な挽歌によってその死を荘厳にする必要もなくなる。詩人の役割は終わろうとしていた。
…冷静な計算、巧妙な虚偽、極端な吝嗇、残忍な刑罰。その反対の精神が、詩人・柿本人麿の精神であったろう。
▽287 死罪には、斬罪と絞罪があったが、身分の高い人間には、名誉を重んじて自殺を賜ることになっていた。…大友皇子も
▽292 大国主も息子のことしろぬしも、入水による自殺。荘厳にして華麗なる死を賜った。
▽312
▽344 「古今集」は、古代、中世をつうじて美のバイブルだった。これに疑問を投げかけ、万葉集こそがそれ以上だとしたのは、徳川吉宗の次男田安宗武と、その国学の師・真淵だった。しかし真淵の弟子、宣長によって否定された。その後も、子規の時代まで、古今集は美のバイブルでありつづけた。
万葉復帰を唱えたのは、子規であった。子規の時代から、古今集は美のバイブルの地位を万葉集にゆずりわたす。
▽386 真淵は、古代人はおおらかで正直であるという。…万葉集にせよ、古今集にせよ、ひそかな政治的配慮をその背景にもっている歌集である。真の意味をくみとるためには、その時代のきびしい政治的状況を知らねばならぬ。
▽387 正史にないことが、人麿六位以下説を生み、古今集序文の誤謬説をいっそう強力にした。
▽388 天武十年に小錦下をさずけられ、和銅元年に死んだ柿本猨(佐留)。これを人麿と考えられないか。
▽388 古代・中世の歌学者にとって「古今集」は絶対の権威であった。それゆえ、人麿が正史に登場しないという事実と「古今集」の序文の権威との間の矛盾に苦しんだ。中世人は懐疑の自制を知る人間だった。彼らは矛盾を矛盾のままに残しておいた。
しかし、近代の国学者は、矛盾を理性をもって解決しようとする。真淵はそういう合理主義を、儒学から学んだのであろう。…古今集の序文を削除、改竄するにおよんだ。(都合のわるいところを)後世の追記であるとする。紀貫之が、こんな愚かなことを書くはずがない、という理由で。
▽404 持統皇后は、自己によく似た中国の則天武后(623−705)を見習おうとした意志があったのではないか。
則天武后のように、持統皇后も、物部麻呂と中臣大嶋を寵臣とする。名門の大伴氏をさしおいて、朝臣という姓をあたえた。
…日本第1の名家をほこる大伴氏が、差別に憤り、…それが、大伴旅人の酒となり、大伴家持の歌となった……
▽409 柿本人麿は、「朝臣」。人麿は猨の近親者ということになる。多くの人はそう疑った。…人麿は、猨とほぼ同時に死んでいる。
▽419 (猨との年齢のちがいは真淵の誤解ではないか)
■水底の歌 柿本人麿論 下<梅原猛>新潮文庫
▽43 人麿の歌 大祓祝詞 古事記 日本書紀 それぞれに天孫降臨の神話がえがかれるが、少しずつ異なる。
①一番古い人麿の歌では、降臨の主体は皇子であり、命令するのは八百万の神の合議だ。
②2番目の大祓祝詞では、主体は皇孫であり、命令するのは①同様の神々の合議。
③古事記は、主体は皇孫で、命令者は天照大神と高木神。
④日本書紀は主体は皇孫で、命令者は高皇産霊尊(高木神)
神の衆議は、天武帝死後の不安な政治情勢を示す。持統皇后は大津皇子を殺す。
天照大神(=持統天皇)と高木の神(不比等)の合議 絶対的な皇権は確立されたが、外祖父、高木の神がじょじょに力をもつ。
高木の神の独裁。彼が、天照大神の孫で、己の孫でもある首皇太子を皇位に就ける。
神話の変化のなかに権力の推移が反映された。
▽49 草壁皇子が死亡して皇子降臨の神話は無意味になり、皇孫降臨の神話が必要になってくる。それは持統の最大の願望の表現だった。
▽54 高市皇子をはじめとする、持統の血をひかない皇子に皇位を渡さないために皇后が即位した。
▽59 元明帝から元正帝への譲位。元明が首皇子の成人まで生きていなかったら、天孫降臨の実現は不可能である。彼女は、自分の分身=新しいアマテラスによって、天孫降臨神話を実現しようとした。
そしてその降臨の実行者がニニギの外祖父・タカミムスビノミコトであったように、首皇子の外祖父の藤原不比等。
▽73 持統のたびたびの吉野訪問。吉野といえば宮滝〓。中国風の景色。
▽103 天皇というのは道教的概念。中国の皇帝で、最初にこの称号の自己の名として採用したのが、持統と同時代の女帝・則天武后の夫、高宗。天皇制と同時であると思われるアマテラス神話の誕生も、則天武后の影響であり、道教の影響があるのではないか。…天皇信仰、天照信仰は、持統のときできはじめたのではないか。
▽109 真淵: 伝承通りに人麿が60すぎに死んだとなると、人麿は60を超えて、石見国の小役人になったことになる。だから人麿の死亡年齢を若くしたかった。
▽129 人麿が60余で死んだとすると、天武10年に従五位下相当の位をさずけられた柿本佐留(猨)と同じになる。
▽135 正史になく、卒や薨ではなく「死」と記されていることから人麿は六位以下とされてきた。だが…猨が人麿であれば、正史に載っており…大津の皇子ら罪人には「死」がつかわれている。大伴家持も三位でありながら、暗殺事件に関係したかどで「死」がつかわれた。
▽155 人麿は持統への挽歌をつくらなかった。…人麿が女帝に猨と改名されて追放中であったとしたら…
▽猿丸大夫と人麿は同一人物では? 猿丸大夫は古今集にも「有名な歌人」とされているのに古今集に採用されていない。古今集は万葉にのったものはとらなかった。人麿=猿丸ならば符号する。
▽213 従五位下相当の近江権守に従三位でなるというのは、高官が流罪になるとき。
▽227 人麿ははじめて近江に流人となり、その後四国の狭岑島、最後は石見の鴨島にながされ、海の藻屑と消える。
▽240 柿本神社は全国70あり、…人麿にゆかりのある処には、すべてそこに人丸塚ができ、霊を鎮めるために神社が作られる。…「年老いて自然の終わりを遂げた人」は神に祀られない…
櫟本に柿本寺があり、いまはもう廃寺になっているが…
大和の新庄にも柿本神社があり…祀ったのは真済(800〜860)で…
▽253 人麿像 新庄の柿本神社のものはもっとも古いもののひとつであろうが…首は入首になっていて、すぽっと撮れるのである。櫟本の柿本寺の像も首がとれる。…後世の像も、…首がすっぽり抜ける点は、同じである。
▽268 すでに天平年間において、人麿は水難の神であった。
人麿=猨 年齢・官位が同じであり、その改名の理由もはっきりし、その痕跡も猿丸大夫の伝承として存在している。
▽321 怨霊の周期は1世紀で、1世紀たつと、別の怨霊が力を得るようになる。奈良時代でもっともおそろしい怨霊は、聖徳太子の怨霊であり、平安時代のはじめにおいては崇道天皇、10世紀はじめからはあたらしく菅公の怨霊が猛威をふるう。
▽322 菅原道真が官をもとにもどされ、位を1階級あげられて正2位になったのは…その後、正一位左大臣、さらに太政大臣がおくられた。
▽325 猨が死んだ和銅元年4月20日。この年3月13日、正2位の不比等は右大臣となって、独裁的権力を完全にかためた。それから1カ月後、柿本猨は死んだ。
…あの有名なる詩人すら、殺された。人々はあらためて恐怖の思いで奈良遷都の命を聞いたはずである。
▽331 神亀年間、猨の子らしき人が殿上人になる。高津の柿本神社の創建も神亀年間と伝えられる。
▽342 折口は、真淵以来忘れられていた宗教や死、霊の意味を発見する。万葉の歌を鎮魂の歌と解釈する。
古い日本の魂は、国学者が考えたように、浄く、明るく、直きものではなかった。浄く、明るく、直き魂は、律令支配者がつくった道徳にすぎない。不気味で、暗いものが、日本人の魂の底にある。
▽346 相聞歌の多くは引き裂かれる男女の歌。挽歌の多くは強いられた死の歌。権力者の野望によって殺されていった使者の魂。
万葉集の巻一と巻二、すなわち「原万葉集」の中心テーマは人麿の死なのではあるまいか。…その死は、流罪であり刑死であった。
鎮魂の「原万葉集」のねらいは、人麿を死に追いやった藤原権力の告発。それが橘諸兄によって、藤原氏との対決を覚悟しはじめた天平勝宝5年という時期につくられたという伝承は十分に信憑性があると思われる。
▽352 諸兄や家持の時代に、人麿の復権があったのはほぼまちがいない。
▽377 大伴家持は、死の直後、大伴継人の反乱?に関与した容疑で官位を剥奪される。ところが、かれらは桓武天皇の死の間際に復位される。崇道天皇の怨霊鎮魂のためだろう。崇道天皇の近臣として大伴家持があげられている…
▽378 3月18日は、小野小町、和泉式部、柿本人麿らの怨霊の命日(柳田国男説)。3月18日は彼岸のはじまりであり、怨霊の命日。
▽381 京都の上御霊神社。延暦13年、崇道天皇の神霊をまつったのにはじまり、非業の死を遂げた人を祀った。祭神は崇道天皇のほか、…火雷神(菅原道真)、吉備大臣の8体とされる。この神社の代々の別当を五百枝王の子孫がつとめている。
現在の宮司の小栗栖憲昌は、36代の子孫であるという。
▽386 柿本猨(佐留)は流人で、大宝ごろに都から追放されたと考えた。とすれば、彼が死んだとき、官位を奪われていた。人麿が「死」すと書かれているのはそのためであろうし、「続日本紀」に「…柿本佐留卒す」とあるのは、続日本紀がつくられた延暦16年までには復位されていたのである。
▽390 万葉集A=原万葉集は、橘奈良麻呂の変囲碁、勅撰集あるいは準勅撰集の地位を奪われていたにちがいない。藤原仲麻呂にとってけしからぬ本だったから。
仲麻呂体制の成立とともに大伴家持も左遷されたが、…そのなかで全部で20巻におよぶ大部の歌集をつくった=万葉集Bの成立
宮中に眠っていた万葉集が大同になってにわかに注目され、勅撰集にされた…。桓武天皇が没し、早良皇太子(崇道天皇)の怨霊のたたりがおそれられた大同元年に、家持および彼の主君の早良皇太子の怨霊鎮魂のためにふたたび勅撰化された。
▽396 私が人麿を論じるきっかけとなったのは、斎藤茂吉の「鴨山考」がまちがっているのではないかとの疑問であったが、茂吉の「鴨山考」も、真淵の人麿論にもとづく、人麿の死亡地についての推論であった。
▽あとがき
徳川時代の国学者たちはほとんど、浪人とか町人出身で、身分秩序のきびしい封建時代を暗い社会とし、それを否定する明るい社会の理想を古代に投影し、日本古代を理想化したのである。古事記や万葉集を理想社会のうんだ「聖典」と考えた。素朴で明るい神話=古事記、健康でますらおぶりな歌集=万葉集、という見方が国学者たちによってたてられ、明治以後も受け継がれた。



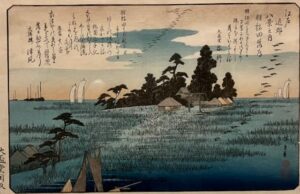
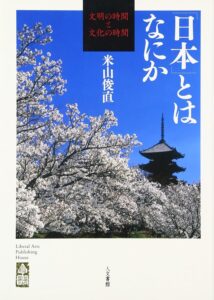

コメント