■中公新書20230625
1972年の古い本。二上山や三輪山が信仰の拠点として生きていた飛鳥から奈良時代、当時の人々はなにを信じて生きていたのか知りたくなった。「神々の体系」というタイトルがぴったりに思えて入手した。
信仰の中身を描いたものではなく、記紀の神々が意味する歴史的意味を説き明かすもので、私のねらいとはずれたが、内容はおもしろかった。
記紀は、天皇の権威の由来を説くためにつくられたと津田左右吉らによって主張されてきた。だが筆者は、記紀のねらいは、皇室の権威というより、藤原家の権力の正当化にあるという。
日本の農耕社会は弥生時代にはじまり、3つの覇権の時代があるとする。
その最初が応神陵や仁徳陵に代表される大王が統治した5世紀の「倭の五王」の時代、2番目が鎌足・不比等以来の藤原時代、3番目が徳川の時代だ。
大王の力がおとろえ、6世紀初頭あたりから、大伴、物部、蘇我のような諸豪族に政治の実権がうつる。聖徳太子から中大兄皇子をへて、天武・持統にいたる、律令制による皇権回復の試みは、「氏姓制度」とよばれる伝統的秩序を崩壊させた。天皇家をふくむ豪族たちの力をそぎ、律令制を推進した新興の藤原氏が実権を掌握することになった。
天武天皇の妻の持統天皇は息子の草壁皇子を皇位につけるため、彼の異母弟の大津皇子を謀殺するが、草壁は天皇になる前に夭折してしまう。そこでまだ幼い草壁皇子の息子(文武)を天皇にするため、みずからがピンチヒッターとして天皇になる。
文武が天皇になり、不比等の娘の宮子が皇后になるが、文武もまた夭折する。まだ幼い息子(聖武天皇)を天皇にするため、草壁の妻であった元明がピンチヒッターの女帝となる。皇后の経験のない女性が女帝になるのは前例がなく、子から母への皇位継承も異例中の異例だった。
はじめは持統が息子を帝位につけるためであり、次は持統と不比等の意思だった。
その際、「皇位継承における直系相承(父子相承)の原則」をかかげた。応神天皇以降は、父子ではなく兄弟で天皇をつぐことが多かった。たとえば、天智天皇の次は、天智の息子の大友皇子に壬申の乱で勝利した天智の弟の大海人皇子が天武天皇になった。
ところが記紀によると、実在がうたがわしい仲哀天皇以前は父子相承が連綿とつづいている。
古事記も日本書紀も、藤原不比等の時代に完成した。記紀の記述は、父子相承の確立をはかったのではないか、という。それによって天皇の祖父としての藤原の権力が絶対的なものになった。8世紀前後の律令国家の成立は、政治的実権の藤原家への移行の転機だったという。
そのほか……
・古事記の神々は、タカミムスビーイザナギーアマテラスーニニギという高天原の系譜、カミムスビ-イザナミースサノオーオホクニヌシという根の国(出雲系)とにわかれる。その両者がイハレヒコ(神武天皇)において統合され、そこから天皇家がはじまる。
・はじめは仏教、徳川時代は儒教、明治以降は西欧思想……と、日本文化は外からの輸入によって形成されたネガ(負)の文化であるという指摘は、内田樹の「日本は辺境」という論とおなじだ。
本居宣長以来、第二次大戦にいたるまで、「ポジ」くらべの理念で、戦争での死者に栄光を与えようとしてきた。ネガ文化の自覚を忘れて自分を見失っていた。
====
▽16 精神的なつながりは、根の国系では心情の絆という形をとり、高天原系では意志の絆という形をとる。(ロゴスとエロス? 理性と情?)
▽23 根の国系の心情の原理は、母をおもい、母の国をおもう心に源をもつのかもしれない。…海のかなたからやってくる神と、天からおりてくる神のイメージに、それぞれつながるのだろうか(沖縄の神はだから女性的?〓)
▽25 陽と陰、天と地、高天原と根の国のどちらにもよらぬ中立の立場がアメノミナカヌシにおいて先取りされ、…
▽42 記紀の一部に、老荘風の宇宙発生論のロジックの借用を認めざるをえない…。
…本居宣長は、古事記の序はシナ風の慣習にしたがった「虚飾」であって、本文に記された「正実(まこと)」とは無縁であると言い切っている。
▽47 古事記=和風 日本書紀=支那の王朝正史に似せたモダンなスタイル
…2つの書物の出現。2人の女帝のもとで、政治の実権をにぎっていたのは大宝律令と養老律令の制作をリードした藤原不比等を中心とするグループだった。
▽51 オリエント・ギリシャ・シナ・インドによって生み出された文化を、つぎつぎと貪欲に吸収してあくことのないこの列島のネガの役割こそが、縄文の昔から今日まで、日本文化を一貫している基本的な特質であり……少なくとも大陸渡来の農耕文明の波をかぶるようになってからの歴史をふりかえると、よくもこれだけ好奇心の心に満ちあふれて、つぎつぎと外来の文化を摂取しつづけてきたものと思う。(辺境文化論〓)
▽52 はじめは仏教、徳川時代にはいると、儒教など、つぎは西欧思想の摂取。…日本における思想の歴史は、まさしく外来思想の輸入の歴史に尽きるといっても過言でないようなありさまである。
…日本文化をネガ(負)の極致とみなす主張を、よろこびに近い感情をもって、是認する気持ちになっているのである。
…日本 あらゆる文明がここに流れこんでくるが、ここからなにか独自な文明がよそに流れだしたということをきかない。消極的凹型文化の創造的意義を肯定する哲学を、「老子」のことばに見いだすのである。
▽57 本居以来、大戦にいたるまで、戦争での死者に栄光を与える光源の役割を果たしてきたポジくらべの理念に、長い長いネガ文化の歴史に対する反逆の情念をよみとりつつ、自らの根ざす文化の本来の姿が、このような情念によってゆがめられてとらえられてきたことを、反省の意味をこめて、確認せざるを得ないのである。(〓自分を見失い、ポジをもとめた無理〓)
▽86 鎌足・不比等父子。鎌足は大化改新によって律令国家の地ならしをし、不比等は、大宝律令の実質的な編纂責任をはたすと同時に、平城京遷都の推進力に。
…摂関政治の実現にいたって、政治的実権の天皇家から藤原家への移行があらわになる。
…8世紀前後の律令国家の成立は、政治的実権の天皇家から藤原家への移行の転機ととらえられる。
▽91 6世紀初頭の継体朝あがりから、政治の実権は、大伴、物部、蘇我のような諸豪族の手にうつり、聖徳太子から中大兄皇子をへて、天武・持統にきわまる皇権回復の試みも、天皇家をふくむ旧来の豪族たちの富と力の基盤をほりくずす律令制を確立させる方向に作用し、…律令制の推進力となった新興の藤原氏の実権掌握への動きを促進…
▽92 鎌足らが、律令の制定に力を入れたのは、「氏姓制度」とよばれる伝統的秩序にあぐらをかく名門豪族たちの基盤を崩壊させる新兵器として、活用しようとしたのではないか。
▽93 記紀によって、天皇家の権威をおしあげ、律令国家の権威を強化し、律令国家の実権掌握をねらう藤原家の権威を高めようとした。シンボルとしての権威を最大限活用。
▽112記紀のしあげは、平城遷都から不比等の死去(720)のあいだ。
記紀に方向づけをあたえたのは、藤原不比等ではないか。
▽162 その当時は、皇位継承における父子相承の原則は確立していなかった。当時まで支配的であった兄弟相承のルールにしたがえば候補者があるというのに、あえて父子相承をかかげて幼少の軽皇子(文武)をつけるというのは、無理をともなう措置であったにちがいない。
▽172 父子相承の皇位継承ルールを確立するため、天智の権威が借用され、歴史による権威づけも。…天孫降臨の場面や、神武以来の父子相承もそのためではないか。
▽180 大化改新から不比等の死まで。①天智・鎌足体制(天皇家と藤原家の橋梁体制のはじまり)、②持統体制(天皇家指導権発揮)、③不比等体制(律令政府の実権握った藤原家の指導権確立)
▽188 蘇我氏を打倒した大化改新。大臣・大連の制度をささえていた氏姓制度が廃止されて、律令制が導入され、新たな代行機関として太政官制度がつくられた。
…氏姓制度のもとでは藤原氏の前身である中臣氏は、大臣・大連のメンバーの資格をもつ家柄ではなかった



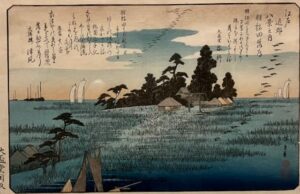
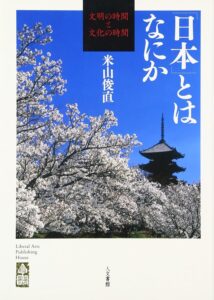

コメント