■集英社241231
超少子高齢社会の日本のどこに希望があるのかを、宗教哲学者と医療福祉制度を設計してきた医師が論じる。
長谷川は阪大医学部4回生のとき、心斎橋で「ロックンロール神話考」というミュージカルを見た。演じていた長髪ヒッピー男が鎌田だった。しばらく交渉がとぎれるが1998年、映画監督の大重潤一郞を通して出会い直す。
宗教と現代医療は水と油の関係にみえるけど、近代を懐疑的に見るヒッピー的感性と「ケア」というタームが議論をかみあわせる土台になっている。
長谷川は、「内科医なんかやっていたら世界革命に貢献できないよ」と言われて外科医になりアメリカに渡った。1984,5年ごろ、医療人類学や新しい公衆衛生を日本に紹介するオピニオンリーダーとして有名になり、厚生省にはいって医療福祉行政にたずさわる。
当時、大熊由紀子による「スウェーデンには寝たきり老人はいない」というレポートが脚光をあび、老人保健課課長補佐だった長谷川が「寝たきり老人ゼロ作戦」を先導した。
鎌田は、社会変革には、人間の根底にある思考や行動を変えるしかない。その源泉は神話にあると考えた。
日本の神は旧石器時代から、いろいろな神が合体・分離した「神神習合」だった。神道には天皇系とは別に、イザナミ・スサノオ・オオクニヌシ……大本へとつながる系譜がある。その「国つ神」の系譜を1975年から研究してきた。
オオクニヌシは稲作・養蚕・織物・製鉄・醸造などの生産系、それとコンビをくむスクナビコナは薬草や温泉などの医療系の役割をになう。オオクニヌシが因幡の白ウサギを助けた物語は、医療の発生という。
オオクニヌシが多くの名をもつのは、いくつもの神々の複合神だからだ。いろいろな部族が婚姻関係を結んで習合し、オオクニヌシの話を共有の物語としてきた。
そこには医療技術をもつ人も、歌う人もいた。スサノオの「八雲立つ 出雲八重垣……」は日本の歌のはじまりであり、スサノオは聖なる琴の所有者でもある。出雲は芸能の発祥地でもあった。医療的に癒やす行為と琴を弾きながら歌う行為は、出雲式ヒーリングのパフォーマーであるスサノオとオオクニヌシの特徴だった。
天皇家ファミリーと、オオクニヌシのファミリーという2つの系譜があることは、「縄文と弥生」「鎌倉と京」「神神習合」「神仏習合」と同様、日本文化のダイナミズムを生みだしてきた。それらは古代の民間医療、ケアの文化につながり、未来においても活かしうるという。
患者のQOLを高めるには、死を納得する死生観が必要だ。神道の祭りや寺の行事も、コミュニティの人たちの共有文化だからコミュニティの相互ケアを支えている。そうした神話的思考や物語的思考を展開していけば新たなセラピーになりうる。
「心のケア」という言葉が出てきたのは、阪神・淡路大震災のときだった。
2003年には厚労省が、地域で死ぬまで暮らすには、住まい・医療・介護・予防・生活支援が提供される仕組みが必要という発想から「地域包括ケアシステム」を提唱する。じょじょに「ケア」が重視されるようになってきた。
東日本大震災を契機に、公共空間において共同の宗教的ケアができる宗教者として「臨床宗教師」が誕生する。それまで宗教学は客観・中立を旨としてきたが、国立大にも臨床宗教師を育成する講座が立ちあがった。
過疎の進行とともに寺社は無住化がすすみ、心の安全装置としての機能を弱めてきた。地域コミュニティ維持のためにも、文化的・歴史的な資源である神社と寺を活用する必要がある。
地域の歴史、地理、経済などを住民が主体になって「地域風土記」にまとめ、それにもとづく公共的な政策を主導する地域コーディネーターを配置するべきだと鎌田は言う。「地域風土記」とはまさに時間軸と空間軸で地域をとらえなおす「地区診断」である。
医療の変革には、「どういうケア」をめざすかという目標と、「技術体系」「専門家育成」「組織と制度」のありかたをワンセットで構想する必要がある。そのためには基盤となる「生命観」「身体観」「世界観」がつくられなければならない。
50歳未満が全体の8割を占めていた1970年代までを「19世紀型」とすると、2050年以降は50歳未満が4割で定常化する「21世紀型」になる。19世紀型にもとづく近代国民国家モデルは終わっているのに制度も意識も「19世紀型」のままなのが現実との齟齬をきたしている。
たとえば若い人の急性期ケアは、今後10年か15年で半減する。そのぶん「ケアサイクル医療」にシフトしなければならない。
高齢者は複数の病気をかかえ、悪化と改善をくりかえしながら暮らしている。今後の医療のゴールは、個々の疾病の治癒ではなく、ADL(日常生活動作能)とQOL(生活の質)の向上であり、それに対応するシステムをつくらなければならない。
また現在の医療は、時間と技術を駆使して「異常死」に抗おうとするが、まもなく毎年170万人が死ぬようになる。「ごく普通の現象としての死」に対応するシステムにかわらなければならない。
そうした状況に対応する世界観や体系をつくりだせるのは、日本、韓国、中国という東アジアの国しかないと長谷川は考える。
日本では介護保険・医療保険のデータベースが充実していて、新しいADLの方向を予測し、ADL改善に有効な医療行為のありかたも見えてくる。どういう世話をすればADLとQOLを維持できるかという方向に医療とケアは変わらなければならない。
医学は、薬草や温熱療法、シャーマニズムの催眠療法などの「経験医学」にはじまり、紀元前1000年から500年くらいに、農業を背景として、「伝統医学」が登場する。そこでは生命エネルギーや体液のアンバランスを病因論とした。さらに伝統医学を否定して「近代医学」ができあがる。
この流れは宗教の変遷と軌を一にしている。伝統医学が成立する2500〜2000年前に世界宗教が生まれる。背景には都市型の文明社会の成立や文字の普及がある。薬草治療が体系的にできあがるのはインドも中国も2500年ぐらい前で、儒教、仏教という世界宗教の発生とほぼ同じ時期だった。
近代医学を支える西洋近代の思想は時間感覚を欠いている。
「近代医学」が失った時間感覚をとりもどし、ADLやQOLを重視するケアを実現するには、機械的な病気治療ではなく、経験医学や伝統医学にまなぶ必要がある。時間の補助線を引くことで近代医学の欠点を補う手法が「進化生態医学」だという。
また従来「高齢者福祉」が重視されてきたが、今後は「若者が生き生きと自己実現できる環境づくり」を優先し「高齢者こそが若者を支える必要がある」と言う。高齢者福祉を削れという意味ではない。「高齢者と若者が共に人生の発達をめざしチームとして支え合う社会システム」が超少子高齢社会のモデルになりうるという主張だ。
宗教も、各宗教の限界や、自分たちの地域の限界を認識したうえで、有機的にむすびつき、宗教をメタレベルで包括するような宗教をデザインしなければならない。その分野で日本が役割を果たせるとしたら、神話・儀礼・聖地をもつ宗教文化にもとづいた自然生態倫理と自然生態美意識だという。
鎌田は縄文の真脇遺跡を未来的ビジョンとして重視する。
ウッドサークル(環状木柱列)の外が金剛界、内が胎蔵界の「金胎不二」の構造であり、宇宙の声、生命の声を聴くパラボラアンテナになっているという。さらに、地震でも壊れない柔構造である縄文建築やコミュニティを見本として、ソリッドなシステムからの転換をはかるべきだという。
縄文の生活やコミュニティには、神や自然の声に耳をすますことが基盤にある。その象徴がウッドサークルである。そうした「声」をうけとめる柔構造に未来への希望を見ている。
医療もコミュニティも宗教も、機械的・分節的な近代思考を超えて、ケアの視点から巨視的に「全体」や「命」をうけとめる必要があるのだろう。
===========
▽12 1970年にはじめであう。
長谷川さんは阪大医学部4回生。心斎橋を歩いていたら「ロックンロール神話考」というミュージカルをやっていた。長髪のヘンな人たちがヒッピーのようなかっこうでミュージカルをやっている。
1,2回しか会っていないのに、鎌田さんの彼女といっしょにぼくの部屋に泊まってもらった。2人は駆け落ちだった。
……私が言う「天才」というのは、曼荼羅的に幅が広いということ。普通の人は、3つか4つのチャンネルが精いっぱいで、それ以上は興味がないとか理解ができないということになる。ところが天才の人たちはウインドーが四方八方にバンバン開いている。
▽17 日本の学生運動は、医学部の医局制度の改革からはじまった。
▽19 社会構造を変革するのは意味があると思うけれど、人間が変わらない限り社会は変わらない。。人間の根底を支えている思考、イマジネーションとアクション、行動を変えるしかない。それらがどこから来るかというと、神話から来る、というのが私の思想だった。思考や行動の根源は神話にあると思いこんでいるので……
▽21 真の父とは真の母とはなにかを探していくという現代からのベクトルと、いなくなった子どもたちを探すという神代からのベクトルが時空融合しながら立体交差しながらすれ違っていく。……シュルレアリスム的な夢の世界における、少年少女たちの幽界遍歴、異界遍歴。善財童子が53人の善知識と出会っていくというような。時空の間でイザナギ、イザナミとも出会っていくのだけれど最終的に、全員死に絶える。
▽25 70年の夏に出会って長谷川さんは大重潤一郞さんの「黒神」の映画上映を手伝った……
▽26 赤軍派だった後輩から「長谷川さん、内科医なんかやっていたら世界革命に貢献できないよ」と言われて、それで「分かりました」と、外科医になることを決めたんです。
……アメリカに行く前に船医を(3カ月)やっていた。発展途上国のいろんな国を若いときに経験できたんです。
▽32 レジデントは奴隷だと言われていた。朝6時から9時まで働いて土日がない。5年間。
▽41 「現代医学がベースにしているデカルトの機械論的な生体観・生命観は果たして医学には適していたのか」
▽42 人類未到の超少子高齢化デジタル社会に先頭を切って挑戦するわけですから、日本が人類のための実験国家です。トイレに行くときも、ごはんを食べるときも刻一刻これまでの人類が経験したことのない社会を、日本国民は一人ひとり実践研究していることになるのです。
▽59 1984,5年ごろ、アメリカ帰りの医療人類学や新しい公衆衛生にかかわる分箭のオピニオンリーダーであり紹介者として登場。
再会するのは1998年、大重さんを通して。
▽68 よく言われるのは、アメリカ人には肩こりが見られない、日本特有のものだ、と。……最近では欧米でもこる人がではじめているようですが……
▽79 手かざし療法 1970年代初頭に開発。……世界救世教の岡田茂吉は、1935年から手かざし療法(浄霊)をはじめ、真光教や神慈秀明会などはそれを継承している。
▽90 厚生省老人保健課でのぼくの最大の仕事は「寝たきり老人ゼロ作戦」。あの基本概念はぼくが企画してつくったんですよ。
……当時、大熊由紀子記者による「スウェーデンに行ってみると寝たきり老人はいないことに驚いた」……が出て、大騒ぎになった。厚生省として対応しないといけないということになって、、筆頭の課長補佐のぼくがその担当になったわけです。
▽92 スウェーデンでは、座って服を着替えてお話をしてごはんを食べてでないと人間ではない、物体にしかすぎないという人間観があるので、着替えさせて座らせるというわけです。「仮説というのは200字以内で立てなければ証明できない」 共通の単純な定義でデータを整理したことが良かった。マスコミ報道と科学の専門家のノウハウとエビデンスが合体した医療政策の好例だと思います。
▽104 宗教には、神話と儀礼と聖地という三大要素がありますが、聖地にあたるのが「鎮守の森」であり、神社です。戦後、その神社を整理・包括したのが神社本庁で、それを支える教育研究機関として国学院大学とか皇學館大学とか神道宗教学会とかがあった。
……1985年ごろ、国学院大学や神社本庁の100名前後にあてた怪文書がまかれた。……鎌田は共産党第5列である。鎌田の思想と研究は異教的・異端的なものである。鎌田に天誅をくだして国学院がから追放せよ、と。
……私がやっているのは……日本の神様は唯一神ではなく、いろいろな神様が自在に合体したり、分離したりする。そういうものをとりあえず「神」と呼んできた。これはおそらく縄文時代以前の旧石器時代からそう変わらないだろう。そういう「神神習合」感覚や思想がベースにあって、日本人の神話的思考やさまざまな習俗的な儀礼などをつくりあげてきた。……律令制になっても、神に対する根本の構造は変わらずに、今日までずっと来ている。……それが私の根本認識です。
……神仏習合以前に神神習合があった。いろいろな神が寄り集まって複合神をつくり、あるいはそれを解体して別のものにしたりという、かなり自由自在な習合的な思考ができあがっていた、と。
▽113 お遍路さんを身近に見ていた。お接待というのは、医療ではないけれど、まちがいなくホスピタリティですよね。病気をかかえる人も多く、お接待がその人たちにとってエンパワーメントする力になっているということは、感じるものがありました。
▽119 オオクニヌシのファミリーの元はスサノオです。……天皇家のファミリーの流れとは別のラインとして、イザナミ、スサノオ、オオクニヌシとつながる系譜を位置づけたい。その系譜の先には、近代に生まれた、出口なお、出口王仁三郎の大本がある。〓大本は追いやられて隠遁してしまった神(艮の金神=うしとらのこんじん)が維新後のどうしようもないどん詰まりの時代に復活してこの世の中をよくしていく、そういうビジョンを見たわけです。
……そういう国つ神系ファミリーの系譜が私のなかで課題としてあって、1975年に出雲大社と綾部の大本のみろく殿に参拝した。……龍笛を吹き、私はこれから出雲の神々の系譜、国つ神の神々の系譜の神道を研究していきますという誓いを立てたんです。
▽121 オオクニヌシとスクナビコナは医療の神様。浪速区に大国主神社、道修町には少彦名神社がある。オオクニヌシは稲作・養蚕・織物/製鉄・醸造などの生産系、スクナビコナは薬草や温泉などの医療系の役割分担で全国を巡った。
……「出雲国風土記」には風土記のなかでは一番たくさんの漢方薬の名前が出てきます。今もう一度、新しい国づくりのためにオオクニヌシとスクナビコナは必要なのでは!
オオクニヌシが因幡の白ウサギを助けたと言う物語は、医療の発生であり、医療のひとつのケアのかたちである。同時にオオクニヌシは、ガバナンスとして、戦争ではなく、和解でもない、国譲りという不思議な方策を編みだした。
……オオクニヌシは、古事記では、大穴牟遅、葦原色許男、八千矛、宇都志国玉神の4つ。日本書紀では大物主、大己貴、葦原醜男、八千矛、大国魂、顕国玉の6つの名がある。いくつも名前があるのは、それぞれに別の伝承があったということで、いくつもの神々が複合神として一つになったのがオオクニヌシという神様だと思います。いろいろな部族同士が婚姻関係を結んで習合しながら、オオクニヌシの話を共有の物語として支えていたわけです。
そこには医療技術をもつ人たちもいたでしょうし、歌を歌う人もいたでしょう。スサノオの「八雲立つ 出雲八重垣……」という歌は日本の歌のはじまりであり、スサノオは聖なる琴の所有者でもある。いろいろな意味で出雲は芸能の発祥地でもあるえあけです。つまり、医療的に人や動物を癒やす行為と琴を弾きながら歌を朗唱するという行為は、出雲式ヒーリングのコア・パフォーマーであるスサノオとオオクニヌシの二大特徴で、神道ソングライター&ガン遊詩人である私のアクションの原型はここにあります。
……天皇家中心のファミリーと、オオクニヌシを中心としたファミリーという2つがあることが重要なんです。縄文と弥生、鎌倉と京のようにふたつあることがもつ両義性、両面性、相互補完性、こういうもののなかに日本文化のダイナミズムがある。そのワンオブゼムとしての神神習合や神仏習合があり、そこに民間信仰も接着剤としてくっついている。それは同時に古代の医療、民間医療、ケアの文化、それら全部につながっていて、そういうものを未来においてもどこかで活かすことができるはずだという確信があった。「翁童論」ではその辺の思想的整理と解釈をしていったわけです。(〓〓未来へのヒント)
▽125 患者のQOLを定めるのはなにか、と問うていくと、その人の死生観が問われることになる。……死ぬときに、死にゆく自分自身のQOLというか、死についてのありようを自分なりに納得するにはその人の死生観が働く。……民間信仰によって救われる人もいるだろうし、宗教的な信仰や信念によって救われる人ももちろんいる。
▽127 「艮の金神」は鬼門の神だから鬼神でもある。だから大本では「鬼は内」という。
天河大辨財天 「鬼の宿」という特殊神事。鬼を迎える不思議な祭り。鬼を先祖として迎えて……。天河でも「鬼は内」ととなえて豆まきをする。……宮司は役行者に従う前鬼・後鬼の前鬼の子孫だといわれ、辨財天の少し上に鬼の岩屋がある。
▽133 カトリックの典礼も、神道の祭りも、何百年も続いている。積み重ねによるリアリティは半端ないものがある。それは同時にコミュニティの人たちの共有文化でまおるから、コミュニティの相互ケアを支えている。そうした神話的思考や物語的思考を演劇的空間で展開していけば、信じる信じないのレベルではなくて、新たなセラピーになるのではないか。(〓仁江の祭り)
……人類の最も古い治療法のシャーマニズムも一種のドラマ療法といえると思います。
……外に出られない子がアバターがあることによって救われているか……一種の遊びですが、遊びはセラピーになりうる。遊びというものは、自由であることを担保することもできる。自由であることは、患者のQOLを大切にするために絶対的に必要なプロセスであり……
▽139
▽142 医学教育 知識の量は昔は100倍、千倍。覚えるだけで疲れて、人間に興味をもたない医師をつくってしまう。そこで、要素知識をつなぐ方法として、新しい学問領域「進化生態医学」を構想しました。身体の各部分の関係、環境との関係をできるだけ俯瞰的につないで把握する視点です。
▽151 阪神大震災「神戸からの祈り 満月祭コンサート」喜納昌吉さんから電話。「鎌田さん、神戸で何かやろうよ。鎮まっていないと思うんだよ。亡くなった人も、生きている人も……神戸から神の戸を開こうよ」とアジる。
▽152 「縄文」「久髙オデッセイ」などを大重さんと一緒につくりました。……2015年に看取って、葬儀もアニミズム方式でフリーランス神主として司式しました。
▽153 私はオウム真理教の危険性を察知していました。
▽154 阪神・淡路大震災によって、日本列島改造計画ではなく、神話から発するところの日本の国生み、国づくりをどう再構築していくことができるのかという課題を自分が背負ってしまったと感じたところに、地下鉄サリン事件が起きて、宗教の再構築という課題も背負うことになった。
文化的にも信仰的にも、心の安全装置として働いてきたものが、今までのような安心・安全の装置たりえなくなってしまった。
……コミュニティの問題としても、もう1回宗教施設を問い直し、やりかえるという問題意識を強くもった。
……1998年に東京自由大学を立ちあげた。大重潤一郞さんや宮内勝典さんら10人の発起人を集め……
▽157 「心のケア」という言葉が出てきたのは、阪神・淡路のときで、京大の河合隼雄さんの臨床心理学の流れと、神戸大の中井久夫さんの精神医学の流れが大きな軸になっていた。……2003年には厚労省が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される仕組みが必要だということで、「地域包括ケアシステム」を提唱するなど、じょじょにケアの領域が社会問題として取り上げられるようになってきた。
▽158 東日本大震災 共同葬儀をしなければならない。公共空間において共同の宗教的ケアができる宗教者が必要だということで「臨床宗教師」という新たな日本的チャプレンができてくる。……どの宗派かわからない人のために、教団・宗派を超えて、共有できる普遍性をもった形の宗教的ケアとか傾聴そかスピリチュアルケアをやっていこうという形ででてきた。
……それまで宗教学というのは、客観・中立を旨として、特に国立大学法人だったら、特定の一宗一派に偏ってはいけない。ところが東日本大震災を契機として、超宗教的な特定集団の枠組みを超えた形での臨床宗教師を育成する講座が立ちあがった。東北大・上智大・龍谷大などが協力関係をむすんで、日本臨床宗教士会という資格を授与できる団体が2016年に発足。
▽160 日本には8万の神社と7万5000の寺がある。開業医の数はかつては7.8万で一定だった。2020年は10万カ所に増えている。……7万8万というのはマジックナンバーで、かつての日本には酒蔵がそのくらいの数あった。人が歩いていける距離には必ず酒蔵があった。生酒だったので、直接買いに行ける範囲に造り酒屋が必要だったのです。
いまコンビニが6万弱というから、コミュニティを営んでいく上で5〜8万というのは重要な数値になるわけですね。
▽ 宮司も僧侶も食っていけず、いくつもの神社・寺を兼務することになる。兼務が増えると、本当に必要なケアとか、地域の人たちとのやりとりがどんどん手薄になって中身が空洞化してしまう。
だから、地方コミュニティを維持するためには、文化的・歴史的資源としての有用なリソースとして神社と寺をうまく活用しなければいけない。神社や寺を地域で公共化する形をどうつくっていくか。
そのときに、……どのようなライフスタイルとデザインがあれば使命感をもって宮司・僧侶という職業が成り立つことが可能なのか、そのモデルをつくっていかなければならない。
▽163 神社境内をヘリポートにつかおうという案も。
集落そのものの看取りをどうするかという課題。鹿児島県の肝付町の能勢佳子さんという保健師「私は集落の看取りをやってるんです」 町内130集落のうち33が限界集落。
▽164 能勢さんは、集落同士の間をとりもってお見合いをしているそうです。……何百年もの歴史や文化をもつ平家の落人集落もあって、どう記録を残すかが大きな挑戦と言っておられました。……保健師さんはいわば「地域の師」であって、地域の師を各地域にどう位置づけていくのかは重要な課題だなと。
▽166 「地域風土記」をみんなでつくるべき。自分たちの地域についての歴史、地理、経済などを地域が主体になって記した新しい風土記をつくらなければならない。それにもとづいた公共的な政策を主導できる地域コーディネーターを配分すべきだと提案・要請した。コーディネーターのなかに、臨床宗教師も含め宗教、医療、芸術などいろいろな分野の人を取り込んでいく。それでも消滅を免れない地域も出てくるだろうけれど、その際にはそうした地域同士が互いにやわらかに溶け込んでいく、地域結婚みたいなやりかたのなかで地域同士を再結合していくような新しい結びつきかたをつくっていかなくてはいけない。
▽コンパクトシティ政策 富山市がしっかりしていくとまわりの地域も活性化される構造に。
砺波市の佐藤伸彦さん「ものがたり診療所」
患者一人ひとりがもつその人の「ものがたり」を中心に医療を組みたてていく。
地域で最後まで暮らせるように、医療や介護を生活の場でも受けることができる施設としてた立ちあげた。現在は秋田県由利本荘市、北海道当別町、鹿児島県伊仙町、沖縄県宮古島市や南城市でも同様の取り組みがある。
▽169 レイチェル・カーソン、石牟礼道子らは予言者の系譜。これから先におこってくるさまざまな予兆をキャッチする。彼らには滅亡の声や世界が崩壊する音が聞こえている。
▽170 1960年代のアメリカ西海岸は、欧州やアジアから多くの人が集まり……世界観、ライフスタイルを変えて行かざるをえない……そうした流れに一番敏感だったのが詩人、ギンズバーグらのピートニクの詩人。それがヒッピームーブメントになっていく。……大きな文化潮流がニューエイジ。
「近代が終わりつつある今、近代の裂け目が見えている人たちにその裂け目から見えているものを聞いてまわっている」
▽172 医療はシステムなので、……医療だけではなく、具体的に一人ひとりのケアの問題まで落とし込まないといけない。その目標にむけて、具体的に「どういうケア」をすべきか、それを支える「技術の体系」「専門家の育成」、それを運営する「組織と制度」、さらにはそのための「基礎医学や基礎科学」をどうすべきか……それらすべてをワンセットにつくる必要がある。
そのためにはそれを支える「生命観」「身体観」、「世界観」をきちっとつくらなければならない。こうした土台まで含めた問題を世界に提起できるのは、日本しかないとぼくは確信しています。
▽173 1970年代までは50歳未満が全体の80〜85%を占め一定でした。これを「19世紀型」とすると、2050年以降は50歳未満が40%くらいにまで減少して定常化する「21世紀型」に移行していく。現在はその過渡期。
19世紀型人口にもとづいて近代国民国家がつくられたが、そのモデルは明らかに終わっている。なのに制度も意識も「19世紀型」で残っている。
たとえば若い人の急性期ケアは、今後10年か15年ぐらいでほぼ半減する。その分ケアサイクル医療のほうに提供体制をシフトしなければいけない。
……死者のボリュームが増え、毎年170万人もの人が死ぬ。之を上まわったのは、スペイン風邪が蔓延した1918〜21と第二次大戦中だけです。
死ぬというのはごく普通の現象へと変わっていく。
……現在の医療のメニューは、異常死をなんとかしようとさんざん時間と技術を駆使して抗おうとするのだけど、結局は本人も家族も社会もアンハッピーになるという構造になっている。もっと死というものは普通であることを受け止めましょうと。医療界は押し売り産業なので、普通死をリストに入れないとクライアントは異常死を無理やり押し売りされる。
▽179 高齢者は複数の病気を同時に抱え、悪化と改善をくりかえしながら生活するのが常態となり、病院で完治することは期待できない。今後の医療のゴールは、悪い部分の除去ではなくむしろ、ADL(日常生活動作能)とQOL(生活の質)を高めていくところにあって、新たなゴールへ向けてケアもシステムも変わって行かなければならないのだけど、この新たな体系ができていない。体系をつくれるとしたら日本、韓国、中国という東アジアの国しかありえない。大東亜共老圏としての課題です。
日本では介護保険・医療保険のDBが充実していて、AIをつかえば、新しいADLの方向を予測することができる。医療保険のデータと組み合わせれば、一番ADL改善に有効な医療行為も抽出できる。
▽182 ……ケアのゴールの優先順位は、疾病の治癒よりADL改善となる。……どういうふうに世話すればADLが保たれ、かつQOLを上げることができるかという方向にケアは変わっていかなければならない。
……21世紀の医療の一番のコアは、人口遷移とケアサイクルを支援できるような医療システムで、現在の医療システムをどう脱構築し再構築するかということ。
……超少子超高齢社会の未来ビジョンということでいえば、日本、韓国、中国という東アジアの3国が、ここ数十年の帰趨を体現してしまわざるをえない。
▽184 長谷川さんのいう新しい医療システムへの転換をはかるには、そうした意識転換を図る新たな宗教のフレームが絶対に必要になってくる。宗教自身もまた、地球全体のなかから見通す視点をもたなければならない。……メタレベルの宗教の包括的な見方をつくらなくてはいけない。
▽186 近代医学はデカルトの心身二元論に基づく機械的身体観。西洋近代の概念では時間感覚を欠く傾向にある.現在の身体理解には、時間の補助線を引く必要があります。その基本となる手法が進化生態医学です。進化という時間の補助線をひく……
▽187 真脇遺跡を未来的ビジョンとして重視するのはウッドサークルの内と外の世界観が明確に分かれていて、密教でいう胎蔵界と金剛界のように相互浸透的な「不二」の構造になっている。……宇宙の声、生命の声を聴くパラボラアンテナで、外側が金剛界、内側が胎蔵界の「金胎不二」の構造になっている。
これからの社会のモデルは従来のソリッドなものではなく、この遺跡の建築学的構造、つまり能登半島地震でもまったく倒壊することのない柔構造のようなくらげのようにしぶとく生きられるようなモデルでなければいけない。〓
▽189 石破の「防災省」は正しかった。長い時間かけて蓄積したものをすべて結集できるような防災省という組織がかならず必要になる。今後起きることは首相直轄の緊急対応といった付け焼き刃でできるはずがない。……地球防災全体を考える機関が必要だ。
▽190 介護保険は、福祉増進のためということで通したけど、厚労省幹部の考え方は、医療費削減だった。その背戸設計においては医療と介護をなるべく離そうとした。……最近反省されていて、やはり医療と介護をはっきりわけるべきではなかった、と。医療と介護が連携しながら全体構造を支えていかなくてはいけないことが、介護保険をやってみたわかった
。 2005年の介護保険法改正で「地域包括システム」という言葉が使われた。2011年のさらなる回生で条文に「自治体が地域包括ケアシステム推進の義務を担う」と明記された。
▽196 経験医学→伝統医学→近代医学
実践的な知識による薬草とか温熱養蜂、シャーマニズムによる催眠療法。
紀元前1000年から500年くらいにいわゆる伝統医療が登場スル。生命エネルギーあるいは体液のアンバランスを病因論として、東洋と西洋で共通している。その背景には農業があると思うのだけど。
伝統医学を否定したところで、近代医学ができあがってくる。
▽199 世界宗教がでてくるのが2500〜2000年前、つまり伝統医学の成立のときです。背景には都市型の社会、文明社会ができたことがある。文字の誕生と普及も大きい。
それ以前の口承伝承型のものは、シャーマニズムも呪術医療、マジカルメディスンがベーシックにあって、薬草治療が体系的にできあがるのはインド医学も中国医学も2500年ぐらい前で、儒教、仏教という世界宗教の発生と並行している。
近代において宗教は世俗化する
▽200 それぞれの宗教の限界、自分たちの地域の限界を超え、有機的にむすびついていかないといけない。……各地域のリージョナルな限界状況と自分自身の能力やネットワークを含む限界状況を自己認識した上で、それをどのように活性化できるか、再生するためのコーディネートは何なのかを協働的にデザインしなければ……
▽204政策の優先順位が高齢者の課題に片寄りすぎたのでは。……気がついてみたら若者はずっと低賃金、非正規雇用で置いてきぼり。これでは少子化はとまらない。・・・優先すべきはあきらかに「若者が生き生きと自己実現できる環境づくり」です。高齢者こそが若者を支える必要があります。
……高齢者と若者が共に人生の発達をめざしチームとして支え合う社会システムを構築することが、超少子高齢社会の新しいモデルではないか。それを高齢社会先進国の日本から発信することが、世界から期待されています。
▽日本がもし役割を果たすことができるならば、神話・儀礼・聖地をもつ宗教文化にもとづいた自然生態倫理と自然生態美意識だと思います。。生体智的美的倫理というのは、自然界の仕組みの整え方に沿っているのですが、もともと自然そのものがたとえようもなく美しいんです。


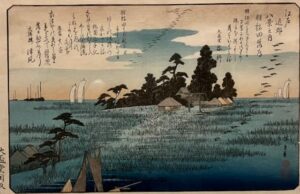
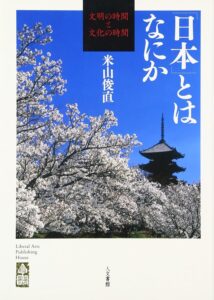

コメント