創風社出版 20050307
博物館学芸員が、自らの出身地の愛媛県八幡浜市周辺の民俗文化について地元紙に掲載した記事をまとめた。
自分が育った土地に伝わるなにげない習慣・文化が、民俗学の世界では、全国的な事例として取り上げられていた。「外の目」を通して郷土の民俗の価値に気づかされ、「八幡浜人」としての誇りをもてたという。
昔から伝えられてきた伝承知としての民俗文化は、今この瞬間にも失われている。
たとえば後産を寺の裏山に埋める、という処理の仕方は、昭和50年ごろまで残っていた。「初詣」が盛んになったのも、旧暦が日常生活から消えた昭和40年前後からだという。
いま記録しなければ、失われていく民衆の知恵を収集するのは、ノスタルジックな志向によるものではない。その土地に生きてきた民衆の知恵を伝承し、「外 の目」で客観視し、その知恵から学ぶことが、「個」に分断されて不安の海にただよう現代社会を生き抜く知恵にもつながるのではないか、との問題意識が貫か れている。 ------------------
▽筆者は病院出産だったが、後産は寺の裏山の墓地近くに埋めた。病院出産であっても、昭和50年ごろまで後産処理の習俗が残っていた。
▽祭りや盆踊りは、男女が恋仲になるきっかけだった。若衆たちが気に入った娘を待ち伏せして誘拐する。娘もひそかに期待していた。親や娘は、青年たちに 相手にしてもらえなくなると、酒を贈り「まともな女にしてやってください」と頭をさげた。だがこの習慣は、警察が目を光らせるようになって次第にすたれ た。……明治10年には、県が盆踊りの規制をしている。
▽青年団は、学習活動や夜警、軍人支援などを目的にして日露戦争後に町村を単位として結成された。国から強要されて組織されたという側面があった。だが多くは、従来存在した若者組の活動機構や役割を引き継いだ。
▽「死」という言葉をさけ、「逝去」「永眠」という。八幡浜などでは「別府の湯に入りに行った」「ヒロシマに鍋を買いに行った」「ヒロシマに行く」と言 う。「ヒロシマ」は、西日本各地に見られる。宮島は厳島神社の鎮座する神の島でケガレを極端に忌み嫌う島。島内には墓地はなく、現在でも本土対岸の赤崎に 埋葬される。かつては服喪が明けるまで島に帰れなかった。宮島ではその風習がもとになって「広島に行った」というようになったという。その後の厳島信仰の 広がりとともに各地に伝播した。「別府に行く」や西海町の「大阪にいく」は「広島へ行く」の変化系と言える。
▽戦没者の墓標(p36)
▽八幡浜地方で正月が旧から新に完全に移行したのは昭和30年代に入ってから。旧暦によって営まれていた農業、漁業などの生活慣習が、高度成長をとげて都市の慣習へ移行したことを物語る。
松山の椿神社でも、かつては初詣客は極端に少なく、昭和40年ごろから急激に増え始めた。旧暦重視の正月が新暦重視へと移行したのに加え、同時期にテレビで頻繁に全国の初詣の様子が流され始めたことにより国民行動が均一化した。
▽正月15日前後の早朝、正月飾りを燃やす「どんど焼き」。
▽真穴の座敷雛 少子化で座敷雛を出す家がヘリ、一時存続の危機に。行事をする地域が校区全体に広がり、長女の誕生した家だけだったのが県外在住者に長 女が生まれた場合でも、実家で座敷雛をおこなうまでになった。対象者を拡大することで存続を可能とした。観光行事化して、マスコミに取り上げられること で、観光役を意識したものへと変化した。これによって、住民は独自の文化に誇りを持ち、地域アイデンティティを確立する契機となった。
▽冬至の民俗 太陽の活力が最も減退するため、健康の再生・回復を願う民俗行事が見られる。ゆず湯、お大師講……。西洋のクリスマスが25日に定着した のも、冬至の習俗が基礎になっているといわれる。イスラムのラマダンも、太陽の陰る季節に断食と饗宴を繰り返し、新たな生命を付与させようとする。古今東 西の共通点になっている。
▽牛鬼はかつて丸型を基調としたが、宇和島型へと発展し、喜多郡や上浮穴郡では、伝播する際に鬼の要素が解消されて、牛に近い表情となったのだろう。分布の周辺部にいけば古態の型の牛鬼が見られるという傾向がある。
▽らい病の伝説 感染力がきわめて弱いライ病が業病とされた背景には、仏教思想が関与している。「法華経」はらい病について、法華経を受持するものを軽笑したりしたら、「この人は現世に白ライの病を得ん」という記述がある。
▽埋蔵金伝説 古代末期から中世にかけて流通したのは、中央に四角孔のある銭であり、中国文化の模倣的要素が強い。だが、大判・小判は日本独自。米俵の 形で、藁のような筋目を付けており、稲を連想させる黄金色をしている。米を象徴するからこそ、我々のイメージに定着しやすかった。
▽よもだ 言わなくていいことを言ってしまう者、筋道のはずれたことを言う者、行う者。四方山話というように、「いろんな」という意味が転化して派生した独特の方言なのだろう。
▽だんだん 県内では「ありがとう」を意味する。西日本各地にある。なかには「ありがとう」ではなく「いろいろ、重ね重ね」という意味の地域もある。そ ういう地域では「だんだんありがとう」と言う。これが省略されて、愛媛の「だんだん」ができたものと思われる。「だんだんありがとう」は、江戸中期の京都 の遊里にはじまった挨拶語。だが、近畿では「だんだん」は廃れている。上方で使われた言葉が周囲に伝播し、上方では、新しい言葉が創出されて古い言葉は使 われなくなる。
▽カボチャは「カンボジア(産の野菜)」がなまったもの。ナンキンというのは「南京瓜」の省略形。宮崎の一部では「ナンバン」、高知県の沖之島では「チョウセン」、関東では唐茄、ロスン(ルソン)と呼ばれるところも。
▽大黒山吉蔵寺 幻の四国霊場〓野本吉兵衛の正体は?〓
▽へち(辺地)、へんど 「辺土」は、現在でも遍路の別称として残っているが、「遍路」がなまって「辺土」になったのではなく、その反対だった。平安時 代に四国遍路の原型が成立した際の言葉が今でも用いられていると言える。霊場を結ぶ遍路道はいまだ成立しておらず、僧侶たちは「地」を修行の場としていた ため「辺土」と呼ばれていたが、中世以降、遍路道が存在するようになると、その「路」を歩く人々を「遍路」と表現するようになったと思われる。
▽忘れられた遍路道 歩き遍路が多かった昭和20年代以前は、八幡浜には、九州からの遍路のために、遍路宿があり遍路衣装一式をそろえられる店もあった。
野村町の惣川には「へんどくえお堂」(遍路供養)がある。南予地方の山間部の人が遍路に旅立つ場合、惣川から河辺村北平をへて、小田町を通る通常の遍路 道に合流したという。南予山間部にある茶堂では、大師の命日にあたる3月21日に、遍路さんや旅人に茶、米、金などの接待が行われていた。札所のない地域 にも、遍路道は存在し、お接待という文化も息づいていた。
▽御霊信仰(怨霊)は、愛媛県南予に多いことを柳田国男は指摘している。金剛院を「金剛さま」、和霊神社を「和霊さま」、「八幡さま」……と「さま」をつける。一方、松山地方では「椿さん」と「さん」付け。
南予は、御霊信仰が根強いなど、神が未だ荒ぶる存在として認識されており、なれなれしく「さん」付けできず、「さま」と呼んで畏敬の念を抱いているとみ ることができる。神輿の担ぎ方も、中予では、激しく揺さぶったり鉢合わせしたりする。神は普段は寂然とした存在である。南予では、未だ若々しい不安定な存 在であるという認識があるため、神輿は静かに厳かに担がれる。激しく神輿をふったりすると、ようやく鎮めた祟りが再発しかねないという無意識の心意がある のではないか。
▽鮫を食べる文化をもつ地域 伊勢地方と広島山間部、愛媛南予。伊勢では、安産で生命力が強いことから鮫は神饌とされた。南予でも、フカの湯ざらしはハ レの食事だ。臭みの正体はアンモニア。これがあることで防腐効果があって長持ちするため、全国的には山間部で好まれる傾向がある。広島の山間部の江の川水 系では「わに」と呼び、郷土料理になっている。
▽サツマ 南予だけでなく東予の海岸部や久万町にもある。ただ、久万町では、ウグイやアメノウオといった川魚を用いている。
▽東中南予というわけかたも、最近になってできた。かつて松山周辺が北予と呼ばれていた。大正3年には「中豫新聞」が内子町にあり、昭和2年には「中豫民報」は長浜周辺の新聞だった。



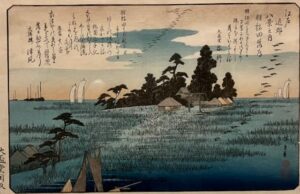
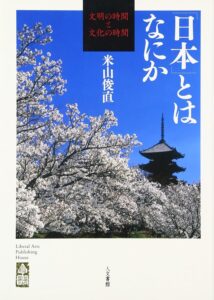

コメント