集英社 200503
市の広報に「町づくりの一環でとなり町との戦争をします」という主旨の記事がのる。詳細なプランは、コンサルタント会社が作成したという。
戦争が始まるというその日、となり町に通勤している主人公は緊張しながら車を走らすが、これといった変化はない。その後も特に変化がないまま時はすぎる。発行される広報に時折、「死者5名」といった記事が載るくらいだ。
市役所に呼ばれ、職員の女性「香西さん」と偽装結婚し、となり町のアパートにスパイとして住まうよう指示される。
スパイといっても、ふだん見聞きしたことを報告するだけだ。
だがある日、となり町の公安?が部屋を調べに入るという情報が入る。主人公は、旧知の花屋に助けられて夜間、自分の町に逃亡する。段ボール箱に詰められて車の荷台に載せられ、ゴミ焼却場とおぼしき場所で傍らにあったやわらかな荷物はドスンとおろされ……。だが実はその荷物は、戦死者だった。しかも香西さんの弟だった。助けてくれた花屋は主人公を逃がした直後に殺されていた。
そんなことがあったあとも、特に町全体が変化するわけではなく、淡々と月日はすぎ、そして戦争は終わる。
そう、戦争とはそんなものなのだ。大部分の人にとっては、普通の日常が流れ、身内が殺されたり自らがけがをしたりした者だけが、「戦争」のリアリティを実感しているのだ。
大戦中に書かれた清沢冽の「暗黒日記」にもそんな様子が記されている。南方で中国で、凄惨な殺し合いをしているとき、彼は、戦争に反対したいと内心では思いつつも軽井沢でゴルフをしていた。戦没者の家族は悲惨だったが、大部分の人たちは食料不足は感じながらも「日常」をすごしていた。「戦争」を実感するのは自分の身近に爆弾が落ちてきたときだった。
反戦運動が「戦争は悲惨だ」というイメージだけを増幅してきたことは、ある意味で間違いだったのかもしれない。
目次





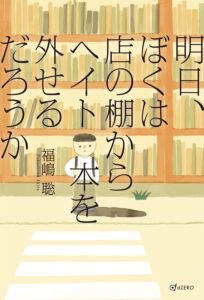
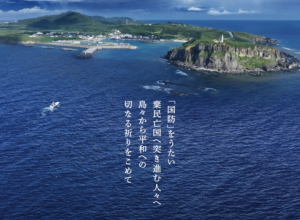

コメント