■今よりマシな日本社会をどう作れるか 経済学者の視野から<塩沢由典>SURE 20131007
1970年代にインフレと不況が併存したことが、ケインズから、反ケインズの新自由主義(neoliberalism)への転換の契機になった。
世界大恐慌のとき、米国は銀行と証券を分離するグラス=スティーガル法をつくり、銀行を公的な存在と位置づけて利益追求を制限した。その法律を1999年につぶすことで金融ビックバンが起きてアメリカやイギリスはうるおった。
だが2008年にリーマンショックが起こり、長い間無視されてきたケインズ流の財政政策が見直され、各国が大規模な財政政策に踏み切った。--
対談形式で世界の経済政策の流れがおおざっぱに理解できる。
アベノミクスは、利子率を重視するリフレ派のクルーグマンが唱える金融緩和と、旧ケインズ派の「大胆な財政出動」、新自由主義的な規制緩和を中心とする「成長戦略」という三つの潮流のごちゃまぜ経済政策だという。「大胆な金融緩和」は、ほかに利益が上がる使い道がなくて現状でも日銀当座預金残高がふくれあがっているため、効果は薄いと見る。
ではどんな経済政策を採るべきなのか。
日本経済はデフレだから停滞しているのではなく、物価は安定しているが有効な需要が伸びないために停滞していると筆者は分析する。そこに必要なのは、新しい種類と質のサービスの拡大だ。介護保険が介護需要を高めたように、医療や保育や教育の制度設計が重要な鍵をにぎるという。サービス産業は輸出入から比較的切り離されており、自立した経済をつくりやすいというメリットもあるという。
また、「トヨタ生産方式」がアメリカの研究者によって体系化され、日本生まれの品質管理システムを「シックス・シグマ」としてアメリカで理論化されたことをあげて、「新しい概念体系をつくるには、博士論文を書くような過程が必要だが、日本では大学院教育は軽視されている」と指摘。「高学歴ワーキングプア」が生まれる現状を「日本の大学院教育は潜在的な需要は非常に大きいが、まだ芽が出ていない段階」と位置づけている。
=============
▽11 新自由主義(neoliberalism) 一九七〇年代にインフレと不況が同時に併存した時代があった。これがケインズから反ケインズへの転換の契機になった。それから30年、08年にリーマンショックが起こり、長い間無視されてきた財政政策が見直されて、各国が大規模な財政政策に踏み切った。
▽12 アベノミクス 巨大な補正予算。短期間では細かな予算など立てられないから、建設関係になりやすい。とくに補正予算ではそうなりやすい。
アベノミクスは、経済政策の「ミックス」になっている。金融緩和はクルーグマンが唱えていることで、リフレ派。利子率を重視する。「大胆な財政出動」は、旧ケインズ政策。3つめの「成長戦略」は竹中平蔵が「規制緩和」と言う。これは「新自由主義」
▽23 2012年12月に、日銀当座預金残高は、法定準備預金額の5倍の43兆円以上あった。ほかに利益が上がる使い道がないから。インフレになって(お金を増やせば)景気がよくなるとは言えない。…日本で余っている金は、ニューヨーク市場で使われた。
▽26 日本はデフレだから経済が停滞しているのではない。物価は安定しているが、有効な需要が伸びないために長期に停滞している。
▽27 90年代まで、日本の有業人口にしめる建設業の就業者は9パーセントいた。ヨーロッパなどでは4.5パーセントぐらいが普通。
▽28 規制は理由があって生まれたものだが、規制というのはすぐに過剰になる。日本は一般的に規律密度がとても高い。それを下げる努力は必要。
▽30 1999年に、銀行と証券を分離するグラス=スティーガル法をつぶし、金融ビックバンに。金融派生商品が次々に生まれ、アメリカやイギリスはうるおった。
▽34 アルゼンチンは戦争前、1人あたりのGDPが世界で五本の指に入る国だった。長期間のポピュリズムの弊害で、高度のインフレがつづいて衰退した。
▽38 需要が伸びない原因。すぐに買いたいものがないという需要飽和。将来不安による貯蓄。長時間労働で使う時間がない。
▽48 2000年代の「戦後最長の好景気」。成長のほとんどは輸出が支えていた。輸出依存型の経済成長。
▽56 リーマンショックのとき、リーマンよりももっと大きな会社が実質的に倒産していた。AIG。米政府が救済した。
▽65 日本で必要なのは、物の生産と消費を増やす成長ではない。新しい種類と質のサービスの拡大。「サービス経済化」を提唱。
▽71 日本の農業生産性は非常に大きく向上した。60パーセントの人が農業に従事して食べさせていたのが、3パーセントでそれが可能になった。
▽87「トヨタ生産方式」はアメリカの研究者によって体系化された。品質管理の「シックス・シグマ」も、日本で実現していたものをアメリカで理論化した。新しい概念体系をつくるには、博士論文を書くような過程が必要だが、日本では大学院教育は軽視されている。「高学歴ワーキングプア」が生まれ、優秀な学生は大学院に行かないという事態を生み出した。日本の大学院教育は潜在的な需要は非常に大きいが、まだ芽が出ていない段階。
▽89 ポストイットは、無料で配布して使ってもらうことで需要がほりおこされた。潜在需要を掘り起こすには、医療も介護も保育も教育も、制度設計が重要な鍵をにぎる。
▽93 スウェーデンは、大学が生涯教育型になっている。30代50代の人が普通にいく。
▽115 サービス産業は輸出入から比較的切り離されている。海外の状況に振り回されない、自立した経済をつくりやすい。国内経済の安定化のためには、サービス化をすすめたほうがよい。
▽118 労組は世界的に弱くなった。日本でインフレが起こらなくなったのは、労組がおとなしくなったおかげでもある。春闘をやって賃金を上げるというのは、経済全体にとってもよい役割を果たしていた。それがなくなり、株主の力だけ強くなると、今の状態に陥りかねなかったし、高度成長もストップしたかもしれない。
▽125 貿易は、長期的には相互に利益がある。自由化とか関税撤廃のスピードはあまり急激にしない、しかし、無期限に引き延ばしもしない。適当な移行措置を取るということが大切になる。(経済学者の視点)
▽140 広域がれき処理 地元に簡易焼却場でも設営して、雇用がつくられたほうがよい。1トン1万円たらずでやってきたゴミ処理を、何十倍の費用をかけてやることに、どういう意味があるか。
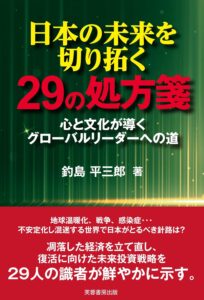

コメント