■「分かち合い」の経済学 <神野直彦>岩波新書 20141218
スウェーデン語の「オムソーリ」。悲しみの分かち合い、という意味。競争一辺倒ではない「分かち合い」の経済をめざす。「ラーゴム」はほどほどという意味。極端に貧しいことも、極端に豊かなことも嫌悪するスウェーデン人が求める重要な価値。
経済史を踏まえ、
パックスブリタニカは軽工業による自由主義。
それが第一次大戦で失敗し、金本位制はダメに。恐慌への対策として、ファシズムや社会主義、ニューディールが生まれる。ブロック経済化して失敗する。
大戦後は重化学工業が主流に。戦時中の中央集権体制を活用してインフラを整備する。国内資本の統制で累進課税と高率な法人税をかけることで、所得再分配を果たす。それが購買力をつくった。ケインズ。
ところが、生産性が伸び悩むと、資源が相対的に高くなる。それが石油ショックとしてあらわれる。スタグフレーションが起きる。再分配が困難になる。変動相場制では資本の統制ができない。新自由主義が幅をきかすようになる。
格差が生まれ、そこでは社会統合が崩れる。治安が悪くなる。国家権力が強まる。
政府を最小限にすればよいというが、実はコストがかかっている。
どんな体制がよいのか。「知識集約型」になると見る。
そこでの再分配のあり方は、パックスアメリカーナ時代の現金によるものではなく、スウェーデンのような現物給付による分配が必要だという。
どんな社会に
福祉のありかたも、現金給付では〓で格差をつくってしまう。現物給付にすることで〓になる。
財政赤字も〓〓が原因。
▽5
2002年から長期にわたる「いざなぎを越える景気」を経験する。にもかかわらず、労働賃金は低下しつづけ、「生活が苦しい」と答える国民は増加の一途をたどった。これは、労働市場への規制緩和が影響している。
▽12 パットナムが明らかにした「社会資本」(人間の絆)という概念。南イタリアの経済が停滞しているのに対し、北イタリアには人間の信頼の絆としての社会資本が強固に存在しているからだと分析したのである。…パットナムは、不安定就業の増加が、社会資本を著しく衰退させていくことを指摘している。
▽15 スウェーデン人は、週末には、田園にもどる。書を読み、大地を耕して、自然に抱かれて時を過ごす。…ストックホルム市は、市の面積の2倍にあたる面積を所有している。市域の7割が公有地であり、居住地として提供される。市域外に所有する広大な土地は、別荘地として賃貸されている。(菜園家族の発想〓)
▽21 「分かち合いの経済」が存在しなければ人間は生存できない。幼児が生存できるのはそれが存在するから。
▽23 新自由主義も、市場経済を機能させるには物理的暴力の存在が必要不可欠なことを十分に認識した上で、正当化された暴力を独占している政治システムが暴力によって、社会秩序を維持することを当然の前提としている。
新自由主義者の推奨する「分かち合いの経済」とは、あくまでも貨幣を使用しない「分かち合い」なのである。貨幣の必要のない無償労働による「分かち合い」でしかない。もうひとつの「分かち合いの経済」である財政によって「悲しみを分かち合う」という発想は、そこにはない。
▽29 人間の歴史はより人間的に人間が投企していく過程。(実存)
▽32 市場社会は「経済」「政治」「社会」という3つのサブシステムが、財政を結節点として結びついていると財政学ではとらえている。
▽35 (イギリスを覇権国とする世界経済秩序は、軽工業を基軸とする産業構造を基盤としていた。財政は「小さな政府」)第一次大戦後、パックスブリタニカを再建しようとする。金本位制への復帰が目指される。緊縮財政が強制される。その結果、1929年のNY株式市場大暴落を引き金とした世界恐慌が起きた。第一次大戦前からはじまる「パックスブリタニカ」の解体過程が終焉を告げる晩鐘だった。
▽37 世界恐慌からの復帰は、悲惨な総力戦の遂行とともに実現した。ファシズムも社会主義もニューディールも、社会を崩す「悪魔の碾き臼」である市場経済からの「社会防衛」であり「社会反動」。その結果、ブロック経済化が進み、破局を迎える。自分さえよければと、他国の経済状況を悪化するような政策を採用したからだ。
▽39 パクスアメリカーナ 「パックスブリタニカ」のように「金本位制と自由貿易を軸とする自由主義」ではなく「国内における市場介入(所得再分配)を前提」とした国際主義。
重化学工業が基盤。大量生産・大量消費を支える前提条件として、交通網やエネルギー網という社会的インフラが要求される。つまり、大戦中に形成された中央集権的国民国家が、重化学工業を基盤とする産業構造の発展を支えた。
…戦時経済の資本統制と絡み合いながら、資本所得への課税は強化される。高率の法人税と所得税の累進性。戦時税制の遺産を継承してスタートした。
…財政による所得再分配を強めることは、耐久消費財の需要を高めるだけでなく、市場経済が引き起こす社会不安をも安定させると考えられた。
…ブレトン・ウッズ体制とは、所得再分配国家を機能させるために、資本統制の権限を国民国家に認め、固定為替相場制のもとに自由な国際貿易との両立を意図した。
▽46 パックスアメリカーナの解体は1973年を象徴の年としてはじまる。
チリの「9.11」。アメリカが覇権国として君臨する際に掲げた「民主主義」の旗印を、アメリカ自身が野蛮な暴力によって引き裂いた事件。
石油ショック。重化学工業は、自然資源多消費型産業。多く消費すれば資源価格は上昇する。そうした相対的上昇を絶えざる技術革新が抑制していた。ところが技術革新が停滞すれば、資源価格は相対的に上昇する。それが中東戦争を契機に爆発したのが石油ショック(そういう位置づけだったのか〓)
▽51 石油ショックは、所得再分配国家=福祉国家を支えた重化学工業による経済成長という前提条件の喪失にほかならない。固定為替相場制から変動為替相場制への移行は、福祉国家の所得再分配を可能にする条件である「ブレトン・ウッズ体制」の資本統制が認められなくなることを意味した。
9.11は、所得再分配を推進する民主主義という実現条件が失われたことを示す。ピノチェトはフリードマンの仲間たちを経済閣僚に据える。野蛮な暴力による強力な後押しで新自由主義の経済政策が表舞台に登場する。
▽53 インフレと不況の同時並存というスタグフレーションが、石油ショックによって生じる。「大きな政府」を形成した福祉国家の失敗だと新自由主義者は批判する。
(重化学工業の生産性ののびがなくなって福祉国家が行き詰まる〓…という流れ そういうことだったのか)
▽54 新自由主義で不平等が激化すれば社会統合が困難になる。そこで、民主主義を弾圧する「強い政府」を主張することになる。()
▽56 技術革新に果敢にチャレンジすることもなく、無慈悲に人間を切り捨てる企業は、新しい産業を創造する投資を担うはずもない。
▽58 大量生産・大量消費にかわるのは知識社会。工業よりもサービス産業という人間が人間に働きかける産業も主軸を占めるようになる。新自由主義が推奨する「無慈悲な企業」には、知識社会へと移行する技術革新を担うことはできない。無慈悲な企業にできることは、人的投資にほかならない人件費を削減することである。
▽59 オイルマネーに代表される国際的過剰資本を、最初に導いたのは中南米。メキシコ・アルゼンチン・ブラジル・チリは活況を呈する。が、82年のメキシコをはじめとして、次々にバブルがはじけて対外債務返済困難に陥る。80年代に中南米は「失われた10年」となる。
その次には国際的過剰資本は日本へと流し、バブル景気に踊ることに。だが90年は「失われた10年」に。
次には東南アジアでバブルを発生させる。21世紀には、中国とインドが台頭し、ブラジルとロシアを加えてBRICSと呼ばれるようになる。
▽72 日本は、家族という共同立ちそのものの機能が「大きい」ということが「小さな政府」を可能にした。家族経営である農民や中小自営業者という旧中間層が大量に存在していた〓。
▽79 日本の財政の所得再分配機能は、アメリカよりも小さい。ところが「悪平等」の大合唱のもとに、労働市場への規制緩和が一挙に進む。その結果、先進諸国では最も平等であった財政介入前の所得分配が一挙に不平等化する。
▽86 OECD 日本の相対的貧困率は、80年代中頃の11.9%から00年には15.3%にもはねあがっている。
▽88 知識社会では、教育サービスこそが、格差を是正する。公教育に対する支出は、OECD27カ国のなかで日本はトルコに次いで下から2番目。
…日本は対人社会サービスのウエイトが小さい。対人社会サービスの提供は地方政府の使命だが、地方分権が進んでいないからだ。育児サービスや養老という福祉サービスがほとんど社会的に提供されていないといってもいいすぎではない。
▽92 人間は「分かち合う動物」である。「共同体的動物」(贈与と交換は?)
▽94 知識は蓄えることに意味がない。惜しみなく与え合うことで、知識の知識による生産が可能になる。
▽96 工業生産では、機能別に分別し、ピラミッド型に編成した組織が効率的かもしれないが、知識生産には、頭脳集団が研究分野別に組織され、それが相互に連携する大学の組織の方が有効である。
日本は愚かにも、大学の組織を解体し、時代遅れの工業社会の組織である「株式会社組織」にしてしまった。これが国立大学の法人化である。
▽103 コミュニティでの「分かち合い」 雲南市大東町の海潮地区。子どもの育児をコミュニティで分かち合い。自治会費は月額2000円から4800円を徴収。それで相互扶助や共同事業を実施。
▽114 貧困者に限定した現金給付(社会的扶助支出)よりも現物給付を。現金給付という垂直的再分配よりも、育児や養老、医療などを無料にする水平的再分配のほうが、格差や貧困を解消してしまう。
スカンジナビア諸国では利用者負担は所得比例となっている。教育サービスにいたっては、無料でないと考える日本こそ非常識。
…日本では、生活保護費の半分以上が医療費にかかっている。「生活保護を給付するので、貧困者はそれで患者負担を支払い、国民健康保険を支払え」といっているようなシステムになっている。…医療や教育が無料ならば、生活保護費は本人の食料費と衣料費という生活費を一律に給付すればよいということになる。
▽125 〓日本の財政運営は、まず大幅な減税を実施して財政収支の赤字を発生させて、それを根拠に「分かち合い」の縮小を説いていくという手段が採られていたのである。…90年代になると、財政赤字が急速に増大。その要因は、租税収入が減少基調に転じたことにある。減税政策が要因。
さらに98年度以降の構造改革としての大減税では法人減税に焦点が絞られていく。次いで高額所得に対する所得税減税が展開されていく。
…00年代に入ると、日本の法人税の税率が国際的に高いということが、先進国との比較では唱えられなくなったために、経済界は発展途上国を引き合いに出し「アジア並みに法人税を引き下げる」ことを要求しはじめていた。
…その上で財政収支の赤字幅が拡大したとして「分かち合い」への経費支出を削減していく。
▽134 社会的支出が大きいか小さいかは、経済成長率とは無関係。「小さな政府」にすれば、経済成長が実現するという「小さな政府」のドグマは迷信にすぎないのである。
▽136 「分かち合い」の経費は削減できても、警察と刑務所にかかわる経費は削減できない。公務員は大幅に削減されているにもかかわらず、警察や刑務所における職員は増加の一途を辿っている。「分かち合い」に携わる職員は、大幅に削減されてしまう。
▽142 「経済中立性のドグマ」を信じ、所得税・法人税中心税制をかなぐり捨てている国は、日本だけ。…個人所得税を90年から顕著に減少させている国はスウェーデンと日本だけ。…日本は90年から法人税の負担水準を激減させた唯一の例外国家。
▽156 「市場の神話」を説く者は、自己利益という個人的意義だけに目を向けようとする。新自由主義にとっては恐怖は、人間が人間の行為の社会的意義を考えるようになるのではないかという危惧である。人間は孤立した存在ではなく、相互に結ばれ合っているという真理に気づかれてしまうと、「市場の神話」の魔法が効力を失ってしまうから。(〓中間団体の解体)
…「市場の神話」は「仲間の分断」を図る。組合に組織される者と、組織されない者との分断。共に働く「仲間」の間を分断させようとする。
▽165 成長産業へ労働者を移行させるには、再教育、再訓練などの積極的条件を整備しなければならない。これを積極的市場政策と呼ぶ。それへの支出はスウェーデンがGDP比で最も高い。それによって新しい就業を保障する。旧来産業にいつまでも固執しないように、解雇を容易にする一方で、失業しても生活が保障されるだけでなく、新しい就業へ就けるように社会的セーフティネットを社会的トランポリンに張り替えている。
スウェーデンでは、失業者に対して、失業保険による「所得保障」を失業前の所得80%程度が14カ月間支給されう、さらに、6カ月間就労先が見つからなければ、職種転換・再就職のための活動保障プログラムに移行する。
…「誰でも、いつでも、どこでも、ただで」を原則にした「リカレント教育」と関連づけられている。学校教育を終えた後も、生涯にわたり学びつづけることのできる制度。勤務期間が2年を超えれば最長で1年間の教育休暇を取得でき、賃金の68%が教育手当として受給できる「サバティカル制度」すらある。
▽178 ポスト工業社会である知識社会では、高い人間的能力を必要とする職務が急増し、知識産業が産業構造の基軸を形成するようになる。
▽180 自然に存在する物量に対して、追加する知識量を飛躍的に増加させれば、当然のことながら自然に存在する物量の使用は、飛躍的に節約される。「量」が「質」に置き換えられれば、耐久性は向上する。
大量生産・消費のもとでは、生産の場と生活の場(消費の場)が離れているが、情報は生産の場と消費の場を近づける。注文方式のように、需要のあるもののみに限定して供給することができ、無駄のない多様な生産が可能になる。(〓分権の時代、地方の時代へ)
▽187 知識社会では、「型」にはまる人材ではなく、変化に応じてさまざまな型にはまることのできる、「潰しのきく能力」が必要となる。その能力を支えるのは、幅と深さのある「教養」。「学びつづける」教育体系を整えなければならない。それがリカレント教育。
知識社会とは「学びの社会」。
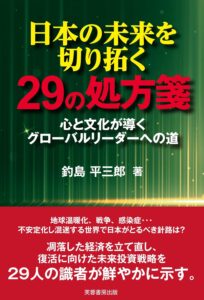

コメント