■成熟ニッポン、もう経済成長はいらない<橘木俊詔、浜矩子>朝日新聞出版20111210
「国」が問題解決ができない現状では、きめ細かく問題を解決するため日本全体を顔の見える規模に分割するべきだとして、2人とも地方分権を主張する。それには共感できる。だが、橘木氏が首都機能の分散という意味も込めて道州制を勧めることには疑問符がつく。100万都市でさえも官僚組織が権力化してしまい、民主主義が機能していないのに、数百万人から1千万人になる道や州では、広域化による効率性と、「住民自治」が働く規模とのバランスをとるうえで、あまりに「効率」に傾きすぎないか。
浜氏の地方分権のイメージは幕藩体制だ。グローバル化によって国民国家が適正な通貨圏としての力を失うから、地域共同体が独自の通貨をもつようになると予想する。こちらの方がおもしろい未来図に思える。
同じ理由で、ユーロは消滅する運命だという。グローバル化が進む21世紀は集権ではなく「分散」が時代の流れなのに、EUは逆行し、政治主導で経済力がちがう同士が通貨統合したために泥沼にはまったと説く。
借金漬けの日本経済の未来も厳しく見通している。日本国債の大半が日本の機関投資家が保有しているが、「いつまで日本国債を持っているか」「売らなければ株主代表訴訟で訴える」と株主に言われたら売らざるを得なくなる。そうなれば暴落するだけだ。バブル崩壊前、多くの評論家が楽観論をふりまいていた。「日本国債は安全でギリシャとはちがう」という論は、当時の楽観論に似ていると思った。
今後は成長路線ではなく「衰退の甘い香り」路線をとるべきであり、そんな世の中を生き抜くためには、大学教育ではスキルではなく抽象的思考力を重視し、リベラルアーツを施す方向に変えるべきだとの主張も共感できる。
一方、橘木氏は消費増税と納税者背番号制が必要だとし、浜氏は「アメリカから押しつけられた貿易不自由化の囲い込み」であるTPPには反対するが、本来はWTO主義でいくのがよい、とする。
……おもしろい指摘が随所にあるが、全面的にうなずくことができる本ではない。
=================
▽16 GNPのほうが、ほぼ恒常的にGDPよりも大きい国になった。国内で生みだされる価値よりも、外で稼いできた所得を含めた付加価値総額のほうが大きい。典型的な成熟債権大国。
若い経済は、外資が国内で生産するからGDPは大きい。外資が本国に送金してしまったあとの数字であるGNPは小さくなる。アイルランドが典型。
▽32 東大阪や富山の高岡でも、新たな取り組みが……
▽48 「無縁社会の正体」日本は有縁。社会から「無縁社会」に移りつつある。血縁も地縁も社縁も弱まる。そこで「国縁」が必要に。
▽55 「絆」という言葉が、震災後やけにはやっている。「応援よろしく」というスポーツ選手、「勇気をあげたい」という発言。自己中心的なおしつけがましさが伴う。人のことを思っているようで、実は自分のことしか考えていない深層心理があるのでは。
▽80 (橘)道州制がよい。日本全体を小さい単位に分割させる。
政府の質が悪い。でも、顔の見える規模に分割すれば、問題があってもきめ細かく解決していける。(分割さえすればよいのか)
▽94 パックス・アメリカーナの時代、アメリカが世界の工場だった期間はほんの一瞬だった。
▽96 経済や体力、発展度合い、成熟度がちがう同士が通貨統合をすると、今のユーロ圏のような泥沼にはまる。強い者が弱い者を支える体制を取らざるを得ない。
▽101 浜 単一通貨圏であった国民国家というものの求心力が、グローバル時代には希薄になり、国民国家が適正な通貨圏としての力を失うのでは。地域共同体が独自の通過を持つようになると予想しています。(幕藩体制?)
地域通貨が活躍するプロセスに入る前に、たぶんユーロは消えてなくなるのではないか。
▽105 「アジアユーロ圏をめざせ」という話が下火になるほど、アジア地域における経済融合がうまくいく可能性が高まると思う。EUは政治主導、計画的統合、水平から垂直に向かったという特徴がある。アジアでは、政治主導でやったら絶対だめ。経済実態主導型であることが望ましい。それゆえに「計画的」もだめで、成り行きにまかせるのがよい。現状でも相互依存は強まり、中国と日本は、「サプライチェーン」という意味ではほとんど「ごっちゃ」になっている。
政治の安全保障上の要請のために、ものすごく無理をしてきたのがEUの歴史(浜)
▽117 TPPはアメリカから押しつけられた「貿易不自由化」ととらえる。囲い込みの構想に基づいている。だから反対。本来はWTO主義で「自由」「無差別」「互恵」でいくのがいちばんいい。……私はTPPに唯一救いがあるとすれば、日本の農業がグローバル市場へのアクセスを強まるきっかけになると見ていました……保護してもらう代償として規制がある、という状態から解放されたいという人たちもけっこういる。(浜)
▽124 スウェーデンは、80年から90年代にかけて、与野党がいっしょに年金制度改革の議論をした。……年金の運営方法を積み立て式にして、保険料をまず決めて、運用の実績に応じて給付額を変動させることを認めた。もうひとつは、低所得者対策として、税財源による最低保障年金を設定した。
▽125 国民全体ができれば単一の社会保障制度に入れるようにしていかなければならない。国民1人1人に最低限の社会保障の福祉の保障をする。乱立制度を一本化する。財源は消費税アップしかない〓。
……社会保障の財源は消費税で賄い、東北復興の財源は所得税と法人税で賄ってはどうかと思う。
▽134 年金給付額はこれだけ、医療の給付額はこれだけ提供するから、これだけ負担してください、という基本的なことを示さなければならないのに、まったくなかった。
小さな政府・社会ができあがって、自己責任、自力で自分の「マイ社会保障制度」をつくれとなりかねない。
▽138 日本の社会保障の恩恵を受けない外国人には消費税を還付すればよい。ヨーロッパで買い物をして消費税を払っても、帰りの空港でその還付を受けられますよね。
▽141 橘)間接税は広く浅く網をかけるから、労働供給や設備投資へのネガティブな効果が少ない。間接税の比率を高めたほうが経済活性化に寄与する……納税者番号は、税を公平に運営する点からも大事。改革が進まないのは、徴税は不公平が当たり前だと国民があきらめているからでは。。
▽148 浜)日本国債をもっているのは大半が機関投資家。それも日本国籍の法人。彼らは株主などに「いつまで日本国債を持っているか」と言われたら売らなければいけなくなることが大いに考えられる。「そうしなきゃ株主代表訴訟で訴える」などと言われたら売らざるを得なくなる。いったん誰かが売り始めたらもう止まらなくなりますよ。……国債が暴落しはじめたら早いですよ。雪崩を打って皆が売る。その流れを止めるために日銀の直接引き受けをやろうなどとなると、もっとすごい大暴落がつづくでしょう。
橘)ヨーロッパは各国が困っているとEUが助けてくれる。日本はそうなったらどこも助けてくれない。
▽160 浜)震災と原発問題によって日本経済のもろさが顕在化した。集権的管理のメカニズムというやり方をとった結果、「解体の誤謬問題」を抱え込んでしまった。外からみるとまとまって見えるが、内側に入って、部分部分に解体したらバラバラというイメージ。……原発が沿岸部に集中配置されているわ、首都機能は極度に東京に集中しているわ。ひどく偏りが目立ってバランスが非常に悪い。〓(藩を目指している?)
▽166 浜)subsidiarity 権限移譲と訳されるが「委譲」が正しい。すべての意思決定は市民にもっとも近いところで行われるべし。「自治体が主体となって復興を進めるべき」という考え方が復興構想会議で盛んにうたわれているのはいいことでは。
橘)首都機能の一部を大阪にもってくる、という橋下。それをもっと増幅させて、8つの地域に日本を分割して、地域の中心都市に首都機能を分散していけばいい。ドイツは、ITはミュンヘン、金融はフランクフルト、重工業はハンブルクといった感じになっている。
▽174 浜)20世紀までは収斂のプロセスだったが、グローバル時代である21世紀は、逆の分散の力学が時代特性となってもおかしくない。EUは古い。20世紀の古い設計図に従って時代の流れにさからって統一を追求してきたから、ひどいことになっているのでは。
▽188 浜)大学教育ではスキルを教えるのではなく、もっと抽象的思考力を育てることを目標に考えたほうがいい。リベラルアーツをちゃんとやる方向に変えてゆくべき。
▽191 アメリカは、メインストリート(産業)からウオールストリート(金融)への軸足の変化。事業から虚業へ。ものづくりから金づくりへという産業構造の中核部分の変革。その結果としてのリーマンショック。日本は、完全なウオールストリート化とは相性がよくない。
▽196 イギリスは、サッチャリズムからブレアイズムに至る流れのなかで、少しだけ成長戦略を模索するという年寄りの冷や水路線を取ってしまった。最終的には金融大暴走とロンドン一極集中を招いてしまった。……基本は衰退の甘い香り。成長しなくてもよい……
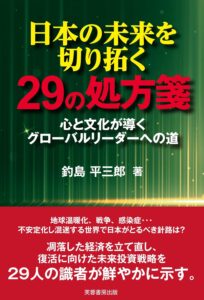

コメント