実業之日本社 20080105
社会主義やケインズ的福祉国家などの「大きな政府」ではなく、かといって市場一辺倒の「小さな政府」でもない第3の道を「ボランタリー」にもとめる。
イギリス産業革命とアメリカ独立とフランス革命によって準備された近代国家は、「機械」「民主主義」「市民」という画期的概念を生みだし、それぞれが、労働からの解放、圧政からの解放、解放主体としての自発性をしめしていた。ところが近代国家は「強さ」をもとめるが故に広義の「大きな政府」になり、帝国主義化し、「自発性を封殺するしくみ」となってしまった。戦後の福祉国家も自発性をもとめないという意味では同類である。アメリカ的な市場主義も、市場をなりたたせるルールを守るための「力」を必要とするという意味で、自発性を封殺するしくみだった。
では、ボランタリー経済とはなにか。
キーワードは「相互編集」である。「力」や上からの権力によるルールによりかかる経済とは反対の概念であり、コモンズのようなもの、ネット上の自発的コミュニティや、小地域の地域通貨、農産物の直売所……がその萌芽だという。参加するメンバーが自発的にルールを決める経済と政治のありかたである。
野沢温泉の共同体のような惣村からの流れをくむ伝統的な住民参加コミュニティから、地域住民が出資しあって24時間医療体制をかたちづくった都市コミュニティ、ネット上のコミュニティなどの例をあげている。いずれにせよ、自発性と相互理解がなりたつためには規模は一定以下でなければならない。
この本では、こうした事例の紹介だけではなく、近代合理主義思想に対抗する現代思想の流れを、「自発性」とリンクして論じている。
客観性と合理的思考を絶対視した近代思想が近代国家や市場を生みだした。一定の労働力と資源と投資という関数をさだめれば景気の変動が予測できた。が、そのシステムは近代哲学と同様行きづまってきた。
今は「情報」という融通無碍なものが跋扈し、経済の原因と結果(景気変動)を直線的には予測できない。香港で蝶がはばたけばニューヨークで竜巻がおこる、といった「複雑系」を想定しなければ説明がつかなくなってきた。「複雑系」とはつまり、そこに関与する人々の「自発性」が多大な影響をおよぼすシステムである。
そこでは、客観的第3者の存在を前提とすることはできない。観察者・研究者が発したひとことの影響をも考慮しなければならないからだ。まさに「関係性」「相互編集性」が大切なのだ……。
ゲーム理論もまた、「相互編集」経済の重要性をささえる理論としてもちいている。たとえば「囚人のジレンマ」や「共有地のジレンマ」。
2人の囚人を別々に尋問し、それぞれに「相手の犯罪をしゃべれば罪を減じてやる」と言いわたす。囚人にとっては、2人がそれぞれ何もしゃべらないのが最高である。が、相手がもし先に証言したら、自分だけが損をする。そう考えて抜け駆けをして相手をおとしめてしまう……。先に裏切ったほうが「得」なのだ。
ところが、このゲームを何十回とくりかえすと「裏切り」は得にはならない。最初の回は相手を信じて、次は、相手のやり方にあわせる、というオウム返しをくりかえすことが、ぼちぼち勝ち、ぼちぼち負けるというパターンをくりかえし、最終的には一番成績がよくなるという。
これはまさに、1人がもうけるより、みんなで適度にゆずりあいましょ、というコミュニティのありかたである。
「弱さの強さ」という指摘も、うなずきながら読んだ。
合理的判断をくりかえす強者が勝ちをおさめる市場主義ではなく、弱いからこそ情報の交換ができ、共有ができ、相互編集ができるシステムがもとめられているという。
自分が突出してまず動くことによって、他から攻撃をうけやすいvulnerableな状態に身をおき、それによってさまざまな情報があつまるようになる。弱さをさらけだすことで、ネットワークが形成される。ユダヤ人・河原乞食……といった差別される側から革新的なものが生まれることが多いのはそのせいかもしれない。
「弱さの強さ」は、実感としてもよくわかる。「強さ」の典型がいわば会社という鎧だろう。会社の歯車として、突出せず、淡々と暮らしていれば心身ともに安定が保証される(幻想ともいえるが)。突出しようとすると、風あたりが強まり、居心地が悪くなるが、新しい人間関係や発想が開ける。むしろ、弱い人間が突出することが推奨される社会をつくることが、自発的コミュニティを形成することにつながるのではないか……
先日、大学で憲法を教えている知人がこんなことを言っていた。
「権利をきっちり主張し、議論できる『市民』になることが大切だと学生に説いてきた。そういう市民がまさに近代国家の前提であると思ってきた。でも実際は、大学の教員でさえも主張できない人が多い。弱さを前提にしたシステムも必要じゃないかって思いはじめた」
近代合理主義はとても大切ではあるけれど、あちこちでほころびがめだってきているようだ。
格差是正にはたす国家や自治体の役割を軽視するなど、にわかに賛成できない部分もないではないが、近代の「次」を構想するうえで刺激的で参考になる本だった。
---------抜粋など---------
▽ボランティアは、長らく「志願兵」をさしていた。
「大震災直後の状況を短期的にみれば、ボランティアとヤクザの動きが一番経絡的だった」どんな社会にも経絡のような短絡ルートがひそんでいるが、震災のときはそのルートをボランティアが発見しヤクザがその後を追った(下河辺)
▽「コモンズ」は、情報がたえず自発的に編集される「相互性」がとびかう。 ボランタリーエコノミーは、たんに物品を媒介にするのではなく、情報関係にコモンズ(共有地)独自の市場価値を認めようとする経済。関係経済圏 〓カラリのような取り組み
▽自分からすすんで関係を求めるときに発生する<弱さ フラジリティ>をはらんだ自発性。
「強さ」を求めてきた近代社会。大きすぎるデメリット。「強がり」を主題にした世界は、ついに「成長の限界」に。ここに歴史上はじめて<弱さ>を実験するチャンスが訪れた。
▽会社が社員に対し、「危なかったときの情報をすべて報告せよ」と命じても、でてくるわけがない。運転手が「居眠りしかけた」などといったらクビになる。事故が起きれば報告されるにしても「危なかった」情報は事前には交わされない。
「囚人のジレンマ」「共有地のジレンマ」 自発的にみなが協力すれば万事うまくいくのに、実際はそれぞれが自分を守るために相手に協力しない。
「危なかった情報」が出てくる可能性のある環境は、ある種の相互性が出入りする情報環境。評価の評価がおこなわれ、情報の情報が自発的に生まれるしくみ。
▽パソコンのフォーラムで、パソコンの使い方を教わる。それと同様のサービスを、企業がやるとしたら莫大なコストがかかる。相互編集(双方向システム)のコストの低さ。
▽ネット だれもが情報発信できる。価格というシグナルの上下動で財とサービスの有効性を生みだしてきた社会システムから、それらの質にダイレクトにアプローチすることで価値を創発するしくみへの移行を示唆している。
価格という単一のシグナルによるコミュニケーションに基盤をおく市場システムは、「危なかった情報」「つながることを待っている情報」といった「ひとりでいられない情報」を流通させ相互編集して価値をつくりだすことが苦手。
(〓大企業は、ゴミ情報を大量に流すことで、個人の情報発信を無化できないか)
▽ヒエラルキー型組織の失敗。「ひとりでいられない情報」をうまく扱えない。
▽情報の非対称性 サービス供給者に情報が偏在する場合、消費者の情報不足につけこむ機会主義的行動(だます)可能性がある。その点、NPOは、利潤追求をしてないぶん、機会主義的行動をとる動機がすくない。非営利性が需要者に「信用」を与える。
教育・医療・福祉など、サービスの質がにわかには判断できない分野では、営利企業よりもNPOがこのましいものになる可能性が高い。
▽パットナムの実証研究 イタリア20の地方自治体の自治が1970年にスタート。20年後、各自治体のパフォーマンスを比較。民度の高い地域は、市民活動ネットワークの密度が濃く、コミュニティ活動への参加が盛んで、平等原則による政治がおこなわれる。市民の間に相互信頼関係があり、自発的に法律にしたがう雰囲気がある。民度の低い地域では、政治的・社会的組織がヒエラルキー的であり、相互不信と社会の腐敗が進んでいる。
一般に北イタリアは南にくらべて民度が高いとみなされる。経済的・政治的パフォーマンスも高い。この差異はソーシャル・キャピタルの差と判断。
北では、長年にわたって、相互協力の社会規範と活動のネットワークが発達していた。ギルド、相互扶助協会、協同組合、労働組合、読書会……など。
ソーシャルキャピタルのあるところでは、「共有地のジレンマ」はおきにくい。「ただ乗り」の動機が薄められ、活動の不確実性が減少する。
(〓日本でも、公民館運動などが盛んだった地域は、経済的にも発展し、平等主義的。ヒエラルキー的な封建的な地域は暗い。ソーシャルキャピタル、という言葉で比較できるのか)
▽エリノア・オストロムの研究 共有地を基礎とした地域自治コミュニティについて、ゲーム理論をつかって研究。ジレンマを解消させるには、自治ルールをもった「会員制度」導入が有効。
ゲーム理論の結果。長期的継続的関係がみこまれる場合は、「共有地のジレンマ」は必ずしもおこらずに「協力」という均衡解になる可能性がある。だが、長期的関係がありさえすれば協力関係が成立するわけではない。実際、南イタリアの閉鎖的コミュニティはうまくいかない傾向がある。「どんな関係をもつか」が大切になる。
▽コミュニティ・ソリューション 強制力をもつ第3者機関にたよらず、かつヒエラルキー的ではない方法による「ジレンマ」の解決法。継続的関係性が維持しやすいコミュニティというかぎられた範囲に対象をしぼり、その範囲で社会的な「信頼」をつくりだすところに解決法の特徴がある。
□第3章
▽株式会社や保険制度、ジャーナリズムなどの仕組みの萌芽は、ロンドンのコーヒーハウスからみつかる。情報を満載したチラシを入れておく情報箱(マガザン)が雑誌や新聞といったメディアに発展する。
▽堺の商人の茶の湯。自分の「好み」によって茶室をつくる。これらの「好み」が参加者が記す「茶会記」によって伝えられ、希少な情報がかえって全国的な流行をつくりだした。窯業・木竹産業・繊維業、食品業、金属加工業、造園建築業にいたる生活産業を高度に発展させたのは、茶会記につづられた情報編集力だった。これが地域産業のコミュニティをも充実させていく。
▽野沢温泉村〓 野沢組 近世共同体は共有地があった。近代法は私有のみをみとめ共有を否定した。野沢組は近代法を拒否した。野沢組は、法的には土地を共有する家々の集合体が自称する任意団体にすぎない。
温泉権という、近代法でみとめられない弱い権利
▽共同知を蓄積するコモンズ p150
伝統的共同体では、言い伝えやしきたり、童謡や民話、祭りというかたちで蓄積され伝承された。グリム兄弟や柳田、宮本が調査したのはこうした共同知だった。昔話のようでいて、実はコミュニティを維持し運営するための問題解決の方法などが語られている。逆にそうした意図を忘れてしまった地域では、伝説も祭りも形骸化してしまった。(〓レヴィ=ストロースの神話分析 フレイレ的な取り組み)
▽ボランタリー・エコノミーは、壊れやすく傷つきやすくみえながら、柔軟な相互作用をもたらしつづける。コモンズのルールは権力に裏打ちされるものではなく、メンバーが自発的に守ることで成立する。自発性を前提にするために、権力や強制力にもとづかない柔軟なパワーが生きる。「弱さの強さ」
政府や企業、官庁といった既存の社会運営システムは、どれも強いシステム。その強さによって手詰まりになってしまった。分散システムである市場システムも、契約と決済の効力が最終的には国家権力によって担保されているという意味では、すこぶる強いシステム。
▽自分から行動することによって発生する傷つけやすさこそが、「つながり」をつけるための秘訣。自分自身をバルネラブルにすることで、情報はむこうからやってきやすくなる。
p170
▽オウム返し 囚人のジレンマゲームでは、はじめは協力し、次からは、前の回で相手がとった手をそのまままねる。自分からは決して裏切らないが、おひとよしすぎもしない。コンピューターゲームでは、これが総合的によい結果をもたらす。=進化論的安定戦略
▽人間は幼児期を延長したことで、学びあい遊びあう性質を図抜けて発達させた。動物は、成熟するにつれて厳重な本能のプログラムにしたがうようになる。
▽古代の貨幣は呪術性をもっていた。……明治にいたるまでただの一度もユニバーサルな統一通貨を発行しなかった。かわりに、民間の自発性を利用した多様な通貨システムが試される。
荘園でとれる米絹布などが現物税として荘園主にはこばれるが、運送コストが大変。11世紀に民間が宋銭を輸入し、荘園から荘園主にはこばれる現物税をもよりの関渡津泊で換金して輸送するシステムをつくった。これが中世貨幣経済システムの誕生。(民間が推進)
西国からは主に米で。東国からは絹や布で。のちの東国の金本位感覚(東北の金)と西国の銀本位感覚(中国貿易に依存)の二分性を象徴。銅銭は全国。
江戸時代、多様な藩札や私札。複雑なレート計算をあてこんだのが両替商。
p212
▽鯛などの貴重な魚は金貨で表示し、米塩薬などは銀貨で、茶や野菜や豆腐は銅貨で表示した。「併行本位制」 各地で自然発生した貨幣制が共存していた。
江戸時代は「米遣いの経済システム」が前提。実物経済。それが元禄以降はしだいに商工業者が勃興し、一方に「金遣いの経済システム」が進行する。
こうした貨幣感覚を変更させたのは、ペリー来航で国際上の貨幣レートを決定せざるをえなくなってから。
▽伝統的貨幣の歴史は、貨幣や市場が、共同体同士を仲介する相互編集メディアだったことを告げる。自律的な共同体の持続が通貨統一を挫折させてきた。逆に、ユニバーサルな通貨が定着すれば、貨幣経済が「共同知」を媒介することは困難になる。
▽「コミュニティマネー」が注目されはじめた。藩札のように、ボランティア・コモンズごとに流通するコミュニティ・マネーを実現し、交換レートをデータベース化し、コミュニティごとの情報価値をふくむ交換を可能にするべき。多様な地域・文化・人々の価値観をふくんだ価値の交換を。
▽封建社会を超克して近代社会と民主主義を形成したという戦後民主主義論につながる歴史観。日本の近代化の条件を近世の商業やマニュファクチュアの発展に求め、西洋型の重商主義と官僚指導が加わったとみる視点。古代中世は中国、近世近代は西欧、戦後はアメリカに学んで社会制度をつくったという議論。これらは、日本の社会や文化には「自発性」がかけている、ということになりかねない。
実はそうじゃない観点から、日本の自発的な社会組織を説明できる。ネットワーカーによって組み立てられ組み直されていた。
(〓宮本常一のよう〓内発的な議論だけではなく、外からの刺激、外とのつながり)
▽結 労働力を互いに提供しあうルール。
祖谷地方の茶摘みの「結」〓 5,6戸の主婦がそれぞれの家に順次でかけて茶摘みから茶づくりまで共同でおこなう。
単なる労働交換ではなく、地域に適した製茶法が共有知として蓄積されねばならず、意見を出し合える場がなければならず、特別料理をださなければならない。この会食が問題を語りあう相互編集の場になっている。
(共同作業がなくなると、隣近所ともあわなくなってしまう内子の例〓 共同知をつくりだす場がなくなる 面河の会食の意味)
「知識結」は、とりわけ外部からのノウハウをとりこんで「共同知」を刷新するソフトウェア。7世紀から8世紀、鎮護仏教拡大につれ、民間の自発的発意で波及した。これが、仏教文化と地域文化を編集し、日本最初の地域共同体の母体となり、律令体制をゆるがせる。
▽「講」(共同体の社会保障システム) 保険や金融である頼母子講や無尽となる。アジアでは「回転信用組合」として知られる。
欧州から銀行と保険のシステムが伝わったとき、銀行を「無尽」と、保険を「頼母子講」とたとえた。明治初期に設立された無尽会社が、相互銀行になった。自発性。
▽「座」 安定時は祭りを実現するしくみだが、時に戦闘体制になり、救助復興体制にもなった。神輿や山車の競争的興奮は戦闘体制のシミュレーションでもあった。伝統的祭りの大半が「座」もしくはそれが変化した「寄合」による。祭りは、伝統的ボランタリーシステムがいまなお活動しつづけている証。
祭りは、共同体の経営方針を、定める機関だった。神事の「座」が、必要に応じて開かれる「寄合」になると、議会システムに発展する。そういう自立的共同体が「惣」である。
▽〓ケアセンター成瀬
1950年には89パーセントが自宅で死んだ。70年代に半々になり、90年には7割が病院で死ぬことに。遺族アンケートでも、在宅死での「心残り」は少ない。
地域住民を母体としたボランティアによって自主的に設立され運営されている。経済的にも合理的。
▽ライフケアシステム(相互編集性をもちこんだ医療システム 会費を払う 東京)〓
24時間在宅医療支援組織。ニーズを効果的に満たし、職場としての条件もよく、財政も健全。
大病院で検査や手術を受ける際、主治医がつきそい、担当医師と情報交換し、手術に立ち会う。
▽寺子屋 世界教育史上、女子の教育機関は寺子屋が最初であった。江戸や関東では師匠の3割が女教師。
謝礼も定められていない。魚や酒、野菜が謝礼のことも。入学時に菓子や扇子をおさめ、盆・暮に贈り物をする例も。営利組織ではなく、コミュニティの人間関係に依存していた。
私塾は、フリースクール。出入りも入退学も自由。授業料は7ランクになっているところも。授業料をとらないところもざら。
これらは、相互編集性にとんだ教育を重視した。
p324
▽産業革命、フランス革命、アメリカ独立による「機械」「民主主義」「市民」というモダンボランタリーのコンセプトは、近代国家の膨張力と収奪力のための歯車として使われた。「強さ」をもとめ軍備競争をもたらし、帝国主義へ。
強さを標榜せざるをえないナショナル・インタレストの矛盾を、公共施設や公共装置の思想でカバー。学校・病院・図書館・保健所。……国家による教育の矛盾を見当するのではなく、子供の異常性が見当される。
……社会主義運動が労働組合や協同組合を発明する。婦人の権利に気づいた人が私立学校や赤十字を創設する。【プレボランタリーシステム】
▽組合運動を抑制するためにビスマルクがつくったのが、国家による社会保険制度。〓組合運動を標的とする上からの抑制のために生まれた。
▽ドイツのラテナウ 企業家が従業員のための所得再配分をこころがけるべき、と考えた。今は常識となっているが、当時は「資本家の裏切り者」。が、ラテナウの理想を政府として採用したのがナチスだった。
▽赤十字やYMCA、ボーイスカウトといったプレ・ボランタリーシステム。ワンゲルは、ナチスの青年運動にも重なっていく。日本の昭和初期の農村運動も、発端は安藤昌益や二宮尊徳のようなボランタリーであったのにかかわらず、その後は愛郷精神や愛国精神の発揚とともに、橘孝三郎などの皇道派の右翼活動に結びついていった例がある。同様に、労働者の社会改革の意識の芽生えが、左翼運動にまきこまれ、ゆがんでいった例も。
政府官庁の許認可、監視監査によって、ボランタリーな本来性が鈍っていく。福祉国家の登場が下からのボランタリズムを上から「吸収」してしまった。
▽第一次大戦 知識人は西洋の「知識」に自信をなくし、一部を文化人類学や民族学にかりたてる。外部性や過去性によって突破口を見出そうとした。
逆に、内部性に着目すると、近代の理性をカントにさかのぼって批判する動きも。……国家自体が自己自体に重くのしかかる暴力装置であった。歴史上初めて「自己」や「自発性」が世界史にさらされる。……「実存」探求で近代をこえようとする。ハイデガーの「現存性」やサルトルの「実存」は、どんな現実にも先行してそこ自体にあるものとみなされる。実存は世界の内部ににいるとともに、自分の内部にもいつづける。近代の認識主体は「外部としての世界」を理性的に眺めるが、そういうことは「世界内存在としての実存」にはできない。
▽オルテガ・イ・ガセット、グラムシら 大戦後、誰も予想できない状況「大衆という状況」が訪れる。大衆とは自己を失ったバッファローのように動く大群。他人志向型の心理。それを知識人は悲観的にみる。……日本の大衆社会化は昭和30年代にずれこむが、知識人には理解しにくかった。「一億総白痴化」(大宅壮一)。
その後、大衆はゆっくりと自律性を内包しはじめる。ハンナ・アレントは、大衆の勃興こそが文化の様式を変質させたと認識しはじめる。
▽レーガン的「新資本主義」vs.ニューディール的「福祉リベラリズム」 → 「相互編集によるリベラリズム」
「行政管理社会」(委員会のような場で行政管理を調整)vs.「経済民主主義」(委員会のような機関に市民参加を求める)→ どんな管理制度新設にあたってもネットワーク上で民意をはかる民意編集のためのフォーラムと分散型「評判システム」を創設して参考にするべき(〓ネットが民意を反映していると言えるのかどうか……)
▽「編集」を重視。
アリストテレスは、テオリア(観相=観る)、プラクシス(実践)、ポイエーシス(制作)にわけて、表現・編集・制作を人間の知的活動の基本とみなしている。制作のなかには、修辞学と詩学があると分類している。
▽現代思想は、権力の意志の代名詞になってしまった「理性」にたいして「解体」を試みることから出発する。実存主義と構造主義の対立。実存主義は「主体」を重視し、構造主義は「関係」を重視する。構造主義は、人間を知るには主体に力点をおくよりも、どのような構造をもち、どのような関係にあるかを見たほうがいいと主張した。
フーコーも「主体」偏向を批判。近代の主体性がたえず権力装置によって支えられてきたことに着目。
アルチュセールは、構造そのものも実のところズレをおこしたり、ゆがみあっているから、構造を動的に見るために「重層的決定」という方法をつかうべきだと提案。主体が関係をつくるのでも、構造が関係をつくるのでもなく、関係こそが主体や構造をそのようにあらしめているという見方〓。
フッサールの「間主観性」(相互主観性)、メルロ=ポンティの「関係間の関係」、ヴィトゲンシュタインの「言語ゲーム」……といった現代思想は、いずれも編集的な「関係」を重視している。
▽ブリコラージュ(レヴィ=ストロース) ありあわせの道具や材料でつくりあげること。古代以来の神話的思考に脈々と維持され、素材はたいしてかわらないのに、いくつもの物語を編集する。編集される構造には、参入して物語をつくる人々の、物語の当事者であるかのような動的な視点が導入される。
ブリコラージュは情報修繕・情報編集の思想。
……現代思想の多くが「方法」を重視し、その方法が関係的で編集的であり、その関係は「一対多」であり、対応関係そのものに「ズレ」や「ゆれ」があり、そのことを通してのみシステムは理解される。
▽かつては、資源を分配し、分野や領域を特定して調査し、工場生産をコントロールすれば需要と供給のバランスの成果を予測できるはずだった。景気変動を予測できた。それが不可能になった。日本経済の予測はバブル当時からまったくあたらなくなった。
複雑系……予想のつかない事態をどう記述するか。科学者がそのシステムを観測しているというふるまいをシステムのなかに「勘定」に入れないかぎり、「科学ゲーム」がなりたたなくなっている。
▽国民・市民という社会活動の「担い手」は、責任や義務をはたすべき存在とされた。そのような責任と義務が、戦争義務をはたすものだったり……した。問題は「担い手」ではなく「存在の行方」そのものにあることが重視されてきた。存在には、自律性や創発性がひそんでいるから、それらを損なわないための哲学や思想が必要になった。そこに、存在の「弱さ」を見つめる見方がクローズアップされてきた。レヴィナスの「バルネラビリティ」(傷つきやすさ)というかんがえかた。傷つきやすいがゆえに、ふだんは見えない意思がそこに発現される。だれもが平均的市民という担い手であるということではなく、誰のなかにもひそむ「弱さ」に光があてられた。
「傷つきやすさ」は、社会的弱者とされた者に集中してきた。が、バルネラビリティは、人間そのものの存在や意識に根ざす。社会的弱者という規範をこえて「弱さ」は偏在しうる。弱きが故にラディカル。
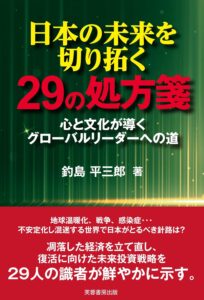

コメント