岩波書店 20081220
中国の大学での講演と講義の内容をまとめている。
ウェーバーによると、資本主義の源はプロテスタントであり、中国や日本の儒教はプロテスタントに近い合理的な宗教ではあるものの、上位者を尊敬する考え方が非合理的だったが故に資本主義をもたらす力にならなかったという。
だがウェーバーは、日本でなぜ資本主義が発展したのか、同じ儒教圏なのに中国ではなぜ発展しなかったのか、説得力のある説明ができていない。
森嶋は、中国と日本の儒教の違いは、カトリックとプロテスタントの差異に似ているとみる。
中国の儒教は「仁」をもっとも大切にするが、日本では「忠」が重視される。同じ「忠」でも、中国の忠は、自らの良心に誠実であることを意味し、主君が道をふみはずしたときはそれを制止することも含まれるが、日本の忠は、主君への絶対服従を意味する。
中国の王が絶大な権力をもってはいたが、官僚は科挙によって能力に応じて選ばれていた。一方の日本は、革命が絶対に起こらない国をつくるため、官邸や政府を貴族階級でかため、江戸末期に至るまで民主的な選抜制度は生まれなかった。
中国の科挙制度と儒教は、「文」の優位をもたらし、武=科学を軽視することになった。日本の儒教は、武=科学の優位をもたらした。明治初期の文官のほとんどは旧士族だったため、近代産業は急速に発展した---などなどと説明する。
ところが最近は、中国共産党の指導部の大半を理科系が占めているのに対し、日本の政治家は文科系がほとんどだ。森嶋はそこに中国台頭の力の源を見ている。
森嶋は、東アジアの発展の希望をEUを模した「東アジア共同体」づくりに求める。
儒教文化を共通の基盤にもつ中国・日本・韓国・北朝鮮の結合は、まずは、中国の奥地などを共同で開発する「建設共同体」としてスタートする。「上からの資本主義(=中国の社会主義もこの一種)」によって、辺境を開発することで、域内の経済は活性化する……。
首都は、日本から独立させた沖縄に置けばよい。公用語は必然的に英語になるが、自国語以外の共同体内のもう1言語の習得を学校で義務づける……
共通貨幣の導入の段取りや、教育水準の均一化、議会のつくりかたなどなど、具体的に緻密に描いているから何となく実現しそうな気がしてくる。
国家の大きさを規定するのは、武器と交通・通信手段の発達水準だという。奈良時代から足利時代まで、武器と交通手段はほとんど変化がなかった。本州・四国・九州を領土とする国は、当時の交通手段に比して大きすぎたから、中央政府は荘園の特権を認めざるを得なかった。武力を背景にした幕府も統制できなくなり、戦国時代になった。
統一を果たすには、鉄砲という新武器の導入が不可欠だった。だが、交通手段は未発達だから全国を直接統治する中央政府はつくれなかった。幕末、欧米の技術を知ったことが、幕藩体制(上部構造)を陳腐化させ、日本にはじめて民族国家が形成された。
戦闘用の技術(武器)と生活用の技術(交通・通信・生産など)のうち、前者が進みすぎれば、領土は直接統治できなくなり、小さな共同社会(藩)が並立する。生活用技術が低ければ、生活上の諸目的を達成するための社会規模は小さい。別の地域に住む人との交流は少ないから、共同生活の結合体である共同社会もまた小さい。
後者が前者より進んでいる場合は、国家の範囲を超える規模の活動範囲をもつ結社が次々に生まれる。異なる共同社会間の混合結婚がおこなわれ、共同社会の規模は大きくなる。EECからEUへの発展はそうした流れであり、東アジア共同体もそうした経済・技術的な必然性があるという。
森嶋は数理経済学者だが、歴史や宗教、文化も綿密に検討したうえで、壮大な「絵」を描いている。素人が同じ主張をしたらハッタリとしか思われないが、緻密な研究を積み重ねてきた経済学者が壮大なオーケストラを奏でると、妙に説得力をもつ。
日本では民衆レベルでは、儒教よりも先祖信仰のほうが根強かったのではないか……とか、いくつか疑問がないではないが、とてもおもしろかった。
==================抜粋・メモ=====================
▽16 倭は朝鮮と九州の双方に基地をおく一種の海上民族であったと想像しうる。当時は日本(大和王朝)は倭よりもはるかに後進国だった。その倭が挫折し日本に吸収された。倭のようなことが日本に起きないようなイデオロギーを国民に植えつけるために、「日本書紀」「古事記」は編纂された。
▽28 日本共産党はヨーロッパ的だが、その他の日本の政党はガタガタで近代性を全く欠いている。だから共産党は共産主義の党としてではなく、日本を代表する党として活躍しなければならない。しばらくの間は党名からも共産を降ろすべきだ。マルクスもエンゲルスもレーニンも「そうだ、近代化が先だ。名望家が支配している社会に共産主義を導入してどうなるのだ」と言うことは確実である。
社会に風を起こす、ニューアイデアをつくりだすのは政治家の仕事である。日本の保守系政治家にはその力はない。だから私自身はラディカル・リベラルであるにもかかわらず、日本では共産党に期待する。国民政党に成長し、東アジア諸国と交渉し、経済共同体をまとめあげる……
▽39 倭の文化程度は、他の日本の諸国よりはるかに高く、大和王朝よりも早く漢字を使用していた。韓国の眼から見ると、北九州以外の日本各地は未開であり、未開なるが故に可能性があると思われた。コロンブスが北米を発見して以後に、イギリス清教徒が北米に移住したころの英米関係に似ている。
米国の成長率がイギリスより高かったように、3,4世紀から10,11世紀にかけての日本の成長率は韓国よりもはるかに高かった。日本は外国との文化格差を有効に利用して急成長したが、そういう国の国民は劣等感の裏返しとして、アロガントである。こういった空威張りは、中国や韓国ではさげすまれる。
韓国からのルートは倭(博多)だけでなく、唐津、出雲、若狭、越前にもあった。継体天皇は越前から来た。彼の一族が韓国から来たのかもしれないし、彼が渡来人を有効に使ったこともあり得る。越前は鉄の産地であり、それによって富を蓄積したと想像できる。彼らの一族が大和に入り、古大和を継いだのである。
▽49 日本の帝国主義は、マルクス的な帝国主義ではない。資本主義がまだ幼、青年期にあったときにすでに海外侵略をはじめている。古代ローマ帝国や近代欧州の専制君主国のように、国家は無制限の拡張欲をもっている。このような侵略はむしろ非合理的な前資本主義段階に生じるのであり、国家がよりゲゼルシャフト化し、個人が自立し、自己主張をするようになった資本主義段階では、発生することは困難になる。日本は近代化したから侵略したと思っているが、前近代的だったから侵略したのである。
朝鮮に日本の近代工業が進出したのは、合併後かなり時間がたってからだし、満州に対しても、財閥系企業は、進出するのを最初は渋った。満州には満州重工業(日産)その他の企業が存在したが、それらは大企業だから満州に進出したのではなく、進出したから大企業になったと見るべきだろう。
このような前近代的帝国主義は、マルクス-レーニン主義のそれよりはるかに狂暴であり、征服された諸国の人民を奴隷化してしまう。侵略の首謀者は軍人と右翼であり、天皇や資本家、実業家には彼らを抑止する勇気がなく、追認した。首謀者の多くは、徳川時代は武士だった。維新で没落したため、外国を侵略して利益を得ようと常に思っていた。
▽55 対米英戦争 もし中国から撤兵したら軍の面目が丸つぶれになり、彼らが国内で失脚するので、彼らは自分の身を守るために、国全体を危険にさらした。この決心は天皇臨席の御前会議で決められた。「自存自衛のため」という理由にもならない不分明な理由で、何百万人という日本人が死ぬことになる戦争が決意された。
出先機関が勝手におこなった犯罪的行為を追認しつづけた上層部は、今度は彼らの累積債務を一掃するために、天皇自身が臨席するところでその決定を行った。
▽55 国民は「アジアを白人支配から解放する」というスローガンにのった。欧米に対する劣等感に基づく怨念が、日本人に理性を失わせ「天皇の為に死ぬ」ことを誓わせた。
軍人は、忠節を尽くせば出世する。出世を本分として生きていた。軍人が出世する早道は戦争だから、忠義者の集団である軍隊は必然的に好戦的になった。
▽62 各国の戦時中の首脳人事を比較すると、ドイツ・イタリー・アメリカは主将を陣頭に最後までたたかった。イギリスは最初の主将が力不足とみるとすぐにエースに切り替えた。これに対し日本は14人の首相を思いつき次第で登場させた。近衛と東条がもっとも責任が重いが、彼らとて、自分は運悪く、どうしようもない時に起用されたと主張するだろう。
当然のこととして、敗戦の責任は、各首相にはほとんどなく、脈絡のない起用をした天皇にある。精一杯の人選を続けたが、そこには何の筋も哲学もなく、でたとこ勝負の穴ふさぎ仕事でしかなかった。
戦争は、東条が首相を辞任した段階でやめるべきだった。そうすれば朝鮮や台湾を失うがほとんど全ての都市は戦災をまぬがれた。しかし天皇は、敵に一泡ふかせてから、条件を有利にして戦争を終結しようとしていた。
天皇も東条もその他の上層部の人も、軍人すらも良識ある人たちは自発的に戦争を欲してはいなかった。だが、国民の一部には、好戦的信条をもつ人たちがいた。信条を形成したのは、幕末の不平等条約、シベリア出兵・撤兵要求、人種差別にからむ欧米への怨念だった。テロをくりかえし暴走する行為を愛国的行為と主張した。
当時、左翼運動も起こりつつあったから、上層部は自らを防衛するためにも「愛国者」を必要とした。愛国的犯罪人は、内地からは追放されたが満州国では自由に泳ぎ回った。
さらに「愛国者」は、自由思想の弾圧をはじめた。中庸な思想はすべて姿を消した。
▽66
▽70 天皇の名における国民の思想統制(洗脳)の道具が勅語。兄弟が仲良くするのも、夫婦が仲良くするのも、すべてが「天壌無窮の皇運を扶翼する」ためだということがわかり、中学生や高校生のなかには「昔の天皇たちが兄弟喧嘩をして殺し合ったのは、一体なんだ」と言い出す者もいた。
式典は、恐怖政治の手段に使われた。陸軍大将の息子が、軍人勅諭を読み違えて割腹自殺し、美談として報道された。戦後の日本人が極端に国家嫌いになったのは、終戦前の体制が驚くほど前近代的あるいは権威主義的だったからだ。
▽77 日本の儒教と中国の儒教はちがう。日本の儒教は忠をもっとも大切な徳と考えた。中国の忠は、自分の良心に対して誠実であることを意味するが、日本では君主に誠実に仕えることを意味する。両者の関係は、同じバイブルから派生したカソリックとプロテスタントの関係に似ている。〓
中国儒教は文を強調し日本儒教は武を強調する。文は古典の知識、詩歌をつくる能力を尊重したが、武は科学振興をもたらした。このような日本儒教は、8世紀の危機意識の産物である。
中国も日本も官僚国家だったが、中国が官僚を試験制度で選んだのに対して、日本は進歩的な聖徳太子でさえ門閥制に固執した。中国から試験制度を導入しなかった。徳川幕府も同様だった。
▽79 日本の場合、皇帝の上に天があるのではなく、天皇は天そのもの。
ヘーゲル流に言えば、米英はすべての国民が人間それ自体として自由だと自覚している国であり、日本は「ひとり(天皇)が自由だと知るだけ」で、他はそのひとりの言うがままに行動する国だった。戦争は、前近代と近代の戦いだった。
▽85 1864年に4国艦隊が下関を砲撃した際、対岸の筑前の人たちは、戦いを長州対4カ国の戦いと見て、海辺で観戦していた。同様に、武士以外の長州の人たちは、長州武士対4カ国、と見て、自分たちを第3者の立場に置いた。したがって彼らは普遍主義的に行動した。傷ついた4カ国の兵たちも助けた。当時の日本はまだ民族国家を形成しておらず、国家意識が希薄だった。
しかし満州事変の頃にはすっかり変化し、国家主義に染まっていた。1864年と1931年の間のどこかに国家主義と普遍主義が適切に釣り合っている点があるはず。〓日露戦争のころが両者の均衡点だと思う。ステッセル将軍らに対する乃木将軍の処遇、第二艦隊の上村司令長官が敵兵を救助したことにあらわれる。
▽94 どの時代でも必ず大きな共同社会があり、人間はその共同社会の保全発展に貢献しなければならない。……軍事教練ももっと知的に教えられておれば、愉快な科目だったろう。「しかじかかような時に戦争をやれば、必ず負ける、あるいは必ず勝つ」というような討論を生徒に許しておけば、教練は本当の意味で国家を守るのに役だっていただろう。……国民の共同体への義務を明瞭にし、純自己主義教育に歯止めをかけて、集団のために働くという精神を高めるように学校教育を改革する必要がある。
▽99 国家の大きさを決定するのは、技術水準--その中でも武器と交通・通信手段の発達水準。
奈良時代から足利時代まで、武器と交通手段はほとんど変わらなかった。本州・四国・九州を領土とする国は、当時の交通手段にとっては大きすぎた。源氏は独立政権をつくり、中央政府は荘園の特権を認めざるを得なかった。武力を背景にした幕府も統制できなくなり、戦国時代になった。鉄砲という新武器によって統一された。しかし、交通手段は発達していないから、幕府は、全国を直接統治する中央政府はつくれなかった。武力と交通手段のバランスが逆転する明治時代までそれがつづいた。
幕末、欧米の技術を知るに及んで、幕府も諸藩も幕藩体制が時代遅れであると確認した。新技術を知ったことが、幕藩体制(上部構造)を陳腐化させ、日本にはじめて民族国家が形成された。王政復古の革命と言われたが、あくまでも技術の進歩に遅れをとらないように、上部構造を適応させた革命である。
〓戦闘用の技術(武器)と生活用の技術(交通・通信・生産など)
前者が進みすぎれば、領土は直接統治できないほど過大になり、国は分裂して、小さな共同社会(藩)が並立する。生活用技術が低ければ、生活上の諸目的を達成するための社会の規模は小さい。別の地域に住む人ととの交流は少ない。共同生活のための結合体である共同社会もまた小さい。 技術→人工結社→共同社会
後者が前者より進んでいる場合は、現在の国家の範囲を超えるような規模の活動範囲をもつ結社が多数設立される。信頼感は日常的になり、異なった共同社会間の混合結婚がおこなわれ、共同社会の規模は大きくなる。EECからEUへの発展はこう説明できる。〓
▽112 EAC 他メンバー国の経済搾取を防止するため、他国への経済進出には厳重な資格審査が必要。進出企業には、被雇用者に自社の株を所有させることを義務づける。新規被雇用者には株式取得の資金を貸与することを企業に義務づければ、他メンバー国の企業参入は民族資本の充実をもたらす。資金貸与は、EACの開発援助資金で一部を負担すればよい。
▽115
▽121 EAC発注プロジェクトが進行中は、日本は経済の行き詰まりを打破できる。奥地の未利用資源が経済資源に転換されるから、奥地住民がだれより利益を得る。開発が進むとともに、東アジア諸国の所得は均等化される。域内関税は撤廃され、域内貿易を大拡張される。物と人が激しく交流するようになると、文化も交流し、一様化しはじめる。……
▽130 社会主義の国は、ある段階で私経済間の競争を許さねばならず、国有企業をどう私有化するか、だれに売り渡すか。どのような企業を国家の企業として保有しつづけるかが大きな問題になる。
日本もそういう時代経験した。明治政府支援の諸会社(上からの資本主義)は順調に発展したが、しだいに経営が悪化した。賃金を高く設定したからだ。1880年ごろから官有物の払い下げがはじまり、84年に官営企業の払い下げがおこなわれた。払い下げを受けた民間人は一挙に金持ちになった。国営企業は技術的に優れており、資本設備も民間と比べると、非常に近代化されていた。払い下げを受けた人たちは、政府の近辺に常にたむろして、さらに甘い汁を得ようとした。こうして政府と財閥の結託が可能になった。政官財の複合体の原型は明治初期に払い下げを通じて形成された。
▽134 随になって、科挙を導入。中国皇帝は暴君どころか、世界にぬきんでた民主主義者だったと言える。
日本の上部構造は専制的だが、下部構造はマルクス的ではない。土地が広大で大河が流れているアジア的自然状況はないからだ。マルクス主義への反証となるのは、アジア的専制君主だったのは、日本の天皇だった、という事実だ。
日本は革命が絶対に起こらない国をつくろうとい思ったから、官邸や政府を貴族階級で固めようとした。徳川末期に至るまで、中国式の試験制度を導入しなかった。
▽135 科挙は、才能ある人がみなチャレンジしたからますます難関となった。こうして、科挙に合格したことが必ずしも役人として適正な人を選んだということでなくなった。不良役人がでるたびに科挙が批判され、哲人政治への要求が高まり、科挙合格者の受ける教育は、文人墨客になるものではあっても、政治家には役に立たないものになってしまった。
……科挙は中国を文人支配の国にした。武官よりも文官が高位に置かれた。19世紀後半には中国は武が文に牛耳られる国になってしまった。文官は科学に興味を持たないから、軍備が劣弱になっただけでなく、近代産業も根付かない国になってしまった。
一方日本は、武官支配の国であり、明治初期の文官のほとんどは旧士族だったため、近代産業は急速に発展した。
しかし現在では、日本の政治首脳部に理科出身者がほとんどおらず、中国共産党のトップは理科系の大学出身者で占められている。
▽139 明治以後、日本儒教の聖典ともいえる「教育勅語」が国民教育のバイブルになった。にもかかわらず天皇家の祭ごとは神道によっている。その結果、日本の天皇は、中国の皇帝と同様、昼間は儒教徒として振る舞い、夜は神道者(あるいは道家)として行動している。天皇および皇帝のこのような二重人格性は中国が共和国になるまで中日共通のことであった。
それ故、俗世の動きは儒教で説明されなければならない。上下の関係を貴び、祖先を貴ぶ。儒教は上位尊敬の心情に基づく教義である。(〓祖先を貴ぶのは儒教と関係なく、日本古来の祖先崇拝では? 庶民には儒教の影響よりも祖先崇拝の影響のほうが大きかったのでは?)
ウエーバーが言うように、儒教はプロテスタントに次ぎ合理的な宗教だが、上位者尊敬心が不合理をもたらしている。上位者が尊敬に値しない場合、儒教徒は目をつぶって最後まで沈黙を守るだろう。この行動様式がアジアでの不合理のもととなっている。
▽143 忠の概念を国家主義的に理解する日本儒教と、よりヒューマニスティックに理解する中国解釈の違いが、武器への態度を通じて、近代科学への興味の差を生じさせたことを私は明らかにした。その結果、日本に生じた資本主義は中央政府を中核とした上からの資本主義だった。中国の経済は華僑に見るような商売上手の横の経済であり、中央政府はそれを先導する力はもたなかった。
日本の侵略の前に、中国人は中国人同士の競争に打ち勝たねばならず、競争は貧富の格差をつくった。その上、富者ですら対外競争や戦争で隷従を強いられた。戦後中国では上からの経済を必要とした。こうして共産主義がイデオロギーとなった。「上からの資本主義」の代替物。共産主義の経済理論と中国儒教を比較すると、前者の上下関係は中国儒教のそれよりも日本儒教のそれによく似ている。
(〓華僑に感じる自由さと横のつながり。それでは産業は発展しなかった。だから「上」の力を必要とした、という説明は納得させられる)
▽158
▽177 EACの首都は大国にあってはならない。EUのベルギーがそうであるように。沖縄を独立させ、琉球国を復活させてEACの首府にする。
EACは建設共同体からはじまるから、まず必要なのは鉄道建設や運河建設、水力発電用のダム建設、中国海岸部や朝鮮・台湾に港湾がつくられrなければならない。リストのドイツ統合計画が、ドイツを農業国から工業国に大転換させたように、共同体はアジアを一変させるだろう。
▽183 共同体の共通語は、自然発生的に英語に落ちつくだろう。しかし、共同体の各国は、自国語のほかに共同体の他の言語の1つをマスターするように、学校教育を充実させる。
大学の教育レベルを均一化させる。卒業証書の質的水準の均一化。
▽195 パレートは人間の性格形成の基本要素は6つあると指摘。うちここで重要なのは2つ。第1は、新結合を発見しようとする本能で、第2は、全体への関心。
シュンペーターは、企業家は第1要素を持つ人と規定し、社会主義者は第2要素を多く持つ人と規定した。企業者が新結合をどんどん発見して裕福になると、人間が不平等になっていることが問題になり、社会主義的な人の発言月欲なり、社会主義政党が勝つようになる。
しかし、ここには(1)新結合を追求するが社会への関心を持っていない人がいるという仮定(=私企業)と、(2)新結合の追求と社会への関心が両立している人が存在しないという仮定。
第二の仮定が問題にしているタイプの人とは政治家である。だから、シュンペーターの第2の仮定は、政治家不在の仮定である。
しかし現実には社会のために新結合の導入をはかる人がいる。サッチャーはそういう人である。国有企業の民営化を社会主義を阻止する手段として導入した。彼女の出現によって、体制変換は方向を反転させ、社会主義から資本主義に逆進しはじめた。
体制変換論で「政治家」の導入。経済体制が変わる必要があるほど社会が行き詰まっているのなら、必ず政治的な新結合が模索され、政治活動、すなわち社会全体のために新結合を求めるという行為を行う人が現れる。
東アジア共同体を建設するのは「政治家」の仕事であり、こうして生じた上部構造の変化は、EACメンバー諸国の経済活動を刺激し、下部構造の変換をもたらす。
▽205 企業が拡大、成長する見込みがないときに終身雇用を約束し、年数が増えると高給を払うということは不可能。だが、EAC結成に向かって動きだすと、経済環境は一変し、日本的経営を可能にする。EACの経済は上からの資本主義の形をとるから、日本式経営は、社会主義といわれる中国や北朝鮮にもなじみやすいだろう。しかしやがては下からの資本主義に転化しなければならないし、建設共同体は市場共同体に転化するだろう。日本経済はこの段階に達したときにバブルが生じて日本式経営がつまずいた。EACもこの段階を乗り切れるよう、十分な準備をしなければならない。
▽207
▽211 日本は戦争に負けたとき、米軍は日本の教育を変えたが、大人の社会をこう変えろとは細かく指示しなかった。他方、大人の社会は旧来の道徳をかえなかった。……新世代は日本的道徳も知らず、アメリカ式道徳も学校で学んだ以上には知らなかった。その結果、「自由勝手に自分の利益を追求する」のが新しい生き方であるという他は、いかなる道徳的思慮もほとんどない人間になってしまった。教育の高さは、知識の量だけで判別されるようになってしまった。
さらに、「政治家」にすぐれたものがいなかったことが、日本の悲劇を一層深刻にした。
▽215 註 5代の孫である継体天皇が継いだ。当時の人口は300万人、平均10人の子がいたとすれば、30人に1人が5代の孫になる。なのにわざわざ福井から探しだされたということは、大和に内乱が起こっていないかぎり考えられない。しかも探し出されて天皇になったのは、武烈の前の仁賢も顕宗もそうだった。内乱が非常に長かったことを暗示している。
古田武彦「失われた九州王朝」〓
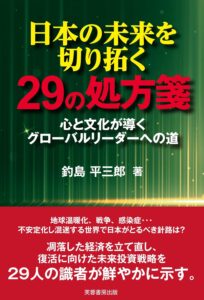

コメント