春秋社 200812
福岡正信氏は2008年8月に亡くなるまで、いかに手をかけず野菜や果物をつくるかを追求し、何十年も試行錯誤を繰り返した。その結果、不耕起直播の米麦連続栽培が生まれた。密柑山は、高木・ミカン・クローバー・野菜……が立体的に生育し、足元を鶏が走りまわる桃源郷のような風景になった。「自然農法」の畑や山は、自給自足にぴったりである。福岡はだれもが自給用の畑をもつべきだと主張し、その具体的な方法をこの本で紹介している。
さらに、科学的で効率的な大規模農業と流通機構が、実はまずくて栄養価の低い野菜や果物をつくり、消費者にも農家にも害であること、世界一効率的であるはずのアメリカの大農場が土を荒廃させ、農家を困窮させることになっている……といった実例を示す。
科学農法は、さまざまな技術を編み出した。農薬や化学肥料、除草剤は、それぞれ数%ずつの増産効果がある。だがそのすべてを適用しても、そのぶん飛躍的に生産量が増えるわけではない。それどころか逆効果さえももたらす。ひとつひとつの「知=技術」は正解でも、総合すると誤りとなる。だから福岡は、分別化された人間の知は無意味であり、キリストも釈迦もガンジーも実践した、すべての農の原点である「自然農法」にもどるしかない、と言う。
科学や人間の知を全面的に否定するが、科学的な検証を徹底的にくりかえし、自然農法の有効性を証明しつづけてきた。だから、「科学者は自然をわかる、利用できると思っている。しかし哲学的に宗教的に見た場合には、人間は自然を知ることはできない。人間は自分の頭で解釈した自然を自然と思っているにすぎない。自然を知っているのではない、と知ることが自然に接近する一歩である」という言葉も説得力をもつ。
分別化された「客観的な科学」の有効性は、科学の歴史の側からも、疑問視されつつある。観察者自身の存在が対象に影響を与えることが明らかになり、原因-結果という単線の論理では説明がつかない「複雑系」の理論が興隆するなど、福岡の科学否定を追いかけるような展開になっている。福岡の思想はある意味で科学の最先端を走っていたとも言える。
だが、客観科学の反省から生まれた相対主義をも福岡が否定していたことは忘れてはならないだろう。あらゆるものが相対的であるのではなく、「自然」という根本原理が存在すること、人間はそれを「知る」ことはできないが、草木や虫たちと接しながら感じること。百姓こそが、そうした「自然」ともっとも触れることのできる存在であることを繰り返し説いている。
=======抜粋・メモ=========
▽5 43 麦は反当たり10俵、部分的には12,3俵。農機具も肥料もいらない。稲のあるうちに麦をばらまいて、稲のわらをその上にふりまいただけ。
麦まきのときに、麦と籾を一緒にまいてしまう。
麦まきの前の10月上旬に刈り取る前の稲の中にクローバーを1反あたり500グラムばらまき、中旬に麦(早生の日の出種6-10キロ)をまく。下旬に稲を刈り取る。稲刈りの2週間前にまいておくと、稲をかるとき、クローバーも麦も2,3センチ以上にのびておればよい。稲わらを長いままふりまく。11月中旬から下旬に籾6-10キロを粘土団子にしてまく。そのあとで乾燥鶏糞をアールあたり20-40キロ散布すれば終わり。粘土団子は、粘土に籾をまぜ、水を入れて練り、金網からおしだして半日乾かしてから1センチ大の団子にするか、水で湿らせた籾に粘土の粉をふりかけながら回転させて団子をつくる。
5月麦刈り。脱穀がすめばその藁をふりまく。クローバーに稲苗が負けるときは、4,5日か1週間、田に水をためてクローバーを抑圧する。6,7月はあまり水をやらず、8月以降、時々走水をかける無滞水(1週間に一度くらいの走水でもよい)にして秋を迎える。
▽18 ミカンを放置したら、枝が混乱し、虫がつきみな枯れてしまった。「放任」と「自然」とはちがった。父が村長をしていて、奇行の息子がいては世間体も悪いし、憲兵の世話になるのもいやだから、高知の試験場へ。
▽26 自然農法は科学を否定するが、科学の批判にたえられる、科学を指導する農法でなければいけない。……大事なのは、まず不動の原点をつかむこと。どんな時代でも原点は常に同じ。自然農法はキリストの言葉にも、ガンジーの農法にも、トルストイの「イワンの馬鹿」にもでてくる。
▽30 各地の試験場で試してみて、この農法が収量が低いという成績がでている県はほとんどない。なのになぜ普及しないか。あらゆる点で専門化され、高度化されたため、全体的な把握ということがむずかしくなった。……消毒しないのにウンカがなぜ少ないか、と調べると、天敵が多かった。でも、土壌肥料などの学者は来ていないから、会議であんな作り方をやってみようと意見をだしても、試験場全体では「時期尚早」となる。
▽32 一枚の田圃をながめるのは、分科した科学者だけの頭ではだめだ。科学者と哲学者と宗教者、政治家も芸術家も集まって評議しないといけない。
科学者は自然をわかる、利用できると思っている。しかし哲学的に宗教的に見た場合には、人間は自然を知ることはできない。人間は自分の頭で解釈した自然を自然と思っているにすぎない。「自然を知っているのではない」と知ることが自然に接近する一歩である。
▽37 田圃にかまどの灰をふるだけで、クモの糸が切れ、クモがいなくなってしまった。灰でさえもそうだから、農薬はなおさら。ウンカの天敵であるクモを殺すだけでなくて、どんなに自然のドラマを破壊するかに気づかなきゃいけない。薬剤散布は病虫学者の問題ではなくて、哲学や宗教、芸術家の問題でもある。(〓大きな目でみないととらえられない)
▽42
▽47
▽51 耕耘した所に直播したほうが発芽しやすいが、雨にふられると泥田になり、田に入れなくなり、直播を中止しなければならない。不耕起はその点安全だが、雀やネズミ、ナメクジに芽を食われる。粘土団子がひとつの解決法になった。
耕さないと雑草の種類が単純化し、雑草、とくにヒエなどが少なくなった。前作のある間に次の作物の種を播き、時間的な隙間をあけない。作物の足下に緑肥(クローバーか馬ごやし)を播いて雑草の種をきる。
▽55 化学肥料 田にアヒルを放し飼い。中耕、除草して、その上、糞で肥料がいらない。わら還元、緑肥、水藻、アヒルや魚の放し飼いがうまくやれたら、完全無肥料でゆける。三大病害といわれる稲熱病や菌核病、白葉病などは、弱い品種を使わない、窒素過多にしない、灌水量を減らして根を健全につくるだけで、消毒剤など廃止できる。害虫も、水管理次第で、夏ウンカや秋ウンカなども制御できる。
▽56 消毒の農薬全廃による収量減は5%くらいとされている。水を使うのを抑えさえしたら、その年からでも1割以上の減産になることはない。
今、農薬のなかで一番廃止しにくいのは除草剤。田を鋤くのも、水を張るのも、田植えそのものも、主な目的は除草対策だった。緑肥田に生わらと鶏糞をまいて湛水すると、酸酵現象がおこり、若い雑草を枯らし、夏草の発生をぴたりとおさえる。
▽69 理想型の稲 その格好さえ示せば、百姓だったら、水をやったらできないとか、肥料をやっていないな、とか、すぐわかる。目標の稲型をそれぞれの地帯でどう作るかを考えればいい。
▽73 ミカン 天敵は殺してはならない。モリシマアカシヤなどの木を植えると、新芽にアリマキがつき、これを食べてテントウムシが繁殖し、アリマキを食い尽くすと、ミカンの木におりて、ヤノネカイガラ虫などを食い……天敵保護樹。モリシマアカシヤは、樹皮からタンニンがとれ、木材は堅く、花は蜂蜜の源になり、葉は飼料になり、根には根瘤菌があって肥料木になり、防虫木にもなる。
▽75 理想の樹型 自然型は主幹型では。杉の木のように、根から1本仕立て。無剪定にするにはこの自然型がいいし、病虫害も少ない
▽79 モリシマアカシヤ、寒いところではフサアカシア。日本にある外来樹でこれほど成長率の高いものはない。7年もすればよう伐らんまでに成長する。根元の皮をはいで枯らす。1反に5本から10本植えたら深層の土地改良ができる。クローバーでは、表面の3,40センチの黒土はできるが、それ以下の土の改良はできない。そこで樹木を利用し、さらにルーサンを導入した。1カ月か2カ月で根が1メートルか2メートルまで深く入って土壌改良に役立つ。クローバーとルーサンをまぜまきにするのが、果樹園の土壌管理では一番いい。一方、モリシマは、防風・防虫の役目もある。高い樹木があり、ミカンがあり、その下草にルーサンやクローバーがあるのが一番よい。クローバーを一度播いておけば、7,8年は雑草が全くなくなる。クローバーが弱って、雑草が再び生えだしたら、新しい種か野菜まぜまきをする。自然農園の果樹園は、ブドウのツルがからんだ肥料木がニョキニョキ立ち、果樹の下に緑肥や野草のような野菜が茂り、鶏が遊ぶというような、立体的な農園になる。
▽82 戦時中、多収穫をはかるため、肥料部は肥料を設計し、2割増を果たし、病虫害対策で農薬を使用して2割増、品種改良で2割増ということになった。ところが、あわせてもそんなに増えない。それぞれウソは言ってないが、正しいことを寄せ集めた結果はウソになる。
▽92 あらゆる面がいっぺんに解決されなければいけない。全体的な問題。たとえば瀬戸内海の汚染問題は、生産者も消費者も漁業者も農民も、すべての人の意識変革がなされなければ公害問題はとまらない。
▽95 自動車の排ガスを規制して、新しいエンジンをつくっても、次の大きな禍根の原因をつくっているだけ。公害を防ぐため、いろいろやればやるほど、問題はますます内部化し、深刻化する。……人間は何一つ、根源・原点というものをつかんでいるのではない、知っているのではない、ということからおきる。
▽98 共同選果場 選別するため、何百メートルもころげるから、打撲傷ができ汚れる。だから防腐剤や着色剤がふきつけられる。最後にワックス仕上げで表面にロウがひかれる。外観のよいものを買おうというわずかな気持が百姓をここまで追い込み、苦しめている。
▽101 新鮮でないのに、見かけだけ新鮮にして売られる。むしろしなびているほうがいい。しなびているということは、消費エネルギーを最小限にしている状態だから、味は落ちなくてすんでいるから。見かけの鮮度を保ち、湿気を保つと、野菜や果物は自己消費するから栄養がなくなり味も落ちる。
大量に作り、流通させるほど、生産者は泣かされ、消費者は高くて価値のないものを食べる結果になる。流通機構の改革の根本的原点を見失っている。
▽109 ナズナがダイコンの先祖みたいなものだが、ナズナはなごむという言葉と関係がある。ワラビやゼンマイ、ナズナなんて食ってりゃ人間もおだやかになる。昆虫類で食べられないものはない。戦争中、調べたら、シラミはすりつぶして麦飯を一緒に食うとてんかんの薬になるとか、ノミはしもやけの薬になるとか、うじ虫も、蚕も珍味だし。蛾もつきまぜて、羽の鱗粉を落として食べるとうまい。
ニラやニンニク、タマネギなどの百合科の植物のなかでも、一番野草に近いノビルとかニラが栄養が高い。改良されたネギやタマネギは栄養価は低いのに、好まれてしまっている。乳でも、山羊のほうが牛よりも価値が高い。
魚も川魚のほうが身体によい。その次は浅海の魚で、一番悪いのが深海や遠海の魚。身土不二。
▽117 40年ほど前には、アメリカからパン用の小麦を入れるのは不都合だから、日本で小麦を作ろうという運動を国ぐるみでやった。だが、アメリカの小麦は収穫時期が遅く、梅雨に入るから不安定。日本の裸麦や大麦、めん用の小麦を作っていた百姓にアメリカ小麦を押しつけた。ところがどんどん輸入されはじめる、日本の小麦が割高になってくると、「麦作りをやめろ」と農林省は言い始める。もちろん、農家は喜んでやめた。現在、山陽筋から東海道筋に麦がないのは、40年前に無理に作らせたことが原因。ところが四国に渡ると、香川や愛媛には麦が残っている。裸麦で、梅雨前に刈れるから安定しているから。
日本の麦は高くつく、ということで、麦作りを廃止させようとしてきた。ところが10年たつと、自給用の麦を作れと言い始め、米はいらない、と言う。日本の農政は、日本の作物を追い出し、百姓を田圃から追い出す政策をとってきた。
また、全人口の1割だけを農民にしておいて、それ以上のものは切るという方針だ。私は、国民皆農というのが理想だと思う。日本の農地は、ちょうど面積が1人1反ずつある。5人家族なら5反。一反で、家建てて野菜つくって米作れば、5,6人の家族が食える。自然農法で日曜日のレジャーとして農作して生活の基盤を作っておいて、あとはお好きなように、というのが私の提案。 玄米や麦飯がいやなら、日本でもっとも作りやすい裸麦で作った麦飯やパンもよい。
▽122
▽131 昔は百姓がどんなに楽な農業をするかに役立つ研究をするのが技術者のつとめだった。今は、人間の欲望に追従した研究をして、それに向かって百姓を叱咤勉励するかっこうになっている。苦農。
米と麦と野菜を食っておれば生きられるということになってきたら、日本の農業も楽になる。ふつうの人でもやれるようになる。食糧問題も解決してしまう。役人や農業技術者も10分の1に減らすことができる。
▽135 百姓が大経営をするほど、物心両面に追い回され、詩や歌をひねるひまなどなくなってしまう。昔の5反百姓は、年末がきて正月があけたら、1,2、3月はウサギ狩りなんかにばかりでかけておった。正月というのが、昔は3カ月あった。それが2カ月、1カ月となり、15日で注連飾りをのけるようになったのはつい近年のこと。さらに、15日も廃止され、このごろは3日間になってしまった。その3日も農村では丸休みすることがほとんどなくなってきた。
ムラの小さな神社の拝殿を掃除しているとそこの額に20人30人の俳句がある。それだけの余裕があった。
▽145 自然農法というのは、農業を指導する父でもあるし、迎える母でもある。人間のあらゆるものを包括したところの原点の農法。現代科学文明のいきづまりを打開する出発点としての基盤にまでもっていきたい。
▽152
▽160 人間が見た生と死の現象は、近視眼的視野からの一時的認識でしかない。……人間は日々の生を生として喜ばず、死の直前になってはじめて生に気づいて生に執着し、生への執念が、死の恐怖となってあわてふためいたりする。あるいは過去や死後の生死のことばかりを気にして、今日生きていることを忘れてぼんやり一生を過ごしてしまう。
▽166
▽179 東海道の車窓 かつて整然とした青い麦、レンゲ、菜の花の咲く風景はどこにもない。雨にぬれる稲わら、散乱するわら。わらの始末がつかないことは、米麦づくりの技術が混乱している証拠。
▽213 一昔前のこのへんの百姓の食事は、麦飯に醤油のもろみ、漬物でけっこうおいしくて、月一回の野菜の煮物がついた小豆飯は最高の御馳走だった。西洋の栄養学は、人間としての目標がない。自然に近づけようという努力が見られない。人知を過信するため、反自然的孤立化人間をつくることになる。さらに、人間が精神的動物であることが忘れられている。さらい、部分的な把握に終始していて、とうてい全体的把握とはなりえない。
▽235 アメリカ 褐色の草 きつねのしっぽばかり。畑に土を入れて、大型機械で年に4,5回もこねくるものだから、壁土のようになり、亀裂ができている。……牧畜をやれば土地は肥えるはずと言うが、実際はどこもやせてしまう。雑草が単純化するから。スプリンクラーで水をまいて草を生やし、化学肥料で太らし、それを世界中に飼料として輸出する。荒れ果てて畜産農家が脱落したところへ、今度は果樹農家が入ってくる。化学肥料とスプリンクラーで。水が蒸発するとき、地中の塩分が吸い上げられ、地表に塩がたまり、塩田のようになってしまう。
アメリカの農業は、単一の作物ばかりつくっている。自家用の野菜はほとんど作らない。自給自足じゃないから生活は苦しい。肉食のために農業がはじまって、それがアメリカの大地を狂わせてしまった。
終戦後、パン用の小麦は、病気に弱く、収穫期に雨がふるとみな腐ってしまう




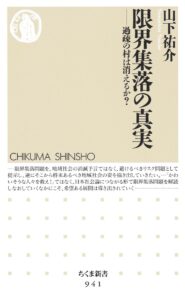
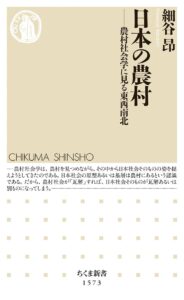


コメント