日本では儒教が、忠君愛国を正当化し国内統一を果たす役割を果たした。武士階級を大学卒業生という知識階級に発展的に解消させたことが、封建主義を資本主義に転換させることにつながった。政治家も官僚も国営企業の首脳も国会議員も学者も……武士出身で占められ、明治の日本は武士国家だった。
忠君愛国の日本型儒教が「上からの資本主義」を形成した。次の段階の「下型」に移行するには日本型から中国型儒教への切り替えが必要だが、日本的儒教精神を高揚させればよい、と考えることで軍国主義を招き、統制経済の道を歩んでしまった
戦前戦中の「上から」型で養成された優秀な官僚によって戦後の復興を果たし、石油危機によって政府の経済干渉は支持されつづけ、80年代中期まで「上からの資本主義」が活力を保ちつづけた。
戦後、アメリカ式教育への転換によって、国家主義的な日本型儒教とともに、個人主義的な中国型儒教をも棄ててしまった。そこに戦後日本の不幸があったととらえる。
アメリカ型教育で、西欧の精神を理解しない先生に教えられた子どもは、自己中心主義で記憶重視で多数になびくという西欧人としても落第生に育った。カイシャでは戦前生まれの経営陣による儒教的社内教育をおこなったが、1990年までには大半が戦後教育を受けた層になった。戦後の教育改革は50年遅れで効果をあらわし、日本社会から「武士」を消し去った。
江戸時代の経済は元禄時代がピークで、明治まで回復することがなかった。江戸時代後半は、勤勉で誠実だった日本人のエートスは死滅しており、刹那的快楽にふけった。まさに90年代の日本とそっくりだという。
下からの資本主義を進めるエートスを提供できるのは儒教だが、宗教教育が禁じられ、世俗的労働倫理がぼろぼろになった現代の日本人は「資本主義の精神」のための倫理的背景を備えていない。だから、日本は現在の危機から立ち直れないと予想する。
==========抜粋・メモ==========
▽5 「上からの資本主義」を形成する。上型から下型に移行する際には、第二の宗教革命、日本型から中国型儒教への切り替えを唱道するべきだった。そうすれば、昭和の軍国主義はおこらなかった。
日本的儒教精神=日本精神で成功したのだからこれを高揚させればよい、と考えることで、軍国主義になり、下からの資本主義を選べなくなり、統制経済、計画経済の道を追求し……
戦後は戦後で、アメリカ式の教育に切り替えることで、国家主義的な日本型儒教とともに、個人主義的で人道主義的な中国型儒教をも棄ててしまった。
日本型儒教を持つ戦前派とアメリカ式教育を受けた戦後派からなる二層社会になった。
▽29 ウェーバーは、儒教はプロテスタントと同様、合理的な宗教と考えるが、両者には対照的な違いが存在すると指摘した。儒教における現世への適応に対立したのは、ピュリタニズムにあっては現世の合理的改造という任務であった。
▽32 カソリックとプロテスタントの違い 僧院内部に限られたものであった禁欲主義を、外部の俗世に自由に公開させた宗教改革。その後、人々は禁欲的かつ合理的に行動しはじめた。
▽36 「教育勅語」が日本的儒教を明確に規定。こういう倫理的自覚が、近代日本をつくりあげた動因であったが……
▽39 戦後のアメリカ型教育で、西欧の精神を理解しない先生に教えられた子どもは西欧人としても落第生-自己中心主義で、記憶重視でなぜそうなるか尋ねることがなく、社会活動は多数に常に与する……-に育った。一方カイシャでは、儒教的社内教育をおこなった。……だが1990年までには50歳以下は全員、戦後教育を受けた層になった。儒教教育の効果も90年代にはあがらなくなった。日本社会のエートスは激変した。教育改革は50年遅れで効果をあらわした。
▽69 明治政府の経済 武器・艦船・機械などを生産する上層グループ企業には、政府が支援。有効需要。この需要に融資するため、地主や農家に重税を課した。農業所得が独立企業の労働者の生活水準になっていたため、低賃金だった。一方、政府部門の従業員は高賃金。下層部分は競争的だったが、上層部分のとくにホワイトカラーは終身雇用。
▽74 1700年にすでに1801年のイギリスと同じ段階まで都市化が進んでいたが、その後、逆行する。
▽78 17世紀後半、武士に仕える使用人は供給不足に。賃金上昇でインフレ。武士部門が縮小し、武士の購買力が弱まることで、都市の繁栄は下り坂となる。
▽84 町商人と農村商人の対決
▽87 各藩と幕府はそれぞれ新形式の機械設備を導入したが、300の藩に分裂していては、西欧に抵抗できない。ドイツ統一の3年前に1868年に日本は統一された。維新を生き延びた生産工場は、明治初期には国有工場に。
明治の政治家と財閥の新しい連合は、封建大名と江戸初期100年を通じて支配的であった特権商人の結びつきが復活したものだった。……地方部門は生産性の下の層を受け持つことになった。維新は、武士階級が主導権を握り、城下町経済が繁栄していた1680-90年の段階に逆戻りさせる一種の「復古」だった。
▽92 大工場/小工場 の二重構造は、徳川時代の 特権商人/地方商人 の二重構造に紀元をさかのぼれる。1980年代の中期まで、この症状に手を打つことができないままだった。
▽100 武士の占める割合は政治家および政府の役人は77%。国営企業の首脳及び上級経営者は86%。国会議員は41%。科学、工学、農学の学者は75%……明治の日本は武士国家だった。
▽104 GHQによる戦後教育は、日本社会から武士を消し去るための教育だった。……儒教的行動は知らず、極めて不完全な西欧式教育を受けたから、西欧的なエートスも理解していない。西欧人は物質的であり快楽主義的であり、どん欲であると信じるようになった。
経済の崩壊よりもモラルの激変が、日本に先にやってきた。
▽111 財閥解体。各企業は自社株を所有することを禁じられたから、株式の持ち合いをするようになる。カイシャは財閥家族から切り離され、財閥家族からすら指図されない経営陣は安泰となった。財閥家族追放の結果、経営者の会社支配が実現した。メインバンクもがそれを支える。
▽113 ところが、公開市場で株式を時価で発行すれば、簡単に低コストで資本が集まる。メインバンクの役割も減る。義理人情ではなく市場原理・競争原理が幅をきかせるようになる。
▽116 株の持ち合いの確立という組織イノベーションの基礎の上に、70年代から89年における繁栄の道を開いた。イノベーションを可能にしたのは、日本の高等教育。明治維新後に中央政府を形成した「武士」グループを、東京大学の卒業生が継承した。大学エリートによる支配は、富裕家族らによる金権政治的な資本主義よりは、生産的な社会だろう。80年代半ばまではそうだった。
▽145 ケインズの「一般理論」出版以前に、ケインズ主義政策を実行していたのは高橋是清。それによって日本は不況から急回復した。が、これらの支出拡大政策は戦争拡大を準備していた軍関係者を助けた。ケインズ主義政策によるインフレに加えて、戦時インフレが追加されて、法外なインフレがおきた。これに気づき、彼は軍事支出増加を最少にするべく態度を変えたため、殺害された。
彼の死後、「ケインズ主義」の悪用が継続され、軍部の財政需要を受け入れつづける。
▽149 政府は1943年、軍需会社と都市銀行間の「結婚」を斡旋しはじめた。軍需会社にわりあてられた銀行が、会社が必要とする資金を供給する責任をとった。銀行と製造会社との組み合わせは戦後もつづき、「メインバンク」システムとなった。日本の会社は、保護者役の銀行によって、金融面での面倒をみてもらえるようになった。
▽151 ……日本銀行は政府からの独立性を失った。政府発行の国債引受人になり、通貨量は急速に拡大する。……
▽187 士農工商 商家は奉公人制度を敷いていた。商家の主人と奉公人の関係は生涯つづくものだった。終身雇用だった。
古い商人家族の一部が大財閥に成長した。
明治はじめの国営企業では、経営者と従業員との関係は武士の家族のものであって、厳格な命令と服従の関係だった。
官僚主義的および家父長的という2タイプの終身雇用が大会社(軍需会社と財閥会社の双方)を通じて育成された。
▽199 財閥解体が、日本の会社が会社法タイプ(株主こそが会社そのもの)から共同体タイプ(労働者と管理職社員は移動しないで、株主が始終動く)へ向かう転化の根源である。社長らは解雇され、会社の官僚構造の頂点にいた人を新しい社長を選出した。日本の実業家たちのほとんど全員が元会社官僚である。
▽202
▽275 イギリス ヨーク朝時代の農地の囲い込みで農業が大規模化し、牧羊業が成長。イギリスのジェントリーは製造業の原料補給のための産業として農業を育てた。ジェントリーの次男三男は商人の徒弟となり、商人はカネが貯まると土地を買い、農業をした。農業と商業が一体となり、ヘンリー7世の重商主義の基礎となった。しかし、絶対王政が確立された段階では、上からの資本主義の色彩も濃厚になる。
ジェームス1世が王権神授説を使ったとき、人民はコモン・ローを主張し、議会派と王党派が衝突する。=清教徒革命 は、下からの資本主義と上からの資本主義の戦いだった。
▽279 農村における地主ジェントリーの支配体制が崩れ、イギリスに下からの資本主義、競争的資本主義の時代が実現した。アメリカも、大西洋岸の工業地帯建設はイギリスに多くを負っており(上からの資本主義)、そういう関係がなければアメリカは純粋農業国に終わっていただろう。
▽282 日本の大陸進出は国際的孤立をもたらし、下からの企業の多くは淘汰され、上からの資本主義の時代に。戦争中に日本は優秀な経済行政官を育成できた。戦後も、上からの資本主義であるような経済状態。戦争中の若手経済官僚と主要企業の若手重役が、戦後の日本経済体制をつくった。
戦後も、政府は経済に関与しつづけた。復興が事実上終わった1960年代末にこういう体制は終わるはずだったが、石油危機のために、政府の経済干渉は支持されつづけ、80年代中期まで上からの資本主義は活力を保ち続けた。
「上からの資本主義は下からのそれよりも成長率が高い」が経験的になりたつように思われる。
▽290 明治 1872年に義務教育制度。82年にベルギー国立銀行を手本にして、日本銀行を設立。これらの業績は、優秀な官僚なしには不可能だった。日本の行政制度は儒教の影響のおかげで徳川時代でさえ、すでに極めて官僚的だった。
戦前の日本の制度は、関東大震災の壊滅的結果に極めて見事に対処した。
武士は、明治になって職を失った。一時金の補償を受け、それで新事業をはじめた。当時では最高の教育を受けていた武士が質の高い人的資本を必要としていた実業界に送り込まれた。
▽293 国営企業の私営化・払い下げ。世界で最初に成功した私営化と強調するにあたいする。明治の武士官僚の現実主義を示す。
▽295 1920年代と1930年代には、ソビエトもナチスも国家社会主義の形をとった。ナショナリズムの全盛期には、政治の最も重要な原則は経済を民族国家の意志に服従させることだった。だから日本でも、西南の役で敗北したグループからはじまった右翼は、ブルジョアや貴族階級で極めて批判的であった。北一輝は、朝鮮併合を是認しているが、朝鮮の人々についての見解は当時のいかなる政治家よりもはるかに進歩的、友好的だった。現在(1939年)から20年後には、完全な政治的権利が朝鮮人に与えられるべきであり、私有財産や土地および企業の私的所有権に対する限度は朝鮮人と日本人は同じであるべきである……
▽300 高橋是清は、農民や労働者を救う目的で支出政策を実施した。その金を捻出するために陸海軍の規模縮小を望んだ。それゆえに226の標的の1人になった。だが彼の政策は、悪用される。軍部は十分な金を得た。
▽301 戦争中、企画院、アジア開発局、軍需省、大東亜省などから多くの有能な経済官僚がでてきた。彼らは戦後の産業復興に大いに貢献した。
▽309 「日本株式会社」の強さは、石油危機のときに確認された。代々の首相は主要な実業家と緊密な関係を保った。定期的な会合をもって議論した。イノベーションのための国家的プロジェクト選出の合意が形成された。メインバンクもそれに応じて動いた。
シュンペーターのイノベーション理論の全国的な適用だった。
▽315 徳川時代に、日本人は儒教から官僚的民主主義を学び、1980年代半ばまでは、官僚的民主主義と特徴づけられる。国民は金権政治を好まなかった。この気風は、上からの資本主義によく適合していた。
しかしこの経済は、急速な崩壊の兆しを示している。日本における上からの資本主義から下からのそれへの転換は、イギリスで起こったと同じように容易で円滑ではない。
▽321 日本は、上からの資本主義から下からの資本主義への移行に3度つまづいた。
1回目は、徳川時代。各藩は政(=大名・家老など)官(中級武士)財(物納された年貢米などを売りさばく中下級武士と御用商人)の三角形を構成し、元禄時代末まで繁栄した。が、その後、緊縮財政をとらざるをえなくなり、城下町の町人に帰農をすすめる。彼らは農業を農業を資本主義的に運営し、村落産業をおこした。これが日本の下からの資本主義の源泉をなすが、大商人が三角形に属していたため十分な資金がまわらなかったため、十分に発展しなかった。
2回目の困難は、「昭和維新」。右翼傾向の強化を象徴し、資本主義の拒否を主張した。真に競争的な資本主義を実現することなく、日本をファシズムに方向転換させた。
戦後、1980年代後半から90年代はじめ。バブル期に3度目のつまずきをした。
▽336 1980年代はじめまでは、日本は政治家・官僚・財界人が互いに協力してよく働いた国として知られている。だが、バブルがはじけた1990年以来、3つの集団の団結は崩れた。90年代前半には、官僚はすべて戦後教育を受けた人だが、企業トップ経営者はまだ戦前世代か過渡期世代であり、政界にはまだ時代遅れの考え方をする人たちが残っていた。これらが協調するのは不可能であることがわかる。
▽340 80年代の政治家、たとえば中曽根のエートスは、儒教の線に沿っているといえる。教育勅語は、明朝の洪武帝の儒教の「六諭」を基礎とした。
▽348 ソフトのプログラミングが進んでいる諸国の金融組織は、日本の組織に対して優位だったから、金融市場を開放することは日本の組織を不利な立場においた。さらに、子会社は、必要額の資金を新株発行により、証券取引所を通じて取得できるから、親会社が子会社をその統制下におくのが困難になった。こうして、金融革命は、日本の「系列」制度の崩壊をも引き起こした。
戦後に教育された人たちは個人主義や自由主義を信じるが、満足な教育を受けていない。縁故びいきを受け入れ、おどしに容易に屈する。国家資本主義を崩壊するのには貢献したが、下からの資本主義の発生に不可欠だった人々の倫理的強さを今日の日本人に見ることはできない。
▽351 日本の今は江戸時代後半と共通点がある。経済は元禄時代がピークで、明治まで回復することがなかった。長期間のあいだ、勤勉で誠実だった日本人のエートスは死滅しており、刹那的快楽にふけった。
……戦後の新制教育は、われわれが今必要とするタイプの人をつくりだすことに失敗した。
▽356 新古典派的競争システムを進めるエートスを供与できるのは、プロテスタント。東洋では儒教だろう。学校で宗教教育をすることが禁止され、新古典派的競争に駆り立てる世俗的労働倫理の精神的基礎がむしばまれた。それゆえ現代の日本人は「資本主義の精神」のための適切な倫理的背景を備えていない。したがって、日本は現在の危機から立ち直れないだろう。
▽360 戦後は、国内の諸階層の利益を得るためにたたかうばかり。政治の中央舞台がますます村落や町の地方舞台に似通ってくるにつれ、国民は政治への関心を失ってしまった。
一報、西欧諸国では、ニューディールや、イギリスの福祉国家、ヨーロッパ共同市場、サッチャーの私企業化政策など、多くの成功した政治的イノベーションがあった。
日本は、政治家の考えることは、党内の派閥再編成のようなおよそイノベーションにつながらに小粒の改変だけである。
▽369 バブルがはじけ、成長の追い風は停止した。日本の政治かと官僚の誰かの指令に従うという態度は、戦前・戦中の軍部独裁時代に学び取ったものだ。彼らはその態度をアメリカ政府に対して示しつづけた。日本は卑屈なまでに忠実な敗戦国であり、そのことが日本が成功した最大の理由のひとつである。しかし、風もなく推進力もない状態では、日本は忠実に振る舞うための相手を持っていないことを知った。日本のリーダーたちがこんなにもひ弱く、自信をなくしているかぎり、日本の苦悩はつづきそうだ。生活水準は高いが、活動力がなく、国際的に重要でない国。これが21世紀半ばにおける私の日本のイメージである。
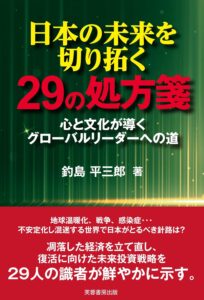

コメント