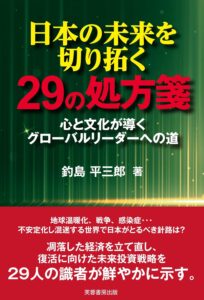岩波新書 20060610
①会社の仕事の一環で書いた記事を大幅にリライトして本にする場合、著作権はどうなるか。
②講演会できいた話をネットにだした場合、著作権にふれてしまうのか。
③ネット上に自分がだした文章をそのままほかにコピーされ公開されつづけた場合、著作権上はどうなるのか。
③引用はどの程度が許されるのか。
そんな疑問がここ数年、少しずつたまってきて、著作権問題を身近に感じるようになりつつあった。
せめてその基本の基本くらいは勉強しておこうと思って手に取った。
結論的には ①はわからなかった。②③④についてはなるほど、と思った。
著作権の法律の歴史の流れを知るうえではぴったりだ。
具体的な解決法を見つけるための本ではないようだ。
---------抜粋・要約-----------
▽無断でコピーされない権利 ……また、「生の固定されていない著作物」を「固定する」つまり、録音、録画、速記などをするということも「コピー」に該当する。「メールで送信する」という行為は「コピーする」ことだ。
▽「雇い主」が「著作者」となる場合 会社などの「発意」に基づく著作物(「会社という組織の一員として仕事上発意した」のであれば会社の発意となる)、「職務の一環として」つくった著作物、「会社側の名義」で公表される著作物。
▽権利者に無断でレコードを輸入・輸出してはいけない、とか、無断で外国から輸入されたレコードを売ってはいけない、などといった権利を「著作権」に加えようという動き。消費者の不利益を招く。反対の国も多い。
▽レンタルコミック店=貸与権 権利者に無断でレンタルできない、という貸与権ができたが、例外を設けられた。「書籍・雑誌の貸与」は「当分の間」。貸本屋への配慮だった。
▽〓学校の校歌 著作権契約が不備なために「校歌集」をつくれないケース。校歌はすべての権利者や相続人をさがしだして了承を得ないと掲載できない。
▽アメリカでは、学校のパソコンをネットに接続するときは、すべての保護者と、子どもたちの「肖像権」「著作権」について契約書を交わすのが常識になっている。
▽途上国は、いわゆるフォークロアを保護すべきだと主張する。民族特有の絵画、彫刻、……木工、歌、音楽、踊り……が含まれる。先進国の企業によってTシャツのデザインやレコードなどに使われているが、国際著作権ルールでは、古くからあって、誰がつくったかわからないため保護対象とはされていない。たとえば「コンドルは飛んでいく」は、もともとペルー民謡なのにかかわらず、サイモンとガーファンクルは、利用料を支払っていない。
▽