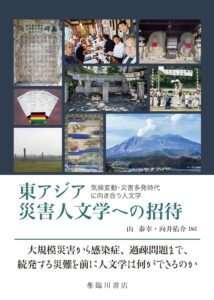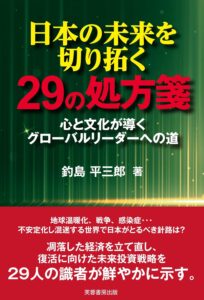文理閣 20090118
自由主義が不況によって破綻することで、経済における政府の役割を重視するケインズ主義が生まれる。税金を投じることで景気対策をするというシステムが機能するには、大量生産・大量消費のシステムが不可欠だった。それが第二次大戦後の福祉国家の成立の背景となった。
ところが、70年代に入ると福祉国家が行き詰まり、主要国の財政赤字は深刻化する。とりわけ、不況なのに物価は上がるというスタグフレーションは、ケインズ主義では想定されていなかった。さらに、南北間の格差はケインズ主義ではまったく修正できなかった。
そこで不死鳥のように脚光を浴びたのが、政府が口を挟まず、市場にさえまかせておけばよい、という新自由主義だった。サッチャーやレーガンがその典型だった。(レーガンは軍事支出というケインズ主義的な面ももっていたが)
その結果、インフレは抑制されたが、貧富の差が拡大し、むしろ社会的支出が増大する傾向さえ生み出した。
国家の役割を重視したケインズ主義も、市場原理主義も、貧困を解消し、真の福祉社会を世界にもたらすために有効に機能しなかった。
ではどうしたらいいのか?
ノーベル賞を獲得したインドの経済学者アルマティア=センはその解の一部を提起しているという。
功利主義的な経済学は最大多数の最大幸福という形で、主観的な幸福感(効用)に依存していた。逆に、ロールズたちの厚生経済では、客観的な「財」などに依存した。
センは、財と効用の間にある人間の「機能=潜在能力」に着目(財→機能→効用)する。潜在能力とは、人の福祉を実現する自由度(福祉的自由)であり、栄養や健康、教育、自尊心をもって地域に参加できる機能、社会的便宜、政治的自由……など多彩なものを含む。
人間は経済的に合理的に行動するエコノミックアニマル(功利主義的な人間)ではなく、財さえあれば幸せになれる機械のような存在でもない。幸福をもとめる潜在能力(福祉的自由)にこそ人間の幸福の基礎があるという考え方である。
このほか、日本の福祉や労働法制の変遷と、その背景も分析している。どういう世界的な経済の流れから日本の民営化路線が生まれたか。派遣労働などの日本流貧困が、国際法のレベルといかにずれているか、という指摘も興味深かった。
=============覚え書き・抜粋==============
▽13 アダム・スミス 自由主義だが、市場万能主義の主張者ではない。防衛や安全とともに、有用ではあるが個人に利潤をもたらさぬ公共事業を国家の義務と認め、それらが社会の商業を助長し、公共の福祉(一般的効用)を増大させる点では、支出を認めた。マニュファクチュア分業時代、分業に基づく生産システムを評価する一方、労働貧民の人間的能力をゆがめると認識し、その治癒策として国民教育の意義を認めた。
後継者 リカード マルサス
▽17 産業革命 ドイツでは新旧中産階級を含む国民が貧困化し、社会主義も伸長する。ビスマルクは、国内秩序と国民統合をはかるため「社会主義取締法」と「社会保険法」を軸としたアメとムチの政策をとる。
社会保険をささえたのは、新歴史学派の経済学者。社会政策の名による社会改良を提唱。有機体としての国民経済観。全体的な利益の調整や干渉を当然とする国家観。
産業平和と生産性向上、労働者問題に対する妥協として、自由主義原理よりも家父長制的な社会国家の理念からの社会政策の導入だった。
▽21 第一次大戦後、資本主義は機能不全に陥り大量失業をひきおこす。→ケインズ 有効需要の創出と完全雇用のための公共事業。
▽ケインズ主義的福祉国家とアメリカ的生活様式
▽32 アメリカ的な生産様式や生活様式は、フォード主義的な生産・蓄積様式--大量生産・大量消費を代表する自動車産業とともに生みだされた。
▽39 1970年代のアメリカの社会的支出の増大の背景には、ベトナム戦争介入と公民権運動の昂揚も。日本は高度成長下の公共投資への重点化と環境問題の激化……ようやく福祉元年。
欧米諸国はいずれも、社会的支出を増大させた。その背景に、戦後民主主義の一般的条件の拡がりがあった。
その一方で財政危機を深め、74年のフランス、76年のイタリアの黒字を最後に、主要国は年々膨大な財政赤字を累積しつづけた。
1978年、アメリカのカリフォルニア州で、肥大化した財政に対して、納税者主権からの減税要求として、住民投票が成立した。ケインズ主義的福祉国家の流れの転換点を示す象徴。
▽41 ケインズ主義は、「豊かな社会の中の貧困というパラドクス」両大戦間の遊休資本と不完全雇用に対して、国家がなすことを示した。有効需要原理にもとづく総需要管理は、不況対抗的であっただけでなく、成長経済の枠組みを提起した。
こうした枠組みの基盤となったのは、フォード主義的蓄積のアメリカの生産・生活様式だった。大量生産・大量販売・大量消費を結合したのは、国家による貨幣関係と賃労働関係への介入だった。
しかし70年代になるとその限界が見えてくる。エネルギー・資源問題や環境問題として矛盾を露呈し、アメリカの貿易収支の悪化、財政危機、ドル危機として表面化する。71年に金・ドル交換停止から変動相場制へ。……絶えざる通貨価値の変動とインフレか、経済停滞下での失業率上昇をともなったスタグフレーションかに直面する。
「大きな政府」の介入主義は、その内部で貧困を解決出来ていないだけでなく、「南の貧困」はさらにその埒外に置かれた。
▽福祉国家の危機と再構成
▽45 不況下にインフレが加速するスタグフレーション 従来型の政府による有効需要管理政策では解決できないことを露呈。さらに財政危機が加わり、「市場の失敗」より「政府の失敗」を問うようになる。国家から市場への全面的回帰を主張する。
▽52 ハイエク ケインズ有効需要原理に基づく完全雇用政策は、貨幣価値の低下によるインフレ政策で操作しようとするもので、労働者が完全雇用を前提に力を背景に、高賃金を要求するならば、累進的インフレになる……と批判。
(〓インフレなき完全雇用は、生産性上昇が不可欠?
▽57 70年代のイギリス 工業生産シェア低下、スタグフの傾向と、行政機構の肥大化。サッチャー革命=規制撤廃・減税・民営化・組合への介入……
政権成立と同時に北海油田が操業を開始しエネルギー生産基盤を得ていた。そのため、労組の主力だった炭坑労組の運動解体にそれを差し向けられた。フォークランド戦争による熱気のなかで、国営企業や公営住宅を払い下げ。大ロンドン・カウンシル解体など、地方支出の中央集権化。自治体・福祉専門職などにたいする削減・抑制。
失業者を増大させ、生産性上昇のきっかけを生みだした。インフレ抑制には成功した。一方、若年労働者を中心に長期にわたる失業の常態化を招き、公営住宅の払い下げや家賃補助打ち切りは、ホームレスを広げる。失業手当や退職年金の増大、防衛や治安支出など、むしろ社会支出は増大した。
ハイエクとフリードマンの政策を純粋かつ全面的に志向した。
▽59 レーガン 福祉給付削減する一方で、膨大な軍事予算を採用する。軍事支出による需要創出という点では、ケインズ主義的な効果を期待した。その結果、巨額の財政赤字を抱え、異常な高金利とドル高によって、国内産業の空洞化と貿易収支悪化を定着させ、世界中から資金集中を引き起こした。財政赤字にかかわらず、資金供給を保障したが、膨大な経常収支赤字を累積させ、最大の債権国から最大の債務国に転換した。
▽アルマティア・センの「福祉経済学」
▽厚生経済学 功利主義 最大多数の最大幸福 主観的な効用(utility)をもとに快楽や苦痛を計算し、全体の幸福を最大化しようとする。分配による不平等よりも総和を最大にすることに関心を集中し、自由その他の非功利的な関心事より快楽や幸福のような精神的特性に関心を寄せる主観主義に依存。
もっぱら市場における人々の厚生条件に矮小化され、「合理的個人」が競い合うホモ・エコノミックスの経済論に差し替えられた。
▽73 ロールズ 功利主義の持っていた効用主義の主観主義から、人々の権利、自由と機会、所得と富、自尊心の基盤など、客観主義的なものに考え方を転換させ、結果や成果における不平等から、機会や自由における不平等へと関心を向けさせた。
▽74 ロールズは、社会正義に関して重要な貢献をもたらしたが、財そのものに集中しすぎた点で、物心崇拝的。功利主義が結果(幸福観?)を考慮し、福祉に関心を寄せていたのに対して、手続き的な形式や財貨保有に集中しすぎて点も、後退だとセンは批判する。
▽センの潜在能力アプローチは、人間の「機能」-あり方・生き方に焦点を置く。
「財」は「機能」に先立ち、「効用」は機能の後に来る。財→機能→効用
効用アプローチは、主観的情報に依存した点で、厚生経済論としては限界があった。センは前者については「物理的条件の無視」と呼び、後者については「評価の無視」と呼んだ。〓
▽76 福祉の解釈と評価は、富裕や効用と区別される人の機能-行為と存在-に焦点を置いて捉えることであり、人が享受する生活の質の全貌をそれ自体として評価すること。「潜在能力」とは、人の福祉を実現する自由度(福祉的自由)として捉える。潜在能力には、栄養や健康、自尊心をもって地域に参加できる機能、社会的便宜、政治的自由……も含む
・効用・富裕・機能
・市場における購入データ・アンケートへの回答・個人の状態に関する非市場的な観察▽高齢社会と所得保障
▽114 1.039%から1.84%の経済成長率なら、現行制度を維持できるだけでなく、拡大することが可能。生産力の発展と国民所得の増加があれば、社会保障制度は削減されることなく育てることが可能。要は、経済成長に結びつく経済政策が採られているかであり、公的年金制度でいえば、その制度設計が、将来への計画性と世代間扶養と社会連帯に正当に支えられているか……である。
▽122 措置制度は、GHQの指導と、国の責務を定めた憲法25条を基礎に制度化された。GHQの福祉3原則 (1)無差別平等(2)公的責任(3)必要充足。
(2)は、「政府は財政的援助、実施責任体制を確立」すべきであり「私的、または準政府機関に対し、委譲・委任してはならない」とした。
(3)%E