現代教養文庫 20090109
米国人の人類学者が、敵である日本人の人生観を日本人の立場に立って見ようとしているから、外部からの興味本位の観察とちがって説得力がある。著者が来日したことがなかったとはとても思えない。構造主義的な観察眼の強みだろう。逆に、日本人との比較によって、日本人には理解しがたい米国人の生態が浮き彫りになっている点もおもしろい。
結論としては、平時においてと同じように、戦争においても日本人は日本人らしくふるまったという。彼女の分析する「日本人らしさ」とはどこにあるのだろうか。
日本の兵士の多くは俘虜として連合軍に積極的に協力した。アメリカ人はそれが信じられなかった。日本人は、あるひとつの行動方針にすべてを打ち込んで、それに失敗したときは、別な方針をとることは当然なことと考えているようだった。それは敗戦後、天皇の言葉によって一気に「民主主義」へと転向する態度にも露骨に表れた。
戦後の転向にはまた天皇への「忠」が大いなる力を発揮した。多くの西欧人が、日本が降伏すると信じなかったのは、「忠」を勘定に入れていなかったためだった。
「名に対する義理」(=名誉)への執着も日本人はとりわけ強い。名誉が脅かされた場合、自殺など自分自身を攻撃する傾向が強く、そこまではいかなくても、憂鬱と無気力に陥ることが多い。大正・昭和初期の多くの知識人が憂鬱に陥り、逆に1930年代中頃には国家主義的目標を得て、攻撃の対象を自分自身から外へ向けた。その両方とも伝統的な日本人の流儀だった。
「名誉」の獲得が何より大切だから、事態が変化すれば、名誉のために態度を一変させることができる。西欧人はたとえ敗北しても同じ考えを抱き続けようとするが、日本人は、古い主義を固守しようとはしない。世界の人々から尊敬を受けるため武力を増強したが、それが失敗して、侵略が名誉に至る道ではなかったことを知ると、敗戦後は180度転換した。(罪の文化と恥の文化の差)
「(筆者の観察する戦後直後の)日本人は、平和な国々の間で尊敬される地位を回復したいと希望している。そのためには世界平和がなければならない。もしロシアとアメリカが軍備拡充のなかにすごすならば、日本もその戦争に参加するだろう。日本の行動の動機は機会主義的(場当たり的)である。日本はもし事情が許せば平和な世界のなかにその位置を求めるだろう。そうでなければ、武装した陣営として組織された世界の中に、その位置を求めるだろう」という著者の指摘も、その後そのとおりに推移していくことになった。
競争によってアメリカ人は努力するが、日本人は競争があると作業能率は低下するという観察も興味深い。競争相手に負けるかもしれないと気に病んで、競争を外からの攻撃と感じてしまう。だから、仕事に専念する代わりに、注意を自分と攻撃者との関係に向ける。スポーツなどで「試合に負けて泣く」というのも、アメリカ人から見ると「負けっぷりの悪いやつ」と、軽蔑の対象になるという。このへんにも彼我の「名誉」(=他人の評価)の差があらわれていておもしろい。
日本の近代の小説は、愛や人情を「義務」や「義理」のために棄てなければならない物語を描いている。だから、日本の戦争映画が西欧人には反戦宣伝と受けとられやすいという。この指摘は、「男たちの大和」や特攻隊を描いた映画を反戦と見るかナショナリズムと見るかに割れる現象にもつながるのだろう。
西欧人は、これらの作品は自由の拡大を望む訴えと解釈するが、多くの日本人は、個人的幸福を度外視して義務を全うすることを評価する。
アメリカで重視されるsincerityはは、自己の内なる声に従う心の純粋さを示すが、日本の「まこと=誠意」は、「日本精神」の示す「道」に従う熱意ということである。個人の良心ではなく「世間」を土台とする道徳とでも言えようか。
世界には、恥(世間)を基調とする文化と、罪(絶対的な善悪)を基調とする文化があり、日本人は前者である。「罪」を犯した人間は、告白することで重荷をおろせるが、「恥」が力をもつ場では、あやまちを告白しても気持は楽にならない。それどころか、悪事が露見しないかぎり悩まない。
神のような超越的なものを信じないから、仏教国であるのに、輪廻と涅槃の思想が根づかない。死後の生活に興味をもたず、因果応報の思想さえ棄てた。「どんな人間でも死ねば仏になる」という教えは、ほかの仏教国にも存在しない。
宇宙や神と合一するというヨガのような信条もない。忘我の境地に達するための修行は神との一体化ではなく、現世において「一点集中」の態度を養う訓練法とみなす。日本人は恍惚状態を六感が鋭敏な状態に達した状態とみる。ふだん慎重に行動することを強いられているから、無我状態になり、自己監視の重荷がはずれたときに最高の力を発揮しうる、と言う。「死んだつもりになって」という言葉も、さまざまなことに思い煩う必要を超越した状態になることを意味する。
一方、アメリカ人は、「観る我」を理性的原理とみなし、それを常時もちつづけることを誇りにする。アメリカ人にとって、良心=意識を持たぬ人間は「悪」だが、日本人が無心・無念・無想というとき修行を積んだ人間を意味する。アメリカ人にとって、良心=意識が麻痺した人間は反社会的だが、日本人にとっては、人間は心の奥底は善であり、それが素直に行為にあらわれるなら徳行をおこなうことができる……。
日本の戦後の発展も、以下のように予言している。
「真珠湾にいたるまで10年間、軍備をまかなうため歳入の半ばを費やしてきた日本のような国は、その支出を廃し、農民から取り立てる租税を軽減したならば、健全な経済の基礎を築くことができる。日本の農産物の配分は、耕作者に6割で、4割は租税や小作料だった。ビルマやシャムでは、9割が耕作者に残された。日本のこの莫大な税金が、日本の軍事機構の経費を可能にした。ヨーロッパでもアジアでも、今後10年間軍備を整えない国は、軍備を整える国を凌駕する可能性がある」
文化人類学者が、経済や政治の分野まで見通す目をもっていたことに驚かされる。
=================抜粋・覚え書き===================
▽35 キスカの占領も、空襲も、……、「すべて予知され計画されていた」と日本人は言った。フィリピンでマニラが陥落したのも山下将軍の戦術の結果とされた。一切はこちらから積極的に欲した、という態度だった。
▽38 天皇は長らく影のような存在で、存在感はなかった。……第一次大戦後、だれもがデモクラシーを口にした時代、軍国主義が不人気だった時代にも天皇に対する崇敬の念は同じように熱烈だった。
▽41 俘虜は一人残らず天皇を誹謗することを拒んだ。連合軍に協力したものでさえそうだった。
▽44 戦争中でも、政府や大本営、直接の上長に対して日本人は批判を加えた。だが天皇だけは批判を免れた。天皇が命令する限り、竹槍で死ぬまで闘うだろうが、同様に、それが勅命ならば、敗戦と占領を甘受するだろう、と日本の俘虜たちは主張した。
▽46 前線の仮収容所、後方の野戦病院、さらに遠く離れた大規模病院といった組織だった医療システムがなかった。危急の場合患者は見殺しにされた。
▽48 西欧諸国の軍隊では、戦死者が4分の1ないし3分の1にたっしたときは、その部隊は抵抗を断念するのが自明の理とされる。投降者と戦死者の割合はほぼ4対1だ。ところが、日本軍がはじめて大量に降伏したおりでさえ、その割合は1対5だった。北ビルマでは1対120だった。
▽51 日本の兵士は、西欧の兵士と異なって、俘虜として連合軍に協力した。アメリカ人は、俘虜がこのように回れ右をするとは信じられなかった。日本人の行動は、あるひとつの行動方針にすべてを打ち込んで、それに失敗したときは、別な方針をとることは当然なことと考えているようだった。
▽「各々其の所を得」
▽58 日本人は、他の多くの太平洋諸民族と同様に「敬語」をもっている。
▽61 中国は、先祖をともにする宗族ごとに、家憲があり、その家憲にしたがって、家族のなかで犯罪を犯したものを国家に引き渡しを拒むことさえある。
日本では、ちがう。名字を許されるのは貴族と武士だけ。一般に姓に相当するものがなければ氏族組織は発達することはない。日本では系図をつけたのは上層階級だけだったし、現在から時代をさかのぼるものであり、始祖から現在までをもれなく網羅するものではなかった。
そのうえ、忠誠を捧げる相手は親類縁者の一大集団ではなく、封建領主だった。
〓氏族を制度化するもうひとつの方法は、遠い祖先や氏族の神々を、神社や聖所で崇拝することだ。ところが日本では、遠い先祖をあがめる崇拝はおこなわれていない。「庶民」が祭をする神社には村民が集まるが、彼らが「氏子」であるのは、その祭神の領域内に住んでいるからである。彼らは共通の先祖の血を受けた緊密な氏族集団ではない。
(〓柳田の考えとの違いは?)
祖先崇拝は、家の仏壇でおこなわれ、そこにはわずか6,7人の最近の死者のみがまつられている。墓地においてさえ、三代前の先祖でさえ、それが誰の墓かということは急速に忘れられていく。日本の家族的つながりは、西欧と大差ないところまで狭められている。
▽73 商人階級は封建制度の破壊者である。江戸幕府の鎖国は、商人の立脚地を奪うためだった。海外貿易を阻み、、商人の低い社会的地位を強調するために驕奢な着物や傘を取り締まり……
▽74 刀狩りによって農民と武士は分離された。武士が生産者になることは禁じられ、寄生的階級となった。一定の俸禄に依存する年金生活者だった。
▽77 シャムでは伝統的年貢は10%だったのに対し、徳川時代の日本は40%。あるいはさらに高率だった。
▽85 金貸しや富豪は、養子縁組によって、武士の身分を「買う」。富裕な商人が下層武士階級のなかに侵入する。
ヨーロッパで封建制度を崩壊させたのは、中産階級だったが、日本では、貴族と市民階級との間に階級闘争がおこなわれた形跡がない。
衰えた幕府を転覆させた同盟は、商人・金貸階級と武士階級との同盟だった。
▽明治維新
▽91 農民は新政府に反発。最初の10年に少なくとも190件の一揆がおこっている。明治政府は、下層武士階級と商人階級との「特殊な連合」だった。大名の側用人・家老として政治的手腕をみがき、藩独占事業を経営してきた武士たちと、武士の身分を買い取り、武士階級のなかに生産技術の知識を普及させた商人たち。
▽105 明治の政治家は、政治においては国家の権能のおよぶ領域を、宗教においては国家神道の領域を慎重に区画した。他の領域は国民の自由にまかせたが、直接国家に関係する事柄は、最高官吏である自分たちの支配権を確保しようとした。……軍隊では、家柄ではなく、一兵卒から士官まで出世できた。同じ地域からきている近隣の人たちで中隊や小隊は編成され、武士と百姓、金持ちと貧乏人に関係なく2年間共に生活することになった。軍隊は、民主的地ならしの役目を果たした。軍隊は小農階級に同情を寄せ、この同情が、資本家に対する抗議にたたしめた。
▽109
▽110 日本人はたえず階層制度を顧慮する。年齢・世代・性別・階級がふさわしい行動を指定する。「ふさわしい位置」が保たれている限り、日本人は不服を言わない。
階層制度による「安全」の信条を国外に輸出しようとしたときに、猛反発を受けた。「おのおのにふさわしい地位に甘んじる」道徳体系が、他国で期待することのできないものであることに気づかなかった。
▽過去と世間に負い目を負う
▽116 ハチ公 119
▽139 「仁」は、日本人の倫理体系から追放されてしまった結果、なにかあることを法の範囲外ですることを意味する。「仁義を行う」も「法の範囲外」のもうひとつの意味で用いられる。こうして日本人は仁の地位を零落させた。
▽153 日本が降伏したとき、「忠」が信じがたいほどの大きな力を発揮した事実を世界は目撃した。多くの西欧人は、日本が降伏するなど信じなかった。「忠」を勘定に入れていなかった。玉音放送を阻止しようとした人はいたが、一度それが読まれると、逆らうものはいなかった。
▽155 義理ほどつらいものはない 「義理」は儒教から得たものではなく、日本独特の範疇である。
義理には2つの異なる部類にわけられる。「世間に対する義理」は、「恩」を返す義務である。名に対する義理は、ドイツ人の「名誉」のようなもので、自分の名を他人から侮辱されて汚さないようにする義務。
「義理の母」「義理の父」
▽168 汚名をすすぐ 「名に対する義理」は、自己の名声を擁護することとともに、誹謗もしくは侮辱を取り除く行為を要求する。名誉毀損者に復讐することも、自殺することもある。
▽178 競争によってアメリカ人は努力するが、日本では逆になる。競争があると作業能率は低下する。日本人は、自らの進歩を自らの成績と比較しつつ測定するときに、良好な成績をあげ、他人の比較測定する場合はそうならなかった。競争でやると、負けるかもしれないという危険に心を奪われ、仕事がおるすになる。競争を外からの攻撃と感じるから、仕事に専念する代わりに、その注意を自分と攻撃者との関係に向ける。
試合に負けて泣く、というのは、アメリカでは「負けっぷりの悪いやつらだ」と言われる。負けたからと泣いたりわめいたりする人間をわれわれは軽蔑する。
▽189 汚名をすすぐため、「義理」は単に忠誠であるにとどまらず、ある場合には裏切り(謀反)を命ずる徳でもある。
▽195 「名に対する義理」が脅かされた場合、攻撃を自分に向ける(自殺など)傾向がしだいに強くなりつつあるが、自殺まではいかず、憂鬱と無気力、インテリに独特の日本人独特の倦怠を生み出すにすぎない場合もある。
インテリが過剰になり、野望を満たせる人はわずかだった。さらに1930年代にインテリ階級を「危険思想」の保持者として当局が疑ったため、二重に心を傷つけられた。……日本人特有の気分の激変は、熱烈な献身から極端に倦怠に移り変わることであって、多くの知識人が遭遇した心理的難破は、欧化による混乱ではなく、伝統的な日本人の流儀によるものである。1930年代中頃に彼らの多くが免れた方法も伝統的だった。国家主義的目標を抱き、攻撃を自分自身の胸から再び外へ向けた。全体主義的侵略のなかに、再び「自らを見だす」ことができた。
(インテリの名誉が傷つけられることによる攻撃を自分にむける傾向)
▽199 日本人の恒久普遍の目標は名誉である。その目的のため、事態が変化すれば、日本人は態度を一変し、新しい進路に向かって歩きだすことができる。
西欧人はたとえ敗れても、依然として同じ考えを抱き続ける。
日本人は、古い主義を固守する道徳的必要を感じない。アメリカ人は単独で旅行してもなんの危険も感じなかった。敗戦後の日本人の180度の転換は、アメリカ人には理解しにくい。多くの欧米人は、敗戦は死にものぐるいの暴力によって報復するべき侮辱であろうと信じ、いかなる講和条件も受託しまいと信じていた。
▽200 日本人は、世界の人々から尊敬を受けるため、武力を増強した。それが失敗することで、侵略は結局名誉に至る道ではなかったことを知る。敗戦後も日本人の目標は依然として名声を博することである。
▽人情の世界
▽206 日本人の好む肉体的快楽のひとつが温浴である。公衆浴場で湯につかり、人々と交歓する。(西欧人には珍しい快楽〓)
日本人は入浴中ひとに見られても少しも恥ずかしがらない。〓
▽214 芸者や娼婦と遊ぶ遊興は、おおっぴらに行われる。それらは「人情の世界の中に」あるものであって、「孝の世界」に倦み疲れた人に慰安を与える。娼家の店先には娼婦の写真が張り出してある。遊客は平気で長い間かかって相手を選択する。昔、日本人が西欧人の非難に気づかなかったころは、娼婦は自ら人目につく場所に座り、その無感動な顔をさらしていた。写真はそのかわりである。(〓西欧との接触でなくなった文化、飛田の場合は……)
同性愛も、武士や僧侶の公認の楽しみだった。明治になって、西欧人を意識して、この習慣も法律で処罰されることになったが、今も「人情」のひとつとされている。
▽216 自淫的享楽も、やかましく言わず、さまざまな道具を工夫している。手淫を非難する西欧人の強硬な態度に比べ、日本の少年は厳しく禁じられる経験をもたない。
酒に酔うこともまた、許しうる「人情」のひとつである。酒に酔っている人間を嫌悪するべきとは考えない。
▽徳のジレンマ
▽238 近代の小説は、愛や人情を「義務」や「義理」のために棄てなければならない物語を描いている。日本の戦争映画が西欧人には西欧人には反戦宣伝と考えられやすいように、これらの小説は、自由の拡大を望む訴えのように思われる。ところが日本人は、別の解釈をする。日本人にとっての強者とは、個人的幸福を度外視して義務を全うする人間である。性格の強さは反抗することによってではなく、服従することによって示されると考える。(〓男達の大和、につながる議論 反戦と愛国の双方に架橋する作品があり得る)
▽240 妻は、義務の世界の中心に置かれることはない。妻との関係を、両親や祖国に対する感情と同一水準にあるかのごとく取り扱ってはならない。1930年代に自由主義者が、「日本に帰ってうれしい」理由として「妻との再会」をあげたため、悪評を被った。両親に会えるから、とか、富士山が見られるから、とか、言うべきだった。
日本人は「忠」を至上の徳としてきた。天皇を頂点におき、将軍や封建諸侯を排除することで階層制度を単純化したように、下位の徳をことごとく「忠」の範疇の下に置くことで、義務の体系を単純化しようとした。このための最も権威ある表明が「軍人勅諭」。これと「教育勅語」こそ、日本の真の聖典である。
神道には経典がないし、仏教も「南無阿弥陀仏」といった文句を繰り返しさえすればよいと教える。ところが、勅諭と勅語は真の聖典である。(〓久野収、顕教と密教)
▽249 日本人の「マコト」は、アメリカで重視されるsincerityとはちがう。sincerityは、人をして自己の内なる声の命ずるところに従って言動をなさしむる心の純粋さ、純粋に自己の信念に従って行動することををさすが、日本の「まこと=誠意」はちがう。
日本人の「誠実」とは、「日本精神」によって地図の上に描きだされた「道」に従う熱意ということである。(〓個人、ではなく、世間、を土台とする道徳?〓=世間に対するマコト?)
▽252 まこと、とは、独立した徳ではなく、その他の徳の大きさを高める自乗数である。
日本人の徳の原理は、それじたいは善であるある行動と、それ自体では善である他の行動との間のバランスを保つことである。
▽256 日本人は罪の重大さよりも恥(世間)の重大さに重きを置いている。さまざまな文化人類学研究で重要なことは、恥を基調とする文化と、罪を基調とする文化を区別すること。
罪を犯した人間は、告白することで重荷をおろせる。恥を主要な強制力となっているところでは、あやまちを告白しても一向に気が楽にならない。それどころか、悪い行いが露見しないかぎり、思い煩う必要はない。したがって、恥の文化には、人間に対してはもとより、神に対してさえも告白する習慣はない。
▽275 日本は仏教国であるのに、輪廻と涅槃の思想が信仰の一部となったことはない。悟りを開いた人間にとっては、涅槃は今ここに、時間のただ中にある。日本人は死後の生活の空想には興味をもたなかった。仏教の死後における因果応報の思想さえ棄ててしまった。どんな人間でも死ねば仏になる、という仏教国はほかにはない。どのみち仏になるなら、わざわさ肉体を苦しめて、絶対的停止=涅槃に達しようと努力する必要はない。
ヨガの宇宙と合一するという信条もない。神秘主義的修行は「神とひとつになる」ことを意味することが多いが、日本人は、忘我の境地に達することも「一点集中」の態度を養う訓練法とみなす。恍惚状態になると五感が活動停止状態になる、とは言わず、六感が鋭敏な状態に達するという。修行によって、あらゆる感官を鋭敏にすることを学ぶ。
▽287 舞台見ていて我を忘れたり、爆弾を発射するときに自分がしている、という意識をなくしたりする。「無我」となり、「観る我」を失う。こういう状態を日本人は最上のコンディションという。アメリカ人は観る我を自己の内の理性的原理とみなし、それに注意を払いつつ行動することを誇りにする。日本人は、慎重に行動することをたえず強いられているから、無我状態になり、自己監視の重荷がはずれたとき、力を発揮しうる、と言う。
「死んだつもりになって」という言葉も、さまざまなことに思い煩う必要を超越した自由なものになることを意味する。「私の活動力と注意力とは、何の束縛も受けずに、まっしぐらに目標に向かって進んでいく」と。
▽290 アメリカ人にとって、良心=意識を持たぬ人間とは、悪人のことだが、日本人が無心・無念無想というとき、善人・修行を積んだ人間を意味する。アメリカ人にとって、良心=意識が麻痺した人間は反社会的だが、日本人にとっては、人間は心の奥底は善であり、それが素直に行為にあらわれるなら徳行をおこなうことができる。そこで、「練達」の修行を積んで、恥の自己監視を排除しようとする。
▽293 育児
アメリカでは、赤ん坊は、体によい一定の食べ物をきちんと食べなければならない。日本人はもっと厳しいと思いきや、逆である。日本では、赤ん坊と老人とに最大の自由が許される。
▽299 日本の赤ん坊は、満一歳になるまでは、立ったり歩いたりさせてはならないとかつては考えられた。歩くより先に口がきけるようになる。
▽317
▽321 徴集兵は、軍隊教育を受けてでてくると、すっかり人間が変わったようになり、「真の猪突的国家主義者」になると言われてきたが、この変化は、全体主義的国家理論を教えられるからではなく、屈辱的な芸当をさせられる経験のほうがはるかに重大な原因になっている。家庭生活で自尊に真剣だった青年ほど、そのような事態に置かれると理性を失い、獣的になりやすい。彼らはなぶりものにされるのが耐えられない。これらの事態が、今度は彼らを辛辣な拷問者にする。
▽347 マッカーサーによる日本の管理は、ドイツやイタリアの管理とまったく異なり、上から下まで日本政府と日本人官吏を利用した。日本国政府の機構を浄化し、それを利用することで、時間と人員と財力とを節約した。
日本人にとってこの政策は、敗戦の事実から屈辱の表象を取り除き、彼らに新しい国策の実施を促すものだった。その政策を受け入れられた理由は、特異な文化によって形作られた日本人の特異な性格にほかならなかった。
▽355 敗戦直後の新聞論説は、「世界の国ぐにの間にごして尊敬されるようにならねばならない」と繰り返して論じた。尊敬に値する人間となることが日本国民と義務とされた。少数のインテリだけでなく、一般大衆もまた回れ右をする。
占領軍の将兵には、このような友好な国民が、死ぬまで竹槍でたたかうことを誓った国民とは信じられなかった。
▽363 真珠湾にいたるまで10年間、軍備をまかなうため歳入の半ばを費やしてきた日本のような国は、その支出を廃し、農民から取り立てる租税を軽減したならば、健全な経済の基礎を築くことができる。日本の農産物の配分は、耕作者に6割で、4割は租税や小作料だった。ビルマやシャムでは、9割が耕作者に残された。日本のこの莫大な税金が、日本の軍事機構の経費を可能にした。ヨーロッパでもアジアでも、今後10年間軍備を整えない国は、軍備を整える国を凌駕する可能性がある。
▽366 日本人は、平和な国々の間での尊敬される地位を回復したいと希望している。そのためには世界平和がなければならない。もしロシアとアメリカが今後数年間を軍備拡充のなかにすごすならば、日本もその戦争に参加するだろう。日本の行動の動機は機会主義的(場当たり的)である。日本はもし事情が許せば平和な世界のなかにその位置を求めるだろう。そうでなければ、武装した陣営として組織された世界の中に、その位置を求めるだろう。


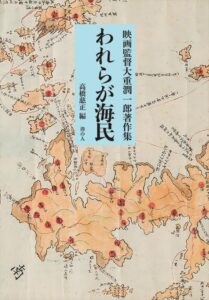

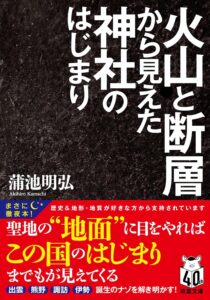

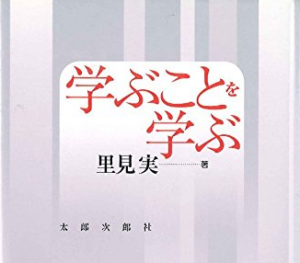

コメント