■太郎次郎社20231226
テーラーシステムとフォード・システムの特徴は、労働過程における「構想と実行の分離」にある。働く者の「構想する」権利を拒むことによって、巨大な生産力を実現してきた。それによって、生き甲斐と自己実現につながっていたはずの労働は単純化し、無意味化された。シニカルな態度で「生の無意味化」に耐える労働者のシニシズムは教育にも浸透し、「学ぶ」という行為そのものの手応えではなく、その対価として得られる報償が学生の関心事になっていった。
若者たちは、没意味化され、手段化された学習をとおして、疎外された労働に耐える訓練をほどこされる。学習に対する態度が功利的・打算的になり、進学や就職につながらない勉強をしようとしなくなっていった。
本来の学びとは、好奇心をもって世界と対話し、モノやコト、本との交渉をとおして自分の世界を構築していくいとなみだ。
本を意味深く読むには、読者のなかにそれをうけとめる文脈ができていなければならない。各地を歩き人々とふれあって、本の外部の文脈が豊かになることによって、本はより興味深いものになる。
経験を表現することは、その経験を生き直し、新たな次元をきりひらくことになる。現実の体験は、テキストを「読む」ためのcontextであり、逆に自分の生を「読もう」とすれば、「読書」でふれる他人の物語が、自分の「実体験」を解読するためのcontextになる。読書と実体験は、たがいにtextとなり、contextとなって、人生を意味深いものにしていく。
経験を放置しておけば、時間とともに風化するが、反対にささいな経験でも、それを言語化し、そこにふくまれた意味をくみつくせば、広がりと深さをもった経験と化すことができる。テキストで表現することは、その行為をとおして経験をつくり出していくことでもある。
学生が本を読まない、ということ自体が深刻なのではない。本を読まなくてもすむような人生しか生きていない、ということが深刻なのだ。
つくることから学生を疎外してきた日本の教育の体質は国語教育にあらわれている。「正しい解釈」を先生から教えられ、それを「覚え込む」という「読解指導」が支配的だ。
フレイレの成人識字教育や日本の生活綴り方はそれとは反対で、学習者を「語り手」にするものである。
▽13 テーラーシステム 労働と学習にささげられる時間の徹底的な手段化。労働そのものを単純化し、無意味かしていきました。労働者はシニカルな態度で、この生の無意味化に耐えていくのですが、シニシズムは若者の学びのなかにも浸透していきます。「学ぶ」という行為そのものの手応えではなく、その対価として得られる制度的報償が、学生たちの唯一の関心事になっていきます。
=人生の時間、生きることそのものの「手段」化。若者たちは、没意味化された学習をとおして、疎外された労働に向けての予備訓練をほどこされている。
▽29子どもたちが「問題を考えること」そのものを拒絶しはじめていることに目を向けないで、正答率の低さをあげつらっているのが、昨今の「学力」論議。若者たちが「問題を考えること」そのものを拒絶するのは、かれらが「無気力」だからではありません。というより、その「無気力」こそが、あたらしい自分の学びを生みだしていく下地なのです。
▽33 学習に対する態度が功利的・打算的になっている
……成績に結びつけばなんでもするけれど、結びつかないと受けつけない。
(五教科だけを重視する感覚〓)
学生が、自分の得になることしかやらないと嘆くけど、自分の得というよりも、そもそも自分がない。学びのなかに自分がない。何を学んでもその知識はテストに答えるための知識であって、自分のアイデンティティとはかかわりがない。
▽44 まなびとは、好奇心と驚きをもって、世界と対話することです。そうした学びを持続できる人は、精神において、つねに若いのです。
▽64 品川区 学校選択自由化 低所得地域の学校は小規模化して、山の手の学校が生徒数を増やす。でも、学校選択そのものを否定するのは賛成できません。小規模化する学校には、小さいからこそ開発可能な実践のスタイルがあるはずです。
▽67 テーラー・システムとフォード・システムの特徴は、労働過程における「構想と実効の分離」。働く者の「構想する」権利ヲ徹底的に拒むことによって、巨大な生産力を実現してきたのでした。そのつけのひとつのあらわれがいまの学校の姿でしょう。
▽76 学ぶということは、自分のなかにある認識の構造をつくりだすことだと思う。
▽100 知識というのは自分のなかの磁力を強めていくことなんだ。
▽127 大学生の不勉強は受験勉強の後遺症。内発的な動機なしに「勉強」してきた学生たちは、受験の圧力がなくなれば、勉強を放棄します。勉強しなくなったことが堕落なのではなく、勉強してきたそのことが堕落なのです。
▽128 勉強を強いる圧力から解放されるということは、大学生の最大の特典だと思います。大学はレジャーラン……そういう情景を「なくしてしまう」ためのすべての企てに、ぼくらはNonといわなければなりません。なくしてしまったら克服することはできないのです。
▽131 学習とは、「自分の知識」をつくりだしていく営み。モノやコト、本との交渉をとおして自分の世界を構築していく、すぐれて構成的な行為です。
▽135 本を意味深く読むには、読者のなかにそのための文脈ができていなければなりません。その土地を歩いたり、人々とふれあったりすることで、つまりが本の外部の文脈が豊かになることによって、本はより興味深いものになる。
▽145 ある経験を表現するということは、その経験を生き直すということ。行為を思い返し、反芻することをとおして書き手は、かつての行為を越える新たな次元をきりひらいているのである。
▽177 できあいの賞品を消費するばかりの社会では、しばしば学びもまた、出来あいの知識を買い求め、それを頭のなかにためこむ行為に堕してしまう。自立的・創造的に思考する力が掘り崩されていく。そういう社会をイヴァン・イリッチは「学校化された社会」とよんでいる。学校は人間を受動化し無力化していく消費社会のシンボルなのである。
▽181 電子メディアは、プログラム化された世界のイメージを子どもたちに与えつづけ……物語る力を失った子どもたちは、識字能力をも失っていく。経験を解釈し、世界を構成していく「自分」というものを喪失していく。
……テレビがなげかける仮想現実に侵されて育ち、自らの物語を織り上げる言葉を失った若者は、世界にたいするいらだちを暴力で表現する。拳銃は文字を失った若者たちの筆記具なのである(米国)
▽190 フレイレの影響を強く受けた識字ワーカーたちは、コード表示にあたって、しばしば「演劇」という方法に訴えている。……フレイレの識字実践に演劇を接合したのは、アウグスト・ボアールというブラジルの演出家。
▽198 つくることから学生たちを疎外してきた日本の教育の体質は「読み」の教育に端的にあらわれている。「正しい」解釈を先生から「教えられ」、それを「覚え込む」という「読解指導」が国語教育においては支配的だ。学生から「テキストをつくりだす力」を奪うために「教育」がおこなわれているとしか思えない。
……フレネ教育やフレイレの成人識字教育、日本の生活綴り方は、いずれも学習者を「語り手」にする、という共通の志向を示している。人間の教育を考えるとき、人間を、テキストを産みだす存在として捉えることがきわめて重要。
▽200 現実の体験は、テキストを「読む」ためのcontextを構成している。逆に、自分の生をひとつの「物語」として「読もう」とすれば、「読書」をとおしてふれる他人の物語が、自分の「実体験」を解読するためのcontextを提供するだろう。読書と実体験は、たがいにtextとなり、contextとなって、人生を意味深いものにしていくのだ。
……学生が本を読まない、というそのこと自体が深刻なのではない。本を読まなくてもすむような人生しか生きていない、というそのことが深刻なのだ。
▽203 経験を放置しておけば、時間とともに風化する。反対にどんなささいな経験でも、それを言語化し、コード化し、そこにふくまれた意味をくみつくしていけば、それは巨大な広がりと深さをもった経験と化していくだろう。
テキストを生み出すということは、その表出行為をとおして経験をつくり出していくことでもあるのだ。
▽223人間は認識能力、知性があるというだけの理由で認識したり知ったりすることに努めるのではなく、反対に、認識したり知ったりしようとする以外に手がないので、利用できるあらゆる手段を動員する。……だから人間の知性が実際に知性であるとは言えない。むしろどうしようもなくまきこまれているところの課題、が、人間を定義するものなのです。
……人間を定義するのは能力ではなく課題である、というオルテガの言葉。……疑似生物学的な「能力」信仰にたいする批判。人間を機能としてしか捉えようとしない能力主義社会のもとでは、能力とよばれているものは、たんなる性能に矮小化されている。「能力」信仰のもとで、人間は人間に固有な課題を見失っていく。課題を見失うことで、その課題に向かって発動されるべき能力をも、結果的に空洞化させてしまっている。
……天与の財宝として人間の思考能力を定義することは、人間が人間になる、という困難で、その成否の不確かな課題から私たちの注意を遠ざける生セイレーンの歌になりかねません。人間は「すべては自分でつくりあげねばならない」のです。
人間は、人間でありつづけることを保障されてはいないというのがオルテガの論旨。……自己疎外・自己喪失という非人間化の危険が、今日ほど高まっている時代はない、という危機意識が、オルテガの文章には脈打っています。


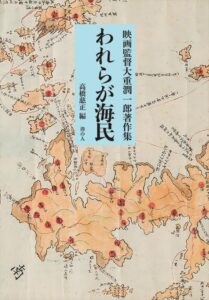

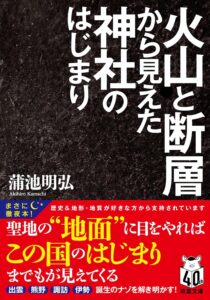



コメント