20090120
土地問題の研究から「住居は人権」という考え方が生まれ、「居住福祉資源」にまでたどりつく著者の歩みがつづられている。
「住居は人権」という位置づけができていないから、阪神大震災後、「私有財産の形成になるから住宅再建の補助はしない」と政府高官が声高に語るとそれが通ってしまい、仮設住宅や郊外の復興住宅で多くの人が孤独死した。その前に、人権としての一定水準以上の住居が保障されていないから、何千人もの人が倒壊した建物の下敷きになって死んだ。
「住居は人権」というコトバ・概念を語りつづけ普及させることの大切さがよくわかる。憲法の「生存権」もそうだけどタテマエは大切なのだ。著者たちが「住居は人権」と言いつづけたからこそ、ここ10年ほど、一部の自治体で災害時の住宅再建を補助する制度が生まれてきた。
「居住福祉」という概念も、生活や福祉の基盤としての「居住」という考え方を広めようとするものだ。一定以上の水準の住居のみならず、孤独に陥らずに暮らせるコミュニティなども含めた概念になっている。
著者は「居住福祉資源」を訪ねる旅をつづけ、「おばあちゃんの原宿」と呼ばれる巣鴨のとげ抜き地蔵商店街や、視覚障害者も自由に暮らせるコミュニティをつくった草津のハンセン病療養所、旧沢内村の集落などを訪問しつづけている。筆者の旅は、「居住福祉」というコトバ(概念)の中身を築き、豊かなものにするための旅なのだろう。
==============抜粋・メモ==============
▽5 研究の方法論としては毛沢東の「矛盾論」が一番役立った。大塚久雄の「学問の精神」(『考える人ー』五つの箱)
武谷三男「自然科学概論」3巻「科学・技術のストラテジー」
「境界領域こそは本質論的考察が有効性を発揮する分野であり、専門分化の泥沼におちいっていたのでは、ろくろく意味のある成果をあげえないような分野である。だからこそ、境界領域の研究は一般に著しく遅れており、亦このような分野での研究こそが、既成のの学問体系に対しても、しばしば前進のための決定的な突破口をひらくきっかけを提供する」「理論的に前進するつど、その成果の評価が、隣接する学問領域からあたえられなければならない」
▽空間的価値論
▽14 住宅貧乏物語」住宅の状態が与えている諸々の影響を、現実の世の中に起きている諸現象の新聞記事や多分野の調査結果を引用して明らかにしようとした。国立公衆衛生院、教職員組合、第gく図書館に通い詰めて……家裁調停員、保健師など多分野の専門家にインタビュー。
▽「住居は人権である」という気づき。
▽19「貧乏物語」の一カ月後、ECが内部文書で「日本人はウサギ小屋に住む働き中毒」と報告したことがつたわってきた。政府は「日本の住宅は欧米水準に達している」と反論した。反論の1つは1戸あたりの居室数で、英国や西独を上回っているというものだが、欧米では、寝室、リビング、専用トイレ、浴室、台所、物置がなければ住宅と認めず、各居室の最低面積が決められている。日本では、共通の入り口と共通のトイレと1つの居室があれば1戸の「住宅」としてカウントする。だから、住宅戸数は世帯数を上回り、住宅数は足りているという認識になる。
異国では、サッチャー政権後、住宅の状態と健康に関する調査が再燃していた。現状を放置しない医師や専門家には感心した。
▽23 46歳で外国へ。「住宅・土地政策が生活環境形成に果たしている役割」アメリカ二カ月、西独4カ月、半年はLSEの森嶋通夫研究室に席を置いた。「現在の経済学はすべてフローがベースである。あなたはストックの経済学をやってほしい」
覚知の空き家占拠運動やコミュニティ再生運動などの居住権運動を訪ねる。
▽45 住宅会議 震災の年に神戸大をやめ、研究室がなくなり、事務局長をバトンタッチ。その後は社会的発言は影をひそめ、サロン化した。
▽49 ゼミ生にまず「ストラテジー」と「矛盾論」を読ませる。
▽52 学生に自主的テーマが浮かばない場合、一番てっとり早いのは、外国の住宅政策や都市計画の居住権運動などを現地に行って調べてくることである。国際会議でもらった世界の資料のなかから好きな国を選んで出かける。
▽59 保団連を通して、疾病と居住条件について調査。教職員組合と調査。先生と生徒両方の調査票。県内の全老人施設の6326人対象に調査。
▽68 研究の目的や方法を議論しているあいだは、方法と主体性のかかわりは密接ですから、まだ主体が生きているのです。それがいまは道具になってしまっているから学問の方法など必要を感じないのです。
知識人の責務 サイード
▽75 居住福祉学会 徹底して現地から学ぶ。山古志村、栗生楽泉園、沢内村、江戸川区、とげ抜き地蔵、奈良町、鷹巣町……18回。
「居住福祉資源認定証」を毎年数件活動団体に贈呈。
08年に沢内で第一回サミット。
▽76 05年「東アジア居住福祉宣言」 西欧近代主義のもとでの住宅建設・住宅政策への反省。アジア固有の居住文化の評価・再生と居住保障の必要性・課題を論じた。〓学校をでてすぐ書いたル・コルビジェ批判の延長線上にあった。〓
▽79 「居住福祉」概念 住宅は自己責任という政府の基本姿勢、持ち家一辺倒の価値観、そのマインドコントロールにかかっている社会では「住む」ことの本質への認識や「住居は基本的人権」という権利意識をうけとめる土壌はない。だからこそ、居住の現実に根ざしながら人間にふさわしい居住条件の実現に寄与しうる学術・社会的活動がもとめられる。(〓福祉社会、と同じ。概念じたいを浸透させなければならない)
▽83 裁判所は、「人間らしく住むことは二五条の生存権、国の社会保障的義務」などといっても、努力目標にすぎないと退ける。国際人権規約(社会権規約)が「居住の権利保障は政府の責務」と規定し日本政府が批准していても日本の実定法にはない、裁判とは無関係、と無視する。
▽85 メディアも、ネットカフェ難民などをとりあげるが、生存権の基礎としての居住保障としてのとらえ方は少ない。住むところにさえ不安がなければ人は生きて行ける、という視点は希薄である。
そういう認識がないから、地震で住居を失った人々に対して個人資産に公的援助はできない、と公言する政府のアナウンスを報道するだけで、その責任回避を追求しない。
▽92 「居住福祉学」の前進のため、「空間価値論」と居住福祉をつなぐ、ストックとしての「居住福祉資源」という概念にたどりついた。安全に安心して生きる基盤となる「資源」。
国民自身が、まちや村や国土のすべてを居住福祉の視点から見る目を養うことがまず求められる〓。
「居住福祉資源発見の旅」として全国行脚。10数年のあいだに100数十回。震災復興調査だけでも20回以上。
「中山間の居住福祉」〓〓





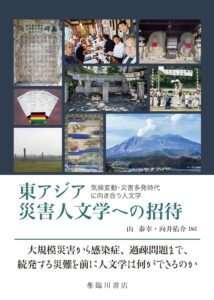


コメント