信山社 20090211
東アジア諸国の福祉社会開発と地域コミュニティ再生。欧米的文脈ではない福祉社会のありかたの模索。その流れがわかる。すでにここまで理論化されている。
===============メモ・抜粋=================
▽4 福祉社会開発学 現代社会の問題群を解決するんは、さまざまな学問領域からのアプローチが必要。「誰もが安全に安心して住み続けられる家庭と地域社会」の可能性のシナリオを「福祉社会開発学」という新しい概念で説明する。
地域環境や福祉問題の生成の場としてのグローバル化と、問題解決の場としてのローカル化が求められている。(=まさにその通り。必要なグローバルな視点とは、抽象的な鳥の目ではなきう、世界各地のローカルな視点(虫の目)のつながりネットワークではないか)
地域福祉論や居住福祉学は、実際に現場で生じている事実や人々の声に耳を傾ける学問である。
▽8 比較福祉国家論のアプローチ (= 福祉社会開発の対立軸)
階層間格差と社会的不平等という課題に立ち向かうために出現した国家枠組み。各国の特徴を比較分析する方法論。
残余的モデル(residual welfare model)から制度的モデル(institutional redistributive model)へ。
▽12 中国 「高齢者の面倒を家族がみる」という伝統的風潮は、社会的ケアへ急激に変化。高齢者の共同団地、一般の集合住宅のなかに、一定比率で高齢者向け住宅を含める、病院から退院した高齢者世帯に看護士を派遣し、家政サービス(ヘルパー)を提供、高齢者の「慢性病院」設置。
韓国 老人亭(デイサービス)を、100世帯以上の集合住宅あるいは300戸以上の戸建て住宅を計画する際に義務づけた。
これからの居住福祉の政策展開は、次の点に焦点化される。
(1)居住空間 さまざまなリスクを支えることのできる住宅政策
(2)コミュニティ 社会的排除や孤立、人権侵害という福祉諸問題を克服していく実践の構築
(3)公共政策 生活の質を保障するための公共政策の実現。
▽15 住民参加の促進こそが、福祉問題の解決の主体者としての住民意識の向上、近隣関係の希薄化による孤立化の防止、人間の尊厳を侵害している状況の改善など、地域福祉の政策や実践が連動したまちづくりにつながる。(そういう「参加」は稲葉的。そうじゃない参加を強制する動きも〓)
▽16 広井 欧州の文脈では、市場の自由放任かケインズ主義かの政策対立の構図がつづいてきたが、現在では、それは解消に向かい、新たな対立軸である、成長(拡大)志向から環境(定常)志向へとその重心を移動させてきている。
日本では、経済成長によってパイを拡大することで、皆がそれなりに豊かになってきたから、富の分配を正面から議論する必要がなかった。
経済成長至上主義の日本経済は、冷戦構造のなかで達成しえた。だが、1985年のプラザ合意、冷戦体制の崩壊によって、一変する。
我が国の福祉レジームのベクトルは、中央集権的な経済成長至上型の福祉国家レジームから、地方分権による福祉環境型の福祉社会レジームへ方向転換していくことになろう。〓そのたmには、分権型福祉社会を地域福祉の考え方がリードしていく必要がある。
▽18 世界市場を高速に移動する資本、国をまたいだ労働力の移動、情報の瞬時の移動……これらは、地域社会に影響を及ぼし、その場での問題解決がせまられている。日常生活から遠く離れたところで生成した問題が身近な地域社会のなかで解決を求められる。
▽22 我が国の地域コミュニティは、……元気を失っているように見える。それは1960年代を契機に、大量生産・大量消費社会を実現させ、個々人の欲望の極限化社会をつくりだしてしまったことに起因する。
▽26 福祉政策の当面の課題
1) 幅広いニーズに応えられる「対人福祉サービス」の促進。
2) 地方自治体の分権化を進めつつ、自治体が財政的に自立すること。
3) 福祉サービス提供事業者の多元化を進め、新しい公私の役割分担を明確にすること。
4) そのうえで予防的な施策を打ち出す。
5) 現代の福祉問題に立ち向かう主体形成を勧め、住民が自律化すること。
(5番目が地域福祉の最大の問題では?〓)
地域コミュニティの持続のためには、福祉社会開発学に内包される地域福祉や居住福祉といった方法論が有効。
▽28 鶴見和子「内発的発展」は、近代化論(後進国も欧米と同じコースをたどって近代化するという考え)に対抗しうる地域社会の論理。それぞれの地域がそれぞれの自然生態系と文化にしたがって、住民の創意工夫によって発展の道筋を創り出すことを提唱。
「近代化論の場合は、はじめに一般理論があった。その理論にしたがって、国際比較をすればよかった。内発的発展論の場合は、順序が逆である。地球上さまざまの場所に芽生えつつある実例を、注意深く見守り、……相互に比較をすることをとおして、理論を、低い段階の一般化からより高次の一般化へと、徐々に構築してゆかなければならない。そのようにして育まれる理論は、それぞれの地域に根ざして、多様であろう。多様な実例と多様な理論とを、どのように共通の目標にむかって、つなぎあわせてゆけるかが、内発的発展論のもっともむずかしい挑戦的課題である」
地域福祉や居住福祉は、実際に現場で生じている事実や声に耳を傾ける学問であり、……福祉社会開発学構築の方法論として、内発的発展論は不可避なのである。
▽吉田邦彦 民法学者
▽32 所有権問題の川島理論 「商品交換」が強調され、所有の対象物の商品化が一般化されるが、居住問題にそのしわ寄せが出ている。居住は甲斐性の問題とされ、、災害にあっても個人補償はされないというドグマは、そのあらわれ。市場主義社会のアメリカの萌芽よっぽど、居住問題では議論が多い。
▽35 地方=中山間地には「公共的価値」があることに目を向けることが、所有理論の問題として忘れてはならない。中山間地問題は、個人主義的な私的所有理論では賄えず、ここでも公共的支援のシステムが必要になる。
▽40 合併の影響 教育機関統廃合、医療機関減少、交通機関削減(ふるさと銀河線=池北線が終了)、過度な規制緩和による大型店進出に起因する中心部商店街の空洞化。高齢者福祉に配慮する商店街の再生としては、巣鴨のとげ抜き地蔵、米子の田園プロジェクト、松江の天神町商店街の白潟天満宮を核とするもの(とげ抜きがモデル)……。〓
▽48 「西洋をモデルとした近代化の論理では日本の近代化を完全にはとらえきれない。切り捨てられたりしたものの中に大変大事なものがあるのだろうか」という鶴見和子さんの考え方を軸に、高度成長期におけるコミュニティ形成と現在のコミュニティ再生の意味の違いを論じる。
▽50 伊丹空港に隣接する中村地区 大騒音があるが、不法占拠ということで防音措置は全然執られていない。家屋によっては汚い水を今も飲んでいる。
ペルーでは、何百万という不法占拠者urban squattersに所有権限を与え、経済発展につなげるという注目すべき施策。
▽53 居住の問題は「蛸壺」的に細分化させて考えるべきではなく、関連する雇用や医療・福祉、消費生活、交通などをトータルに見て、コミュニティ再生のあり方を考える。 ▽61 早川
全国の地蔵を訪ねる旅〓
▽70 ニュータウン 身のまわりに老人や障害者や病人がいない。死者と向き合うことがない。そういうことが子供の優しい心を育てられなくなっているのでは。身のまわりに病人がいたら見舞いに行きなさい、死んだ人がいたら子供を連れてお葬式にいきなさい。
商店街 総合的生活居住福祉空間という視点で再生するのが課題。その大きな柱が人が住むということ。……さまざまな店がある。生活文化の結晶。子育て支援センターとか、共同作業所とか工夫している。江戸の街と同じように、後ろに住宅がたくさんないと繁栄はもどってこない。
中心市街地に人が住めるようにしていくことが商店街の再生。
▽74 寺とか地蔵とか、銭湯をデイサービスにしたり。山陰の八橋駅は無人駅がふれあいセンターになっている。これらを居住福祉資源として評価し、再生していく。
とげ抜き地蔵 190の商店のうち6割は自由にトイレを使える。
鷹巣町でも、地元青年団といっしょに元気ワールドという休息室をつくって、大きなトイレをつくった。それ以来、障害者やお年寄りの外出が増えた。
▽76 伊達市 知的障害者の施設。民家を借り上げて町に住んでいる。家賃は北海道と伊達市が保証する。だから家主も安心して貸す。
商店街の空き店舗を使いたい、というとき、米子市や鳥取県が保証しましょう、というのがあれば、ずいぶん貸してくれるのでは。
▽77 沢内村
▽79 深沢村長 教育長になると、婦人が意欲をもてなくては村作りはできないと、地域ごとの婦人会をつくる。これが、「自分達で自分達のいのちと健康を守る村」の組織的な活動母体となった。
▽88 沢内村の村政をなしえた理由 (1)深沢村長の村づくりの哲学と住民の村自治意識の継承 (2)沢内村の状況をふまえての地域包括医療体制の確立 (3)国民健康保険法が1958年に全面改正され、農民や自営業者も国民健康保険の被保険者となったこと。
▽91 国民健康保険料の収納率も99%。会計も黒字だったが、医療費抑制や交付税削減で、次第に窮地に追い込まれる。保健・医療スタッフの不足を拡充できないまま。2人の常勤医師が週3日ずつ泊まり。そのほか毎月50人ほどを3人の医師が訪問。
介護保険をきっかけに、保健師の仕事がデスクワークに縛られがちになり、住民との接触が減る。
▽96 合併を選ばなかった自治体。人口1万人未満の自治体が27%。
▽98 湯田町 ダムによる中心部の水没、鉱山も相次いで閉山。過疎化がすすむなかで、巨額を投じて銀河ホールを建設。演劇活動が高齢者の自己実現や仲間作りに展開。2004年までの10年間に住民の3分の1が部隊に上がった。
▽101 「まず、集落単位に農村自らが自前で努力すること」「集落が活性化すると、役場の重要な役割は、住民の取り組みを応援することに変わる」
▽鷹巣町の場合
▽107 ケアタウンたかのすは、全国で初めての「全個室・ユニット型」老健を基本にした在宅複合型施設。監視カメラやセンサー、外からの鍵などは一切ない。人員配置は国基準の3対1を大きく上回る1.4対1。
▽109 高齢者安心安全条例 介護スタッフによる、利用者の心身への介入行為を「権力行使」と呼び、にらむ、無視する、利用者の手をとって意思に反する方向に誘導したり……もそれに該当した。権力行使を記録に残し、町に報告することを義務づけた。じょくそうの報告も義務づけ。
▽ 2000年の地方自治法改正が追い風に。「国は国家存立に関わる事務を重点的に担い、住民に身近な行政は地方公共団体に委ねることを基本とする」と明記。「機関委任事務」が廃止され「自治事務制度」が登場。自治事務の代表選手が介護保険。「自分たちのことは自分たちで決める」という住民自治の本旨を介護保険を通じて住民が学べないか考えた。介護保険料をワーキンググループ方式で決めることに。
……鷹巣町は健全財政を維持。2003年の地方債現在高倍率0.957 (県内69市町村で1位)、起債制限比率4.1(3位)……
▽2003年に町長交代。「合併」が「福祉」を凌駕した。多くの高齢者が「もう福祉はいい」と考えるようになっていた。相手陣営は「福祉に掛ける金はもったいない」と、高齢者を追い込んだ。その結果、高齢者は、福祉政策を拒否し、その分、子や孫達にお金を掛けるべきだと考えるようになった。
新町長は、福祉公社への補助金を2年かけてゼロに。ミニデイ廃止、紙おむつ支給廃止、グループホーム廃止、、「上乗せサービス」廃止で上乗せ分が1割負担だったのが全額負担に。高齢者安心条例廃止……。08年、ついに「ケアタウンたかのす」の管理、運営を福祉公社から市社協に切り替えた。
▽長野県栄村 合併否定
▽122 ヘルパー資格者は2,3級あわせて160名に。村内8地区8班に編成。「げたばきヘルパー」。
▽鳥取県三朝町・智頭町
▽137 鳥取県・岡崎博司 従来の補助事業を廃止。三朝町の中山間の活性化交付金をつくった。2000万円までは県が出す。あとは市町村が御自由に。補助率は市町村で決めて、その二分の一の財源を保険する。……というと、市町村担当者は「ほかの町村とのバランスが悪いから困る」という。
地域座談会を1年間で180箇所回った〓。いつも夜。しかも土曜・日曜。各地域から知恵がどんどんでてくる。〓「標準化政策をするな、国と一緒のことをするな」と注文される。農村という言葉も中山間地という言葉もあわない。専業農家など10人いない。その中で農業政策をしていっても何もできない。
▽140 110の集落にアンケートをとった結果、福祉関係では、中山間地のほうが進んでいる。
何が問題かというと、「コミュニティ」が根本的に欠落している。それと住んでいる人の意見がはっきり聞こえてこない。それなのに、周りの人たちが勝手に動いてしまう……
▽145 「ひまわりシステムのまちづくり」 智頭町のひまわりシステムの意義は、手間暇かけてコミュニケーションをはかること。
▽148 鳥取地震 壊れた家屋にいつづける人。「一度でたらもう帰ってくることができない」という。そこで、住みつづけるシステムをつくり、ほとんどの人が帰ってきた。県による300万円の住宅補助。
▽智頭町 寺谷篤 1983年に智頭町に帰郷
▽155 地域住民が身近に社会科学を学習する場を設ける。山林を持つ者と持たない者という関係性、山林地主=有力者という図式。
「社会システム論」
青少年の海外派遣事業、カナダからログビルダーを招いて智頭杉を使ったログ建築事業、年1回2泊3日で地域リーダー、行政マン、研究者らがあつまる「杉下村熟」開講……
「社会心理学」
▽161 「人材がいない」と言っている人は、マネジメント能力がないと言っていることと同じ。人材がないと言っている人こそ、ボス的感覚の持ち主である。良い舞台では、誰でも人生役者になれる。社会システムという舞台と土俵づくりを。ただ、舞台づくりをした者は絶対に役者になってはならない。
人は一人として同じ者はいない。その人の個性を認め、その人自身が気づいていない特性を引き出し合う関係をつくれば、今すぐにでも変わる。
ところが、本質的に自分は認めてもらいたいが、相手に関心がないというのが、人の陥る所為である。
▽162 自分自身を開放する術として言葉の持つ意味を考え、語彙にこだわり続けてみると、物事の本質が見えてくる。
▽164 1996年、私の住む長瀬集落にも、すったもんだの抵抗はあったqが、集落が希求している公民館の建て替えをえさにして全員参加のボランティアの「集落振興協議会」が設立。
月2回発行の地域内情報は240号……味噌づくり、食文化の伝承活動、東屋を建て……
実際の地域の活性化に挑戦しながら、地域社会の外にヒューマンネットワークをつくりあげていた。集落内に自閉し、地域変革だけに捕らわれていたなら早々に挫折したろう。誹謗・中傷・電話での抗議などで、家族も毎日が緊張状態となっていた。それでも孤高を貫けたのは、社会システム論、人間科学論を教えていただき、2人の先生を通じて、各国の研究者や活動家と出会い……
▽吉野
札幌のNPO「森を建てよう」、「川上さぷり」……
▽177 吉野林業の特徴 山守制度 植林面積の90数%が村外の人が所有。地元の人間が山主にかわって木を植え管理する。伐期に入ると、優先的にその木を分けていただく。川上村には田圃がない。山一本で今まできた。山を持っていただくと、年利3%でまわす。「山に投資してくれあませんか」ということで、村外の資産家の方々の資金を導入してきた。それが山守制度。
▽183 外材より、私たちの組合の材料は2割高い。でも、1棟建てるのに木材の構造材は10%。1棟1000万円としたら、2割高くても20万円。だから、宣伝広告費を使っているハウスメーカーと十分に競争できる。





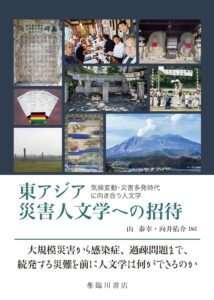


コメント