ハジリコ 20080311
木次乳業をつくった木原忠吉さんの半生の記録。
木次は、たたら製鉄が戦前まで継続していた。エネルギー革命と繊維革命で、たたら製鉄はもちろん、副業だった炭焼きや和紙、養蚕がダメになる。和牛もすたれる。タバコもうまくいかない。そんな状況で酪農に目をつけた。
1961年の農業基本法以来、国は乳牛にホルスタイン導入を進めたが、木次では風土に合うブラウンスイスを導入した。農林省の指導で、化学肥料をばらまくと青々とした牧草ができたが、牛は情緒不安定になり、妊娠しなくなった。山野草中心の飼い葉をやると健康を回復した。主流の高温殺菌に背を向け、自然に近いパスチャリゼーション(パスツール殺菌法)を導入した。
「私は政府の政策は無視する。お上が決めたことがえらいという権威主義とは縁をもちたくない。……農水省は北から南までホルスタインならホルスタインを入れろという。北方系の牛を南で飼ってもうまくいくわけない」
木原によると、農民が自立の精神を失ったのは、戦中の食糧不足でできた食管法に始まる。戦後の昭和22年に食管法が強まり、農業協同組合法ができ、農協に専従が設けられて農作物をぜんぶ農協に売るようになり、農家は売る努力をしなくなった……。
「自分の生産物を自分で売ろうとしたら世界経済も見とらんといけんから。そういう自分の考えで行動できる農民になろうというのが大坂君や私の考えだった」と言う。
売り先も、経営判断も、「依存」から「自立」へと、ひたすら歩んできた。
彼のような人物が生まれ、木次乳業ができた背景には、その土地で培った風土もある。
そもそも出雲の古代王権は中央政権に滅ぼされている。さらに木次は、保守的な出雲にあって、戦前の産業組合運動の中心であり、社会主義やキリスト教の運動があり、つねに中央に異議を唱えてきた。戦後は生活綴り方運動もあった。行きすぎた「農村の近代化」によって、着物をやめて洋服を着るとか、村のしきたりや祭り、伝統芸能を因習として廃するといったマイナス面もあったが、反権力と民主主義の伝統が、彼らの反骨精神の背景にあったのは間違いなかろう。
======================覚え書き・抜粋======================
▽14 ホルスタインをやめてブラウンスイスを乳牛として導入。
穀物依存型の飼料になったのはなぜ? 1961年の農業基本法から、食べ物は工業製品化していった。1頭あたりの乳量を増やし、管理コストをおさえる。
▽38 山を崩して砂鉄を沈殿させて採取。だから、土砂が流出して天井川になった。鑪製鉄は戦前までやっていた。江戸時代から和牛の産地。
▽54 藤原藤之助 先生となり、木次の青年を自宅に集めて毎月2回「鶴声会」。
▽57 出雲市は保守的だが、木次は革新の票が昔から多かった。戦前の産業組合運動もここが中心だった。
▽63 木次は、漁港で上がった鯖を生のまま運べる限界といわれた。……名物堅炭でジリジリと焼く焼鯖と焼鯖寿司が名物。
▽78 出雲湯村温泉 酒は「斐伊川おろち」〓上流の田で有機でつくった米を使い、中流の伏流水を用いて酒を醸造し、下流の都市で飲んでもらう。……みんなで10万円ずつ出し合ってつくったあそびと運動を兼ねた酒。
▽ 大阪貞利 亡くなった
▽96 石油、石炭エネルギーが入ってきて、薪・木炭の需要がなくなって、中山間地の主要産業だったがかげりがみえてくる。和牛もだめ、和紙もだめ、養蚕もだめ。いまの町長の田中豊繁と鳥屋久義と3人で酪農でも始めようかということになった。
▽98 大事な副業だった、養蚕・炭焼き・鑪製鉄が、繊維革命と燃料革命でだめになった。タバコもうまくいかない。何もかも専売公社の指導員の言うとおりにやらないかん。
▽104 加藤歓一郎 氏神様で皇軍の無事をいのることを拒否して左遷。特高に思想調査される。神社参拝にも従わなかった。……戦争が激しくなると国家主義に向かうが戦後、復員すると、キリスト者としてやり直すことを近い、日登中学で生活綴方運動をつづけ、文集「ひのぼりの子」を発行した。「考え方は宮沢賢治に、行動は田中正造に学べ」。そのときの愛弟子が大坂貞利。
▽106 農業基本法 農林省の指導で、化学肥料をばらまくと青々とした牧草ができる。収量が増え、酪農経営を安定させるはずだった。が、牛は情緒不安定になり、妊娠しなくなり、しまいには起立不能に。大坂が「化学肥料でつくった牧草が原因では」と。そこで、山野草中心のかいばをやると再び健康になっていった。
▽114
▽118 高温殺菌牛乳が主流。自然に近い殺菌法をさがし、パスチャリゼーション(パスツール殺菌法)を知る。63度で30分、72度で15秒。
最初に扱ってくれたのが、松江の自然食品店の北脇さん〓
▽130 松江「たべものの会」「出雲すこやか会」
▽140 出雲の古代王権が大和朝廷に滅ぼされ……近代になってからも、社会主義の運動、キリスト教の運動があり、つねに中央に異議を唱えておった。除外される立場からモノを見るくせがついとう。
戦後、農村の近代化といって、禁酒禁煙だの結婚浄化運動といって簡素化をすすめるなどあった。……着物をやめて洋服を着よう、非生産的だから先祖から大事にしてきた庭の銘木を切って果樹を植えようとか。村のしきたりとか祭り、伝統芸能はみんな因習ということになって、あのとき一挙にくずされましたな。〓
▽142
▽156 私は政府の政策は無視する。現場を知らんもんが、農民でないもんが、机の上で計画をたててうまくいくはずはない。お上が決めたことがえらい。そういう権威主義とは縁をもちたくない。……農水省は北から南までホルスタインならホルスタインを入れろという。北方系の牛を南で飼ってもうまくいくわけない。
▽164 奥出雲葡萄園のワイナリー〓
▽170 「しろうさぎ」という豆腐屋〓。
「風土プラン」〓
国産小麦と大豆と自然塩の醤油をつくる「井上商店」
「影山製油所」の菜種油 ナタネトラスト
山陰建設 カニの甲羅からキトサンをつくり、それを肥料とした有機のイモ栽培
有機コーヒー豆を扱う「桃翠国」
かん水なしでラーメンをつくった「高橋製麺」
「杜のパン屋」〓〓
▽188 木次・大東・加茂・三刀屋・掛合・吉田など6町村合併で雲南市に。「合併すると画一的になっておもしろみがなくなると思いますがね。しかし上からガッチリ補助金とかなんとか、金縛りになっとうから。合併反対以前にまず、行政に頼らないことからはじめんと、どうしようもない」
▽190 農民が自立の精神を失ったのは、戦中に食糧不足でできた食管法に始まる。戦前も農業組合、産業組合をやっていたが、まだお上の管理がゆるかった。戦後の昭和22年、食管法が強まり、農業協同組合法ができた。農協というところに事務をとる専従がいて、農作物をぜんぶ農協に売れるようにした。競争がなくなり農協の独占になった。……農協は農家の預貯金を農林中金へ吸い上げ、肥料や農薬や機械を農家に売りつける。……農家は売る努力をしない。
自分の生産物を自分で売ろうとしたら世界経済もみとらんといけんから。そういう自分の考えで行動できる農民になろうというのが大坂君や私の考えだった。
▽194 木次乳業 定年は? 72歳の社員もいる。若いもんはこまごますることはいやがるが、年寄りはそれが苦でない。経験もある老人にはただ老齢年金を出し、ゲートボール場を作るというのは福祉じゃない。「若者に希望を、老人に仕事を」〓
▽ついでに遊びの時給。乗馬クラブを立ち上げようと。ついでに音楽も自給してバンドを楽しむやつもおった。あとは教育の自給。




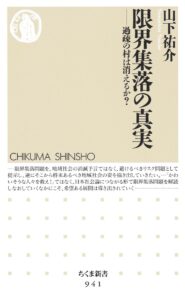
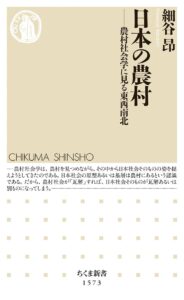


コメント