岩波新書 20071111
セイ法則がキーワード。供給が増えればそれによって需要は増えるという考え方であり、これがなりたつということはいくらでも投資機会がある状態だから、完全雇用がなりたっていた。
ところが、消費社会となり、投資の機会がなくなると、どんなに資金があっても投資しようがない。そういう社会では、神の見えざる手による完全雇用はなりたたない……。
新古典派の経済は、かつてはなりたったが、今の時代にはなりたたなくなった。マルクスは新古典派を批判していたが、セイ法則を無自覚に前提とした理論を組みたてていた。セイ法則=価格機構からきれいに離脱し、反セイ法則=有効需要の原理に経済の基幹部をとりかえたのがケインズだった。
社会主義崩壊についても同様な視点から分析する。
無理をして完全雇用を実現しようとするから、不必要な大規模施設をつくったり、御殿をたてたりする。そういう「社会主義的搾取」が崩壊の原因になったという。
なるほど、そういう分析視点があったか、と思った。トッドは人口や識字率という視点からソ連の崩壊を予想し、クルーグマンは生産性の面から分析していた。それぞれに説得力がある。
経済が上部構造を含めたすべてを規定するというマルクスの唯物論、上部構造の下部構造への影響を重視するウェーバー、下部構造に人口の増加圧力を規定する高田保馬の理論……といった、社会学と経済学を融合させる視点もユニークだ。森嶋自身は三者のいずれかが正しいと結論づけるのではなく、時代によって適用できる理論はかわってくると考えている。が、彼の著書を読むとウェーバーの影響が色濃いことは想像に難くない。
----抜粋・要約-----
▽反セイ法則の世界 耐久財のもつ比重が大きくなり、容易に生産過剰が起こりうるようになったから生じた。社会主義経済でも、生産力が増大して耐久財の生産過剰が容易に生じる段階では生じる。社会主義経済では、ある限りの貯蓄を効率を無視して投資に使用した。効率を無視するから生産すべきものは無限にあり、失業の憂いはなかった。だが……
▽マルクス 大企業はますます巨大になり、必要とする生産手段はすべて社内で自給するようになり、生産手段や中間生産物の市場は存在しなくなる。それらの価格も市場価格でなくなる。それは社会主義的国有化の一歩前の段階である。……イギリスの分析 =コーヒー農園も〓
▽「産業革命は、イギリスにとっては、政治上の革命がフランスに対し、哲学上の革命がドイツに対して持っているのと同じ意義をもっている」(エンゲルス) フランスやドイツにおいては、歴史の経済的説明よりも、上部構造の変化による説明のほうが有効だと主張しているのである。……彼らは十分に謙虚だった。
▽ウェーバー ヒンドゥーや古代ユダヤ教は現世否定的であるから経済を動かす精神的動因でありえず、現世の問題に合理的関心をもつ新教と儒教のみが経済倫理を提供する可能性をもつと結論した。さらに、新教の合理性は、現世を合理的に変革するという積極的合理性だが、儒教は現世に合理的に適応するという消極的合理性だから、儒教社会では、近代資本主義が積極的に興隆することはあり得ないと結論した。
▽ウェーバー私企業官僚制 近代工場においては、一人一人の労働者のすぐれた技能が必要なわけではない。それゆえ労働者のそれぞれの働きを査定することは無意味で、労働者の限界生産力という概念も存在しなくなる。労働者も官僚としてあつかわれ、年限に応じて職階の階段をあがっていく。こういう制度がしかれると、労働者の会社間移動が難しくなる。日本はそうなったが、西欧で労働者の官僚化が遅れているのは産別の労組が抵抗するから。労働者が会社間を移動しなくなれば、産別労組より会社別労組が支配的になる。
私企業官僚層上層部の勢力が強化される。大きな会社になると、株主は分散し、強力な個人株主が少なくなる。株主との比較で経営者の発言力が非常に大きくなる。そういう企業は1930年代に欧米に現れたが、日本ではいっそう徹底的な形で実現された。
><コーポレートガバナンス
▽官僚化した会社員は、出世を望むから、賃金だけを目当てに働いているわけではない。労働争議は少なく、安定している。逆に、官僚は出世主義だから、より多くの部下をほしがる。職員数は増えがちである。官僚機構は自己増殖し、常に拡大する。非効率化し、社会主義国では、体制の命取りになった。
不効率を是正するには、部局を整理し、外部にその仕事を委嘱するしかない。下請け会社の官僚機構の自己増殖は、他の競争的下請け会社があらわれることで抑制される。官僚制のなかにいかに市場を介在させて、競争的官僚制をつくれるかどうかが問題。
……会社官僚は金がないのに大勢力をもっているが、一方で官僚社長は、自ら出資していないことのゆえに、不況時や緊急時に決断力を欠くという弱点をもっている。
▽セイ法則「供給は需要をつくる」 投資需要を分析する必要はなくなる。投資は常に貯蓄に等しくなるから。
「耐久財のジレンマ」
第一次大戦後は、貯蓄に等しいだけの投資がすぐさま準備され、完全雇用が保証されるような世界ではなくなった。「反セイ法則」の経済に転換し、完全雇用はもはや実現しなくなった。
こうした状況下では、強力な政府が政治的に投資を創造する以外にない。手っ取り早いのが戦争。さらに新領土ができれば、新市場向けの生産ができるから、雇用増大に貢献する。日本の満州事変。イタリアのエチオピア侵略、ドイツのヒトラーの1935年の再軍備宣言。軍備と戦争が1930年代の投資をある程度支えた。
このように、経済構造がかわると、プロテスタントの禁欲の精神が資本主義を興隆させるという説もなりたたなくなる。反セイ法則時代には、節約や禁欲は、経済に悪影響をあたえるという意味で悪徳である。こうしてウェーバーの「倫理」における命題は現実的重要性をもたなくなった。
▽社会主義的社会では、人件費の削減は困難。生産物は割高になり、国際競争にやぶれ、国際収支は赤字になる。財政も赤字になる。批判の声がおき、知識人の考えは右傾化する。マネタリストが台頭する。=サッチャー
サッチャーの誤りは、新自由主義が反セイ法則の経済に不適合であることを自覚しなかったことにある。耐久財に関する市場のジレンマのゆえに、見えざる手は働き得ない。完全雇用均衡は、投資不足のゆえに実現せず失業が生じる。
▽社会主義的搾取が高度に達し、それが社会主義的独裁と結びついたから崩壊した。過度な軍備をしたり、党幹部のための豪華別荘を建てたりする搾取。公共財を過度に生産したりするため、人民を過度に働かせる搾取。計画当局が無能であったときに浪費される労働という搾取。そのような搾取を抑止する権力機構が社会主義社会になかったことが、体制崩壊の原因だった。
誤りを訂正するシステム。社会主義社会では、中央政府が意志決定するから、誤りを訂正することは、中央政府の権威を損なうことになる。計画経済での価格適正化が重要なのに、不適切な価格がつづいた。一党独裁社会では、政府を査察・監督する機構が存在せず、搾取が是正されなかった。
よりよい価格を見つける努力を中央計画局が惜しまなければ、生産財の国有化は社会主義経済の致命的障害とならなかった。それには、中央計画局を、いくつかの資本主義国の中央銀行のように、政治的に中立化することが必要だったろう。
社会主義経済でもっとも重要な概念は「計算価格」であり、それを求めるにはスパコンを必要とする。それゆでもっとも重要な産業部門は電子工業部門であったのに、ソ連は軽視し、社会主義とは無関係な軍需財部門や宇宙工業部門を重視した。国家主義がもたらした明らかな失敗である。
▽ケインズ 第一次大戦のドイツの賠償額 不法なほど莫大だった。ケインズはそれに反対した。
「供給(貯蓄)はそれ自身に対する需要(投資)をつくる」というセイ法則が満たされなくなる。こうした時代の転換をみこしてケインズが登場し、セイ法則=価格機構から、反セイ法則=有効需要の原理に経済の基幹部をとりかえた。
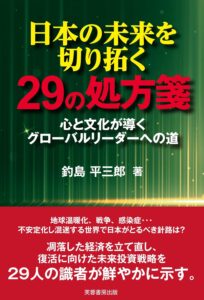

コメント