■地域再生の罠<久繁哲之介>ちくま新書 20100928
専門家が賞賛する地域再生策のほとんどは成功しておらず衰退している。都市計画や建築、都市工学などの「土建工学者」が推奨する、本当は成功していない「成功事例」を視察して模倣するからほぼ確実に失敗する。そんなことのくり返しだという。
たとえば松江市の天神商店街は、お年寄りを対象にした町づくりで「成功」したとされているが、月に一度の「市」の日以外はガラガラ。ふだんは車の通り道でしかない閑散とした町だ。なのにそれを「成功」として模倣させる。
コンパクトシティという考え方も問題だ。岐阜市はコンパクトシティを唱えて中心部に巨大なマンションとの複合ビルを建てた。なのに、町の住民の足である路面電車を廃止してしまった。役所の縦割り行政によってまるで矛盾することをやった。巨大ビルを建てるカネがあれば路面電車の赤字55年分を補填できたという。成功事例とされる富山市も〓〓だという。
そもそもコンパクトシティは欧米で生まれた。人付き合いの積極的な欧米人は、街中にでかけてカフェで食事をして1時間も2時間もおしゃべりに興じる。そういうスローライフの伝統があってはじめてなりたつあり方だ。郊外の住宅から街中に日本の老人を移住させたら、孤独死や認知症が続発することになるだろう。
では本当の成功事例はどこにあるのか。佐賀県武雄市は、役所の意識改革からはじめ、〓〓をした。
新潟市はサッカーの球団を育てることで市民の一体感を増し、その結果、若者が市中心に集まるようになり、その後に専門学校を建設した。
久留米市は名物の焼き鳥屋を子供たちもつどうファミレスのように位置づけ、日曜日などに家族で集えるようにした。そのため外資のファミレスの進出も少ないという。
これまでの「上からの活性化」は提供者目線で成功事例などのハウツーに飛びついていた。それを消費者目線に変えて、表面には見えない「本音」を知ることが大切だ。まさに地区診断の発想であり、消費者目線の物作りの発想である。そんな本音はどこにあるのか。利益追求ではなく「公益」。人との出会いや絆づくりの場……
そのうえで具体的な処方箋として、絆づくりになる中心市街地へのスポーツ施設と飲食店と有機的な連携や〓〓などをあげている。
「心の空洞化を感じる」 市民に愛される「地域づくり」とは、市民が優しく包みこまれる空間と時間を創出すること。交流の「居場所づくり、機会づくり」
地域再生の本質は「交流、心の再生」にある。
街中の衰退が加速する地域は、飲食店を核に、交流需要を創出する施策を打ち出すべき。〓〓
=============
▽17 宇都宮は大型商業施設は相次いで撤退しているが、地域資源を生かす小さな店の集客力は高い。
▽20 「提供者側」の中高年男性ではなく「消費者側」の若者と女性の会話に五感を傾ける。
▽23 民間企業は市場調査をするが、地域再生では、3割の自治体が地域住民の意向を把握しないで計画策定。7割も、ごく簡単なアンケートで住民の意向を把握したつもりになっている。(日本版スローシティ 57ページ)
▽25 自治体アンケート コンサル「丸投げ」が多い。
▽33 中小規模の地方都市街中から、近い将来「百貨店など物販主体の大型商業施設」はほとんどなくなると予測する。大型商業施設の誘致は失敗する。
なのに、街中に一極集中させようと大型商業施設の誘致に邁進する。
▽39 商業施設でも商店街でも「開業時とイベント時は賑わう」=「話題性確認消費」
▽39 松江市の天神町商店街 成功事例とされる。県職員は「月一度だけ賑わう施設を成功事例として扱うのは、問題ありますね」。市職員は「月一度であっても賑わうのだから、成功といってもよいと思う」。前者は「一般市民の目線」。後者は「提供者の目線」。成功事例集とは「提供者の目線」から事例を選び、その良い点だけを記述して賞賛するプロパガンダ。……松江市は商店街に「高齢者に優しいまちづくりのモデル地区に」とお願いした。なぜ税金をつかう商店街支援を「市役所からお願い」する必要があるか。
「成功モデル」とし、視察に訪れ、模倣する。
▽53 ・顧客が不足しすぎるから、顧客を集める事業。・売り手が不足しすぎるから、商店主を集める空き店舗対策。矛盾する施策。客も売り手も少なすぎて困っている商店街は、そもそも必要なのか?
▽54 レトロ化、高齢者対応化は花盛りだが……集客力が限定されている理由はそもそも需要と供給に根本的ギャップがあるから。「商店街の選択と集中」が求められる。
成功事例の「レトロ化」のほとんどは外装だけ。
▽59 イベントは、非日常的な楽しさと、顧客も商店主も気軽に会話できる雰囲気が必要。
▽60 長野市の「ぱてぃお大門」、昭和の町の豊後高田の商店街。立ち寄るだけで、商店利用やリピートにはつながらない。イベントもレトロ化も、今は消滅しかけている「商店主と顧客との交流」を再生する手段として、位置づけることが重要。
▽61 天神市の日は歩行者天国「人間優先空間」になる。それが魅力。でもふだんは「車優先」。出雲市の「中町商店街」も車優先空間で、恰好の自動車の抜け道となっている。▽67 チャレンジショップでは出店者の負担が大きすぎるから応募者がいない。「曜日毎テナント、日替わりテナント制度」ならば、制度を出店者側の都合に配慮するようにすれば、応募者は名乗りをあげてくれる。ただ、管理が大変だから自治体はやりたがらない。
商店街の位置づけを「ものを売る場」から「交流・憩いの場」へ。
▽73 同人誌は一度はすたれたのに、コミケは成功した。「楽しく交流できる」という価値が参加者をひきつけた。商店街再生にも「仲間うちで楽しめる・交流できる場所」への転換が必要。仲間とは「地域の市民」
▽ 松江のカフェの町に。門脇ファミリーなど有名なカフェは郊外にある。これらを松江市の街中や水辺の散策路に好条件で出店してもらう。
島根県は日本で最後の「個人経営者が支えるカフェ文化の聖地」といわれている。個人経営者が増え続けている。スタバは、青森と山形と島根と鳥取の4県に進出していない。島根と鳥取は優秀で意欲的な個人経営カフェが多いため、勝算が低いと判断しているのだろう。〓〓
門脇洋之さん、弟の祐二さん、父の美己さん。日本を代表するバリスタ「門脇ファミリー」に憧れて、バリスタを目ざす若者が集まり、カフェを開業している。
スタバ幹部が門脇さんの店を訪れ「東京でお店を出しませんか」と提案した。理由を問うと「門脇さんがこの地域にいると、うちは進出できないから」
▽84 模倣は「資本や規模の大きな者」に有利なビジネスモデル。地域産品を高く・多く売ろうとする考えをあらため、市民の交流を促す場として野菜直売所を位置づけ直す(内子のからり〓)
▽87 小樽は観光ブランド化、寿司屋通りのブランド化は成功しているが、豊かになったのは、小樽3点セット(寿司、運河、ガラス)を構成する一部の産業者にすぎない。
▽92 長野のぱてぃお大門は、小樽のような3点をセットするという戦略もない。
▽100 中高年男性がまず耳を傾けるべきは、専門家ではなく、顧客や市民の本音の声。旅館の若い従業員に話を聞く。
▽104 若者が自由時間をすごす場所は自宅が圧倒的。
▽119 岩手県滝沢村が「日本経営品質賞」を自治体としてはじめて受賞。地域づくりにもっとも欠ける「顧客志向」が重視された。
自治体固有の風土・文化を「固辞」する岐阜市、「打破」にとりくむ武雄市。
武雄市「いのしし課」。上勝町に視察に行って、葉っぱを安定供給する仕組みを学び、イノシシの安定供給に生かそうとした。葉っぱビジネスの模倣のためではなかった。上勝で学んだのは、役所と市民の信頼関係と、市民が主役になれる仕組みを築くこと。
▽128 衰退する自治体に特徴的なのは、専門家や国など「上から降りてくる情報」のみを収集しがちだ。手間がかからないからだ。
▽132 05年に岐阜市は路面電車廃止。赤字でも残したのは高岡市。「万葉線」存続。
電車が廃止された街中はどこも衰退する。
▽143 松江市など市全体の小売り販売額に占める中心市街地のシェア推移(97から02)はマイナス5からマイナス9%。鹿児島は上昇率が県庁所在地で1位。
▽153 コンパクトシティ 西欧人は人と交流するのが好きで、にぎやかな場所に毎日のようにでかける。おしゃべりを延々と楽しむ。スローフードの本質はここから生まれた。このライフスタイルには、職住近接な都市構造が求められる。
▽157 ネーミングライツはハイリスク。コスト意識やリスク意識が問われる。従来の看板の置き換えだけでもかなりの額がかかる。「5年間5千万円」未満の事例は、広告効果の低い小都市や停留場名などに限られる。
そもそも、「スポーツ競技場の名称」を対象とするビジネス。スポーツならば、施設名称がかわっても、そこで催されるイベント内容はファンに必ず伝わる。「顧客志向」。市文化交流センターを銀行名にしてしまえば、目的が市民にわからなくなってしまう。松山の県民文化会館などは×〓)
▽162 地域再生の罠罠のまとめ 「目に見える」「誰でもわかる」ものを偏重し、とりわけ「数値や力の大きい」ものや権威に依存する。「目に見えない」「気が付きにくい」ものを軽視する。「重要なのに気がつきにくいもの」のうちとくに軽視されやすい「心、文化」
▽167 土建工学者は「人の心を捉えるソフト事業」には目を向けず、「器づくり、箱物づくり」を推奨。器や箱物だけは立派な地方都市ほど疲弊している(伊方・鹿島)
市民が主役になって、「人、顧客の心を捉えるソフト事業」を地域再生の核にすえ、土建工学者や自治体など上流が関与しない地域は活性化している。秋葉原、下北沢、巣鴨地蔵通り、黒川温泉、上勝町
▽168 上勝町 模倣できた地域はほとんどない。「町民に持続的に収穫してもらうことも、市場を見つけて持続的に買ってもらうことも、非常に難しい」。上勝町の横石さんは全国各地に行くと「心の空洞化を感じる」ことがあると述べる。
▽177 ウォークマン開発秘話。ものづくりは「技術者・提供者志向」を改め「顧客志向」へと舵を切り始める。技術者・提供者を暴走させないイノベーションが起きた。そのための仕組みが「マーケティング」「インサイト」などだ。
▽183 コミケ 格差を感じさせない心地よい交流が芽生える。現在の地域再生施策は、心の拠り所の重要性に気づかないまま、「商取引」機能だけを支援しがちだ。このような施策に、ボランティア志向の高い若者ほど拒絶反応を示す。
▽190 FCバルセロナ 11万人の市民会員で構成される「地域スポーツクラブ」でもある。高齢者から子供までが会員だから、世代間交流も促す。市民の地域愛と、経済利益より人との交流を育み、にぎわいを創出する。
「街中の低未利用地に交流を促すスポーツクラブを創る」
▽192 アルビレックスが新潟を変えた。市民の地域愛が高まり、それをみはからって、街中に専門学校を建てる。若者が増えていった。「市民の地域愛が先、箱物は後」
市民に愛される「地域づくり」とは、市民が優しく包みこまれる空間と時間を創出すること。交流の「居場所づくり、機会づくり」
地域再生の本質は「交流、心の再生」にある。
▽202 「店が愛され、顧客から感謝を伝えられると、自分も愛されているようで毎日が幸せだ。顧客も私も幸せ、こんな素敵なことはない」
▽207 飲食店がない街中は、市民の足が遠のき、衰退が加速する。千人あたりの飲食店数やコンビニ数を算出すると、島根県は最もコンビニが出店しない地域。〓
地方都市街中再生には、「物販主体の需要吸収型施設」ではなく「飲食主体の需要創出型」の店舗が必要。街中の衰退が加速する地域は、飲食店を核に、交流需要を創出する施策を打ち出すべき。〓〓
▽210 はこだて市場と牧志市場 交通至便な街中に交流需要創出型飲食店を形成する。農産物「加工品」直売所を街中につくり、若者が好むような「地域産品を加工したおやつ」をそろえ、交流拠点にする。……コンビニで地域産品活用を自治体が推進することは疑問。
▽216 久留米 市民が主役になれる「食の八十八カ所巡礼の旅」。やきとり屋を「子供たちの憩いの場」に。「八十八カ所」は、飲食店の選定を市民がおこなう。……「市民が選ぶ入れ替え戦」を定期的にくり返したらいかが?と提案。
「B級グルメ聖地事業」食のB級グルメ化をスローフードに進化させる取り組み。
焼鳥屋が多い。「子供を中心として親子が交流する場」と位置づけ。ファミレスとして愛用される。市内には全国チェーンのファミレスや居酒屋がほとんどない。
▽224 皇居の周囲にジョギングに来る人たちが銭湯に集まる。交通至便なところだからこそ、スポーツ同好の士が集まる。自然発生的に交流が芽生え、飲食店などににぎわいを波及させる。
……スポーツクラブは交流を促し、近隣施設に消費とにぎわいをもたらす。(〓卓球で絆を深める山村集落) 幸か不幸か地方都市の街中は低未利用地にはことかかない。空き地、駐車場、空きビル、空き店舗。そこにつくるスポーツクラブは「スポーツ空間」にとどめる。交流空間は、商店街の飲食店など既存ストックの活用を優先的に考える。
▽235 フリーペーパーのように「入口フリー」にして集客を高め、関連消費を誘発する。スポーツクラブを集客の入口と位置づけ、赤字でも良いと考える。
水晶する





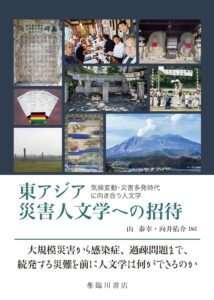
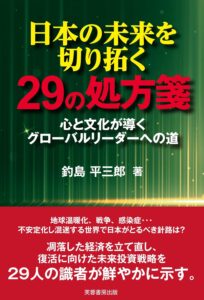

コメント