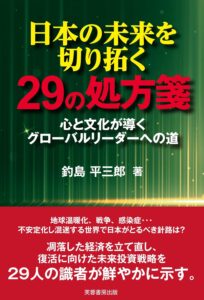洋泉社 20061127
戦略でとらえるだけでいいのか。グローバリズム的な考えだけでビジネスを進めていいのか。モノを媒介に客とのコミュニケーションをはかる、そうしたヒトヒネリした思考のなかに、ビジネスの楽しさややりがいがあるのではないのか---と説く。
「仕事は本来面白いものだ。それが面白くないのは、経営者の底意や制度によって不当に歪められているからだ」といった考えを「マルクス主義的な労働観」と呼んで「いくら仕事は面白いはずだといわれたって、それは無理」と退ける。逆に、最近はやりの自己責任・市場主義・戦略重視・効率重視といったありかたを「ホッブス的」と位置づけて批判する。著者自身は内田樹の友人であり、構造主義的な思考をしている。
ビジネスを哲学のフレームワークで位置づけて説明しているのが新鮮だった。
-------抜粋など--------
▽パワーポイントには、「会社の使命、……市場分析、ビジネスチャンス、コンセプト……」とテンプレートが用意されている。アメリカ型の典型的な要素還元的思考。会社設立に関する要素がきれいに分解されて、わかりやすいロジックで並んでいる。だが、起業家の独創、身体から発せられる言葉だけが入ってない。
▽95年ごろからのシリコンバレーバブル以来、渋谷中心のビットバレーといった恥ずかしい「何とかバレー」があちこちにできた。
▽ビジネスを「モノを媒介としてヒトとヒトの精神の交換」と考えたとき、通常の言葉によるコミュニケーションとは違った含蓄あるコミュニケーションと感じるようになった。モノを媒介としなければ自分の気持ちを相手に伝えることができないようなねじれたコミュニケーションを面白がれるところに自分をポジショニングする。ゲームの参加者になることが必要。
▽シリコンバレーに代表される、スピード経営、戦略経営、直接金融、株主中心の会社経営、労働資本の流動化、企業競争のゼロサムゲーム化といったものが日本に一気に流入してきたのは、勝者の戦略として機能していたから。
これは、米国型の戦略的な経営が米国経済を勝利に導いたということを必ずしも意味しません。経済的勝者が繁栄を永続化、固定化するために現在の戦略を構築したのです。
▽客と「わたし」 商品やトークを媒介して 売る人と買う人という擬似的な人間関係を、それがあくまでも擬似的な関係であると知りつつそれを演じる。演じ方のなかにお互いの「生身」を仮託し、信頼とか誠実といった「本音」を見せ合う。
▽ビジネスの基本にあるのは、よい商品やサービスを作ること、それを必要としている顧客がいること、商品やサービスを媒介として、ビジネスの主体が持っている技術や誠意といったものと顧客の満足や信用といったものを交換することに尽きる。……信用を蓄積している会社が安定的に成長する。
▽「見えない資産」の蓄積には、戦略的、攻略的な方法は必ずしも有効ではない。その蓄積は反戦略的な意思の持続によって確実に達成できる。それは具体的には企業を時間はかかっても着実な成長軌道に乗せる唯一の方法である……ひとりひとりがビジネスの現場で自分たちのモンダイを自分たちの言葉で考えていく。……経営者も社員も「損得勘定」でものを考えるというのがビジネスの世界のもっとも根幹にある倫理……政治的な課題や倫理的な課題を損得勘定のなかで考えるというのがビジネスの思考ですが、ビジネスの課題を政治や宗教の語法で語っているのが昨今の現象であるといえる。攻略しないという方法が、そろばん勘定のなかから出てきていることが重要。
▽「オーバーアチーブ」「その仕事をしますと約束した以上の仕事をすること」「借りた以上に返す」これこそが人間を人間たらしめている根源的な趨向性のように思われる。