■消費税のカラクリ <斎藤貴男> 講談社現代新書 20100830
消費税は逆進性があるけど、消費に対する一律課税だから手間がかからない安定財源である。益税などの業者が得するしくみは直さなければならないが、こうした財政状況では引き上げは仕方ないのではないか--という一般の理解はとんでもない誤りであるという。
まず、消費税の納税義務者は消費者ではない、という指摘に、驚かされる。納税義務があるのは、商品やサービスを売る業者である。中小業者や小売店主は、ほかとの競争があるから消費税分を価格に上乗せできない。なのに赤字経営であっても消費税分は税務署にふんだくられる。だから消費税の滞納は、所得税などに比べても多いという。所得税や法人税は赤字ならば納める必要はないが、消費税はどれだけ損をしていようと取られるからだ。
「みなし仕入れ率」で計算する「簡易課税制度」や、一定規模以下の事業所は免税されるという制度は「益税」として批判された。その批判を利用するかのように、免税業者の枠はどんどん狭まり、簡易課税の適用対象も大きく狭まった。膨大な事務作業の負担が個人事業者にかぶさってきて、税務をこなす社員を置けない小事業所は大変なことになっている。
一方、輸出中心の大企業は消費税によってもうけている。海外への輸出品には消費税はかからないから、その分の還付を受けるからだ。
かくして、消費税を上げるのを喜ぶのは輸出企業であり、泣くのは個人商店などの小規模事業所なのだ。たとえば10%になったらどれだけの中小業者がつぶれるか--と筆者は警鐘を鳴らしている。
目から鱗の本だった。
==================
▽25 19区分最高税率75%だった所得税は、99年から8年間は4区分最高37%になった。住民税の累進課税も89年までに14区分から3区分になり、07年には一律10%のフラット化した。
所得税の再分配機能は消失し、91年に26兆7千億あった税収は09年には12兆8千億に半減した。
▽29 消費税は国税滞納額のワーストワン。滞納額全体の45・8%を占める。
▽34 消費税の納税義務者は消費者ではなく、個人事業者や法人。納税義務者が、その納税分を外部から預かることとされている。が、「価格に消費税を転嫁できない」状態も。
▽43
▽52 消費税転嫁できていないのは、規模が小さな事業所。
▽55 ただでさえ赤字の中小・零細事業者が、力関係で弱いがゆえに消費税分を価格に転嫁できないか、消費税分以上の値引きを強いられ、それでも消費税を納めろと迫られる。滞納だらけにならないほうがおかしい。
▽57
▽60 事業所は消費者に対して、消費税分を上乗せしてもしなくてもよい。
▽62 ……小売商と消費者の間における消費税とは要するに物価なのだ。消費税とは力関係がすべて。
▽64 69 「消費税は消費者からの預かり金的な性格があり、その認識が一部に浸透していないようです」(名古屋国税局長)というまやかしのPR。消費者と小売業者の離反をはかる。
▽77
▽81 消費税の滞納で、従業員の給与まで差し押さえる税務署。自殺。
▽91 仕入税額控除を受けるためには過大な事務負担。専門の要員を置けない零細な納税義務者は大変。
「みなし仕入れ率」で計算する「簡易課税制度」。免税点制度などとともに、中小零細業者のための特例措置のひとつとしてできた。売上高5千万円以下の事業者。当初は5億円以下だったのが大幅に引き下げられた。年商5千万円の規模では専門の要員を置くのは不可能に近い。
▽102 輸出企業は、消費税が還付される。08年度の消費税の還付総額は6兆6700万円。消費税収の約40%に相当する。輸出戻し税
▽105 財界が消費税率引き上げに固執するのは、いくら引き上げても痛くないから。巨大企業は常に価格支配力をもち、消費税を自在に転嫁できる。しかも、輸出戻し税によって巨額の還付を受ける。税率引き上げによって被害を受けないどころか、場合によっては利益を生むことさえ可能。
▽113 直接雇用だが派遣と偽装すれば、「派遣元」に支払う費用にかかる消費税の名目で、税負担を小さくできる。「仕入れ税額控除」の対象にならないものの一つが正社員らに支払う給与。給与などの見返りではない役務の提供を受けた形を整えれば、仕入れ税額控除の対象になる。合法的に節税できる。
▽116 直接雇用をやめて「派遣」に切り替えると節税できる。
▽120
▽125 近頃の建設現場には、雇用された労働者が1人もいなかったりする。全員が個人事業主。1人親方のための健保はない。半世紀前の状況に逆戻り……土建一般労組は独自の健康保険組合を創設。
▽127 安くこき使われるためにだけ独立を強いられ、一人親方にされていく。消費税さえなければ、このような挙にでる必要のない工務店はいくらでもあった。さらに税率を引き上げられたどうなるか……。
▽133 これ以上の税率引き上げは、自営業者の廃業や自殺を加速させ、失業率の倍増を招く。
▽137 1989年の消費税への反発。電通にたのんで、大蔵省がPR作戦。中高年サラリーマンを標的に減税面を強調したキャンペーンが展開された。広告代理店の効果を評価した霞ヶ関は、原発や裁判員制度などでも、国策PRを大々的に展開することになる。
▽148 富裕税廃止と代替財源としての大型間接税
▽157 輸出企業に対し税金を還付することは実質的には輸出補助金に該当し、ガット協定に違反するはず。「ガット協定に違反しないように、国内で負担した間接税の還付である」と主張するため、原材料納入業者に彼らが納付した税額を証明する請求書(インボイス)を発行させた。(フランス)
仕入税額控除方式は、ガット協定に違反せずに輸出補助金を確保するために導入されたものである。
▽167 日本の税率5%は欧州基準なら10%に相当。菊池英博・文京学院大教授が比較。「消費税は0%にできる」(ダイヤモンド社)
▽177 消費者の批判をあおり、利用した政府。免税点や簡易課税制度などの特例措置に、消費者の間から「ねこばば」論議が高まる。で、今度は「消費者の不満」をてこに見直しを図る--。本間正明・大阪大教授「政府のやり方は、一種の確信犯」。3つの特例措置は、数次にわたる法改正で形骸化される。
▽188 「消費税率引き上げをやめさせるネットワーク宮城」 日専連宮城も民商も生協も……超党派。
▽197 消費税とは、力関係が弱い立場にある中小・零細業者、とりわけ自営業に、より大きな租税負担を課し、あるいは雇用の非正規化を促進するなどして、社会的弱者の生活費まで吸い上げ、社会全体で産み出した富を多国籍企業やそこに連なる富裕層に集中させていくシステムである。
▽201
▽204 自殺者に占める「自営業・家族従事者」の割合は極めて高い。
▽209 財界や政府が強調するほどには日本の法人税率は高くない。社会保険料を含めれば、企業の負担は諸外国の法人よりもずっと軽い。赤字でも取り立てる消費税率を引き上げるよりは、利益にかかる法人税の増税のほうがはるかに公正だ。
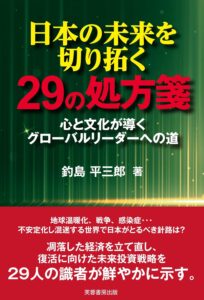

コメント