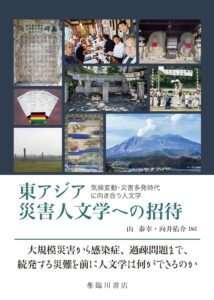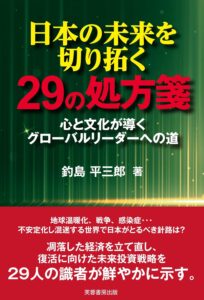筑摩新書 20060906
「福祉」「経済」「環境」「税制」「民俗」……
普通、それぞれの分野でバラバラに論じられ、全体を統合するような議論はなかなか生まれない。
筆者はそのすべてを大風呂敷でおおうような議論を展開するから、新鮮で刺激的だった。
戦後、農村から都市部へと人口の大移動が起きたが、都市的な人間像はつくられず、「会社」というムラ社会をつくってしまった。
国を挙げての経済成長という共有目標が、そうした「ムラ社会」を支えてきた。
だが経済が成熟・停滞するなかで、カイシャの求心力が低下し、ムラが崩れ、個々がバラバラなっている。
1人1人が閉じたムラ社会のようになってきている。
今後は成長を前提にした社会ではなく「定常型」の社会に向かうべきなのではないか
……という現状認識から筆者の議論ははじまる。
日本の社会保障費が他の先進国に比べて極端に少ないのは、終身雇用の「カイシャ」と、田舎における公共事業が社会保障の役割を果たしてきたからだ。
そんなゆがんだ社会保障だったから、「カイシャ」にも「公共事業」にもかかわれない障害者は社会から抹殺され、片隅に追いやられることになったのだろう。
農村のムラも都市のムラも崩壊しつつあり、従来の日本型社会保障ではなりたたない。
そこで筆者はまず、「人生前半の社会保障」を提示する。
教育にかける予算はOECD諸国中でトルコを除けば最低だ。
若年者への年金制度を設けることで、「人生最大の生活保障」である教育を受ける権利を、30歳くらいまでの若者に保障する(機会の平等)という。
「機会の平等」を果たすには、相続税の強化も必要だ。
1988年には最高税率75%だっったのが今は50%、基礎控除も3600万円から9000万円に上がっている。
「親の財産を子がつぐのは当たり前」なのか「財産はその代に限り、相続の時点で再分配するべき」なのか、という選択だが、前者のありかたをつづければ貴族と貧民の階級分化は避けられまい。
産業化前の税制は地租といった形で土地を主たる対象とした。
産業化時代は私利の追求によって拡大し、需要の無限の拡大に支えられて労働(所得・法人税)が財源となった。
消費社会になると消費税が中心になってきた。
市場が停滞し、市場経済の超越するNPOなどの領域が拡大する今後の「定常型社会」では、経済の成長を見込めない以上、所得などのフローの部分よりも、ストックの部分に課税の重点を置くべきではないか、と筆者は説く。相続税もそのひとつである。
ストックという意味では、「環境税」を重視している。
ストックである自然資源を消費することに対して課税し、そのカネを福祉の財源にする、というのはすでに欧州では実現しているという。
社会保険などの「福祉」分野の負担が重いから、企業は雇用増をためらう。
環境税を課すかわりに社会保険や年金などにその財源を振り向けて企業の負担を減らせば、雇用増につながり、環境保全にも役立つ……。
環境政策を「富の総量のあり方」と読み替え、福祉政策を「富の分配のあり方」と読み替えれば、環境政策と福祉政策の統合はむしろ当たり前のことだという。
▽就業期間と非就業期間。欧州の諸国では後者がのびて逆転しているのに、日本とアメリカだけはちがう。就業期間が長いまま
▽医療費の自己負担の割合は先進国でもっとも高い。差額ベッド料などの負担もバカにならない。
▽新制中学の明るさ 同じ地域に住む子たちの間に、それまで進学の際に生じていた疎外感を払拭した。連帯感と生活感覚における平等がもたらされた。(旧制中学を復活させようという一部エリート層の無神経)
▽自助=自由主義=最低限の年金か生活保護のみ
共助=保守主義=社会保険としての年金(仕送りの社会化)
公助=社会民主主義=税方式の厚めの年金(個人単位の生活保障)
▽福祉国家:生産段階は市場経済で、消費段階(所得:フロー)で再分配
ポスト福祉国家:資産(ストック)の再分配への転換
社会主義:生産段階で分配
日本:生産段階に補助金や公共事業といった公的再分配機能の相当部分が組み込まれている(社会主義的)
▽閉じた共同体(ムラ社会)が崩壊し、個々がばらばらになっている。今後は、開かれた共同体をめざす必要性。
コミュニティの中心になるもの:欧米は教会、日本にも寺や神社がある:鎮守の森の再評価。人との「つながりの根拠」をどこに求めるか