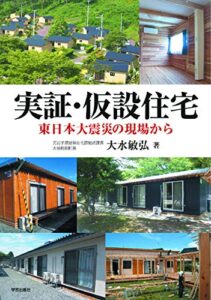緑風出版 20060917
井手氏は沼津市長時代、ゴミ分別を全国に先駆けてやりとげた環境問題の先駆者だ。
「環境問題の人」というイメージだったが、もっと奥深いものがあったことを知らされた。
ゴミ分別の「沼津方式」は、差別されていた清掃労働者が、「ごみのことをいちばんよく知ってるオレたちがごみ危機を突破する先頭に立とう。現場、現場といってバカにされてきたオレたちの力を示してやろう」と立ち上がったのだという。
「焼却場や埋め立て場に皆が反対し、それが当然のように通用するなら、その皆に嫌われるゴミを毎日扱ってるオレたちはいったい何なのか」という屈折した思いのなかから、「ごみかくし」をやめようという訴えが起き、市民に浸透していったという。
たんなる「環境問題」ではなく、差別されてきた労働者が立ち上がり、人間の尊厳を回復する運動でもあったのだ。
コンビナートの反対運動は、「革新」の側でさえ異端だった。当時の革新は「進歩」は肯定的にとらえていたからだ。
国が一律に設定する「基準値」は、汚染を許す指標としてしか作用しなくなる。技術的に基準値以下にすることが可能な場合でも、基準値までは安心して排出する、となってしまう。だからあくまでも「ゼロ」を主張することにした。「(四日市の)現地へ行って目で見、鼻でかぎ、手で触ってきた本当の情報が運動の基本にあったから、それを自分の情報として生かし、力に変えることができた」という。
医師や高校教師が集会のチューターとして活躍した。スライドとテープという情報伝達の方法が武器になったという。
▽1975年から市民の手で分別排出する方式をはじめ、「可燃」「不燃」の別をやめ、「資源ごみ」という新しい概念のもとにごみの分別処理を行ってきた。そのきっかけは、ごみ埋め立て地付近の住民から強い反対運動に直面したからだった。焼却炉の新設計画も激しい反対にぶつかる。そのとき「ごみのことをいちばんよく知ってるオレたちがごみ危機を突破する先頭に立とう。現場、現場といってバカにされてきたオレたちの力を示してやろう」と市の清掃労働者たちが立ち上がった。
びんは高さと色によって区分してもらう。アルミとスチールの区分はまぎらわしいから収集後に行政が区分する……当初は市民負担の増大として激しい市民の抵抗があった。それに対して清掃労働者が懸命に自分たちの労働への理解を訴えるとともに……。
▽コンビナート反対 これによって千葉の五井に
▽公害があっても、それを問題化することが困難であり、問題化しないかぎり公害問題の記録は存在しないことになる。実に公害問題の第一は公害意識をもつことであった。
▽「沼津朝日」の「大企業の植民地になるな」というキャンペーンがすごかった。
▽03年 亡くなる1年前にイラク反戦の意見広告
中国人殉難者の遺骨返還運動 西伊豆町の仁科の白川地区では、178人のうち82人が現地で亡くなった。毎年7月に今でも中国人殉難者慰霊祭が行われている。
▽欧米なみを望むことは、欧米の先進性が国際的な侵略や搾取によって成り立っていることを考えない闘争方針であった。……日本は軍備にカネを使わなかったから今日の繁栄を築くことができた、という主張が、革新の平和論のなかにもある。時にはそれが再軍備派との論争の間で平和論の最後のよりどころのような使われ方をしている。この論理はきわめて危険である。今は防衛費の持続的増強が、大企業の経済要求として景気回復の牢固たる一画を占めているのである。
▽景気浮揚のため国債発行を要求した財界が、いまは行政改革、国民耐乏を世論化しようと必死である。失敗を反省したのではない。失敗のなかで、あくまで財界だけは温存して行こうという主張である。だから、この借金苦のなかで、新しい新幹線や巨大架橋、沖合人工島、ダムなど、大型公共事業が次々に登場する。
▽自治体といいながら、完全に中央集権だ。市の職員が「本省にいく」とか、本省という言葉を常につかう。「お前さんたちは国や県とも対等なんだ」という意識を育てることにくろうした。現場で仕事をしていると、矛盾をしょっちゅう感じる。そういう時にまず六法全書をみて、国の法律がどうなっているかを資料として、そこから現場を規制していく。そうではなくて、まず現場に立ち、現場の矛盾の中から、行政なり法律なりの不十分さを、現場に直していくんだ、という気持ちをもっていた。
たとえば、環境基準なんかは国で一律に決める。これでやっていったら、その基準まで全国が汚れる。
▽コンビナート反対の64年ごろは、地区労の指導権は国労とか公務員の人たちが握っていた。それから電機労連が強くなって色彩がかわってきた。……連合は組合の外の活動はあまりやらない。地域には出ていかない。
▽高校のとき 学生が喫茶店に入っても「学生狩り」と称する警察の咎めにあい、学生がひとり遊んでいるのはけしからんとして「アルバイト」の土木作業に動員される。……しかし旧制高校の特徴とは何であろうか。社会を濁世と見下ろし……弊衣破帽……特権的特徴は何をもたらしたか。常に(戦前も戦中も戦後も)日本の支配層を作り醜い癒着を示してきたのは彼等であり、それが高校時代の理想とどう結びつくのであろうか
▽31歳で会社を首になり、市会に出たのが39歳。その間の苦労が生き方の基本を作ったと思う。その時代の運動仲間が、その後の沼津のさまざまな運動をつづけている。
▽自治会(町内会) 一方でそれを保守を支える地盤として攻撃し、片方で何とか依存しようとするジレンマ。ごみの沼津方式もコンビナート反対闘争も、自治会を頼りにして実現した。自治会は現状では「諸刃の剣」であり、自治会をどうとらえ、民主化するかは大事な視点である。