■亜紀書房20250719
輪島は、日本一人間国宝にあえる町だ。ワイプラザというスーパーに行くと、ちょこちょこ人間国宝さんが買い物をしていた。
この本は、スーパーでよくお見かけした人間国宝の小森邦衛さんと、輪島の漆器業界のトップランナーである桐本泰一さんの対談からはじまる。まずは地震直後をふりかえる。
いま輪島の職人の半分は漆芸研修所の卒業生だ。小森さんは研修所長をつとめている。地震翌日の1月2日夜、研修所を立て直さないと輪島塗がつぶれてしまう……と危機感を抱いた。 「近くの大学の教室を借りて、(研修生に)授業を受けさせてあげたい」と、金沢美術工芸大学や富山大学など4つの大学に教室を借りて研修生を送り込んだ
研修生の住居を確保するため、文化庁や県と掛け合って、トレーラーハウスを用意してもらった。10月1日授業再開の計画だったが水害で1週間おくれ、7日に9カ月ぶりに再開した。
桐本さんの自宅は全壊したが「工房は残されたのだから、仕事をやってもいいんだ」と感じた。3月には紙管を使った仮設工房を建てた。その隣の土地には公費で30棟の仮設工房ができ、9月13日に鍵が渡された。だが1週間後に豪雨が襲い工房の大変は浸水した。
「地震で上にあったものが落ちたから、みんな大事なものを下に下ろしていた。それが水害でやられてしまった……」
能登町で民宿「ふらっと」を営む船下智香子さんとベンジャミン・フラットさんが、がれきの下敷きになった輪島塗のレスキューをはじめた。これに胸を打たれて、欠けや割れのある器を都市部の空間にも合う器として再生する「輪島塗Rescue&Reborn」をはじめた。しっかりした下地がある堅牢な輪島塗だからからこそ、生まれ変わらせることができるのだ。
転んでもただでは起きない。2人の不屈の粘りが伝わってくる。
高森寛子さんは東京でギャラリーを経営し、漆器の「日常使い」を提案してきた。高森さんと桐本さんの対談は、輪島塗の歴史と課題を浮き彫りにする。
輪島塗は明治・大正期には「椀、盆、膳」などが主力商品だったが、高度経済成長期には、高級美術工芸品を百貨店の外商を通じて大量に売った。ピークの1991年の生産額は180億円にのぼった。だがこの年バブルがはじけ、現在の生産額は最盛期の2割を下回った。
「バブル以降、漆器屋は自分のところで職人をあまり抱えないようになった。みんなが切磋琢磨してつくろうとする空気感が、この輪島の町からスーッとなくなってしまったように感じます」(桐本さん)
和室の家具を中心に高額商品が売れたのは昭和30年代後半から64年までの約30年間だった。その後、「自分たちが一生懸命作っているのに買ってくれない」という声がしばらく続いたが、「やっと生活者、使い手の大切さが言われる時代がやってきました」(高森さん)。
豪華なものばかりあつかっていた百貨店が、キリモトなどの普段使いの食器をあつかうようになってきた。
「漆が日常生活の中に溶け込めるのかっていうことを、もう一度輪島の中で話しあわないといけない。もの作りというものを考えなおす機会にしなきゃいけない」「こういうときだからこそ、何かテーマを持ったものを作らなきゃいけない」(桐本さん)
その思いは「輪島塗Rescue&Reborn」にいかんなく表現されている。
また、輪島塗は「行商」だったけど「迎商」もしたいと言う。輪島塗を使う人が輪島に行く「迎商」が軌道に乗ったとき、復興が実感できるのだろう。
外の人に来てもらうには、地元の人たちが能登の魅力を自覚し、発信しなければならない。桐本さんのようなリーダーや高い技術をもつ職人がいて、情報発信する漆芸美術館があれば、輪島塗は復活するだろう。ただつくづく残念なのは「民俗資料館」をつぶしてしまったことだ。輪島塗は、能登の自然や伝統、食文化のなかから生まれた。そうした能登の魅力の全体像を発信する「奥能登民俗博物館」が今こそ必要なのではないだろうか。
=====
□桐本×小森邦衛
▽小森 漆芸研修所 次長に「近くの大学の教室を借りて、授業を受けさせてあげたい」って言ったら、……すぐ金沢美術工芸大学の学長へ「教室をひとつ貸して下さい」と電話しました。他に富山大学など4カ所に教室を借りて、特別研修課程と普通研修課程に分けて送り込みました。……
▽桐本 電気は1月半ばには来ていたんですが、……1月は毎日山水をくんでトイレに流して使えるかとか、生きていくためにどうするか、みたいなことばっかりやってました。……1月後半ぐらいから、問屋さんたちが倒れた建物から在庫を引きずり出してあちこちで展示会をして、応援とかお見舞をいただいて、「売れた,売れた」と言っていると聞いて、僕は逆に不安を感じました。僕らの仕事はまずはものづくりですから。
▽12 4年前に工場は強制移転させられて「輪島キリモト・輪島工房」としてここに新築したのですが、1972に建てた前の工場だったら壊れていたでしょう。もしかしたら、廃業したかもしれません。でも工房は残されたのだから、仕事をやってもいいんだ、そんなふうに感じたんです。ここを工房兼自宅とし最初は家族だけでやりくりし、4月と5月に順番に被災していた職人が戻ってきてくれて、6月から稼働は8割ぐらいになりました。
……坂茂さんのお力をお借りして、3月に紙管を使った仮説工房を建てました。……その隣の土地には公費によって30棟の仮設工房ができ、9月13日にようやく鍵が渡されました。その矢先の大雨。うちは木地工房は3分の2、漆塗り工房は全域が、……浸水がありました。
人生で初めて心が折れたかもしれないです。地震で上にあったものが落ちたから、みんな大事なものを下に下ろしていた。それが水害でやられてしまった。
▽14 僕の家は木地屋をやっていましたが、僕が漆を始めてから、輪島の外に仕事を広げるしかなかった。そういうふうに自分を追いこんでいったんです。
▽小森 いま輪島の職人として活躍している人の半分ぐらいは、研修所ができてから40年ぐらいまでの卒業生です。
輪島塗の業界が研修所に対していい感情を持っていないのは百も承知ですが、研修所をしっかり立て直しておかないと、……輪島塗がどうなるのかこわいなっていうのが、1月2日の夜から頭のなかにありました。
……在校生をどうするかというのがいちばんの問題でした。アパートを解約して実家に帰った子の他に、新入生が20人いました。その子たちは住むところがない。……文化庁に提案をして、県にも掛け合って、トレーラーハウスを用意してもらうことができたんです。
……なんとか授業を10月1日に再開しようととしていたら水害で1週間おくれ、それでも10月7日に9カ月ぶりに再開することができたんです。
……いま聞こえてくるのは、漆器屋の職人が退職していくという話なんです。うちでも35年、木地師として勤めとった職人が通えないと言って辞めました。木地師が一人辞めるといたい。人を募集したいと思うんですけど、やはり住むところがない。
▽17 桐本 高度経済成長期、いい競り合いがあったみたいです。バブル以降、漆器屋は自分のところで職人をあまり抱えないようになった。みんなが切磋琢磨してつくろうとする空気感が、この輪島の町からスーッとなくなってしまったように感じます。
▽20 小森 研修所に入ってくる子は、どこか自分でつくったものを自分で売りたいっていう気持ちがある。輪島の問屋が考えてる職人とは微妙にイメージがちがうんですね。研修所のいいところでもあり悪いところでもあるんですが、量産的なものの作り方をまったく教えない。……私も研修所の2期生ですが……作家になる気はさらさらなかった
……松田権六先生に会ったことが人生の転機になりました。
▽21 研修所は、重文に指定された人がいないと科ができないんです。だからあくまで保持者の先生方の技術を継承、研修するところです。
……私たちは輪島塗の悪口を言うけど、ちゃんと日本でいちばんいい産地だと認めた上での悪口だから……(〓日本一、なのだ)
▽26 イタリアンと発酵食の宿「ふらっと」を営む船下智香子さんとベンジャミン・フラットさんは、災害廃棄物になる漆器を救おうと「能登地震地域復興サポート」を組織し、その活動のひとつとして、輪島塗レスキューをはじめた。
……この活動に胸を打たれた桐本さんは、欠けや割れのある器を生まれ変わらせて販売することを決意。「輪島塗Rescue&Reborn」をはじめた。堅牢で修復が可能名輪島塗ならではのプロジェクト。〓〓
▽30 ……欠けているものには地をして、都市部の空間にも合うような透溜をして生まれ変わらました。……輪島塗の特徴である、しっかりした下地があるからこそ、生まれ変わらせることができるということを伝えたいんです。
□高森寛子
▽36 スペースたかもり 今、私にできることは……少しずつ具体的に考えられるようになったのは、地震が起きてから2,3日後だった。
……2024年はほとんど毎日応援展をしていた。
▽45 鎌田克慈さんの乾漆 赤木明登さん
▽54 小田原寛 漆の置き時計……
「朴木地屋・桐本木工所」が「輪島キリモト」に商号を改めたのは2015年。
□若宮隆志(彦十絵プロデューサー)×桐本
▽59 桐本 1995から99にかけて、漆器商工業協同組合で新商品開発委員会をつくって勉強会をはじめた。……勉強会で感じたのは、ものを新しく生みだすときには、どういうふうなところで情報収集をし、それを分析し、試作しながら、今の暮らしの中で人の心を打つものができるか、それを知らないといけないということでした。(〓文章も同じか)
デザイナーの小田原寛くんや同級生の四十沢宏治くんらが事務局にいたので、勉強会を5年間つづけられました。
▽61 輪島の高度成長期に培われた技術と、私がやろうとしている江戸時代の技術はまったくちがう……「こんな塗り方はやめてください」って言うと、職人さんは「俺はこれで飯を食ってきたんだ。どこが問題なんだ」となる。議論して改善していった。
▽65 桐本 輪島では木地屋としてあってはならないことをやってしまったので、地元とは距離を置かざるを得ない状況に追いこまれ、外へ出て行きました。……
若宮 Wawaさん(マネージャー・台湾出身)がいないと成り立ちません
▽69 金沢では若い漆芸家が増えています……でも金沢の人たちから見ると、輪島はまだまだ聖地で……。でも輪島から出てきた私にとっては、金沢すごいよって思うわけです。20代、30代の作家がいっぱいいて、……作家の仕事だけじゃなくて職人的な仕事もしながら、何とか漆で食べていこうとしている。
▽70 一回もうけたことのある年代の方々は、一切耳を貸さない。その方々の考え方を変えるというのはむずかしいことです。
(〓今の輪島の課題にまで)
□秋山祐貴子 エッセー
□高森寛子×桐本泰一 対談
▽98 高森 私の中のキリモトは、木地が一番で次が漆という印象が強いんです。
▽100 大向さんは、輪島のきのこ会というのをやっていたんです。輪島の山興造林という会社の従業員とその家族の人たち全員できのこを採ってきて、……通産省の伝統工芸品の担当者たちも顔を出す。茅葺きの家で30人ぐらい集めてやるんですよ。僕も、スタッフの一人として動きました。
▽101 バブルが弾けた1991年……輪島塗は1991年の生産額が180億円で一番よかった時なんです。この売り上げを、3000人ぐらいの人でやっていた。
▽102 百貨店の外商さんを通じてどんどん売っていきました。
……今は、彦十蒔絵のものはWawa(高禎蓮)さんが中国にもつないでいる。……中国の人たちは無地のものは好まない。……彦十蒔絵は物語性がしっかりあって、唯一無二みたいなもの……海外などではより好まれます
▽104 輪島塗の、和室の家具を中心に高額な漆器が生まれたのは結局、昭和30年代後半から64年まで約30年だと感じます。今の輪島塗のイメージわずか30年で築かれたものと言えます。そこからさらに40年経っている。
……大きな塗師屋さんが5社あったんですが、相当の売り上げを上げていたと思います。
……バブル崩壊。全体的に売り上げが下がっていったなか、20年程前に木工所の私にいきなり日本橋三越から店を出さないかと声がかかった。その店を出すことで輪島は大騒ぎになりました。
高森 豪華なものばかり扱っていた百貨店が、キリモトさんのところのような普段に使えるものを扱わなければならなくなった。
▽107 高森 自分たちが一生懸命作っているのに使い人が買ってくれないという産地の声がしばらく続いた後、やっと生活者、使い手の大切さが言われる時代がやってきました。私も使い手の立場で一生懸命話すのですが、たぶん、聞き流されていた。以前のようにバブルがまた来て売れるようになるんじゃないかと思っていたのかもしれませんね。
▽110 漆器を特別のものではなくて、日常的に使うものだ、と……30年近く前にスペースたかもり〓をはじめた。2番目が大阪・舎林の山田冨美子サン。それから京都のGALLERYやなせ、栁瀬佳代さん
▽113 地震後に輪島塗が売れたのは、通常の売り上げではないと心に刻まないといけない。……漆が日常生活の中に溶け込めるのかっていうことを、もう一度輪島の中で話しあわないといけない。もの作りというものを考えなおす機会にしなきゃいけない。
……輪島が本当にやらなきゃいけないことは、ものを作ることであるってことは大前提です。……6割ぐらいしか事業再開できていない。……こういうときだからこそ、何かテーマを持ったものを作らなきゃいけない。
▽115 高森 輪島塗は今まで行商だったけど、迎商もしたいとずっと言ってますね。
職人さんの仕事場を回り、民宿・深三を借り切って、夜は昼間訪ねた職人さんたちが、全員来てくださって宴会。
▽117 使う人が輪島に行く……だからいま行商しているんです。迎商をするために。
□基礎知識
▽120 産業構造は分業制。木地が椀木地・指物木地・曲物木地・朴木地4つに分業し、下地、上塗りなどを行う塗師、蒔絵沈金、呂色と八職と呼ばれる職人分野が存在します。それら職人衆をプロデュースするのが塗師屋と呼ばれる漆器製造販売の親方衆なのです。
室町時代には現在の特徴とほぼ同じ漆塗り技法を施した器を生産し、小さな商圏を確立していた輪島塗産地は、17世紀以降珪藻土を使った堅牢な技法を確立し、現在もその技法を中心に様々な漆塗り技術が保たれています。……北前船全盛期に「親の湊」とよばれた良好な港から大量の製品を全国に運ぶコトができた。……明治後期、大正時代には「椀、盆、膳」などの器が主力商品であったことがわかります。
戦争前後、原材料不足、人手不足などによる苦しい時代を経て、高度成長期には、百貨店、消費地問屋との新商品開発、高級美術工芸品の大展示会方式の成功が現在の産地規模を作り出しました。公募展常連作家は100名を超え……
しかし1991年をピークに下降の一途をたどり、現在は最盛期の十数%に落ちこんでいると言われてします。



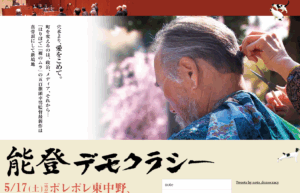
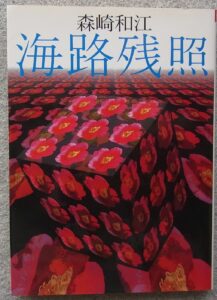

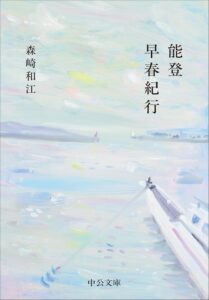
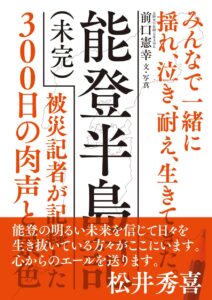
コメント