■地域再生をめざして 能登に生きる人々 <武田公子 いしかわ自治体問題研究所編> 自治体研究社 20110518
金蔵は、もともとあった「価値あるもの」を再評価し、新たな価値を付け加え、外に向けて発信しつつ地域を奮い立たせた。その基盤には、強固な門徒組織があった。
白米は、減反によって耕作放棄地が急増したが、輪島市や県の支援やボランティアで耕作放棄地が縮小し、「あえのこと」も復活させた。春蘭の里(能登町)は、退職後の団塊の世代が中心になって農家民宿をいくつも立ち上げた。
輪島塗は衰退しているといわれるが、昔ながらの訪問販売を続ける業者はそれほど売り上げは落ちていない。マリンタウン計画に反対した漁協の女性部は自ら新商品の開発をし、女性の自立を図ってきた。
祭りでキリコを担ぐことが、能登に特徴的な絆のあり方であり、それが選挙の基盤にもなるし、町おこしの原動力にもなる。あるいは閉鎖性を培う面もある。
地域の資源を生かす。顧客と直接つながる。女性の自立を図る。封建的でない絆づくりをする……。さまざまな事例を並べてみると、うまくいく村おこしの共通点が浮かび上がってくる。
===========================
□金蔵集落
▽11 06年現在、67戸175人。(87戸の住民のうち農家数46戸、水田40ヘクタール、という記述も)集落には大きな寺が5つ。97年に集落にあった小学校が廃校に。建物が壊され、小学校の意味をはじめて実感。危機感が募り、2000年に「やすらぎの里 金蔵学校」設立。
棚田。お寺にお参りにくる集落内の問信徒に依頼して草取りの手を確保。NPO理事4人が「トラクターを買うための禁煙」。
はさ干しの「金蔵米」は、1キロ700円。日本酒「米蔵金」。
05年には慶願寺の境内にオープンカフェ「木の音(きのこえ)」。
▽16 万燈会 室町時代に集落が焼き討ちになった故事にちなんで6年前から。
▽18 かつて寺荘園として栄え、時の支配者に焼き討ちにあったものの、門徒を再集結させて寺を再興した歴史。明治期にも寺を中心に栄え、区会所や駐在所、郵便局も置かれ、旧町野村では2番目に小学校がつくられた。その誇り。
▽21 もともとあった「価値あるもの」を再発見し、再評価し、新たな価値を付け加え、外に向けて発信しつつ自らの地域を奮い立たせるという地域再生のヒント。
▽32 ここのすごさは、門徒組織がまだ生きていることで、万灯会もこの組織なしにはなしえない。
□白米
▽31 白米は、300年前には5人の製塩経営者が村におり、……近世には棚田は2ヘクタール程度だったが、明治期には6ヘクタールに増えた。漁業、養蚕、製塩、林業も盛んで、このころに最盛期に。過疎化で棚田が杉林に。戦後は、林地の牧野利用や棚田復元が進んだが、次第に米の単作に。70年から生産調整がはじまると、耕作放棄地が急増。
最近、輪島市や県の支援や在村農家の努力で耕作放棄地は縮小。団塊世代がリタイヤ後に帰農する動きも。「あえのこと」も復活。
□春蘭の里(能登町)〓
農水省の補助金で廃校になった小学校を利用して宿泊施設。退職後の団塊の世代が主力。
□里海の活用
▽36 クロモ、ツルモなどの海藻は、フコイダンを含有。マツモやハバノリにポリフェノール。
□「能登ワイン夢一輪館」〓の高市範幸さん ブルーベリーワイン作りを村職員時代から手がけ、今では、そばを打ち、キノコ山を育て……
▽42 旧柳田村 梅やラッキョウ、栗などに失敗。全滅した栗の林に自生のナツハゼ。その果実酒が美味だった。ナツハゼと似たブルーベリーによるワイン作りを思い立った。……全国ブルーベリーワインシンポ。ブルーベリー農家は今では150軒ほどに。
▽45 揚浜塩田の天然にがりでつくる豆腐を燻製にした「畑のチーズ」、独特の猿鬼そば。
▽55 「地元で食材を集めて地元で売る、ということを町が公社などを通じて取り組むべき」と高市さん。
□彩漆会の大工佳子さん 輪島塗を日常生活に生かす提案。
▽46 夫と塗師屋の「蔦屋」を経営。輪島塗器商工業協同組合の新商品開発事業にかかわった女性ばかりで「彩漆会」を結成。
▽49 輪島塗は最盛期は年間180億円の売り上げだったが、今は75億円。卸業者は手入れの仕方などを顧客に伝えられない。伝統的な自ら売る販売方法をしているところは顧客の急減に見舞われることは少ない。
□輪島崎漁協女性部の新木順子さん 漁村女性の自立をめざし、カジメの佃煮加工
▽56 女性の自立に向けて身近なもので取り組むことを考えるうち、カジメの佃煮加工に取り組むことに。
輪島港埋め立て事業のマリンタウン計画に女性部は反対した。漁協は推進だった。女性が自立した考えをもち、行動する。〓〓
□輪島・わいち商店街
▽61 隣接する朝市通りがにぎわうなか、空き店舗が目立つ。93年に「わいち商店街振興組合」へと再編。
▽62 駅前商店街や馬場崎商店街などが県の「都市ルネッサンス事業」の対象に。都市計画道路の整備にあわせて町並み整備や伝染埋設、歩道整備。建物の外観に統一性をもたせるため「輪風・まちづくり協定」を策定。
「まちづくり三法」を受けてTMO「まちづくり輪島」設立。中心はわいち商店街振興組合理事長をつとめた中浦政克さん。……06年12月、わいち商店街振興組合は解散(居住者と商店との間の利害のずれ)。
□珠洲市・飯田町商店街と株式会社「夢のと」(TMO)
▽68 珠洲市には「八ケ山ハーブガーデン」があり、「夢のと」ではラベンダー化粧水、ハーブティ……を開発。飯田町商店街の広場空間の各所にもハーブの鉢植えが置かれている。揚げ浜式製塩の塩や、珪藻土のコンロ、珠洲焼き……。
▽70 能登ネットワーク 代表の数馬(数馬酒造=能登町宇出津)さんは酒造会社経営。門前でソバ屋を経営する星野正光さん、輪島のTMOを立ち上げた中浦さん、泉谷・珠洲市長も会員。
▽71 昭和55,56年生まれの地元高校生の同窓会の集まり「鳳遊海」(能登町)。祭りの時は能登に帰ってキリコを担ぐ、というのは能登地域全体に共通した絆のあり方。
▽73 輪島では、中心市街地の活性化を進めながら、のと鉄道の廃止を食い止めることができず、珠洲でも商店街と離れた場所にルネッサンス事業所を指定しており、「ラポルトすず」建設も、まちづくりとの一体性に欠けるものとなっている。両者とも、観光・商業振興がまちづくりの中心となり、福祉や文化事業を誘致するといった、居住者にとっても魅力あるまちづくりという観点は弱かった。わいち商店街振興組合は、住民を含めた組織という独自性をもっていたが、この特徴をまちづくりに生かすことができなかったという限界を抱える。飯田町商店街も同様。〓
▽数馬嘉雄 能登半島活性化のキーワード 自然循環型のトップランナーになれるのでは。いしりや地酒などの発酵産業、寺院や夕日など心を醸す要素もある。
「能登の酒」ブランドづくり 酒造組合


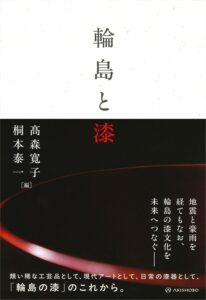

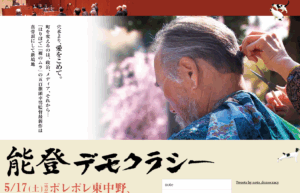
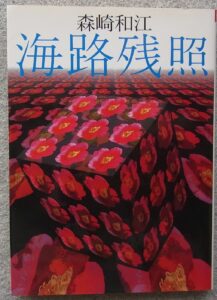

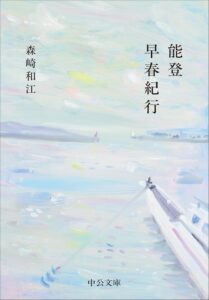
コメント