■ためされた地方自治-原発の代理戦争にゆれた能登半島・珠洲市市民の13年<山秋真>桂書房 20120110
旅行で偶然珠洲に立ち寄った女子学生が、推進派の現職市長に無名の若者がいどんだ1993年の市長選に参加する。原発計画とたたかう人々のなかで、自分の生き方を真摯に考えて運動に取り組み、それゆえに何度も傷つき、それでも真正面から向き合いつづける。息苦しいほどの真摯さを貫いたからこそ、この作品がある。同じように学生時代に公害・環境問題に接しながら、そこで感じたものを誠実に考え続ける純粋さが私にはなかった。だからこそ、筆者のまっすぐさがまぶしい。
珠洲には、国営農地開発事業で開いた900ヘクタールの大半が荒れたまま放置されている。国策失敗による膨大な赤字は地元自治体と入植した農家が背負うことになった。国策に盲従したために、それでなくても衰退している自立の基盤をいっそう掘り崩され、原発に依存せざるを得ない構造がつくられた。
それを「過疎の悲しみ」と主人公の僧侶は呼ぶ。推進派も反対派も「過疎の悲しみ」を共有している。だからどんな嫌がらせを受けても推進派の人々を「敵とは思えない」と主人公はいう。同じ反原発運動でも、都会の人々は「放射能があるから食べない」となりがちだ。それは過疎の悲しみに寄り添う立場ではない。筆者はもちろん「悲しみ」に寄り添う道を歩む。
結果的に原発計画は阻止できたが、反対運動もしだいに勢いをなくしていった。その要因のひとつが高齢化だ。介護という行政の「恩恵」を受けることで自由な投票行動をためらうようになる。行政への「依存」が民主主義の根っこを揺るがせる。逆に、人権としての福祉が確立され、老いても精神的に「自立」できるならばそうはならないということだ。
「過疎の悲しみ」に覆い尽くされていたら原発を止めることはできなかったろう。では筆者が見た「田舎の魅力(強さ)」は何だったのか。
「薄いピンクの割烹着、紫色のもんぺ、紫色の頭巾、手には縄であんだ手さげ袋。ひとつひとつがとてもユニークで、全体としてその女性が立ち現れている。『人間』が服を着ていた」と漁村の女性の姿を筆者は描写する。商業主義に毒されない、土に根付いた「人間」の強さこそが原発反対の原動力になったのではないか。
反対運動内部のいざこざや、お茶くみなどを押しつけられる女性の地位の低さなどの問題点も指摘していて、きれいごとではない部分も描いているのも説得力があった。
====================
▽22 計画が出たのは1975年。はじめは「珠洲方式」と呼ばれる、市の行政主導で誘致活動がすすむ。地域経済活性化と過疎脱却へ市の有力者が誘致に動いた背景。
▽27 1969年から減反政策。だがその5年ほど前から、農業近代化路線のもと開田を進めていた。珠洲市は1970年代以降、国策である国営農地開発事業、いわゆる「パイロット事業」を進めた。開発公社が地主から土地を買い、山林をきりひらき、広大な農地をつくる。地区ごとに栽培する作物を指定し、そこへ入植者をつのる。珠洲市でも900ヘクタールを造成し、200戸が入植した。1973年から91年の終了までのあいだに、総事業費は当初予定の84億円が182億円にふくらむ。失敗した落ちも珠洲市が買わなければならない。国策失敗の後始末を地元自治体が背負う仕組み。
入植するとき、負担金を払うと農家は同意書に判を押す。金額は明記されず、「総事業費の何%」というかたちだから、事業が終わらないと金額がわからない。工期がのび、事業費が増大し、入植者の負担も増えるが、農作物の価格低迷で、負担金を返すのが困難に。
高屋町の指定作物だったクリは生産不振がつづく。
珠洲市は追い詰められていた。
▽29 86年に市議会が誘致決議。89年から93年までのあいだに珠洲市は8300人を原発先進地視察に送り出した。
▽32 高屋の寺で生まれ育った竜一は「世間をみてこい」と親に東京へ転校させられ、中学から大学卒業まで東京都と京都ですごした。卒業して高屋にもどった。
▽34 高屋の人は5人10人で土地登記上の共有名義者となり、土地をもちあっていた。手に入る予定地の土地を購入し、それも共有地に。……関電は、地主と借地権契約をかわし、借地料5年分を前払い。借地だからと安心させて住民にカネを握らせ、懐柔し切り崩していく。
▽41 「クリは実がつくのに3年と言われたけど、1年目から潮風で枯れる状況だったんですよ。クリが収穫できるようになるまでの収入用にと思ってたカボチャや小豆をつくって、スイカをはじめたのは6年後以降ですわ」階段構が多いクリ畑をそのままスイカ畑にはできない。畑を平地にもどす……パイロット事業は「農業と土木、どっちの比重が大きいかわからんけど、土木に比重あったんやないかなと思ったりもするんですわ」……そのスイカ畑が原発予定地にくみこまれた。竜一らも畑での収穫や出荷作業を自発的に手伝う。
▽45 薄いピン。クの割烹着、紫色のもんぺ、紫色の頭巾、手には縄であんだ手さげ袋。ひとつひとつがとてもユニークで、全体としてその女性が立ち現れている。「人間」が服を着ていた。(観察眼、商業主義に毒されない「人間」のいる地)
▽50 藤田祐幸 「放射能を測ってほしい」と食品をもちこむ人に、藤田さんは「測ってどうするの」って聞くんですよ。「放射能に汚染されていたら食べません」というと「そういうことなら測りません」と断るんです。原発でもうけるのは巨大企業、電力を使うのは大都会、原発で傷つくのは現地の人、これじゃあんまりだ、という考えなんですよ。……「放射能があるから食べない」と、都会の人が拒むなら、地元の人にとっては踏んだり蹴ったり。
藤田はあくまで、現地の人の立場に踏みとどまろうとしているようにみえた。
▽53 かつて神通川のカドミウム汚染を経験した蛸島の漁師たちは原発に強く反発していた。1955年から約10年、風評被害で魚の価格が低迷し、どん底の生活を味わった人が少なくない。(カドミウムとPCB、どっちが?〓)
▽57 輪島の海士町で以前は海女だった……とともにビラ配りに
▽「原発ができれば子どもが珠洲に帰ってくるかもしれん」という、過疎ならではの「さみしさ」から原発計画に賛成している人も少なくない。
▽62 立花正寛 敦賀市にある日本原電の原発から8キロの地点に住む僧侶。自宅の庭でコバルト、付近でセシウムを検出。寺の門徒はひとりをのぞいて全員、ガンで亡くなっているという。立花もガンで94年に40代で逝去する。
▽69 「夫にはね、『わたしが考えて、わたしがやるんやから、あなたとは関係ない。それでイヤなら離縁してくれていい』といいました。……」
▽73 「息子の知らない間に、父親が電力会社に土地を売っとった家もあるわね。息子は怒ってちゃぶ台ひっくり返して、でも、もう取り返しつかん。そんなふうに親子関係もめちゃくちゃにされるんよ」
▽78 93年市長選 「投票日の翌日に目をみれば、あんたが誰に投票したかわかる」てな脅し文句があるくらいや。都会の人らみたいに割りきれたらいいんやろうけど、田舎じゃそれはできんて。
元選管事務局長が不在者投票を組織的に動員。組織的な不正転入。むろん実際に転居したわけではない。
▽80 珠洲市がひらいた「まちづくり講演会」市は講演会参加者のため無料バスを運行。……選挙に負ける悔しさ。
▽88 選管ぐるみの不正選挙 2時間の密室作業 投票用紙の箱を入れた金庫の封印を破られる
▽94 6月には国の要対策重要電源に指定。国の後押しをうけ、94年早々にも立地可能性調査を再開するとみられていた。
▽101 用地工作。不動産ブローカーらが小川竜一の寺へ。「寺を立派にしてあげます」「農業研究所の所長に」「ホスピスのような施設の所長に」
▽114 ハーブ園共同事業……原発をたてたくない人の中にも「お花畑」に土地を提供してカネを手にする人があらわれた。
▽121 キリコ収納庫をつくる話。収納庫がないころは、祭りが終わると分解して片付けていた。
▽128 やり直し市長選。3件も4件も電話アンケートがかかってくる。「票読みしとるんやな」。……「金まかれてもうた」
▽133 1999年、東海村のジェーシーオー臨界事故。推進派が、強硬派と、原発にしがみつかず現実的な地域振興策をさがすという現実路線にわかれはじめる。
▽137 だれが市長になっても珠洲には原発は来ないのではないか、という楽観論もではじめた。どうせ来ないのであれば、国とのパイプがあり行政になれた市長がいい、という空気も否定できない。
▽142 「外人」攻撃。「あんたらも、町づくりに参加した責任をとってずっとこの町で暮らすんだろうな」。「町づくり」を争点としたことも反対派の不利に。
「町」を「つくる」ことを考えようとすれば、原発いらんと訴える人びとは不慣れな土俵に立つことになる。
それでも選挙では、実現可能性のある対案をしめすことは必要だ。罠のような難問をつきつけられ、原発をたてたくない人びとは悩んだ……「珠洲市の問題なのに市外の人に頼っていていいのか……」
96年のやり直し市長選のころまでは、市外の人がたくさんきていた。それが活気をもたらしていた。情報交換が、「少数派」とみなされていた珠洲市の人々の孤立感を緩和したように思う。
▽152 2000年の選挙では、わたしの仲間が、自分の言葉ではなく他人の言葉をつかって、わたしを排除しようとする。「外人に頼らず珠洲市民の手で選挙運動を」という声が仲間からではじめ……
▽158 「能登の父楽、加賀の母楽」。珠洲でも、女性は末席にすわる。炊きだしの配膳も女性。お茶やおにぎりも男性から先に配られる。「なんや男の人にお茶をださせて」と高齢の女性に叱られたことも。
漁師の女性は例外的に見えた。船で労働することが彼女らに自信をあたえているのではないか。だがその自信は、身体が自由にうごき労働に貢献しているからこそ……だから身体が動かなくなると自信の裏付けをうしなっていく。自分の存在価値を見いだせなくなっていく。
「外人」排除を支えたのは、差別をはらむ目にみえない力関係と、それにより立場の弱い者がいだかされる劣等感だったのではないか。……「男の人らは『反対するためにわざわざ来てくれとるんやから、刺し身でもだしてやれや』っていう。大変だよ。……」。男性たちはなぜか、上げ膳据え膳で、食事の支度や片づけの一切は女性が担っていた。
▽162 2000年に行政側候補者の得票がのびた鍵は高齢者では。現職や後継候補は福祉政策をアピールする。高齢者の不安が強ければなおさら説得力をもつ。「ヘルパーなしには暮らせんのやから、仮にヘルパーに頼まれたりしたらいちころやろね」
高齢者をかかえる家族は、人質をとられた有権者であり「人質有権者」。介護が行政の恩恵と見なされる限り高齢者は「人質有権者」とならざるをえない。その場合、高齢化するということは「人質有権者」の割合がふえることを意味する。自由な投票行動をためらう高齢者がふえるということだ。(〓依存の弱さ、高齢化による依存度の高まり)
▽170 仕事がないからこそ、仕事のオーナーをはじめとする「強い者」がよけいに力をもつ。「過疎だと公務員万々歳や」という状況だからこそ、市役所の人間がエリートとなり力を有する。(〓自立した漁師は反対の基盤)
▽206 脱税事件の公判 原発ではなく「レジャー」名目で用地をおさえる。「絶対に関電に売却しない」と約束する。うそ。新潟県巻町でも、東北電力が計画を公表した71年には、電力の意を受けた業者が予定地の民有地のほとんどを「レジャーランド開発」名目でおさえていた。
▽221 「推進派」の家にもおなじ手口のいやらせ電話がかかっていた。両者の溝を深めようとした、顔の見えない者の存在。
▽240 脱税事件。売り主と買い主(電力)は同じ穴のムジナなのに、売り主だけが脱税とされる。電力会社や清水建設も公正証書……不実記載罪になるはずなのに、検察は動かない。力の強い大企業に甘く弱い個人に厳しい司法判断。
▽246 「国営農地開発事業」 珠洲市内のハーブ園でいちばん大きい「八カ山ガーデン」は、ティ・エフ・ケイ北陸の岩崎社長の関連会社がつくり、04年に珠洲市が寄贈を受けたとされ、今では市営となっている(今は閉鎖〓)
▽248 元電源立地課長の木之下明は泉谷に市長選にやぶれる。JA?
「勝ち負けより(原発立地問題がおわって)よかったという人が多いんやないかな。原発推進の人は立場が違っただけで、(反対派と)そう違っとらんよ」
「大切な視点は『過疎のさみしさ』や。仕事がないってことや。仕事があったらこんな問題は起きとらんよね。僕は仕事で葬式いくやろ。葬式するとその家はこの集落から絶えてなくなるんよ。過疎は、若者がおらんだけやない。最後には若者が年寄りをまちへつれていくのが『過疎』や。過疎のさみしさがあるから、推進しとった人のことも、僕は敵とは思わんかった」〓
「原発を推進しとった人たちは、『電力がなくなったら日本はどうなるんや』と本気で心配しとった。その、日本を憂える人たちが(凍結後)消えてしまったんよね。どなっとんのかな」「みんな乗せられるんや。美しい言葉でイメージを植えつけて……ドイツの人たちがナチスに流れていったのと共通のもんがあるんやないかな」
……自分は善い人のつもりなのに無意識にそして結果的に、巨悪に加担してしまう人間。なんのことはない。わたしもその一人だったのではないか。
▽254 脱税事件の大地主は土地を売ってしまったが、住民たちは自分の土地を実勢価格より高い価格で購入したようだ。
▽国営農地開発パイロット事業の畑。すっかり荒れた山に。〓検証は?
▽高屋の女漁師。絶景ポイントの徳保のバス停前で茶屋を営業〓。「高屋の人らが集まれる場所を」と03年にオープン。
▽259 原発という国論の争点をせおいながらも、自分の人生をいきることをあきらめない熱い人々。
▽262 大臣や社長みたいな個人や組織が、大きな力をもつことを許しとるのは僕らなんや。さしさわりのないときはそれを許していて、差し障りのあるとき抵抗して逆らって、無力感を味わうんやろな」
▽263 一見すると、地域を破壊したようにみえる。けれどその対立のなかでなされた議論や行動は、地方自治のかけがえのない実践でもあったのではないか。対立がないことは「問題がない」のではなく、むしろ問題を表面化できない閉塞した状況かもしれない。


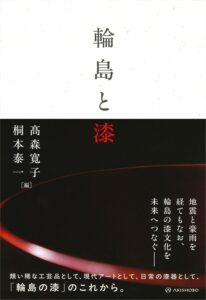

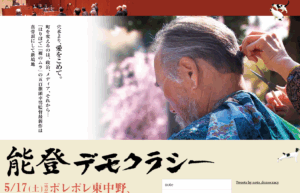
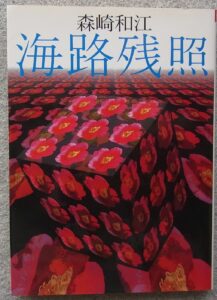

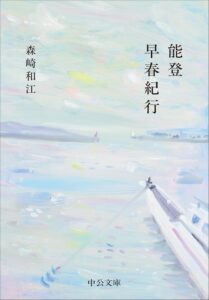
コメント