■山川出版社 20190527
読みにくくおもしろくない。でもまあ、辞書的には使える。以下抜粋。
▽2 「環日本海諸国図」は1994年に富山県土木部が作成。
▽4 城下町富山は「外山」と記載されることが多かった。
…越中の国は、古代のはじめは越の国に属した。越中として定着したのは8世紀中頃。当時の越の国派、朝廷の支配が及ぶ東端の辺境。列島支配のなかで東国と西国の境界に位置した。
…日本の言語を東西に分ける境界線が糸魚川で…越中の民家には東国に見られる土間住まいがかつて見られ、餅の形が、富山県では、西日本のような丸餅ではなく、東日本に見られる角餅。
▽5 九州の馬渡(まだら)の民謡が伝播して、新湊・魚津・福光の「めでた」の民謡となったといわれる
鉄道網整備の遅れと、欧米中心とした経済・文化・国際関係が太平洋岸重視をうみ…裏日本化。
▽7 陶器の積雪は、単作を強いて、農閑期における出稼ぎの必要をもたらし、働き者の女性を生み出すことに。
▽8 中世後期からの浄土真宗、近世の前田家支配のあり方、近世の農業労働のあり方が、富山県人気質の形成に大きな役割を果たした。真宗の信仰は、極楽浄土への往生を願い、今生には勤勉に勤しむ人々を育むうえで大きな役割を果たした(プロテスタンティズム)
…加賀乞食、越中強盗。越中の人々は合理的で実利重視の気風が身についた。
…近代に入ると、これまで被害をもたらしていた急流河川の存在が、日本海随一の工業県へと導くことになった。
…利賀村は演劇文化の発信地に。
■古代
▽17 朝日町の境A遺跡 翡翠を材とした装身具。糸魚川の姫川支流の小滝川流域で産出。宮崎海岸では現在でも翡翠の礫が採集される。
…翡翠加工の遺跡は、新潟県西部、富山県、長野県北部、能登地方に集中する。
▽19 氷見市の大境洞窟 日本ではじめて発見された洞窟住居跡。
▽33 大規模寺院の造営に越と近江の丁が動員されたのは、最新の建築技術を保有する集団が両地域に居住していたことを物語る。
▽51 大陸文化をいちはやくうけいれる環境にあり、在地の信仰と融合する形で仏教信仰が古くから行われたこの地域には、東大寺などの荘園をうけいれる地盤が形成されていた。
…気多神社(高岡)も、古くから仏教との関係を色濃く有し…、現在の気多神社社務所は、慶高寺の本堂であった。
気多神社、射水神社、高瀬神社のいずれにも真言宗の別当寺が付属。高瀬神派、高麗からの渡来神という伝が存した。古くから神仏の混淆した信仰体系を有した神社出会った可能性が高い。
…奈良時代の段階で律令国家が厚遇した地方の神社に共通して仏教とのつながりが認められることは、その地域に早くから仏教の信仰が入りこみ、在地の信仰と融合していたことを推測させる。
▽55 医王山や立山 山岳に対する信仰ともあいまって、修行場として早くから成立した山地が多く見られる。
▽62 南砺市の医王山。15世紀に衰退。立山は近世に入っても発展。…立山山麓には芦峅寺・岩峅寺の2つの拠点寺院があり、雄山神社が所在するという、典型的な山岳信仰の神仏習合の携帯を呈した。…平安中期の浄土教の隆盛とともに現世に存在する極楽と地獄の地として信仰され…
▽66 大伴家持5年間滞在。
■中世
▽81 立山信仰は宗派にとらわれなかったが、中世には浄土信仰の影響を大きく受けた。それと結びつきながら熊野信仰・修験とのかかわりも強かった。
▽85 義経の北国落ちのコース派、室町時代に多かった出羽羽黒山などに至る天台宗系の熊野修験者の道でもあった。
▽100 放生津 守護所所在地として政治の中核に。流通・交易活動の拠点としても繁栄。その後背地には八幡信仰圏が拡大。
■戦国
▽107 12世紀ごろの越中は浄土信仰が浸透。その展開のうえに、鎌倉中期から時宗や浄土真宗が広まりはじめた。
…浄土真宗寺院のうちで、本願寺と直接的血縁関係をもち、越中真宗教団の中核としての由緒をもっているのは瑞泉寺と勝興寺。…加賀藩では東本願寺優勢。
▽142 越中では1反は旧のまま360歩である。
■江戸
▽145 加賀藩や富山藩は、「一揆の国」として領民に対する警戒心をもちつづけた。
元和年間の加賀・能登の総検地では1反300歩制が採用されたが、越中ではふたたび総検地が行われなかったため、全国でも珍しい1反360歩とする中世の遺制が残ることになった。
…農村支配の要となる十村が慶長9年に能登ではじめて設定され…
▽150 加賀藩は、重要な物資・商品の自給する体制を整えようとした。諸商品の出入りを制限。
…塩硝は年貢として五箇山で確保していたが、1637年からは毎年買い上げる御召塩硝となった。和紙、蓑、山菜…も。
▽156 富山藩は貧乏。…年貢のうち相当の部分(55%)が江戸で消費
▽158 無高の農民は頭振とよばれた。高持の場合は百姓、無高の場合は頭振として処遇された。
▽161 元和の一国一城令で高岡・魚津・今石動などの城は廃止。
▽164 越中は、加賀・能登を大きくりょうがする新田開発が進んだ。…砺波・射水両郡の従来の街場は平野周辺の山側に近い位置にあり…新しい農家の人々が市場へ出るには不便だった。
新田開発は小村と散在する農家による散居的農村をうみだしていた。…杉木新町、福野新町、津沢新町などの町立てが実施された。
▽165 18世紀前期、初期特権町人にかわって、問屋商人の成長が見られるようになった。富山の薬種問屋。高岡・今石動では、周辺農村の布を扱う商人が勢力を持った。…城端派、五箇山を相手に貸方をする判方商売に加え、絹生産と絹商いでも栄えた。
▽167 年貢米は上方へ。初期は敦賀・小浜から琵琶湖を経由。直送が定着するのは、幕府によって下関まわりの西廻り海運の整備後。
▽169 富山城下の「船橋」。64艘の舟を鎖でつないで、、そのうえに板を並べてつくった。…船橋のたもとで売られていた鮎鮨が名産だった。
▽172 加賀藩になって大規模な新田開発。荒野や庄川などの河川流域や旧河床が選ばれた。
…もともと小村を主とした砺波地域では、新開による農家形成が散村的景観を押し広げていった。
▽180 売薬は、文化10年ごろ、富山藩領から2500人ほどの売薬商人が全国に出かけており、第一の産業として藩財政に貢献した。
▽184 継承すべき家業・家産のない零細な住民の場合歯、家というものが成立しがたく、稼ぎに占める女性の役割が大きくなるため、妻の地位は低くはなかった。(〓貧しい家の方が女性が強い)
▽185 田地割がおこなわれた加賀・富山藩領では、他地域と比べても、村民の結びつきが非常に強かった。屋敷周りをのぞく農民所有の田地はいずれ交換されることから、村の農地が共有的な意識を生み出すだけでなく、本百姓の村民の強い同苗意識を生み出した。他方では村の排他性を強めた。
…元禄6年に、分割相続が禁止され、農民のあいだにも家というものを広く形成させるようになる。女性はこれ以後相続から排除され、地位が低くなった。
…天明期頃。イネこきの道具派、扱竹から千歯扱き隣、米とおしは千石通しに、箕は唐箕に変わった。18世紀以降は、金肥の干鰯が広く使用され、天保以降には石灰も…
▽188 新川郡の境村は製塩業、新川の高月・水橋は売薬業。放生津と周辺や東岩瀬は北前船の船頭・水主も輩出。
▽193 五箇山の塩硝。中世末期派、一向一揆に供給する軍需用。…海防が重要となった幕末に増産された。
▽194 五箇山 麦・大豆・小豆・稗・粟・蕎麦・蕪と大根など。米で年貢を治められない土地だから金納を求められ、商品生産に依存。紙すき、養蚕、塩硝が主産業に。城端・井波の判方商人が五箇山への資金前貸しや商品掛け売りを行い、その経済は両町の有力商人に掌握されていた。
▽200 備前の医師万代常閑に教えられたとされる反魂丹のように、織物も…他国から技術が導入された。
▽203 鏡磨は、小間物売りを兼ねた行商を行った。氷見地域より1200から1300人が出ていた。
売薬も、蚕種も小間物も、商品をあずけ使用後に代金を回収するかたちをとっていた。
売薬派、立山地域での薬種採取の稼ぎを生み出し、袋用の紙生産を八尾の山地で活発化させ、版画製造という業種も起こした。蚕種歯、桑生産を活発化させた。
▽206 越中農村の人口は18世紀前期以降も増加した。…北関東・東北農村に移住する者も出てきた。北関東・南東北の真宗寺院では、越中農村からの移民の招致を実施した。
▽208 薩摩藩を売薬先とした薩摩組は、薩摩藩の密貿易の移出品となったコンブを蝦夷地より供給した。抜荷取引。長者丸漂流。
▽210 北前船。米国を蝦夷地へ、帰りは鰊肥などを越中へ。大坂へ米穀を、帰りに塩や綿を越中へ。…中小廻船は、能登へ米穀を、能登から越後へ木炭・ソーメン・塩などを移出。越後から越中へは干鰯や木材。
▽225 越中美術の代表的なもののひとつに売薬版画。越中の絵師、彫師、刷師により作成。
…井波彫刻、城端塗、高岡漆器、銅器。
…地域の工芸の粋を集めて越中の街場の曳き山は建造された。
▽231 庶民の信仰は真宗中心だが、氏神ほかの神社や他宗派寺院への崇敬も厚く、先祖への祭祀も重視された。(石見とはちがう)
▽233 真宗寺院の蓮如忌・報恩講等の「他、氏神祭り、氷見では夏に疫病よけの祇園祭り。祭礼の最後には、多くの町で曳山・タテモンを繰り出した。…多くの曳山は、利長より拝領した大八車の御車山をもつ高岡のものと類似したものとしてつくられた。
▽236 3食の習慣が江戸期に広まり、1781年には、下層の町人まで雑穀を食べずに白米を食べているとして、朝夕は雑穀を食べるように命じる町触が出ている。
…農民は質素。…農業に出る時期は、麦籾などの煎粉・動粉団子を麹みそなどにて煎り、菜・大根・茄子・干芋などありあわせのものを入れるもの。米は赤米の大唐米を2,3日に一度食べるが、普通の米飯は盆正月祭礼に一度ずつ食べるにすぎなかった。魚はたまに塩鰯や塩鮪を食べるだけ。
江戸期には、麻とちがい木綿の衣類が普及。町人のなかには絹織物を着ようするものも。衣類も町人と農民のあいだで差が開いた。
▽243 多くの在町の停滞に対して、新川木綿の発展に支えられた上市・三日市などの在町や、福光のような織物の生産で栄えた砺波郡の一部の在町、とりわけ、北前船と地回りの廻船で栄えた湊町は、天保以降も戸口を増大させにぎわいを見せた。伏木、東岩瀬、滑川、東西水橋など。
▽245 安政5(1858)年、飛騨の跡津川断層を震源とする大地震で、立山の大鳶・小鳶が崩壊し、常願寺川流域に二度にわたり大洪水が発生。一方で肥沃な土をもたらしたことで、被災者移住による開拓が行われ、新村が多数生み出された。
■明治
▽255 神仏分離令を受けて、立山権現が雄山神社に改称させられた。
「合寺令」
▽249 石川と富山をふくむ大石川県。土木費の配分を巡り、越中と加賀能登の議員の間で対立。前者は7大河川の治水工事を求めたのに対して、後者は道路改修などを主張。
分県運動が展開され、明治16年に富山県設置。
▽259 明治期を通じて、歳出の半分近くが土木費で、教育・勧業などの費用を圧迫する傾向が見られた。だがその河川改修が効果を発揮し、大洪水がしだいに減って行った。
▽266 地租改正葉、一部の地主への土地集中をもたらし、…明治16年における県内小作率は、全国的に見ても最高値。農民の土地売却による。
▽268 北海道移住。富山はとりわけ多い。明治15年から昭和10年までの北海道への移住戸数は5万4000戸。全国の総戸数の7.6%を締めている。最盛期である明治30年から、10年間には約6万人が北海道へ移住したが、全国府県で最大だった。
■大正・昭和
▽272 ロシア革命への干渉。シベリア出兵による糧米需要の予測が全国で米の騰貴を招いた。…米穀の県外移出停止や米価引き下げなどを求める米騒動が漁師町で発生。
「女一揆」 明治16年ごろから北海道へ漁業の集団で稼ぎをしていた。汽船や電信制度の普及で北前船が衰退。日露戦争後は北洋漁業が合法的になってきたから、北前船主らが北洋漁業に進出。
…滑川の騒動が全国に報道され、全国に波及。電信の発達と新聞というメディアによって、こうした全国的拡大がうみだされた。
▽278 チューリップ生産。現在でも切り花より球根生産。花をつぼみの時期に切り取らないから、きれいな花が見られる。
庄下村(砺波市矢木)の水野豊蔵の貢献。冬期に多くの農民が出稼ぎしていた。裏作にチューリップ球根の生産を導入した。戦争で輸出できなくなり一時壊滅した。…戦後復活…
▽281 富山のアルミ 「高岡銅器」の鋳物技術が活用された。戦時中、動画入手できなかったので、鋳物工場では、もっぱらアルミ製品をつくろうとするものも少なくなかった。高雄かは戦災を受けなかったので、銅器製作の設備が残り、兵器の廃材でアルミの鍋・釜をつくる職人もいた。
▽282 売薬→薬袋をつくる製紙業や印刷業、製缶業、製瓶業も発展。それを支えたのは豊富で安価な電力。
▽288 農地改革。改革前は小作地は全農地の54%を占めていたのが、改革後は自作地94%、小作地6%に。解放率は全国平均をはるかに上まわった。


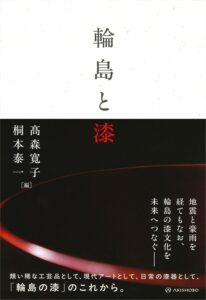

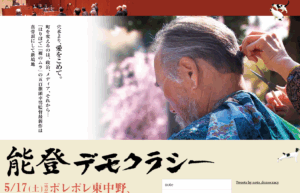
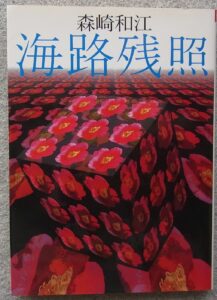

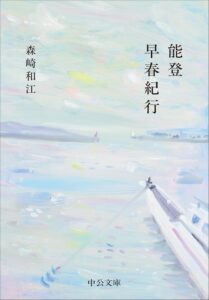
コメント